
2022年もさまざまなEC関連のニュースがありましたが、特におさえておきたいニュースについてまとめました。今後のEC運営にも関わる内容を中心に取り上げていますので、戦略を立てるにあたって参考にしていただければ幸いです。ニュースは「広告・販促」と「決済」の2つに分けてまとめています。
また、合わせてトレンドワードも紹介しています。急成長するEC業界は、トレンドの変化やテクノロジーの進歩が激しいです。こちらも、ぜひおさえていただければと思います。
広告・販促関連
「P-MAX」や「Advantage+ ショッピング」の提供開始
「P-MAX キャンペーン」はGoogle広告の1つで、2021年11月に提供開始されました。Google広告にはさまざまな種類がありますが、「P-MAX キャンペーン」はGoogleが保有するすべての広告枠に、最適な広告を自動で作成し、配信してくれるのが特徴です。入札も自動で行ってくれるので、オペレーションに必要な時間を削減することができます。そのため、EC事業者がGoogle 広告を自社で運用する場合はP-MAXを利用することをおすすめする方も多いです。
Google広告に限らず、SNS広告も同様のサービスが出ています。たとえば、FacebookおよびInstagramでは2022年10月から「Advantage+ ショッピング キャンペーン」の提供を開始しています。
LINE公式アカウントの料金プラン改定
2023年6月にLINE公式アカウントの料金プランが改定されるという発表がありました。LINEのメッセージ配信が、利用料金は据え置きで配信通数が大幅に減ります。配信内容はもちろんですが、セグメンテーションがこれまで以上に重要になってくるでしょう。
ECサイトの購入履歴や行動履歴、ユーザー情報をLINEアカウントと紐付け、お客様をセグメントして応対できるようにする「LINE連携ツール」などを活用するのも手です。
Yahoo!ショッピングとPayPayモールの統合
2020年10月に、Yahoo!ショッピングの豊富な品揃えと、PayPayモールの高品質な購買体験という強みをかけ合わせて生まれた新生Yahoo!ショッピング。UI・UXをはじめ、さまざまなところが変わりました。特に注目すべき変更点は2つあります。
1つは、ポイントルールの変更です。今まではポイントが一番還元される日曜日に売上の山が来るようになっていました。それがPayPayユーザーであれば毎日5%還元となるため、在庫の持ち方や売り方を見直す必要があります。
2つ目は、「優良配送」がより重要視されるようになったことです。「優良配送」の認定を受けることで、検索結果や商品ページに専用のアイコンが表示されます。また、検索結果のデフォルト設定では「優良配送」から表示されるため、認定を受けていない商品と比べ、アクセス・売上とも高くなるのです。
CCIさんとヤフーさんが、「新生Yahoo!ショッピング」をテーマにしたセミナーを開催されました。こちらアーカイブ動画があり、無料で見ることができますので、お時間がある方は視聴してみるとよいでしょう。
「LINE・Yahoo! JAPAN・PayPay マイレージ」の開始
LINE・ヤフー・PayPayの3社が2023年春より、マイレージ型の販促プラットフォーム「LINE・Yahoo! JAPAN・PayPay マイレージ」を提供開始します。
このサービスの目的は、メーカーのLTV最大化です。オンラインではユーザーの行動や購入データを分析し、施策を実施できます。しかし、オフラインでは小売店に来店・買い物をした消費者の購入データは蓄積されず、メーカーは継続的なマーケティング活動ができませんでした。この課題を解決するために生まれたのが、「LINE・Yahoo! JAPAN・PayPay マイレージ」なのです。詳細については、記者発表会の参加レポートをご覧いただければと思います。
ライブコマースが活況なダブルイレブン
中国の独身の日をきっかけにはじまったダブルイレブン(11月11日)。2022年のアリババグループのダブルイレブンの流通総額は前年並みだったと発表しています。実額を公表していないのは、これまでのイベントで初めてのことです。
そのような中、越境ECのモールである「Tmall Global(天猫国際)」では、中国国外における1,009の事業者の売上が前年同期比で100%以上増加したといいます。特に、ライブコマースが活況だったようです。2022年12月に「Tmall Global」はグローバルライブコマース連盟を設立したことからも、今後さらに注力することが伺えます。
中国市場でのマーケティング支援を手掛けるunbotさん主催のセミナーにて、スキンケアブランドを展開するポーラさんが「ダブルイレブンの攻略法」をお話しされました。コマースピックでセミナーレポートとして取り上げていますので、参考にしてみてください。
日本にも浸透してきたブラックフライデー
アメリカから始まり、ヨーロッパ、日本と広がっているブラックフライデーの流通総額は増加傾向にあります。ECプラットフォーム「Shopify」を利用している事業者のブラックフライデーおよびサイバーマンデー期間の売上高は過去最高額だったようです。Shopifyを利用する日本の事業者の売上高も前年比で約20%増加していることから、ブラックフライデーやサイバーマンデーが国内で浸透してきていることがわかるのではないでしょうか。
実際に、とあるアンケート調査で4人に3人がブラックフライデーを知っていると答え、2022年のブラックフライデーで買い物したいと答えた人が4割近くもいます。しかし、ブラックフライデーを実施している企業は全体の2割しかいないことがアンケート調査で明らかになっています。消費者と事業者で認識の差が出ているのです。
さまざまな理由から、値引きは戦略的にどこかのタイミングでやらなければならないと思います。ブラックフライデーは絶好の機会といえるでしょう。とはいえ、イベントに振り回されるのではなく、イベントに乗っかれるよう販促計画を行うことが大事です。
ユニバーサル アナリティクスの終了
広告・販促を行ううえで欠かせないのが分析ではないでしょうか。Googleアナリティクスにおける「ユニバーサル アナリティクスの終了」は大きなニュースの1つです。2023年7月1日にユニバーサル アナリティクスが終了するため、今後はGA4を利用する必要があります。
ユニバーサル アナリティクスはデータの計測にあたってクッキーを利用していますが、GA4はクッキーを利用しない設計になっています。そのため、数値や指標がユニバーサルアナリティクスとGA4では異なります。同じGoogleアナリティクスですが、バージョンが違うわけではなく、まったく別モノと考えたほうがいいと思います。まだ設定が済んでいない事業者さんは早めに対応するといいでしょう。
決済関連
「最終確認画面」の表示義務
2022年6月1日から施行された改正特定商取引法により、EC事業者はカートにおける「最終確認画面」において、下記の6項目に関して、顧客が簡単に確認できる形での表示が義務付けられました。
- 分量
- 販売価格・対価
- 支払の時期・方法
- 引渡・提供時期
- 申し込みの撤回、解除に関すること
- 期限がある場合、申込期間
また、ECサイトに限らず、カタログなど紙媒体にも当てはまるので注意が必要です。
EMV3Dセキュア(3Dセキュア2.0)への移行
3Dセキュアは、クレジットカード決済を行う際に用いられる本人認証サービスです。今まで利用されてきた3Dセキュア1.0は、クレジットカード情報を入力した後に、別のサイトが表示され、パスワードの入力が必要でした。そのため、カゴ落ちしやすいという課題がありました。
そこでセキュリティの質は落とさず、より利便性を追求した3Dセキュア2.0が登場しました。3Dセキュア2.0では、クレジットカード情報を入力した後に、カード会社でリスク判定を行い、そのリスクの度合いに応じて、パスワード入力の有無が求められます。パスワードの入力が必要な場合も別サイトに移動しないため、3Dセキュア1.0と比べて、カゴ落ちのリスクが低いのが特徴です。
コンビニ収納代行手数料の値上げ
2022年の秋頃からコンビニ収納代行手数料の値上げが発表されました。人手不足・業務量の増大・人件費高騰を理由に、1件当たり35~40円程度の値上げが実施されています。
コンビニ収納代行手数料の値上げに対し、決済代行会社がさまざまな方法で対応策を講じています。たとえば、ネットプロテクションズ社の「NP後払い」では、紙の請求書の代わりに電子バーコードで対応することで、費用を抑えています。また、キャッチボール社では新たに、「届いてから払い」というサービスを提供。コンビニでの収納代行の代わりに、キャッシュレスでの支払いで済ませられるようにしています。コンビニ決済を利用されている事業者さんは各決済会社に話を聞いてみるといいでしょう。
トレンドワード
ソーシャルギフト
住所を知らなくても、購入した後に発行されるURLをLINEなどのSNSで送るだけで、ギフトが贈れる仕組みのことです。SNSの利用率が急速に伸びたことに加え、新型コロナウイルスの影響により対面でギフトを贈りづらい状況にあったことで、ソーシャルギフトのニーズが高まっています。LINE社もソーシャルギフトに力を入れており、今後ますます市場は伸びていくと思われるでしょう。
自社ECサイトにソーシャルギフトを導入したい場合は、「AnyGift(エニーギフト)」などのサービスを利用するといいと思います。
BNPL
欧米で話題のBNPLは「Buy Now, Pay Later」の略で、いわゆる後払い決済サービスのことです。日本の従来からある後払いサービスは、同梱された紙の請求書を使って、コンビニや銀行などで支払いをするというものが主流ですが、BNPLの場合、アプリなどオンラインで支払いが完結します。
また、クレジットカードの分割払いと同様に、分割して毎月定額を支払い、分割手数料の負担がありません。日本の従来からある後払い決済サービスは、一括払いが基本で、分割が可能な場合でも手数料がかかるのが一般的です。
BNPLの代表的なサービスとしては、Paidyがあげられます。最近では事業者さんにとって手間が多い代引きの代わりに、BNPLを導入する事業者さんも少なくないです。
ポストパーチェス
購入後におけるアフターサービスのことで、返品や保証・修理などが挙げられます。サービスを実施するにあたって、顧客対応や物流のスキームを確立する必要があるため、大手企業でないと難しかったのですが、Recustomer(リカスタマー)やproteger(プロテジャー)といったサービスの登場により、中小企業でも実施が容易になりました。
返品や保証・修理などのアフターサービスを導入するメリットについては、下記のコラムが参考になると思います。
OMOストア
実店舗とECサイトの双方の機能を兼ね備えたお店のことです。b8ta(ベータ)やCHOOSEBASE SHIBUYA、明日見世があげられます。ZOZO社も昨年12月16日に表参道にOMOストアをオープンしました。コロナ禍でオンラインがモノを売る場として成長する中、「体験」を提供する場として実店舗の役割が変化していることから、OMOストアが注目されているのです。
大丸松坂屋百貨店の洞本さんが、中国のニューリテールからOMOストアの重要性についてお話しされていますので、合わせてご覧いただきたいです。
リテールメディア
さまざまな定義がありますが、小売店が提供する実店舗やアプリ、Webサイトなどを介した広告媒体を指すことが多いです。Amazonやウォルマートが事例としてよく挙げられますが、日本でもコンビニエンスストアやドラッグストアなどがリテールメディア事業に乗り出しています。
リテールメディアを活用する事業者さんも増えており、徐々に成功事例も出てくるでしょう。後日、コマースピックで、I-ne(アイエヌイー)さんのドラッグストアのサイネージプロモーションについて紹介しますので、参考にしてみてください。
最後に:外部環境に左右されない店舗運営を
さまざまなニュースを紹介しましたが、いずれも外部環境の変化に当たるものだと思います。広告やSNS、ECモールなど外部のプラットフォームに依存してしまうのは危険であることがわかるのではないでしょうか。顧客目線に立ったうえで、常に新しい打ち手を考え、チャレンジし続けていくことが事業を継続させるのに欠かせないでしょう。
また、外部環境はマイナスに働くことばかりではありません。コロナ禍では実店舗での販売が厳しかったかもしれませんが、ECでの販売は追い風になったと思います。消費者の行動の変化やトレンドをしっかりとおさえ、乗っかれるようにすることが大事です。そのためにも、情報収集を行い、常にアンテナを張り巡らす必要があります。
2023年も皆さんの店舗運営に何かしらお役に立てる情報を発信できるよう努めてまいりますので、引き続き、コマースピックをよろしくお願いします。
合わせて読みたい

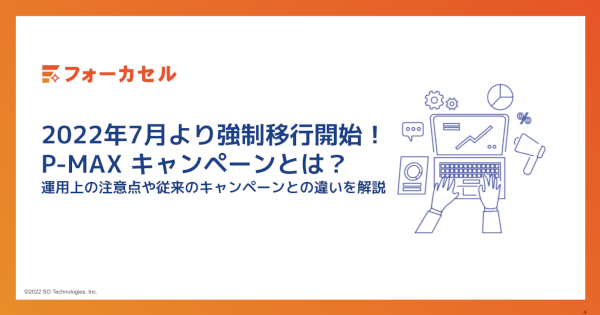
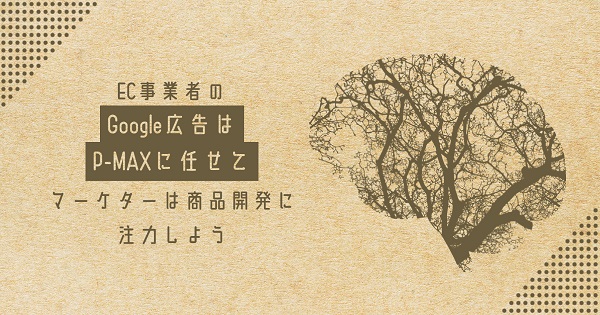
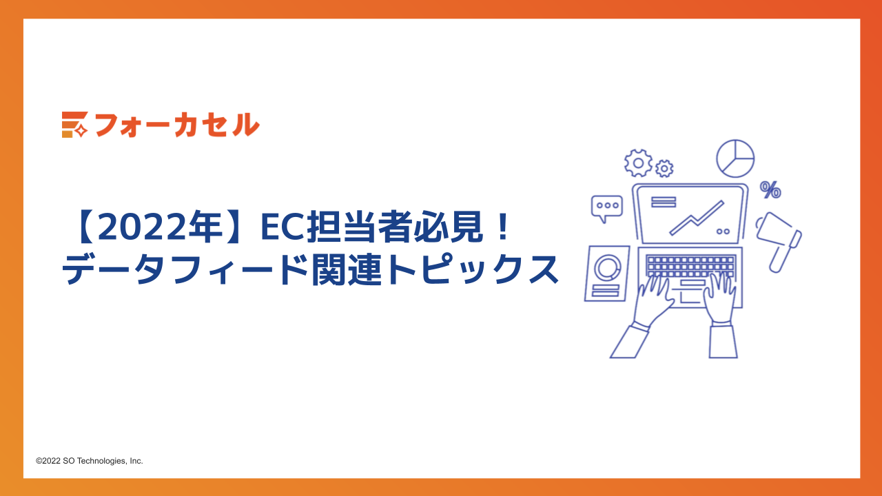







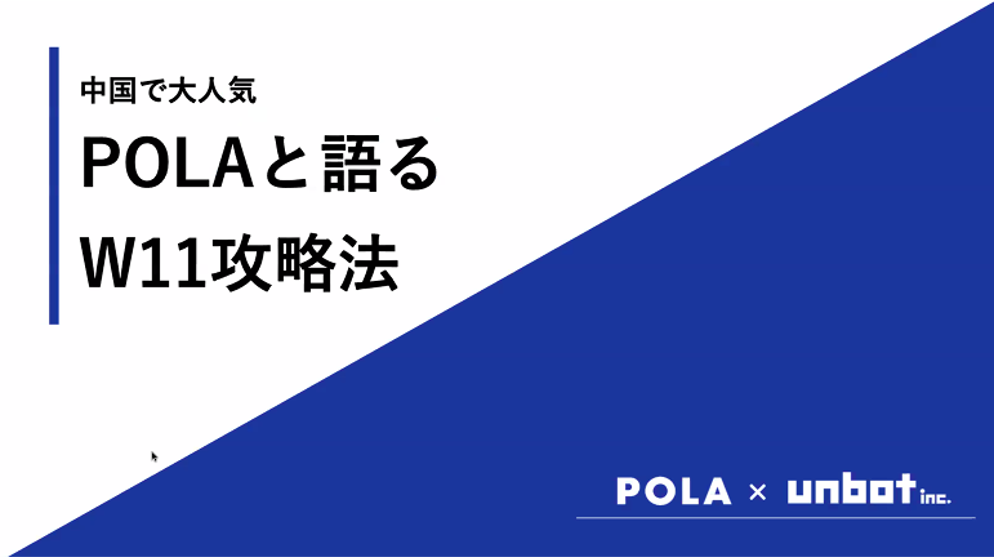




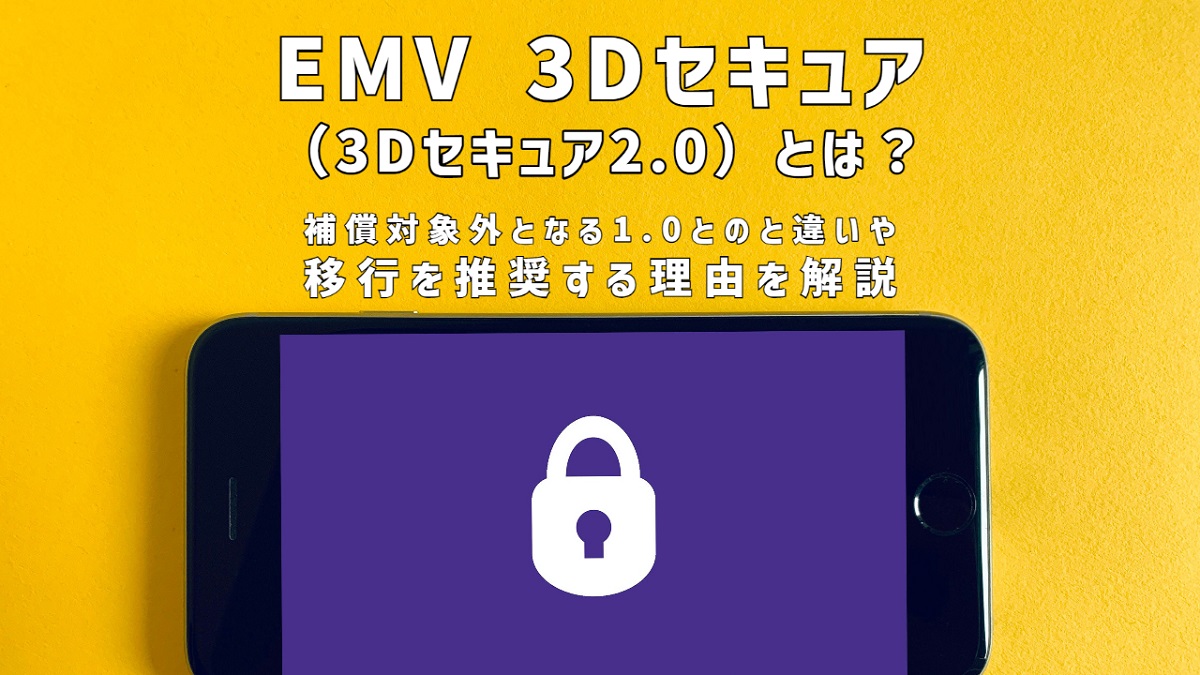






![返品マーケティングとは?返品を活用してEC売上を向上させる5ステップ [事例付き]](https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2022/09/返品マーケティングとは?.jpg)



















