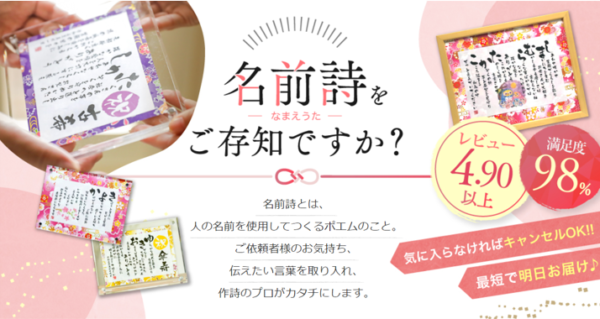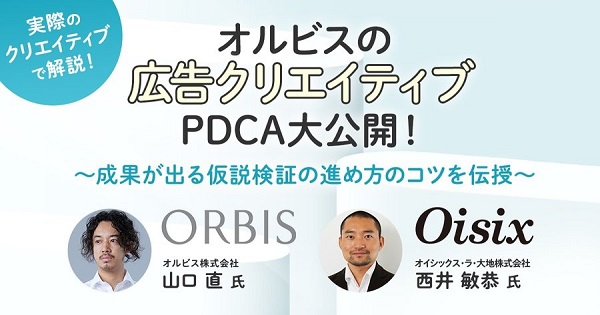この記事の目次
UGCとは?
UGCとはUser Generated Contentの略であり、「ユーザーによって生成されたコンテンツ」を指します。生成されるコンテンツは、InstagramやTwitterのようなSNSへの投稿や商品レビュー、ブログなど多岐に渡ります。最近では画像やテキストだけでなく、TikTokやYouTubeなどの媒体を通した動画によるUGCも増えてきました。
EC・物販においてUGCを活用することで、下記のようなメリットがあります。
- 商品・ブランドの信頼性を高めながら認知拡大ができる
- 顕在層のお客様に対し、具体的なユースケースを想定してもらえる
- 商品やブランドに対する生の意見を取り入れられる
UGCの活用で得られる効果・メリット
では、具体的にUGCを活用することでどのような効果やメリットを享受できるのか、EC・物販における文脈で考えてみましょう。
商品・ブランドの信頼性が高まる
お客様の生の声が発信されるUGCが増えることで、購入を検討している方の後押しになる効果があります。ECモールの商品レビューを例に挙げるとわかりやすいのではないでしょうか。レビュー件数やレビュー評点などの定量的な評価も重要ですが、真剣に購買を検討している方の場合、レビューの内容を精読し、定性的な情報を多く取り入れます。
これはECモールに限った話ではありません。特に、長く使うものや金額の高いもの、ネットでしか購入できないものであれば、InstagramやTwitterなどに点在する投稿内容やGoogle検索で表示されるブログの記事などで、消費者は事細かに情報を収集する傾向にあります。そのため、高い好感度が示されたUGCが多く投稿されることで、商品やブランドへの信頼度は増していき、購買の後押しになることは間違いありません。
ユースケースを想起させやすくなる
商品によっては単体では利用方法や組み合わせ方がイメージしづらい場合があるでしょう。
例えば
- アパレルやファッションアイテムのような身に付ける商品
- 家具やインテリアなどサイズ感がわかりづらい商品
- マニュアルだけでは組み立て方がわかりづらい商品
- 調理が必要を伴い食材の組み合わせが複数ある商品
など、挙げればきりがないかと思います。消費者ならではの視点でコンテンツが生成されるUGCであれば、購買を検討している消費者にとって生活に寄り添ったリアルなユースケースを想像してもらいやすくなるでしょう。
商品・サービスの開発や改善に役立つ
お客様の生の声であるUGCからマーケティングのヒントや、商品・サービスの改善に役立つ意見をもらえるでしょう。また、想定とは違った使われ方や、顧客層が購入していることもあったりします。ワークマンがUGCから客層拡大に繋げた話は有名です。
UGCを活用する際のリスク・注意点・デメリット
次に、UGCを活用する上でのリスクや注意点についてお伝えしていきます。
コンテンツを利用する場合は許可が必要
お客様が投稿したコンテンツを商品ページやLPなど商用目的で利用する場合、必ず掲載の確認と許可を取る必要があります。無断でコンテンツを流用することでトラブルに繋がるリスクを孕んでいるため注意しましょう。
自社のUGCを見つけやすい工夫が必要
SNS上に自社商品のUGCが投稿されたとしても、ハッシュタグやメンションを付けてもらえないと見つけられないことがしばしばあります。そのため、商品やブランドのSNSアカウントを保有・運用し、お客様から認知してもらうための取り組みが必要です。
また、サイト内や商品の同梱物などに特定のハッシュタグを付けた投稿をしたり、アカウントにメンションしてもらったりすることを推奨する記載を行い、見つけやすくするための仕組み作りをしなければなりません。
UGCであっても薬機法の対象になる
化粧品やサプリなど、効果効能に関する商品のUGCを活用する場合は注意が必要です。お客様が投稿したコンテンツであっても、内容が薬機法に抵触する場合、ECサイトや販促物として活用した企業が罰則の対象になります。
化粧品を利用してシワが消えたという表現や、サプリを利用して髪が生えたという表現のようにお客様による個人的な効果を実感した投稿であっても、薬機法に抵触するリスクがあるため利用は控えましょう。
IGCによるヤラセ感は悪影響
IGCとはInfluencer Generated Contentの略でインフルエンサーが生成したコンテンツのことを指します。インフルエンサーが愛用していたことで、UGCのように自然発生的にコンテンツが生成されることもありますが、インフルエンサーマーケティングの延長線上で広告案件として投稿を行うこともあります。
広告案件として投稿されたIGCは、インフルエンサーの見せ方や普段の投稿内容にもよりますが、生の情報を収集している消費者にとってノイズとなるため、悪影響を及ぼす可能性があります。更に、同じタイミングに集中して複数のインフルエンサーから広告案件がSNS上に透過されることで、認知を拡大する目的で行われた施策が、ブランドのイメージを損ない、ヤラセ感が強まってしまうこともあります。
サイト内にUGCを入れるために、インフルエンサーに依頼して投稿されたIGCから活用を始めるケースがありますが、純粋なUGCが投稿されたタイミングで徐々に差し替えることを視野に入れて運用をしても良いでしょう。
UGC活用の流れ
UGCをEC・物販で活用するための流れについて解説していきます。
UGCの生成
まず、商品を購入いただいたお客様にコンテンツを生成いただく必要があります。施策など何も行わなくてもUGCは自然と生成されることもありますが、コンテンツが生まれやすい仕組み作りを行ったほうが良いかと思います。
前述のハッシュタグやメンションを付けた投稿の促進、レビュー記入の依頼などのお客様のアクションに対して、クーポン配布やサンプル品の提供、投稿者から抽選で○名にプレゼントなど、次に繋がる施策を用意すると良いでしょう。商品をまた使いたいと思っているお客様がUGCを生成してくれるため、ポジティブな投稿が増えやすくなります。
UGC投稿者へ利用許可を取得
サイト内や同梱物、パッケージやPOPなど、UGCを利用する場合に投稿者への利用許可を取得します。各SNSに搭載されているDM(ダイレクトメッセージ)の機能などを活用し、個別に連絡を取って許可を取得しましょう。
サイト内にUGCを掲載
許可が取れたUGCをサイト内に掲載します。商品ページや商品LPなど購入に近い場所に追加することで効果測定を行いやすくなります。掲載するUGCの内容や掲載位置によって効果が変わるため、様々なパターンを試してPDCAを回すことをおすすめします。
UGCをサイト内に掲載する方法として、キャプチャを取って添付したり、ツールを活用して埋め込みを行ったりと、その方法は様々です。商品ジャンルや事業の段階にはよりますが、ツールを活用したUGCの埋め込みで、サイト内の接客品質を向上できるようになるでしょう。
UGCの活用事例
コマースピックで行った取材から事業者様に伺った事例を紹介していきます。
感動的なギフトでUCGが生まれるゆうひ堂の名前詩
ギフト品のように記念をお祝いする商品はお客様の期待値を上回ることでUGCが生まれやすくなるでしょう。ゆうひ堂の楽天市場店舗内に投稿されたレビューを見ると、写真付きの長文レビューが多数あります。商品の品質がお客様に感動を届け、レビューとして実績が蓄積し、新たなお客様を集客する循環ができています。また、商品レビューが蓄積されることが集客につながるのは、一般ワードで商品を探しに来るユーザーがいるECモールならではの特徴といえるでしょう。
PHOEBE BEAUTY UPが活用するInstagramのUGC
PHOEBE BEAUTY UP の運営元であるDINETTE株式会社はInstagramに投稿されたUGCを活用しています。その目的として、UGCが生成されることによる集客や認知の拡大、商品LP内に活かすことでの購入の後押しが挙げられます。詳細は下記の記事をご覧ください。
UGCを収集し、CGMを運営するRUSHOUT
CGMとはConsumer Generated Contentの略で、消費者生成メディアを指します。岡山県で古着専門店を営むRUSHOUTでは店舗の公式アカウントとは別に古着情報メディアのInstagramアカウントを持っています。RUSHOUTのテイストに近い古着を中心としたコーディネートを消費者から募集し、掲載を行うことで1万人以上のフォロワーを有しています。潜在層の方々を集客する施策として、事業者によるメディアの運用は効果が出るまで時間がかかるものの、Cookie規制など広告による集客の精度が落ちている時代背景から今後欠かせなくなるのではないでしょうか。
最後に:商品力を磨くことがUGC生成の鍵
自分が体験したことをSNSにシェアする文化が徐々に広がってはいるものの、UGCを生成してもらうにはお客様に行動してもらうための理由が必要になります。単純なプレゼント施策やインセンティブを付与することで投稿を促すことも可能ではありますが、そのようにして生成されたUGCはあくまでインセンティブを目的として発信されたコンテンツです。
「良い商品だから広めたい」という想いの上に発信されるコンテンツを作るには、上記のゆうひ堂の事例のような感動体験や人に勧めたくなるような商品を提供する必要があるでしょう。人に勧めるという行為には少なからず責任がついて回ります。「自分なら胸張っておすすめできるかどうか」を常に胸に、お客様にメッセージを届けていくことが、結果としてUGCに繋がるように思えます。
合わせて読みたい