
デジタル上で発生した危機や重大なトラブルを研究する、シエンプレ デジタル・クライシス総合研究所は、ランチタイムウェビナーを毎週水曜日12時に開催しています。新型コロナウイルスの流行下で移り変わる最新の論調やその変化を多角的に分析し紹介していくことで、業務判断の参考になればと思い、セミナーを開催されています。
2021年6日2日に開催された第51回目のセミナーは、「目指すは広告費0円 ワークマンのアンバサダー・マーケティング戦略」です。当日参加できなかった方も多いと思いますので、コマースピック編集部で内容をまとめました。皆さんの参考になれば幸いです。
【登壇者】
株式会社ワークマン
営業企画部 兼 広報部 部長
林 知幸さん
【ファシリテーター】
シエンプレ デジタル・クライシス総合研究所 主席研究員
桑江 令さん
この記事の目次
客層拡大のため、アンバサダー・マーケティングに取り組む
ワークマンといえば、SNSに注力したアンバサダー・マーケティングで有名です。2020年10月、横浜にオープンした『#ワークマン女子』は、入場制限が行われるほど大反響でした。現在、ワークマンには約40名のアンバサダーが所属しており、製品の宣伝だけでなく、製品開発にも携わっています。
「ワークマンがアンバサダー・マーケティングに取り組んだ理由は、客層拡大のためです。作業服を販売しているので、数年前までワークマンは職人向けのお店というイメージがあったと思います。しかし、人口は減少傾向で、職人さんが減る中、作業服だけを販売するとなると業績が頭打ちになってしまいます。そこで、プロの職人さんも認める作業服の機能性を別の客層に使ってもらいたいと考えました。客層を拡大するため、作業服以外の分野でもファンを獲得するためにアンバサダー・マーケティングに力を入れたのです」と林さんは話します。
客層が異なるお店でも扱っている商品は同じ

2018年9月に「ワークマンプラス」、2020年10月には「#ワークマン女子」をオープンし、最近では、職人さん以外の客層も大幅に増えているといいます。驚いたのは、品揃えの幅は各お店で異なりますが、商品自体は同じものを置いているということです。「#ワークマン女子」で販売しているものは、「ワークマンプラス」でも、「ワークマン」でも販売しているというのです。商品の魅せ方を変えることで、異なる客層に対して、アプローチしています。
ワークマンのアンバサダーの選考方法
ワークマンがアンバサダーに求めている役割は、製品開発の参画と製品情報の発信の2つで、特に前者を重要視しています。現在は40人のアンバサダーがおり、共同開発まで携わっている方は15人、情報発信のみの方は25人となっています。将来的には50人まで増やす予定だといいます。密にコミュニケーションをとることを考えると50人が限界だと考えているからです。
アンバサダーに求めている条件
SNSのエゴサーチをメインに、アンバサダー候補を探しています。ホームページや、SNSでアンバサダーの募集はしていません。選考基準としては、ワークマンの製品に関する投稿数や投稿期間はもちろんですが、新商品などワークマンについての情報を真っ先に取り上げてくれるか、改善点や要望などの意見を発信しているか、意外な使い方をしているかが決め手だといいます。

他にも、フォロワーとのコミュニケーションがとれているかどうかも見ているそうです。製品開発にあたって、アンバサダーにはフォロワーの意見を代弁して、ワークマンに提案することを理想としているため、フォロワーとの情報交換ができているかどうかは大事なことと考えているのです。また、アンバサダーはインフルエンサーである必要はないといいます。現にフォロワーが100人ぐらいのアンバサダーもいるそうです。
「ワークマンの製品は、高機能で低価格をうりにしており、職人さんが過酷な環境で長時間働いていても快適でいられること、汚れてもいいように何枚も買い替えができる価格をコンセプトにしています。長時間着ていても快適でいられる、その良さを伝えるとなると、どうしても長尺になってしまいます。そのため、TwitterやInstagramよりも、ブログやYouTubeなど制限がないメディアやSNSの方が魅力を伝えられるので、アンバサダー候補を探すにあたって、特にブログや、YouTubeを見ています。ワークマンの製品は機能が非常に多いため、店頭のポップやチラシ、カタログでは伝えきれない機能に気づいてくれると、ワークマン愛を感じます」と林さんは嬉しそうに話されました。
人となりを知ったうえでアンバサダーに任命
「いい人がいたら、SNSのDMでアポイントをとっています。熱心なファンがいて、ワークマンプラスが初めて名古屋にオープンしたときに絶対来てくれると思い、新店で待ち伏せしたこともあります」と林さんは笑いながら言いました。
アポイントをとっても、すぐにはアンバサダーに任命しておらず、その後何度かコミュニケーションをとっているそうです。なぜワークマンの製品が好きなのか、どんな風に使っているか、改善点はあるかなど質問する中で、その人がどんな人かを探り、2~3ヶ月かけて正式にアンバサダーに任命しているといいます。
アンバサダーに就任された後でも、製品に関する勉強会やイベントに来てもらい、製品開発の責任者の方と話してもらうなど、密にコミュニケーションをとっています。インフルエンサーを起用して、炎上してしまったという例がありますが、ワークマンでは日々コミュニケーションをとっているため、アンバサダーの発信によって炎上したことはないそうです。
アンバサダーとの取り組み
セミナーの中で、林さんは3人のアンバサダーを紹介してくださいました。
事例1:サリーさん
ママさんキャンプブロガーのサリーさんは、ほぼ毎週キャンプに行っており、キャンプ場で「綿かぶりヤッケ」という溶接工の作業服を着ていました。そのサリーさんの写真を見て、不思議に思いアポイントをとったそうです。
サリーさんは、焚火で、火の粉が飛んでしまい、お気に入りの洋服に穴が開いてしまったり、煙の臭いがついてしまったりしないように、「綿かぶりヤッケ」を着ていると教えてくれたといいます。「綿かぶりヤッケ」は、綿で作られているため、火に強いのです。これは面白いとなり情報交換をするようになったのです。

写真右:共同開発で生まれた「フルジップコットンパーカー」を着るサリーさん
「綿かぶりヤッケ」はあくまでも、職人さん向けに作られた製品であるため、上から被るタイプになっています。そのため、脱ぎ着が大変だとサリーさんは言います。
そこでワークマンと共同開発をして生まれたのが「フルジップコットンパーカー」です。着衣がしやすいようにフルジップにし、デザインも丈の長さを短くし、色もツートンカラーになっています。「綿かぶりヤッケ」は一部の人しか買わないため、1年間で、数千枚ほどの売れ行きでしたが、「フルジップコットンパーカー」は、1週間で1万枚も売れたのです。
「フルジップコットンパーカー」をきっかけに、サリーさんと共同開発で様々な製品を開発しています。
事例2:Nozomiさん

茨城のおばあさんの畑がイノシシの被害にあったのをきっかけに猟師になったNozomiさん。狩猟の際に、ストレスなく着られるということで、ワークマンのウェアを着ているといいます。
Nozomiさんと共同で開発した防寒アウターは、狩猟時に携帯する荷物が多いことから、収納性にこだわっています。また、防寒性が高く、軽くて生地が伸びるため、その動きやすさから、釣りやキャンプ時にも最適です。
店頭のポップには「ミキシング レインパーカー」の商品説明の他に、NozomiさんのYouTubeアカウントに飛ぶQRコードがあります。YouTubeの動画では、Nozomiさんが「ミキシング レインパーカー」について解説しています。
事例3:大屋さん

3人目は、バイクの新型車及びバイク用品のテスターを長年されているモーターサイクルジャーナリストの大屋雄一さんです。様々なバイクウェアのテスターをされてきた大屋さんからは、細かいレビューをしてもらえるそうです。
最初の接点はワークマンへの取材がきっかけで、その後コミュニケーションをとっていくなかでアンバサダーに就任されました。
大屋さんはプロのジャーナリストの方ではありますが、他のアンバサダーの方と同様に、費用はお支払いしていません。その代わり、ワークマンとして取材には積極的に協力しており、要望も可能な限り受けているそうです。
なぜワークマンのアンバサダーは無償でも受け入れられるのか
ワークマンのアンバサダー・マーケティングが他社と異なるのは、金銭のやりとりが一切発生しないということです。たとえ共同開発をした製品がヒットしても、アンバサダーの方にはお金は支払っていません。その代わり、アンバサダーの方の認知度が向上するようにワークマンは取り組んでいるそうです。
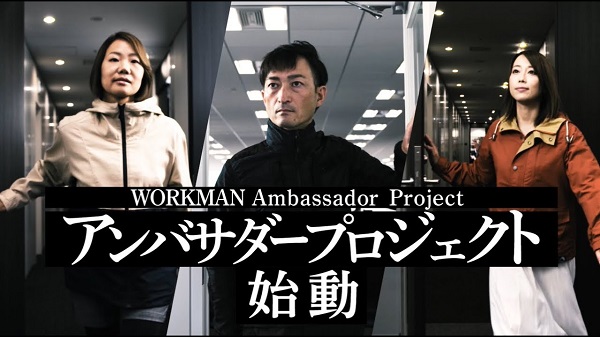
たとえば、CMでは製品の宣伝をせずに、あえてアンバサダーを宣伝したり、過酷ファッションショーというイベントを開催し、アンバサダーに出演してもらったりしています。また、テレビや書籍、雑誌などのメディア露出の際には、アンバサダーを紹介するようにしているのです。
ワークマンがアンバサダーに提供している価値は2点あります。ワークマンがアンバサダーを宣伝することで、アンバサダー自身の認知を向上させ、フォロワー数を増やし、それによってSNSによる広告収入を増やせる点。そして、アンバサダーに製品情報を優先して提供することで、アンバサダー以外の誰よりも早く情報発信ができる点です。アンバサダーが有名になり、影響力のあるインフルエンサーになればなるほど、ワークマンの製品について多くの人に知ってもらえる。ここにWIN-WINの関係があります。
それに加えて、企業と共同で製品開発ができたり、自分の名前が製品に載ったりとプライスレスな経験もできることに魅力を感じているのでしょう。
アンバサダー・マーケティングのKPIとKGI

「アンバサダーではなく、インフルエンサーに頼めばいいのではという意見もあります。よっぽど資金があればいいですが、ほとんどの企業の場合、単発で終わってしまうでしょう。それよりも、たとえフォロワーが1,000人ぐらいであっても、繰り返し発信してくれる方がUGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)や口コミが蓄積します。また、アンバサダーの方がよりリアルなライフスタイルを提案することができるでしょう。製品開発においては、より消費者目線での開発ができるのもポイントです」と林さんは言います。
「アンバサダー・マーケティングのKPIは、アンバサダーのワークマン関連コンテンツのPV数やコメント数、ワークマン関連のUGC数(#ワークマン、#ワークマン女子)などになっています。最終的なゴールであるKGIは、販促費をかけずに製品を売り切ることです」と林さんは続けて話されました。
セミナーに参加して:コミュニケーションを通じてファンに
今ではワークマンのアンバサダーは40人に増え、多くのメディアなどでとりあげられていますが、はじめはサリーさんのブログをみてアポイントをとったところからスタートしています。
一人の顧客とコミュニケーションをとり、ファンからアンバサダーになり、一緒に製品を開発したり、発信したりする。そうして、新しいファンやアンバサダーが生まれる。消費者との地道なコミュニケーションを取り続けてきたことが、アンバサダー・マーケティングの成功の秘訣なのだと思いました。
シエンプレ デジタル・クライシス総合研究所は、ランチタイムウェビナーを毎週水曜日12時に開催しています。経営者、広報、マーケターの方に役立つものばかりですので、機会がありましたら、ぜひ参加されてはいかがでしょうか?
シエンプレ デジタル・クライシス総合研究所のランチタイムウェビナー
https://dcri-digitalcrisis.com/seminar/feature/lunchtime/
【事例1:サリーさん】
HP / YouTube / Twitter
【事例2:Nozomiさん】
HP / YouTube / Twitter
【事例3:大屋さん】
プロフィール(ヤングマシン)/ Instagram / Facebook
合わせて読みたい

















