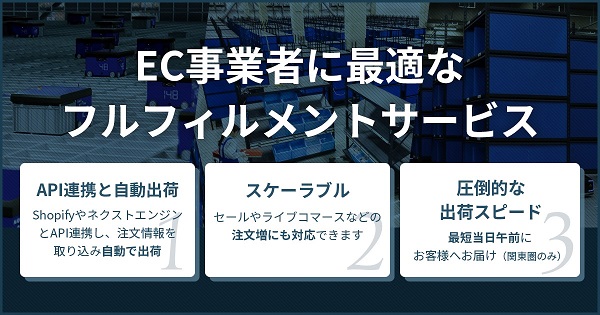この記事の目次
発送業務を外注するタイミングは?
出荷件数が増えると、梱包・配送業務に時間がかかってしまい、他の業務に時間をかけられなくなります。そのため、ある程度売上がたったら、ピッキングから梱包、配送までの業務をアウトソーシングしても良いと思います。
出荷件数が月200~300件になったら、物流代行業者に委託をするタイミングだと言われていますが、実際は月の出荷件数が100件未満でも委託している店舗は多いです。
物流代行業者に委託する場合、出荷件数が多ければ多いほど、1個当たりの単価は安くなります。そのため、出荷件数が少ないうちは自社で梱包・配送を行った方が安いですし、そもそも出荷件数が少ないと物流代行業者に委託しようと思っても断られてしまう可能性が高いです。
最近では、クラウドソーシング型の物流代行など小ロットから対応できるサービスも出てきたので、出荷件数が少ないという理由で断られた場合は、利用してみるといいでしょう。
自社で梱包・配送を行った場合と委託した場合のコストを計算して、外注した方が安いのであれば委託して良いと思います。その際、商品を保管するための場所代も忘れてはいけません。また、採用コストや教育・管理コストも考慮するといいでしょう。アウトソーシングにかかるコストは下記を参考にしていただければと思います。
物流業務のアウトソーシングにかかるコスト
固定費
業務管理費用
倉庫での商品管理全般にかかる手数料で、毎月の出荷件数によって決まる場合が多いです。発送代行業者によってはないところもあります。契約時に基本料として計上されることが多く、在庫管理や梱包作業の料金を含む場合もあるので、詳細を確認するようにしましょう。
システム利用料
倉庫管理システム(WMS)の利用料になります。業務管理料と同様に基本料として計上されることが多いです。発送代行業者によっては、倉庫管理システム(WMS)を導入せずに、Excelなどで管理しているところもあります。システムを導入した方が、ミスのリスクは低くなるため、倉庫管理システム(WMS)の有無は確認しておくといいでしょう。
保管費用
倉庫の利用面積によって料金が変わってきます。一坪あたり、1棚あたり、1パレットと発送代行業者によって設定されている単位が異なるため、注意しましょう。基本的には、棚などを利用して立体的に保管されますが、商品によってはパレットに並べて積み上げる必要があるものもあります。その場合は、リフト作業などの費用もかかってきます。保管場所だけでなく、梱包作業を行う場所も含めた面積になることが多いです。
倉庫の立地で単価が変わります。都心に近いほど料金は高く、地方へいくほど料金が下がります。倉庫の場所によって、購入者まで商品が届くリードタイムと配送費が決まるため、翌日配送などを設けている場合は考慮する必要があります。
また、保管倉庫の温度設定でも料金が変わってくるのも覚えておくといいでしょう。常温が最も安く、続いて一定の温度を保つ定温、冷凍の順で高くなります。電気代などの光熱費がかかってくるためです。
変動費
入庫費用
商品を倉庫に搬入する作業にかかる費用になります。宅配便による入庫か、コンテナやパレットによる入庫かによって料金が変わってきます。小さい商品の場合は、1品あたり(ピース単位)ではなく、1箱あたり(ケース単位)の料金を設定している代行業者もあります。
検品費用
商品の種類や数量に誤りがないか、品質に問題ないかを確認するための作業にかかる費用です。作業内容によって、料金が変わってきます。商品の種類や数量の確認程度であれば、入庫料に含まれることもありま
ピッキング費用または出荷費用
出荷にあたって、商品を保管場所から取り出すピッキング作業にかかる費用です。ピッキング方法や商品の大きさによって料金は変わってきます。また、商品の他に、チラシなどの同梱物もピッキング費用の対象になります。
梱包費用
商品を梱包作業にかかる費用になります。のし袋などギフト用の梱包など、梱包の方法で料金が変わってきます。梱包資材や緩衝材の代金に加え、納品書や送り状の発行手数料などが含まれます。
配送費用
宅配業者、配送業者に支払う費用になります。ほとんどの発送代行業者は、佐川急便やヤマト運輸、日本郵便などと割引料金で契約を結んでいるため、自社から直接送るより費用が安くなります。契約内容は各発送代行業者によって異なるので、配送費用も異なってきます。中には、自前で配送している代行業者もあります。 上記以外にも、オプション費用として流通加工・付加サービスなどがあります。料金はトータルでみて判断することが大切です。
自社で、ヤマト運輸・日本郵便・佐川急便に委託した場合の配送費用をまとめましたので参考にしていただければです。
料金以外で物流代行業者を選ぶポイント
発送代行業者を選ぶにあたって、料金以外にも下記内容を考慮して選ぶ必要があります。
●許認可資格
食品や化粧品、医薬部外品などを扱うには許認可資格が必要になります。そのため、許認可資格がない発送代行業者には、上記の商品を委託することはできません。
【代表的な許認可資格】
高度管理医療機器販売業許可、食品製造業許可、医薬部外品製造業許可、化粧品製造業許可、化粧品製造販売業許可、消防法危険物屋内貯蔵所許可など
●対応可能な温度
常温、定温、冷蔵、冷凍など
●対応可能な流通加工・付加サービス
商品撮影代行、アセンブリ、成分表貼り、ラッピング、熨斗、ラベル貼り、アパレルのタグ付け、採寸、アイロン掛け、検針、ささげ、受注処理代行、コールセンター、海外発送、FBA納品代行、関税立替など
●対応可能日
平日のみ対応、祝日以外対応、365日対応など
●倉庫の場所
北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄
また、BtoC・BtoBどちらが得意かを確認することは大事です。例えば、BtoBがメインの発送代行業者に委託した場合、3回目に購入した顧客に対してチラシを同梱するといったことができない可能性があります。リピート商材を中心に販売している事業者にとって戦略が狭まってしまいますので、マーケティングの戦略も踏まえたうえで、発送代行業者を選ぶようにしましょう。
発送代行業者を選ぶにあたってお困りでしたら、コマースピックにご相談下さい。
▶ご相談はこちら
合わせて読みたい