
ロジザード株式会社 中澤 巌さん(写真右)
「BOTANIST(ボタニスト)」をはじめ、様々なブランドを展開している株式会社I-ne(以下、I-ne)は、ヒット商品を連発し業績も好調です。マーケティングや販売戦略で取り上げられることが多いI-neですが、事業の躍進の裏には物流が鍵を握っています。今回は物流業務のデータ活用をテーマに、同社の木村勇介さんと、物流業務の支援をされているロジザード株式会社(以下、ロジザード)の中澤巌さんに話しを伺いました。
この記事の目次
I-neにおけるロジスティクスの役割とは
―― 木村さんはロジスティクス課に所属しているとのことですが、どういったお仕事をされているのでしょうか? また現在の運用体制についてもお聞かせ下さい。
木村さん:ロジスティクス課という名前の通り、物流の業務を幅広く担当しています。物流費のコスト削減や、委託している3PL事業者(外部委託している物流倉庫)様の業務が効率化できるようにマネジメントをするのが私の課のミッションです。
弊社では、シャンプーや美容家電、飲料水など様々なブランドを扱っていますが、販売チャネルは主にBtoBとBtoCになります。
会社の成長に伴い、扱うブランドや販売チャネルが増えるのですが、新たな業務としてこなすことはもちろん、既存の物流業務を見直す必要も出てきます。出荷方法や納品形態が変わってきますので、それに備えて事前に準備しなければなりません。また、会社が成長しているからこそ、イレギュラーな事態が発生することが多いです。業務は大変ではありますが、私自身やりがいをとても感じていますし、日々新しい学びを得ています。
ロジスティクス課は、私を含めて6名の体制で運営し、コスト・クオリティ・在庫管理の観点で役割を分担しています。この3つの役割に加え、今後は業務フローを整える役割を入れようと考えています。また、現在はBtoBとBtoCで分けて担当をつけていますが、中長期的にはブランド×地域別ごとで担当をつけることも選択肢にあります。
物流のデータを活用して販売部や3PL事業者と連携
ーー ボタニカルライフスタイルブランドの「BOTANIST(ボタニスト)」やミニマル美容家電の「SALONIA(サロニア)」、リラクゼーションドリンクブランドの「CHILL OUT(チルアウト)」など、本当に幅広いブランドを扱っていますよね。物流費のコスト削減にあたって、どのように業務を行っているか具体的に伺えないでしょうか。

木村さん:弊社はWMS(倉庫管理システム)に「ロジザードZERO」を導入していることから、様々な物流のデータをとることができます。そのデータを活用して、現在庫と出荷履歴をもとに、商品ごとの在庫回転率を算出しているのです。それにより、在庫過多や滞留在庫になってしまいそうな商品がないかを確認しています。コストに直接関係してくるため、保管費に異常はないか、在庫回転率はどうなっているかなどを見ることは重要です。在庫過多や滞留在庫に陥らないよう、月1回は必ず確認するようにしています。
ロジスティクス課が最前で在庫を見ているため、できるだけ早く正確にアラートを社内に出せるようにしています。そうすることで、販売部が施策を考えることなどに時間を確保できるようにし、ロジスティクス課の動きが売上につなげられるようになることを心がけています。
他にも、「ロジザードZERO」のデータと配送会社の送り状問番データや地域別送料マスタなど様々なデータを掛け合わせることで、宅配サイズの構成比を算出しています。同じブランドであっても施策の内容によって購入いただく商品の組み合わせや個数が変わるため、60サイズだったり、80サイズだったり、どの宅配サイズで配送するのか変わってくるのです。

宅配サイズの構成比を出すことで、どの施策にどの程度コストが掛かったのかロジスティクス課として把握できます。その情報を販売部に共有することで、上代価格はいくらに設定すれば粗利がどれくらい残るのか、次回以降の施策に活かせるようになるのです。トップライン(売上)だけでなく、ボトムライン(利益)に目を向けて、社内のディフェンスをするのが私たちの仕事です。
コストを見直すにあたっても倉庫の拠点は適正なのか、また弊社の成長に伴い新しい倉庫を構えるのかといった視点は必要です。「ロジザードZERO」から取れる出荷履歴や納品場所などのデータを活用して、トンキロ(重量×輸送距離)を踏まえた上で、より近い距離で運ぶにはどこに倉庫の拠点を構えるのがいいかを模索しています。
WMSを導入する前と後で変わったこと
―― WMSは在庫数を把握・管理するだけでなく、販売戦略やコストの削減、業務の効率化にも役立つデータが取れるのですね。「ロジザードZERO」を導入する前は、どのようにデータを取っていたのでしょうか?
木村さん:「ロジザードZERO」を導入する前は、エクセルで管理していました。当時は物流のデータを活用するどころか、在庫を管理することさえ難しい状況でした。特にEC(BtoC)と卸(BtoB)で在庫を管理する必要があったのですが、在庫の貸し借りなどによって、今どれくらいの在庫があるのか正確に把握できなかったことが大変でした。
もともと自社で物流業務を行っていたのですが、会社が成長するにつれて、物流の戦略に力を入れることが重要であると判断し、一部の商品を3PL事業者様に委託することにしました。そのタイミングで、WMSを導入したのです。「ロジザードZERO」を選んだ理由は、シェア率が高く、3PL事業者様の間でよく利用されているため安心感があったからです。実際に導入してから今に至るまで、ロジザードの中澤さんにはいろいろと要望をご相談させていただきました。当時、私は物流のデータをどのように活用するか十分にわかっていなかったので、本当にありがたかったです。

中澤さん:「ロジザードZERO」を導入する当初は商品も少なく、スムージーがメインだと伺っていましたが、蓋を開けたら「BOTANIST」のシャンプーが非常に伸びていたことがわかったのです。
木村さん:WMSを導入する前はデータが取れなかったため、頭の中ではなんとなくわかっていても、数値として問題提起できませんでした。感覚でしか動けなかったのですが、今は「ロジザードZERO」から出したデータを加工することで、可視化することができるので、問題があったときに何が原因なのかすぐ答えられるようになりました。
また、業務報告を数字で出せるようになったことも大きいです。どれくらいのコストを削減できたか、ケアレスミスがなくなったかを、出せるようになりました。
会社が大きくなって、扱う商品の量が多くなり、いろいろな物流の課題が出てきました。また必要となる情報も増え、その都度、中澤さんに相談し、カスタマイズのお願いをしています。
WMSから基幹システムを軸にした運用へ
――「ロジザードZERO」で様々なカスタマイズを行ってきたとのことですが、一番大きなカスタマイズは何だったのでしょうか?
中澤さん:基幹システムの連携が開発のボリュームとして一番大きかったです。
木村さん:WMSは物流関連のデータを見ることはできますが、会計システムではないため財務関連のデータには特化していません。会社が大きくなるにつれて、在庫の総量(在庫在高)や原価などのデータをより正確に把握する必要があり、基幹システムを導入することに決めました。
その後、基幹システムを導入したのですが、想像以上に会社の成長が早かったため、当初、要件定義した基幹システムでは、会社として管理しなくてはいけないデータを閲覧できないことがわかりました。7割ぐらい基幹システムの導入が完了していましたが、途中で別の基幹システムにリプレイスしています。
中澤さん:今までWMSに合わせて現場を運用してきましたが、基幹システムのデータを軸にその運用を再構築する必要がありました。その際、「ロジザードZERO」のデータを基幹システムにつなぎこむのは大変でしたね。システムだけでなく、3PLの現場でも基幹システムに合わせて運用する必要があるため、現場になるべく負担がかからないように、どういった運用体制を構築するのが良いか考えました。
木村さん:中澤さんには物流の現場にも足を運んでいただき、3PLの事業者様と打ち合わせをしながら、一番スムーズにいくような形にしていただきました。

―― 最後に、今後取り組みたいことについて教えていただけないでしょうか?
木村さん:低コストでありながら高クオリティの物流を目指すことは、会社の利益を確保するうえで大事です。今後、SDGs(持続可能な開発目標)が物流にとって課題となってくるでしょう。特にコストの兼ね合いなど、バランスは難しいと思いますが、腹落ちするまでしっかり考え、会社としてどう取り組めばいいかを物流側から提案できればと思っております。
中澤さん:ロジザードとして、ロジスティクス課と3PL事業者様としっかりとコミュニケーションを取り、どんな課題があるのかを把握したうえで、最適な提案をしていきたいと思っています。そういった情報の共有がしやすい環境の構築は引き続き行っていきたいですね。また、提案する際は「ロジザードZERO」の標準機能を活かして、極力コストと工数をかけないようにしていきたいと思っています。
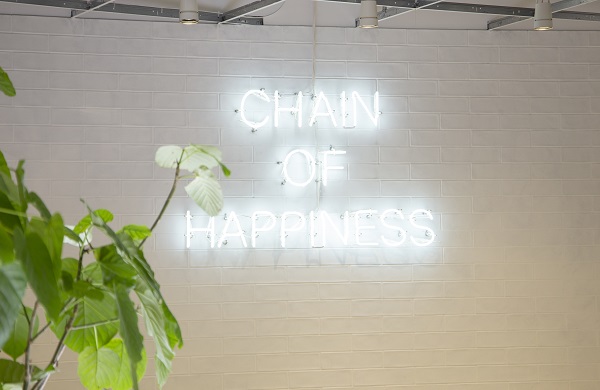
取材を通して:物流業務だけでなく他部署や前後の工程に意識することが重要
インタビューの中で、木村さんがお客様や卸問屋様のことはもちろん、販売部をはじめ他部署の動きを常に意識していることを感じました。物販において、物流業務の前後にはマーケティング戦略や商品到着後のお客様へのフォローなど、部署は違えど一連の流れがあります。ロジスティクス課が物流業務だけでなく、その前後の流れを理解し、スムーズに回るように考えているから、I-neはここまで躍進したのではないでしょうか。
木村さんは今ではI-neの物流責任者ですが、もともとアルバイトとして、梱包作業の仕事からスタートしたといいます。当時からそういった視座を持ってお仕事されたのでしょう。
物流業務の経験があまりない中で、ロジスティクス課を任された木村さんを、中澤さんはサポートしてきたそうです。7年の付き合いになるとのことで、ロジザードはI-neの初期から今までの成長を共にしてきました。今後もロジザードは、I-neの成長を裏で支えていくでしょう。
物流でお困りの事業者様は、ぜひしっかりサポートを行ってくれるロジザードに相談してみるといいと思います。
▼ ロジザード株式会社へのお問い合わせ先はこちら
https://www.logizard.co.jp/contact/
▼ 株式会社I-ne(アイエヌイー)のコーポレートサイトはこちら
https://i-ne.co.jp/
合わせて読みたい


















