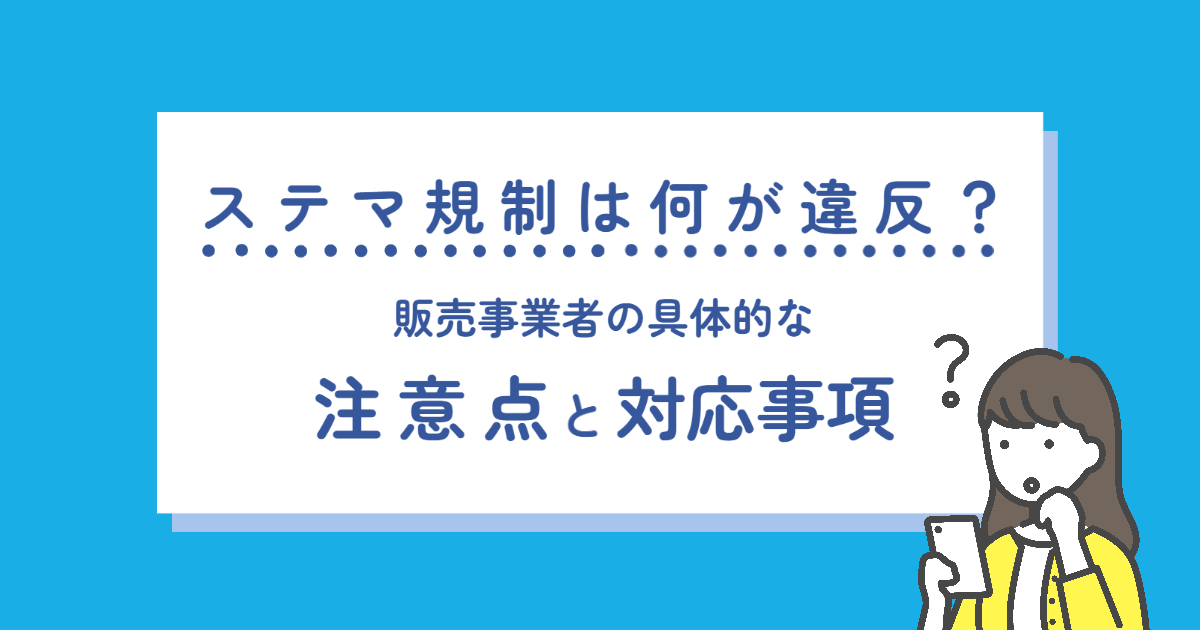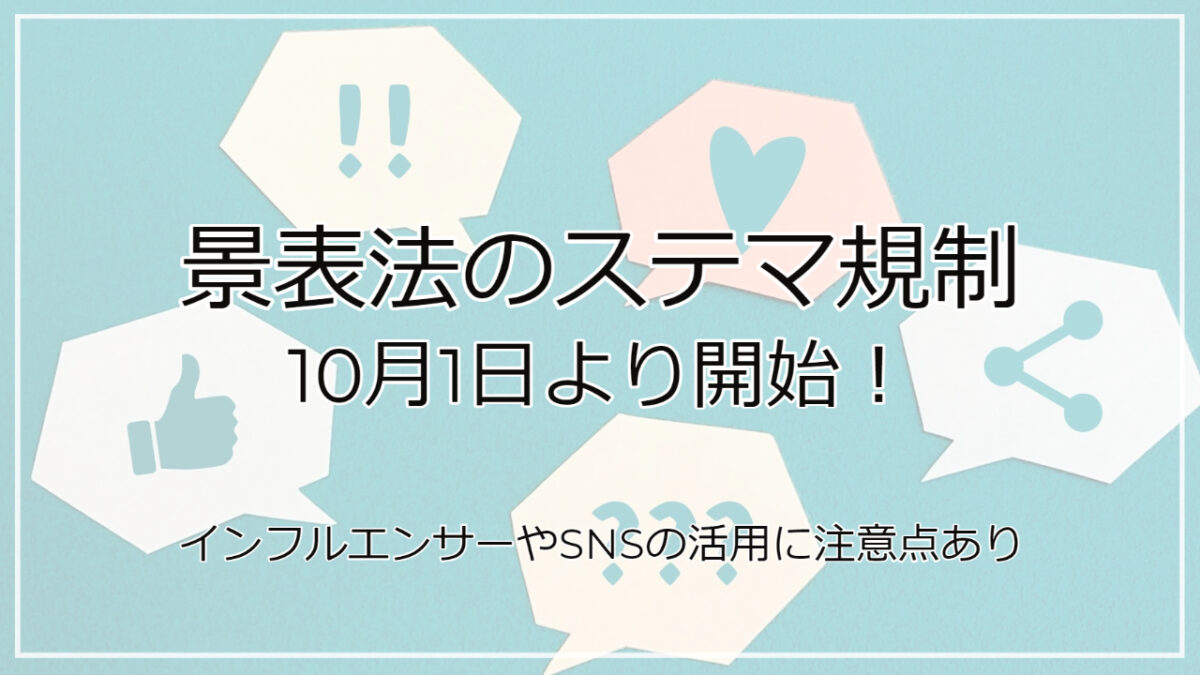
2023年10月1日から、景表法に基づき、ステルスマーケティングをはじめとした、事業者が第三者に依頼・指示を出して行う広告表示に対する規制が強化されます。これにより、商品・サービスの宣伝における著名人やインフルエンサーの起用、SNSやアフィリエイトサイトの活用、レビュー依頼などで、注意すべき点が増えます。本記事では、その内容をまとめた上で、特にEC事業者が注意すべき点についてまとめました。
この記事の目次
2023年10月1日から変わること
2023年3月28日、消費者庁より「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の指定及び「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」(以下、「指定告示」)が公表されました。
これは、景表法第5条第3号に基づくものです。「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を簡単にいうと、実際は広告なのに一般消費者には広告ではないように見える表示のことです。そういった表示を景表法の規制の対象とすること、そしてその規制の基準が定められました。
ステルスマーケティングは、まさにこの指定告示の対象となります。また、「自分たちはステルスマーケティングなんてしていないから大丈夫」という事業者でも、注意すべき点があるので、指定告示の内容は一度チェックしておくことをおすすめします。
ステルスマーケティングの基本的な知識はこちらからご覧ください。
▶ステルスマーケティング(ステマ)とは?違法性や注意点、インフルエンサーマーケとの違い
指定告示施行の背景
現在、大手SNSプラットフォームなどでは、ステルスマーケティングを防ぐために、広告案件は広告であることを明示して投稿することが一般的になっています。
たとえば、Twitterでは「#PR」「#広告」などで、その投稿が広告案件であることを示します。Instagramでは、広告案件であることを表示できる「タイアップ投稿」という機能が搭載されています。
そういったプラットフォームの機能やルール、業界ごとのルールでステルスマーケティングを規制する動きはすでにありましたが、実は今回の指定告示が出るまで、景表法でステルスマーケティングそのものを規制することはできませんでした。
ステルスマーケティングの投稿内容が景表法に違反していた場合、景表法に基づいた措置が取られることはありました。しかし、ステルスマーケティングを行うこと自体は景表法における禁止行為とはされていなかったのです。
しかし今回の指定告示により、景表法でステルスマーケティングを行うこと自体を規制できるようになりました。
なぜ、ステルスマーケティングは禁止されるのか?
景表法は、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ることを目的としています。
たとえば、SNSで著名人がある商品を紹介していたとします。そして、その紹介の経緯が、下記1の場合と2の場合とでは、商品について消費者が受ける印象は異なるはずです。
- 著名人がプライベートでその商品を気に入っていて、自主的に投稿を行った場合
- 著名人がその商品の販売事業者から宣伝の依頼を受けて仕事として投稿を行った場合
2のような広告投稿について、消費者は、基本的にその商品の良い点しか表示されていないということを踏まえて情報を受けとることが多いと思います。一方、1のような投稿は、2よりも感想や体感に信頼性があると感じられるのではないでしょうか。
このような違いがあるにも関わらず、実際は2のような経緯の投稿を1のように見える投稿をすることは、消費者がより良い商品を自主的かつ合理的に選ぶことを阻害しています。
このことから、景表法でステルスマーケティングを始めとした、実際は広告なのに一般消費者には広告ではないように見える表示が規制されることになりました。
EC事業者に必須の知識「景表法(景品表示法)」とは?
景表法とは「景品表示法」の略です。正式名称はさらに長く、「不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」という法律です。
景表法では、商品・サービスを提供する事業者に対して、次の2種類の規制を定めています。これらは、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ることを目的としています。
- 表示規制:商品やサービスの品質・内容・価格等を偽って表示する「不当表示」を禁止
- 景品規制:景品類の最高額・総額等を規制
今回の指定告示は、表示規制に関係します。表示規制には、大きく次の3種類があり、指定告示は3つ目の5条3号に基づいて定められています。
- 優良誤認表示(5条1号):商品・サービスの品質、規格その他の内容について、実際よりも著しく優良であると一般消費者に誤認させる表示
- 有利誤認表示(5条2号):商品・サービスの価格その他取引条件について、実際よりも著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示
- 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(5条3号)
景表法に違反すると、消費者庁より措置命令が出されます。措置命令では、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどが命じられます。場合によっては、課徴金の納付を命じられることもあるでしょう。
措置命令まで行かなくとも、景表法違反を指摘されると、違反していないことを証明する必要があるので、時間と人手が割かれます。そもそも違反の指摘をされないように、景表法を守った表示を行いましょう。
EC事業者が注意すべき指定告示の内容
指定告示の運用基準は、『「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準』(令和5年3月28日 消費者庁長官決定)に詳しく記載されています。ここでは、特にEC事業者が注意すべき点を解説します。
商品・サービスに関して第三者に何らかの表示を指示・依頼する場合
事業者が、商品・サービスに関する何らかの表示を第三者に指示・依頼して、その表示内容の決定に関わっている場合、それは事業者の表示であることを示す必要があります。
考えられる例としては、次のような商品・サービスに関する投稿・紹介で、その内容の決定に事業者が関わっているケースです。
- インフルエンサーやユーザーに依頼した、SNS・口コミサイトでの投稿
- 商品・サービスの購入者やブローカに依頼した、商品購入サイトでのレビュー投稿
- アフィリエイターに依頼した、アフィリエイトでの商品・サービスの紹介
- 他の事業者に依頼した、自社商品を競合商品より低く評価する口コミ投稿
重要なのは、こういった投稿・紹介そのものが事業者の表示(広告表示)と判断されるのではなく、その表示内容の決定に事業者が関わっているかどうかです。
たとえば、ユーザーによる自主的なSNS投稿やレビュー投稿は、当然ながら事業者の表示とは判断されません。レビュー投稿のお礼として割引クーポンなどを配布する場合でも、レビュー内容に事業者が関与していなければ、事業者の表示とはいえません。
ただし、事業者が表示内容を明確に指示・依頼しなくても、第三者が事業者の意向を汲んだ表示内容にせざるを得ないような状況があれば、広告表示と判断されます。
スタッフによる投稿にも注意が必要
事業者の従業員や関係者などで、商品の販売・開発に関わる立場の人が、商品の販売促進のために何らかの表示を行う場合も、事業者の表示と判断されます。
指定告示では、「事業者と一定の関係性を有し、事業者と一体と認められる従業員や、事業者の子会社等の従業員が行った事業者の商品又は役務に関する表示」と定められています。
事業者のサイトやアカウントで投稿を行う分には、消費者はそれを事業者の表示と判断できるので問題ありません。しかし、プライベートのSNSアカウント、あるいはそれを装ったアカウントなどで商品についての投稿を行う場合などは注意が必要です。
事業者の表示はそれとわかるように表示する
今回の指定告示で重要な点が、事業者の表示はそうわかるように表示することです。
自社のECサイトやSNSアカウントでの商品・サービスに関する表示は、消費者にとって事業者の表示であることは明確なので、わざわざ何かを追記する必要はありません。
SNSなどでの投稿を第三者に依頼する場合は、次のような表示を必ず行いましょう。
- 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言による表示
- 「A社から商品の提供を受けて投稿している」といった文章による表示
なお、Instagramでは、ハッシュタグによる広告表示はプラットフォーム側として非推奨といわれており、タイアップ投稿機能の利用をおすすめします。
また、たとえ事業者の表示であることを記載していても、それが消費者にとってわかりにくいものであれば、それは事業者の表示をしているとは判断されないので注意しましょう。
たとえば、次のようなケースが考えられます。
- 事業者の表示である旨について、部分的な表示しかしていない
- 「広告」と記載している一方で、「これは第三者として感想を記載しています。」といった記載があり、広告表示なのか否かがわかりにくい
- 動画において、認識できない短時間・認識しにくい箇所で、事業者の表示である旨を表示する
- 一般消費者にとって事業者の表示であることを認識できない文言を使用する
- 一般消費者が視認しにくい方法・位置で事業者の表示である旨を表示する
- 事業者の表示であることを他の情報に紛れ込ませる
最後の例でよく見られるのが、SNSで大量のハッシュタグの中に「#PR」などを紛れ込ませるケースです。これは、事業者の表示であることを表示しているとは認められない可能性が高いので注意しましょう。
【まとめ】SNSの活用に特に注意が必要
今回の指定告示が出された背景としては、ステルスマーケティングにより、消費者が商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境が脅かされていたことが大きいといえます。
景表法というとECサイトや広告の表現に注意することが多いですが、今回は特に、SNSで外部の人になんらかの投稿を依頼する場合に注意が必要です。
ステルスマーケティングをする気がなくとも、表示に関する不注意で、ステルスマーケティングのように見えてしまうということも起こり得ます。自社が指示・依頼する表示については、それを一般消費者が見たときに、事業者の表示とわかる状態になっているか、より意識するようにしましょう。
【参考】
消費者庁)「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の指定及び「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」の公表について
合わせて読みたい