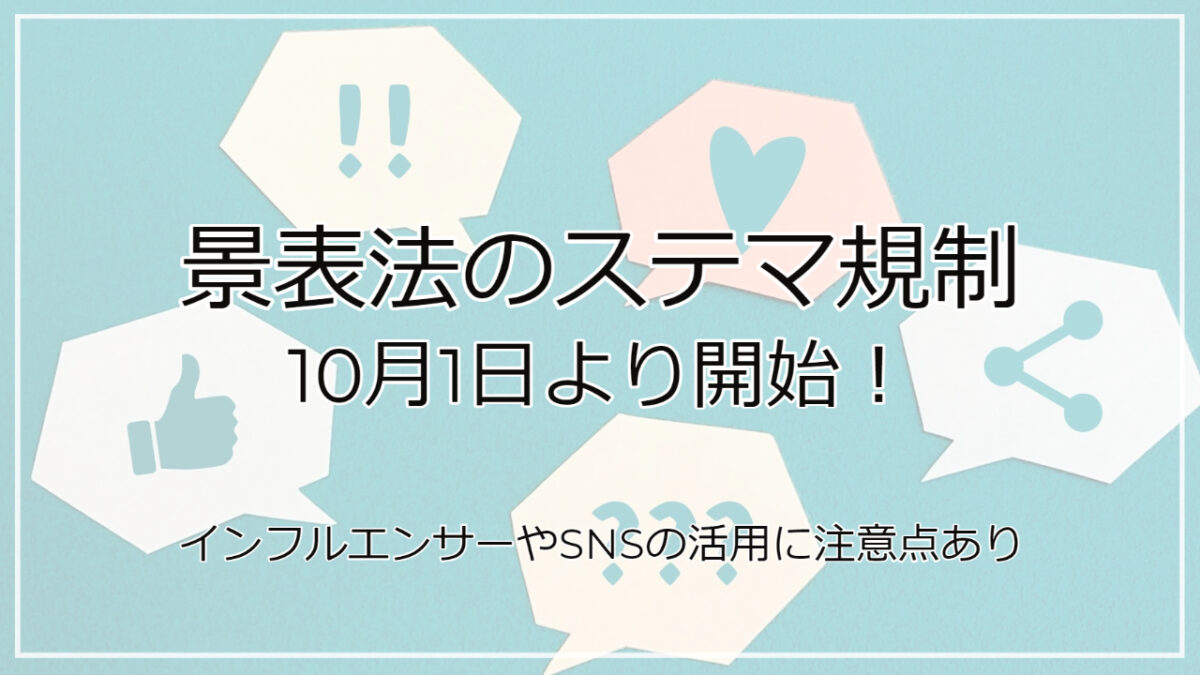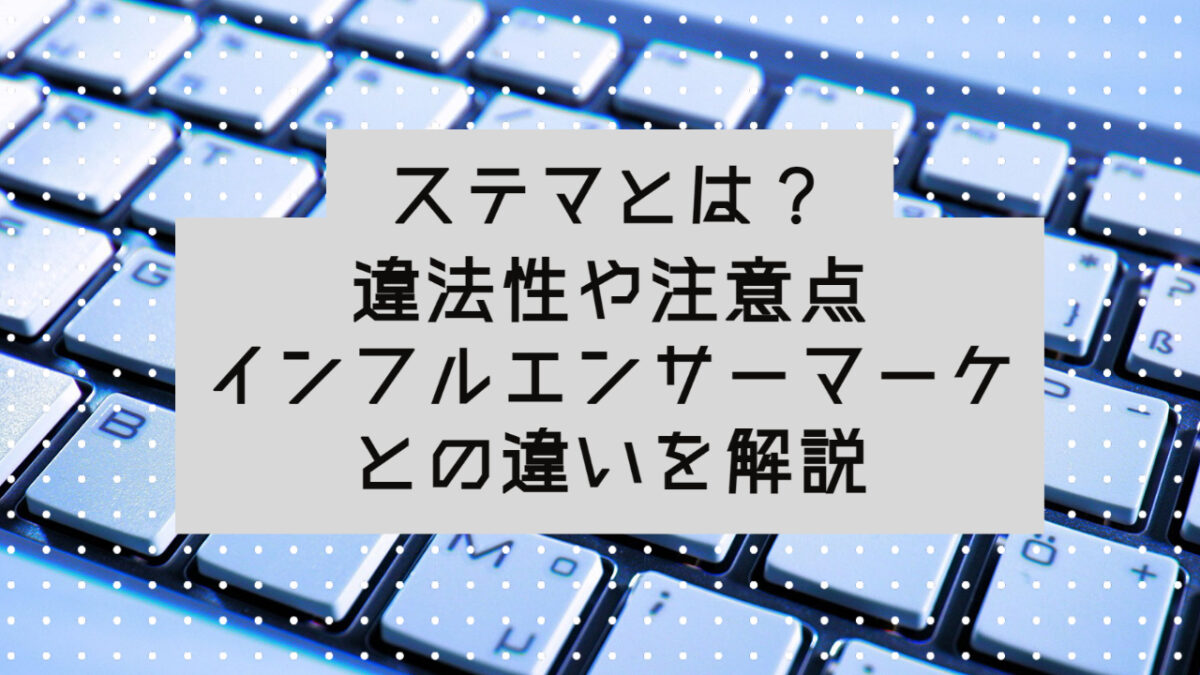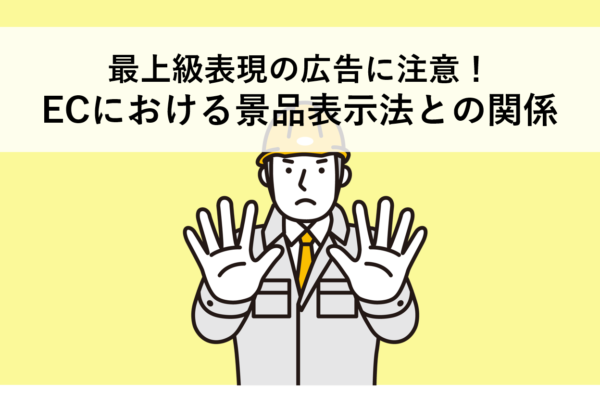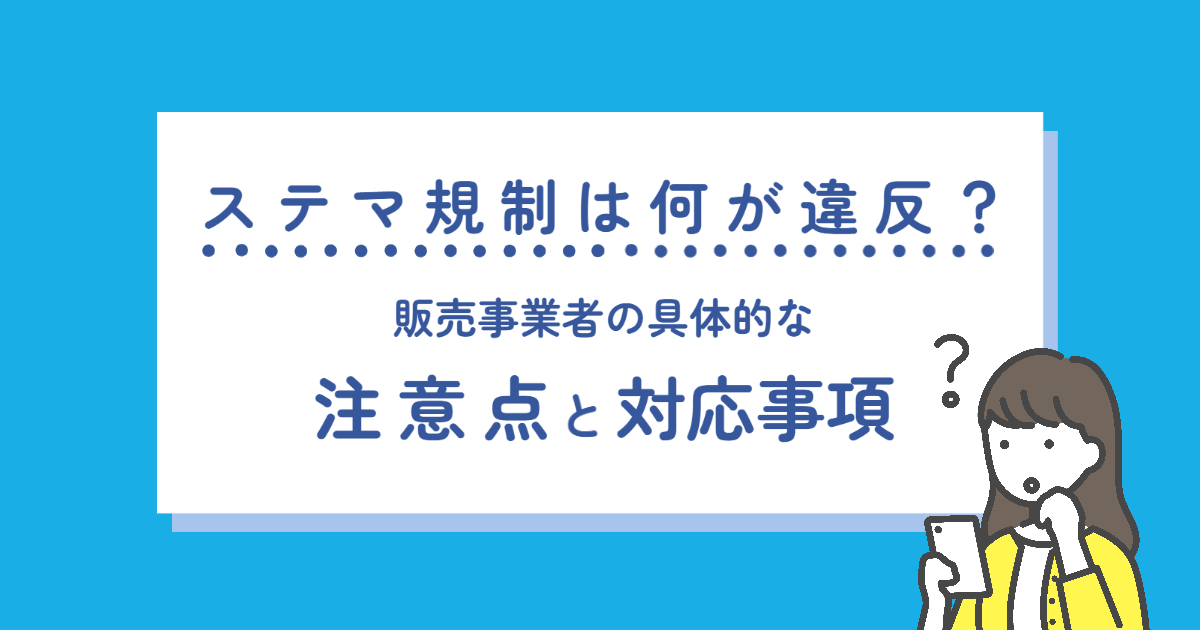
この記事の目次
2023年10月からステマ規制がスタート、販売事業者はどう対応すべきか?
消費者庁は2023年10月1日から、「ステルスマーケティング(ステマ)」の取り締まりに乗り出します。ステマは、販売事業者の広告であることを伏せて、インフルエンサーや著名人、消費者が商品を評価していると見せかける手法。ステマが横行すると、消費者の適切な商品選択を歪めてしまいます。このため、消費者庁は景品表示法の指定告示にステマを追加し、違反者に同法に基づく措置命令を出せるようにしました。
告示では、ステマを「事業者の表示である」「事業者の表示であることが消費者にわかりにくい」の2要件を満たすことと定義しています。
「表示内容の決定」に関与したかが焦点に
これだけでは、販売事業者はどのような場合にステマに該当するのかが判断できません。そこで、消費者庁は「運用基準」を定めています。
運用基準によると、「事業者の表示である」と判断するには、販売事業者が「表示内容の決定」に関与したかどうかがポイントとなります。販売事業者がインフルエンサーなどに対して、表示してほしい内容を指示した場合は「事業者の表示」に該当します。
次に、「事業者の表示であることが消費者にわかりにくい」とは、広告である旨が小さな文字で書かれている場合や、アフィリエイト広告に「広告」と明記していない場合などです。
一方、ステマに該当しないケースには、どのようなものがあるのでしょうか?
例えば、不特定多数の消費者にサンプルを提供したり、単にプレゼントをしたりして、もらった人が自分の意思で投稿する場合はステマに該当しません。
ECサイトで商品を購入した消費者がレビュー投稿するケースも、ステマではありません。また、キャンペーンや懸賞に応募するために、消費者が自分の意思でSNSに表示することも同様です。
事業者が注意すべき4つのポイント
ここからは、事業者が注意すべきポイントを見ていきましょう。
1点目として、事業者は自社やグループ会社の社員を管理する必要があります。
特に販売促進部門や営業部門の従業員が、売上のノルマを達成しようと、消費者のふりをしてSNS上で自社製品を高く評価したり、口コミサイトにライバル製品の悪口を投稿したりすると、ステマに該当します。
2点目として、インフルエンサーを活用する際には、細心の注意が求められます。
インフルエンサーに商品を無料で提供し、SNS上の表示を依頼したというだけでは、ステマに該当しません。問題となるのは、インフルエンサーが自分の意思で表示したかどうか、つまり事業者が表示内容を指示したかどうかです。
インフルエンサーに無料で商品を提供する際に、「SNSに感想を投稿するかどうかは自由」と明記したとしても、それだけでステマではないと主張できません。ステマかどうかは、具体的なやり取りや過去の関係性なども踏まえて、個別事案ごとに国が調査して判断します。
また、事業者からインフルエンサーに対し、投稿の依頼も、表示内容の指示もなかったとしても、高額商品を提供した場合にはステマの疑いが生じる可能性があります。
3点目は、ECサイトで商品を購入した消費者によるレビュー投稿です。
前述したとおり、購入者のレビュー投稿の内容に事業者が関与すると、ステマに該当します。しかし、購入者が自分の意思で投稿したものの、その内容に重大な問題が含まれていれば、販売事業者はどうすればよいのでしょうか?
例えば、健康食品を購入した消費者による「インフルエンザを予防できる」という投稿や、他人を差別するような投稿が行われたとします。その場合、購入者に投稿内容の修正を求めた(事業者が表示内容に関与した)としても、ステマに該当しません。むしろ、コンプライアンスの観点から、不適切な投稿には修正・削除を求める必要があります。
4点目は、雑誌・新聞などのメディアへの記事掲載です。
メディアが自ら企画・編集して商品を紹介したり、特集を組んだりすることは、何の問題も発生しません。ただし、記事を掲載してもらう販売事業者が、記事内容を事前にチェックしたり、修正を求めたりすると話が違ってきます。そうしたケースでは、個別事案ごとに国が調査し、ステマに該当するかどうかを判断します。
日本・EUのステマ規制の共通点と相違点
欧米では早くからステマを取り締まってきました。EUと米国のステマ規制の概要を紹介します。
EUでは「不公正取引方法指令2005」が取引全般を規制し、取引時だけでなく、その前後も含めて幅広く取り締まっています。これがもっとも大きい“網”となります。
その次に大きな“網”として、不公正な取引方法である「誤認を招く取引方法」と「攻撃的な取引方法」を禁止しています。
さらに、細かな“網”として、不正な取引方法を「ブラック・リスト」で具体的に示しているのです。
ブラック・リストでは、
(1)有償でメディアに掲載したにもかかわらず、広告であることを明らかにしていない
(2)有料のランキング広告であることを明示せずに、上位に検索された結果を表示
(3)商品の宣伝を目的に、虚偽の消費者によるレビューを投稿
――などの5項目を例示しています。
このようにEUでは、主に3段階でステマを幅広く規制しています。これは、脱法的な手口を塞ぐためですが、日本のステマ規制も包括的であり、考え方はEUと似ているでしょう。
また、EUでは「デジタルサービス法」によって、デジタルプラットフォーム運営事業者に対し、プラットフォーム上の広告を規制しています。具体的には、「提供された情報が広告であると明記すること」「広告主名を明記すること」「広告費を支払った者が広告主でない場合には、支払った者の名称を明記すること」としています。
これに対して日本のステマ規制は、デジタルプラットフォーム運営事業者を取り締まることができません。この点はEUの規制と比べて緩いと言えるでしょう。
米国はインフルエンサーも規制
米国は「連邦取引委員会法」によってステマを規制しています。同法は「不公正または欺瞞的な行為」を違法としているのです。
ステマなどに特化した「ニュースとしての形態を有する広告に関する勧告的意見」では、広告・プロモーションを行う場合、広告と判別できるようにしなければならないと規定しています。
さらに、「広告における推奨及び証言の利用に関する指針」により、商品を推奨する場合、推奨者の正直な意見を反映しなければならないとし、明示的であっても暗示的であっても欺瞞的な行為を禁止しているのです。広告主に対しては、推奨を通じて虚偽の説明を行った場合や、推奨者との関係を開示しなかった場合に責任を負うとし、推奨者も責任を負うことがあると定めています。
一方、日本のステマ規制は、商品を推奨したインフルエンサーなどを直接規制できません。この点は米国よりも緩いと言えるでしょう。
販売事業者がすぐに対応すべきこと
最後に、販売事業者がすぐに対応しなければならない点を説明します。
2023年10月1日以降、ステマを放置しておくと取り締まりの対象となります。このため、販売事業者には、まず自社商品に関する投稿・レビューなどの総点検が求められます。
次に、周知期間中にステマが疑われる表示を修正したり、削除したりしなければなりません。ただし、SNSに投稿したインフルエンサーなどに修正を依頼しようとしたものの、連絡がつかず、事業者側の努力ではどうしようもない場合は例外となり、規制を受けません。
アフィリエイト広告についてもステマの疑いがある場合には、修正や削除が必要です。アフィリエイト広告はその仕組みを考えると、ほとんどが「事業者の表示」に該当することから、原則として「広告」であると明記する必要があります。
「HAZS SERVICE」のステルスマーケティング対策
HAZS(株)は、通販企業様に向けて「ステルスマーケティング対策」のサービスを提供しています。
<こんな方にオススメ>
- 景品表示法の「ステマ」規制が施行される前に、既存の広告・表示を点検したい。
- 気づかずに「ステマ」を行っているかもしれない、という不安がある。
- SNS上で第三者が自社製品を紹介しているが、ステマに該当するかどうか判断できない。
- 企業コンプライアンスを向上させる観点から、念のためチェックしておきたい。
※詳細はコチラ:「HAZS SERVICE」のステルスマーケティング対策
合わせて読みたい