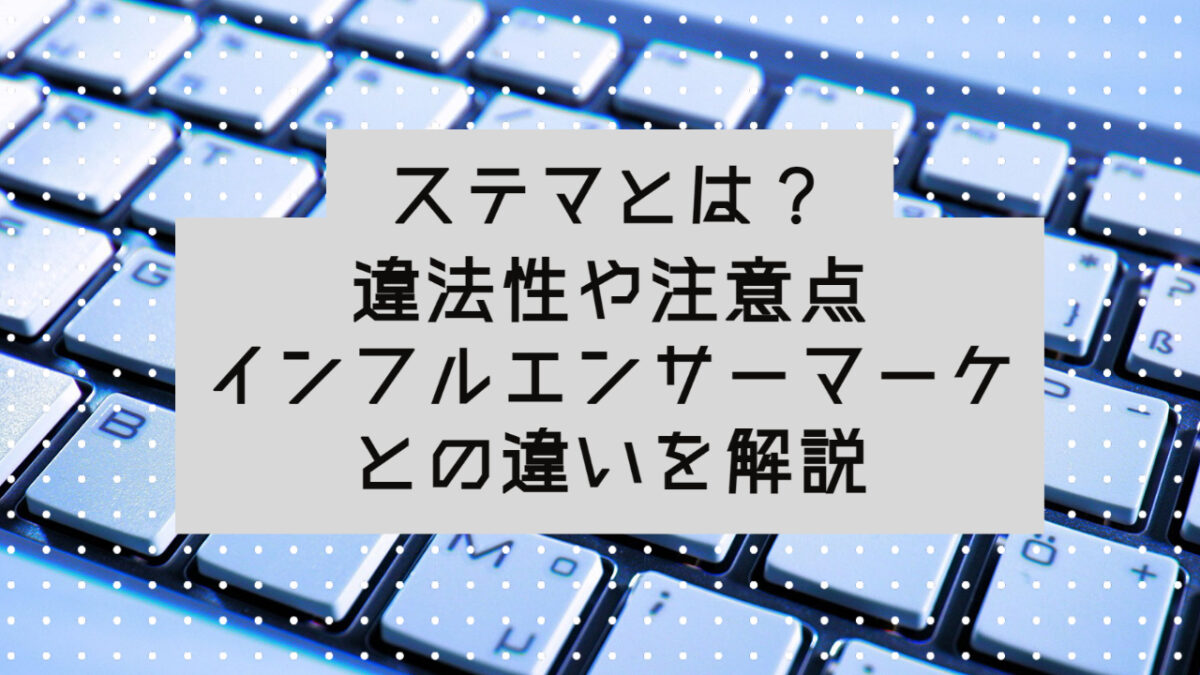
この記事の目次
ステルスマーケティング(ステマ)とは
ステルスマーケティングは大きく2種類に分けられます。1つは、「広告であることが明記されずに、消費者に対して第三者(インフルエンサーやアフィリエイター、購入者など)が商品やサービスを宣伝する」ことです。
広告主である事業者が宣伝の依頼をしていながら、依頼主が商品の宣伝を自然発生によるものかのように誤認させ、消費者に広告であることを認識させないことを指すと考えれば良いでしょう。
もう1つは、事業者が自ら商品について発信しているにもかかわらず、第三者が発信しているかのように誤認させるものをいいます。
なお、不当な表示による不利益から消費者を守るルールとして「景品表示法」がありますが、優良誤認表示や有利誤認表示を伴わない場合、日本ではステルスマーケティングにおける景品表示法の規制はないのが現状です。
しかし、規制はなくともステルスマーケティングに対する消費者の見方は厳しいものがあります。ステルスマーケティングであることが発覚した場合には、商品やサービスのイメージ悪化、SNSでの炎上リスクなどがあり、このような取り組みは避けるべきでしょう。
インフルエンサーマーケティングとの違い
インフルエンサーマーケティングとは、SNSを中心に影響力を持つ「インフルエンサー」に商品やサービスを紹介してもらい、消費者の興味・関心を引いたり、検索や購入などの消費行動を促したりするマーケティング手法のことをいいます。
事業者から消費者向けに配信する商品・サービス情報に比べて、共感しやすく訴求力が高いマーケティング手法の1つとして注目されています。
インフルエンサーに費用を払って、商品やサービスを紹介してもらうこと自体には問題はありませんが、事業者からの依頼による投稿であることを隠すと、ステルスマーケティングにあたります。
インフルエンサーが自ら紹介しているように見えた場合のほうが、効果が得やすいように感じますが、ステルスマーケティングだと判明した場合には、かえってブランドイメージの毀損を招く可能性があります。
ステルスマーケティングが与える影響
ステルスマーケティングを行うと次のような問題があります。
商品や事業者に対する信頼感が低下する
ステルスマーケティングは消費者を欺いて商品やサービスを紹介しています。ステルスマーケティングが発覚した場合には、不快感や不信感を受ける消費者が少なくありません。
依頼した事業者や、情報発信を行ったインフルエンサーの信頼感が低下してしまうことでしょう。一度ステルスマーケティングが発覚すると、その他の商品・サービス紹介についても、ステルスマーケティングなのではないか?と疑いの目が向けられることになり、失われた信頼を取り戻すには長い時間が必要になってしまいます。
炎上リスクがある
ステルスマーケティングが発覚した場合には、SNSなどで消費者から強い非難を浴び、炎上してしまうケースも想定されます。広告を依頼したインフルエンサーに対して攻撃的な投稿をされ、商品やサービスそのものを否定するような投稿をされてしまうことも考えられます。
事業者の注意点
ステルスマーケティングにならないために、広告配信時には次の2点を意識する必要があります。
広告表記をはっきりする
インフルエンサーマーケティングや謝礼を用意した口コミを活用する際には、広告であることを明確に表記する必要があります。小さく表記するだけにとどまらず、誰が見ても広告だと認識できるよう明確に表記しておくことで、消費者に信頼感を与えることができます。SNSによってはハッシュタグが用意されている場合もあるので、活用するといいでしょう。
消費者に誤解を与えるコンテンツを作らない
購入者など第三者による声を活用する際は注意が必要です。例えば、商品LPに第三者のレビューを掲載する際、事業者によって作成された架空の声を掲載することは景表法に抵触する可能性があります。また、事業者による依頼で投稿された広告表記がされていないコンテンツを利用することも同様に、リスクがあるといえるでしょう。
ステルスマーケティングの動向
実際に問題となったステルスマーケティングの事例をご紹介します。
ECサイトの口コミを報酬付きで募る
ECサイトにおいては口コミや評価の数値が売上に大きな影響を与えると言われています。そこで高評価の口コミを投稿した購入者に対して謝礼を支払うことで、口コミの数を増やす事業者が発生しています。
購入者向けに口コミを依頼する報酬(次回使えるクーポンの提供など)は多く見られる手法ですが、高評価の口コミを必ず投稿することを前提に報酬を付与するのはステルスマーケティングにあたるでしょう。
インフルエンサーに「広告表記をしない」などの指示を出す
事業者がインフルエンサーに、広告であることを伏せて投稿するよう依頼するケースがあります。これに対し、インフルエンサーは報酬を受け取っているから従わなければならないと感じたり、今後の依頼が減ってしまう懸念から受け入れてしまったりしている状況があります。
インフルエンサーの知識不足
事業者から広告表記に関する指示がない場合などでは、インフルエンサーの知識不足により、広告表記をせずに投稿を行っていることもあります。双方に悪意のないまま、ステルスマーケティングを行ってしまうことになるので、事業者が依頼する際に、広告表記についても伝える必要があるでしょう。
まとめ
ステルスマーケティングについてご紹介しました。口コミやインフルエンサーを活用する際には、知識不足や配慮不足により、意図せずステルスマーケティングを行ってしまうケースも発生しています。ステルスマーケティングによって得られる成果以上に、発覚した際の損失は大きなものになりかねません。ステルスマーケティング自体は目新しい事例ではありませんが、改めてリスク管理を見直してみてはいかがでしょうか。
参考:ステルスマーケティングに関する実態調査
参考:現役のインフルエンサーに対するアンケート結果
合わせて読みたい

















