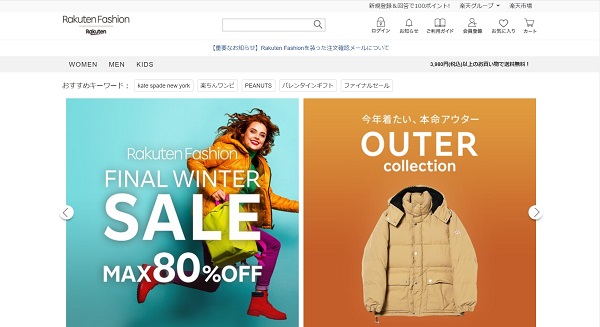環境省は2021年4月に「SUSTAINABLE FASION これからのファッションを持続可能に」という、「サステナブルファッション」に関するレポートを発表しました。このレポートには、ファッション産業の環境負荷とその対策がまとめられています。本記事では、特にファッション・アパレルに携わっている事業者様が押さえておきたいポイントをまとめました。
この記事の目次
サステナブルファッションとは?
「サステナブル(Sustainable)」とは「持続可能な」という意味であり、サステナブルファッションは、「衣服の生産から着用、廃棄に至るプロセスにおいて将来にわたり持続可能であることを目指し、生態系を含む地球環境や関わる人・社会に配慮した取り組み」のことをいいます。
この取り組みは環境省が推進しており、簡単にいうと、環境負荷の大きいファッション産業のシステムを変えようというものです。環境省では、2020年12月〜2021年3月に、日本で消費される衣服と環境負荷に関する調査を実施しました。2021年4月に発表されたレポートは、この調査結果が基になっています。
ファッション産業の環境負荷
環境省のレポートを基に、ファッション産業の環境負荷について大きくまとめると、次のような問題点があります。
ファッション産業全体の問題

日本の小売市場で売られているファッション製品の約98%が海外からの輸入品です。他の業界でも輸入品は珍しくありませんが、ファッション産業の場合、ひとつの製品にいろいろな素材が混合されており、生産が海外の複数の拠点で分業されています。そのため、環境負荷の実態や全容の把握が難しく、環境負荷低減を試みても効果が見えにくい問題があります。
製造時の環境負荷の問題
ファッション産業の商品製造時の環境負荷に焦点を当てると、原材料がコットンなどの天然繊維の場合は、栽培時の水消費や化学肥料による土壌汚染。原材料が合成繊維の場合は、石油資源の使用や工場でのCO2排出が問題となっています。環境省のレポートでは、原材料調達から製造段階までに排出される環境負荷の総量(年間)を服1着あたりに換算すると、以下のように算出されています。
・CO2排出量:約25.5kg=ペットボトル(500ml)約255本製造分
・水消費量:約2,300リットル=浴槽約11杯分
※2019年時点における服の国内供給量約35.5億着をもとに算出
このように、製造時から大きな環境負荷が発生しているのです。
国内アパレル市場の問題
ファッション産業の環境負荷について、製造段階だけでなく、販売のあり方についても問題視されています。環境省のレポートにおいて、1990年~2020年にかけての国内アパレル供給量・市場規模*1と衣服一枚あたりの価格推移*2を見ると、供給数が増加する一方で市場規模は縮小、衣服一枚あたりの価格も下がっています。

左図:1 経済産業省「生産動態統計」、財務省「貿易統計」、矢野経済研究所「繊維白書」より
右図:2 総務省「家計調査」より
つまり、ファッション産業は昔に比べ、安価な商品が大量生産されるようになっていることがわかります。このことは、衣服の製造・販売・購入から使わなくなるまでのライフサイクルの短期化につながり、サイクルが短くなることで大量廃棄につながることが懸念されています。
衣服を手放しても、古着としての販売、譲渡・寄付などでの再利用、資源回収など、廃棄しない方法もあります。しかし、それらの方法は手間や費用がかかる場合もあることから、手放した衣服の66%が処分・埋め立てされていることが、環境省のレポートからわかります。
環境負荷を下げるための企業の取り組み
前述のようなファッション産業の環境負荷を低減するために、環境省のレポートでは、消費者側・企業側がそれぞれできる取り組みが紹介されています。ここでは、企業側の取り組みについて、どのようなことができるのかを考えてみます。
長く着られる商品づくりとサービス
衣服一枚あたりの価格が下がり、安価な商品が大量生産されることが当たり前になっていると、短いライフサイクルで消費されることを前提とした商品が増えていきます。たとえば、長く着ようと思っても素材や作りが弱くてすぐに傷んでしまったり、流行ものばかりで次のシーズンには着にくかったりという商品です。

ファッション産業の環境負荷を下げるためには、まず、そもそもの商品を、長く利用する前提で作ることが必要です。同時に、そういった商品の価値を消費者にわかってもらう、感じてもらうことも必要です。これは、ファッション産業全体の問題で、一事業者だけでは難しいことですが、長く着られることの付加価値を訴求するのは、事業者側でも取り組めることのひとつです。
また、衣服を長く着てもらうために、お直しや修理(リペア)などのサービスを提供することも効果的です。商品のライフサイクルが長くなると、企業側にとっては、新しい商品がなかなか売れないという問題があるのですが、お直しや修理(リペア)などのサービスを提供することで、企業側としても新たな売上を確保する手段となります。
再利用(リユース)商品・サービスの取り扱い
企業側にとっての衣服の再利用(リユース)というと、古着販売がすぐに思い浮かびますが、それ以外に最近注目されているのが、サブスクリプション制の衣服のレンタルサービスです。ユーザーの属性や好みなどを基に定期的に服を届け、気に入ったら購入もできるといったサービスが登場しています。消費者は新しい服を次々と楽しむことができ、企業は商品を長く活かしつつ売上も上げることができる、サステナブルファッションにも相性が良いサービスといえます。
また、アパレル市場で存在感を増しているのが、フリマアプリによるCtoC取引です。フリマアプリにおいてファッションアイテムは人気の高いカテゴリーであり、衣服の再利用を促進する場にもなっています。
在庫管理と販売サイクルの見直し
売れ残る商品を減らすことも、ファッション産業の環境負荷低減につながります。売れ残る商品があることは、その分、使われない商品を製造するために環境負荷が発生していることになります。また、廃棄処分になれば、そこでも環境負荷が発生します。
売れ残りが少なくなることは、企業にとっても製造や在庫管理のコストを低減することになるはずです。EC業界においては、在庫管理システムや物流システムの発達により、季節変動や顧客の行動、受注状況などのデータを活用することで、適切な発注ができる仕組みも作りやすくなっています。
また、事前予約販売やアウトレットを行うことも、余剰在庫を減らす効果的な方法です。これらの方法は、余分な在庫を持たずに済み、環境負荷を低減するだけでなく、商品の販促や店舗の集客にもつながります。
さらに、根本的に商品の販売サイクルを見直すことができると、環境負荷低減に大きな一歩となります。ファッション産業では、シーズンごとに新商品が販売され、シーズン終了前にセールなどで在庫を放出、前シーズンの商品は値下げするパターンが一般的です。これは、商品の大量生産・大量消費を生み出しやすい販売サイクルといえるでしょう。
すべてを変えることは難しいでしょうが、シーズンにとらわれない販売や、セールに頼らない販売を取り入れることができれば、環境負荷低減にもなりますし、企業にとっても安定した売り上げを得ることにつながります。
商品の製造段階を把握する

食品産業においては浸透しているトレーサビリティの確保を、ファッション産業でも行うことも、環境負荷を減らすために重要なことです。環境省のレポートによると、消費者の約5人に1人が「環境に関する情報を、商品購入時に分かるようにしてほしい」と感じているという調査結果があります。
トレーサビリティの確保は、そういった消費者にとって付加価値となります。特に、ファッションブランドはそういった情報を訴求しやすい強みがあります。サステナブルファッションに関心の高い消費者に顧客になってもらえれば、商品の製造段階や販売サイクルについても、より環境負荷の少ない選択をしやすくなります。
なお、ファッション産業のトレーサビリティを判断する基準として、オーガニックテキスタイル世界基準(GOTS)や「国際フェアトレード認証コットンラベル」などのいくつかの国際認証やラベルがあります。これらは、環境省HP「環境ラベル等データベース」にて公開されています。
また、同じように付加価値を出す方法として「アップサイクル」があります。「リサイクル」は商品の再利用を意味しますが、アップサイクルはただ商品を再利用するだけではなく、付加価値をつけて商品をアッグレードすることを意味します。アパレルにおいては、たとえば、衣服の染めなおしや仕立てなおしなどがあげられます。
アップサイクルされた商品は、サステナブルファッションに関心の高い消費者はもちろん、そういったことを知らない消費者にも魅力的に映りやすく、サステナブルファッションを知る入口にもなり得ます。
顧客が手放した服の再利用
冒頭でも紹介した通り、日本のファッション産業においては、手放した衣服の66%が処分・埋め立てされているというデータがあります。これら処分・埋め立てに回される衣類の量を減らし、リユース、リサイクル、資源回収に回すことができれば、ファッション産業の環境負荷を低減することになります。
処分・埋め立てされる衣服の多くは、消費者が可燃・不燃ごみとして出したものです。環境省のレポートによると、消費者が衣服を可燃・不燃ごみとして廃棄する理由の75%が、「処理に手間や労力、費用がかからないから」となっています。サステナブルファッションを啓蒙するだけでなく、消費者にとって手間や労力、費用がかからない衣服回収の仕組みを提供できれば、処分・埋め立てに回る衣服を減らせる可能性があります。
アパレル企業のなかには、店頭や消費者の生活圏内に古着回収場所を設置するなどして、消費者に手間や労力、費用をかけずにいらなくなった衣服を回収する取り組みを行っているところもあります。直接的には企業の利益になりませんが、衣服を安易に捨てない仕組みをつくることは、長期的にファッション産業全体のメリットとなることであり、そういったことに積極的な企業という姿勢を見せることにもなります。
ファッションブランドがサステナブルファッションに取り組むべき理由

サステナブルファッションは、短期的には企業の売上や利益にはなりにくい取り組みです。しかし、アパレル市場を長期的に成長させていくには、着手しなければならない取り組みとも考えられます。
なぜなら、大量生産した商品を安価に販売する方法は、どこかで限界が来る可能性が高いからです。海外の市場も急速に成長しているなかで、これまでとは違った道の開拓が必要になります。
ファッションに限らず、「サステナブル=持続可能」なことは、さまざまな分野で世界的に注目されているテーマです。「SDGs」という言葉を最近耳にすることもあるのではないでしょうか。SDGsは「Sustainable Development Goals」の略称で、「持続可能な開発目標」を意味します。2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載されており、2030年までに目指す国際目標です。17の目標から構成され、そのひとつに「目標12 持続可能な消費と生産」という目標があります。
▼ 参考情報
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html
また、サステナブルファッションは、環境省が進める「2050年カーボンニュートラル」の取り組みのなかでも取り上げられることがあります。カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、脱炭素社会のことです。「2050年カーボンニュートラル」は、2020年10月26日、第203回臨時国会の所信表明演説において、菅総理大臣により宣言されました。ファッション産業においても、商品が製造・販売されてから購入・使用後に手放されるまで、多くの温室効果ガスが排出されています。
▼ 参考情報
https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/about/
このように、サステナブルファッションは、単にファッション産業だけの動きだけでなく、世界的な環境への取り組みに関係しています。そのため、アパレル業界においても、長期的な指針を考えるときに、無視できないものといえます。
合わせて読みたい