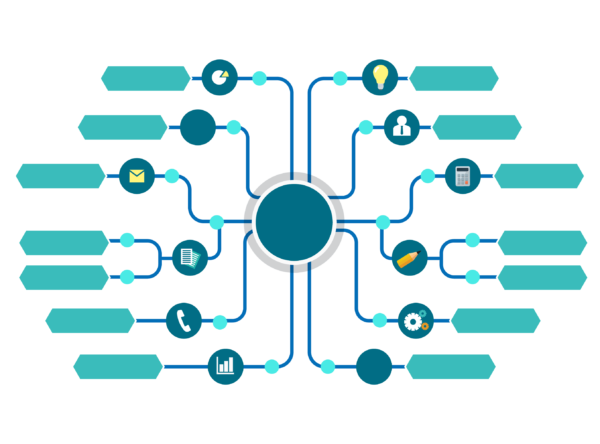この記事の目次
ユニファイドコマースとは?
ユニファイドコマース(Unified Commerce)は直訳すると「統合された商取引」となり、消費者にあらゆるチャネルで統合された顧客体験を提供するための仕組みのことをいいます。
オムニチャネル化が進展し、在庫データと顧客データの統合が進んでいくなかで、1つのブランドを購入する場合でも、実店舗やECサイト、アプリなどのさまざまなチャネルを組み合わせて利用する人が増えています。販売チャネルに捉われずに購買活動ができるようになり利便性は高まる一方で、顧客体験という点には注力されていませんでした。
そこで、オムニチャネルで進められた在庫データと顧客データの統合に加え、顧客の行動履歴をも統合することで、顧客体験をさらに向上させようという取り組みがユニファイドコマースです。
ユニファイドコマースが注目される背景
ユニファイドコマースが注目される背景をご紹介します。
顧客の情報接点や、購入チャネルの多様化
企業の発信の多くがマスメディアに限られていた頃には、多くの消費者が新聞・雑誌・ラジオ・テレビなどで得た情報を頼りに商品の購入を決断し、店舗に出向いて購入する動きを取っていました。購入動機に違いはあれど、きっかけは企業が意図した発信によるもので、その動きは予測しやすかったといえます。
最近ではECサイトやSNSの利用が進み、購入方法の選択肢が増えたのはもちろんのこと、消費者が購入判断に活用する情報も多様化が進みました。企業が自ら発信する情報に加え、他の消費者が投稿したレビューや口コミにも手軽に触れられるようになったのです。
これに伴い消費者の情報収集活動や購入動機、購入場所は多様化し、すべての顧客に一律で仕掛けるマーケティングでは、期待する効果を得にくくなってきました。そこで購買体験にまで目を向けて取り組むユニファイドコマースに注目が集まるようになっています。
広告費の増加によるリピーターの重要性の高まり
ECサイトそのものの数の増加に加え、企業がWeb広告に当てる予算の割合を増やす傾向にあることから、新規顧客の獲得単価は増加しています。そういった理由から既存顧客に繰り返し購入するリピーターになってもらう施策に注目が集まっているのです。
ユニファイドコマースでは、実店舗とECサイトなどのチャネルを超えて顧客行動を追跡するため、より快適な顧客体験を提供し、将来的な再購入につなげることができます。例えば実店舗で店員から商品の説明を受け、その場では購入に至らなかったものの、後日届いたメルマガやDMなどを見て購入を決断し、ECサイトで購入するといったような行動を促すことができます。
ユニファイドコマースを取り入れるべき理由
これまで取り組まれてきた広告やマーケティング活動は、ターゲットとなる顧客のペルソナを設計し、そのペルソナに向けた施策を実施するのが一般的でした。ユニファイドコマースでは、自社の保有する顧客データを活用し、一人ひとりの行動に基づいたOne to Oneマーケティングができるようになります。
顧客のニーズを的確に捉えることができるため、広告費を抑えることができるほか、質の高い体験を得たことで、ブランドへの愛着が強まりリピーターを獲得することにもつながります。
オムニチャネルなど近い概念との違い
ユニファイドコマースと近しい概念を持つ言葉がいくつかありますので、それぞれご紹介します。ユニファイドコマースは「オムニチャネル」と「One to Oneマーケティング」を組み合わせたマーケティング手法と考えることもできるでしょう。
オムニチャネルとの違い
オムニチャネルはすべての販売チャネルを統合することで、販売機会の損失を防ごうとするマーケティング手法です。実店舗とECサイトの在庫データを連携することで、例えばどちらかで在庫切れを起こしたとしても、もう一方の在庫を購入できるため、販売機会を逃すことなく運営できます。
オムニチャネルには顧客の行動データを統合し、顧客体験を追求するというところまでは至っていません。この点がユニファイドコマースとの違いです。
One to Oneマーケティングとの違い
One to Oneマーケティングは、顧客一人ひとりの購買行動からニーズを汲み取り、個々に合わせたコミュニケーションを行うマーケティング手法です。One to Oneマーケティングはユニファイドコマースの一部ということもできます。
OMOとの違い
OMOは「Online Merges with Offline」の省略で、「オンラインとオフラインの統合」という意味を持ちます。基本的な概念はユニファイドコマースと似ていますが、目的が異なり、OMOでは売上の向上を、ユニファイドコマースでは顧客体験の向上を目指す点が異なります。
ユニファイドコマース導入の課題
顧客体験を高めることができるユニファイドコマースですが、導入にあたっては課題もあります。導入を始める前に確認しておきましょう。
データ統合がうまくできない
ユニファイドコマースの成功の鍵を握るのは各データの統合です。在庫や購入履歴の統合はもちろんのこと、店舗での接客内容やメルマガ、DMの活用状況なども把握しなければなりません。
しかし実店舗やECサイト、メルマガ配信ツールなどそれぞれを別々に導入して利用を進めてきた企業は多く、一言でデータ統合といっても、データの持ち方が異なる、表記ゆれなどで名寄せが上手くいかないなど、データ統合に課題を抱えてユニファイドコマースの導入が進まないケースがあります。まずは自社のデータ統合がどのように進められるのか、実施にあたって必要になる費用などを把握するところから始めると良いでしょう。
顧客セグメントがうまくできない
データ連携が上手くできればユニファイドコマースの土台は整ったことになります。次は顧客のニーズに合わせたマーケティング施策の実施が必要ですが、One to Oneマーケティングといっても顧客一人ひとりの行動を分析して施策を行っていてはとても運用が追いつきません。近いニーズを持つ顧客をセグメントし施策を打つことになりますが、この顧客セグメントがうまくいかないケースも見受けられます。
顧客の特性に合う商品がない
適切な顧客セグメントができたものの、顧客の特性に合う商品がなく提案ができないケースも想定されます。顧客セグメントに合わせて商品ラインナップを拡充できると良いですが、なかなかそうもいかない場合が多いことでしょう。
既存商品の使い方をアレンジしたり、デザインを変更するなどして顧客セグメントに合わせた提案ができると良いでしょう。
ユニファイドコマース導入の手順
ユニファイドコマースを導入するにあたっては、大きく次の3つのステップを経る必要があります。
- オムニチャネル化を実施する
- 顧客データの集積と分析を行う
- パーソナライズ施策を実行する
オムニチャネルの実装にあたっては、現在使用しているシステムの改修が課題になる場合が多くあります。オムニチャネルの実装後はスタッフのオペレーション改善を行い、店舗とECの連携を活かせるよう意識改革も必要になります。
オムニチャネル化がうまくいけば顧客の行動履歴を集積、分析を行うことで、パーソナライズ施策の具体案が見えてくることでしょう。
おわりに
オンラインとオフラインのチャネルを統合し、さらに顧客の行動履歴に合わせたパーソナライズ施策を実施するユニファイドコマースをご紹介しました。オムニチャネル化の実施には障壁も多く、導入しているシステム環境によっては統合の負荷が大きくなってしまうことも考えられます。しかし顧客の行動が多様化している状況では、売上伸長にあたってユニファイドコマースが果たす役割は大きく、避けては通れない課題となります。導入時期や導入方法の検討は早期に進めておくべきといえるでしょう。
最近ではOne to Oneマーケティングを実施する上で、AIの活用が増えています。データ基盤とチャネルの連携が実現した後、具体的な施策や顧客セグメントの切り分けなどAIに業務を任せる時代が来るかもしれませんね。
合わせて読みたい