
前回のコラムでは、「D2Cブランドの新しい収益源としてのリコマース・再販」というテーマでお話しさせていただきました。今回は、「顧客がリコマース・再販売に期待していること」について見ていきます。
この記事の目次
リコマースのメリット
リコマースのメリットについて、顧客視点とブランド視点に分けて考えてみます。特に顧客視点のメリットを訴求することで、結果としてブランドの収益構造に寄与することを確認することが大切です。
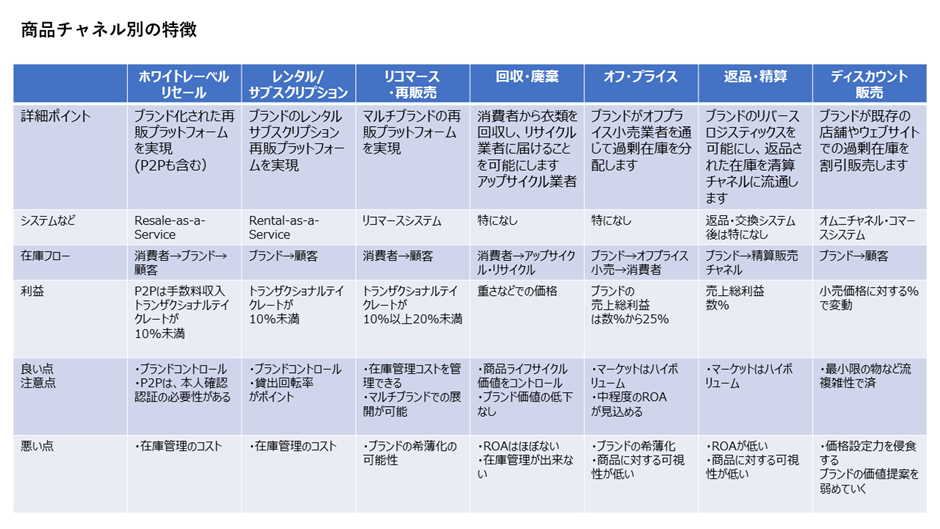
顧客ロイヤルティの向上
顧客視点
クローゼットなどのアイテムを現金化できる
これは、AppleやGoogleなどのスマートフォンや自動車などでは一般的な消費行動です。今保有しているアイテムを下取りに出すことで、新しく購入したい新商品の支払いの一部に充当することで支出を減らしたように感じることができます。
実質のレンタル・サブスクモデルに
上記の消費行動は、シーズンが変わる前に早めに手放してブランドの別の商品へ有償交換するなど、アパレル・ファッションにも当てはまるでしょう。
これはレンタル・サブスクモデルで商品を利用して気に入ったら購入する体験と比較しても同様の購入体験として機能します。
環境に配慮した消費ができる
在庫品や返品・交換品を購入することで、リサイクルや再利用による環境への貢献につながります。また、サステナブルな消費への意識を高め、自分の行動が社会に与える影響を考えるきっかけにもなるでしょう。
ブランド視点
カスタマーエンゲージメントの向上
消費者へのインセンティブを自社で現金に換金するより、自社のストアクレジット(Appleアカウントや、ZARAバーチャルギフトカードなど)に変換することで、価格を上乗せするなどの施策でエンゲージメントを高める施策が提供できます。と同時に、ストアクレジットを活用することで、再購入の可能性を拡げていくことが可能です。
これを、ロイヤルティプログラムと組み合わせることでより顧客とのコミュニケーションを通じてデータを取得し、再購入への可能性を高めることができます。
ブランドイメージの構築
在庫品や返品・交換品を活用することで、リサイクルや再利用による環境への貢献をアピールすることができます。これは、サステナビリティへの意識が高まる中で、顧客からの信頼や好感度を高め、ブランドイメージを向上させる効果が見込めるでしょう。
顧客コンバージョンとリテンションコストの削減
顧客視点
お得に購入できる
在庫品や返品・交換品は、新品商品に比べて最適価格(一般的には低価格)で購入できるため、お得感を味わうことができます。また、新品商品とは異なる魅力を訴求することで、新たな商品との出会いを楽しめるでしょう。
メルカリなどの、P2P(Peer to Peer:※)マーケットプレイスでの購入には不安があるオーディエンス層などへの安心と信頼の購入体験とサービスを提供することができます。
※P2P:顧客間よりも強固な個人間の繋がり
ブランド視点
顧客層の拡大
在庫品や返品・交換品は、新品商品に比べて低価格で販売できるため、価格重視の顧客層の獲得につながります。
既存の顧客に対しての、優待販売、予約販売、通常販売、ダイナミックプライシング、ディスカウントプライシング(セールなど)での販売の通知をメールや、LINE、SNSのダイレクトメッセージやSNSポストを通じて、顧客別のパーソナルページやアプリに誘導することは有効的な施策でしょう。
それ以外の、まだ初回の購入に至っていないオーディエンスで価格に対して敏感な層や、ブランドへのトライユースをしてみたいオーディエンス層の購買プラットフォームを提供できることになります。
これは、いままでメルカリなどのP2Pチャネルで解決されていたニーズを自社コマースサイトで安心して購入できるようになることでもあります。
また、サステナブルな消費への意識の高い顧客層の獲得にも効果的かもしれません。サステナブルなどの社会的課題は、これだけでは顧客は購入してくれないものです。あまりマーケティング的には訴求しないことも重要です。場合によってはグリーンウォッシュとも判断されます。
売上の安定化・増加と新たな収益源の創出
顧客がいて、売上になり、そして利益として反映されていきます。今まで収益に貢献できていなかった商品在庫を収益化するためのアクションの選択肢が拡がることになります。
これまでは”0”のマーケット領域でしたので、新たな売上だけではなく、運用コストをコントロールできれば、利益源の創出にもつながります。
他のマーケティング施策との統合がポイント
ブランドが自社で実施するのであれば、オムニチャネル・OMO施策に最大限活用・影響がでるように、マーケティングプログラムや、コミュニケーションプログラムとの連携・統合は必要になってきます。
このメリットがデザインできないままに、損失を減らすために、ディスカウント率を減らすためだけに、別のチャネルを増やすだけでは、アウトレットストアーがデジタルで1つ増えただけになるでしょう。
同時に同じような失敗として、売上予算優先で、そのための商品を積み上げて、ROA(Return On Assets:総資産利益率)が低下するなどの轍を踏むことになります。 また、回収時に顧客情報を取得しておくことで、リアル店舗顧客で取得できていなかった顧客データを得ることができるため、リピーター獲得にもつながるでしょう。
合わせて読みたい

【資料ダウンロード】.jpg)














