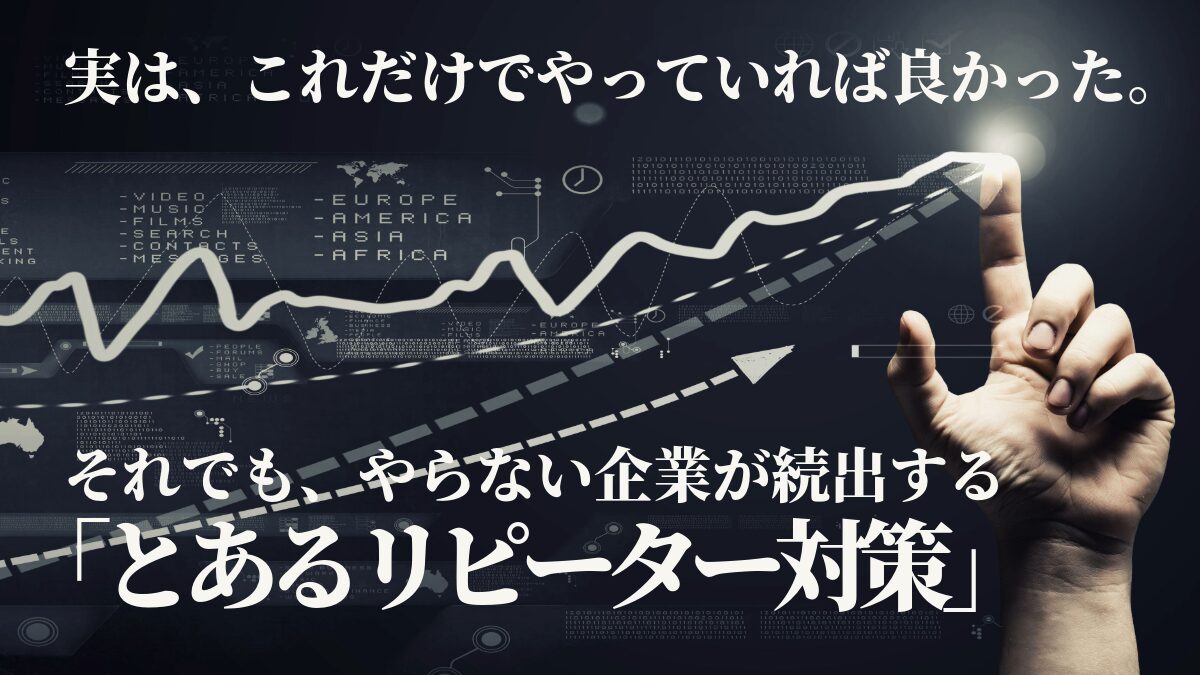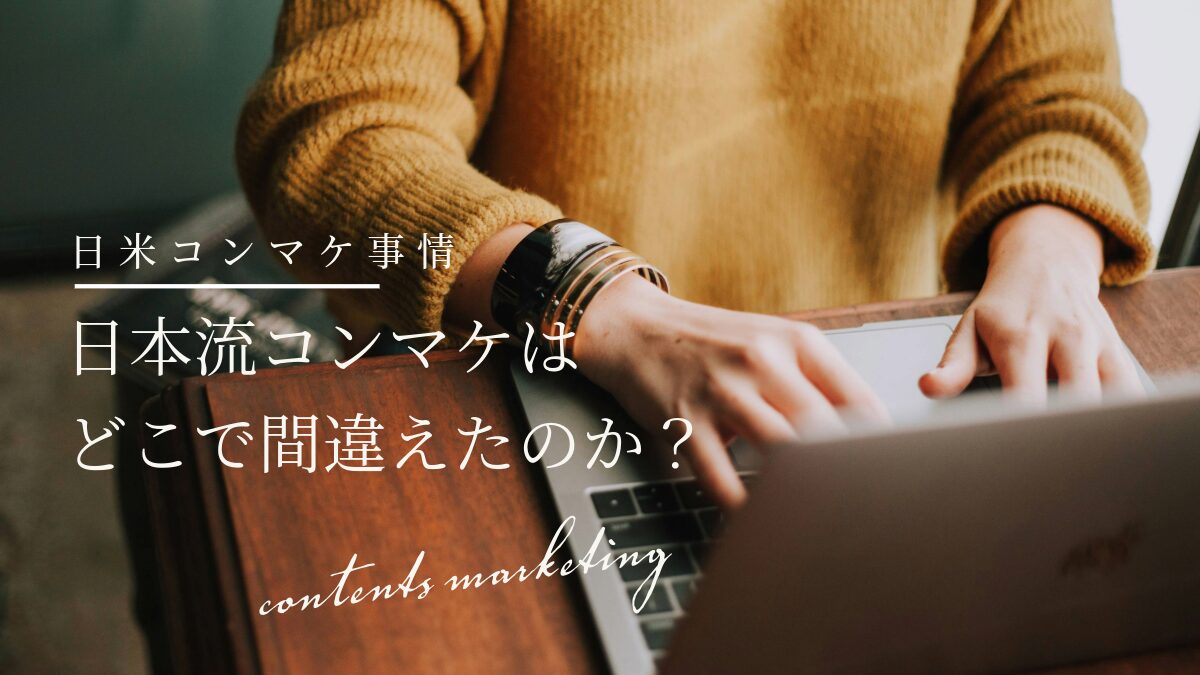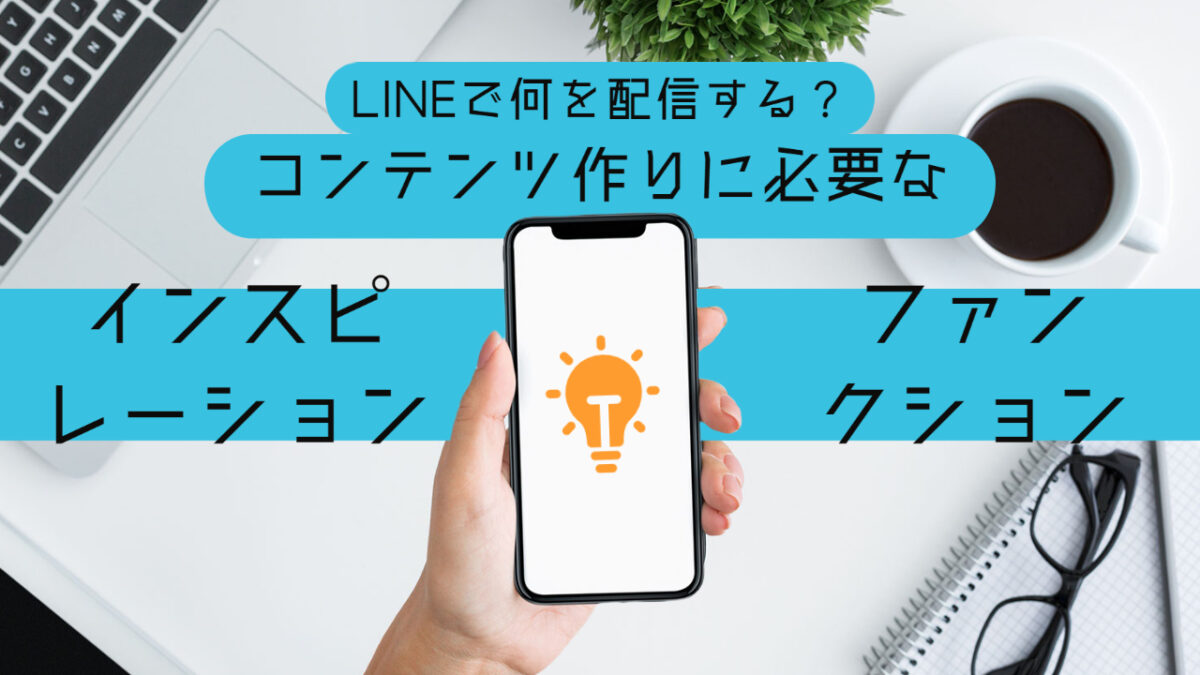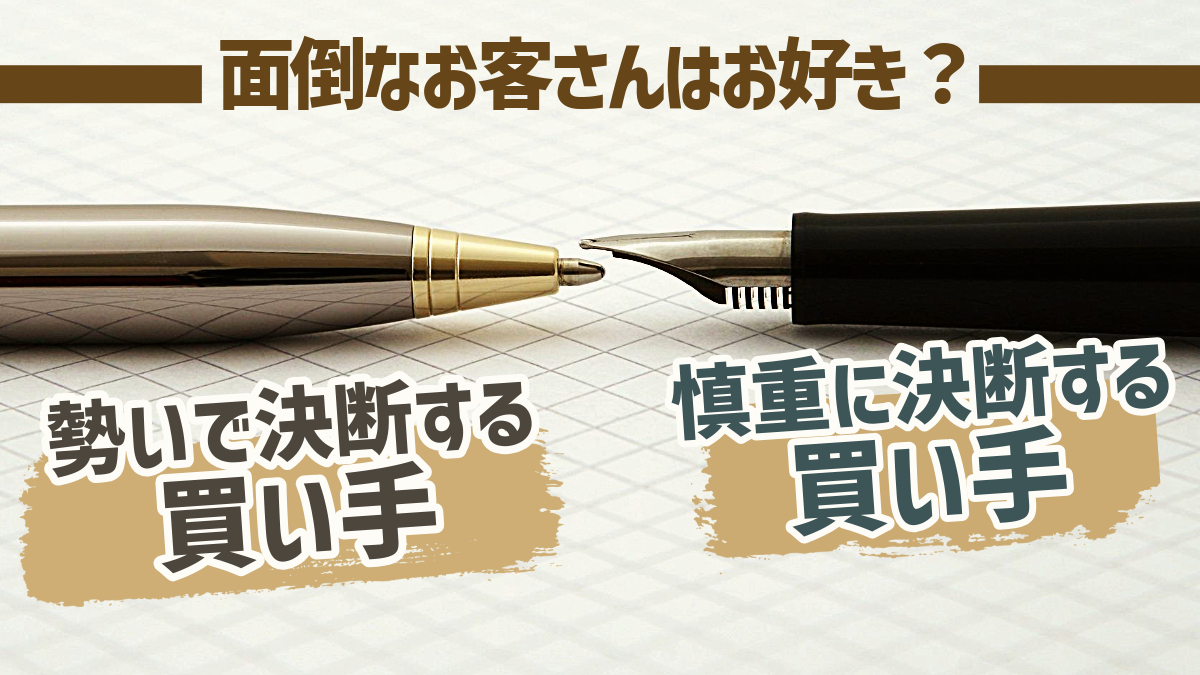
質問が多い、細かい違いを聞いてくる、何度も聞いてくる、やたらと競合製品に詳しい、などなど。いわゆる「ちょっと面倒なお客さん」を大切にしていますか?
面倒なお客さんにチャンスあり?
実は、常連さんづくりにおいては面倒なお客さんほど注力したほうが良いお客様なのです。
スマホでググれば、自社の競合製品が次から次へと表示されるこの時代。購入するモノが、商品であってもサービスであっても、比較検討は買い手にとって当たり前の時代です。
「ひとめぼれで買ってしまった!」というような経験は、旅先などの非日常体験を除けば、今後ますますレアな体験になってくるのかもしれません。
競合製品を隅から隅まで調べ上げて、時間をかけてたっぷり比較してから購入する。モノを売るのが難しい時代になった…。昭和・平成世代の経営者の声が聞こえてきそうです。
ところが、悪いことばかりじゃありません。購入前に綿密な比較検討をする買い手にこそ、自社製品の常連さんになっていただくチャンスは大きいのです。面倒なお客さんこそチャンスあり!なのです。
まずは、その理由を解説し、つづけて、常連さんづくりの一手としておすすめのアイデアについて話します。
買い手は、大きく分けると2つのタイプがいる
A)商品購入までに多くの時間をかけない、勢いで決断する買い手
B)商品購入までに時間をかけて比較検討、慎重に決断する買い手
具体的な行動イメージで言うと、
Aは、広告をクリックしてLPなどに訪れたら、あまり時間をかけず、躊躇なく購入するような人です。LPの来訪回数はそう多くなくとも、初回購入に引き上げられている買い手グループです。
新規獲得の数字を毎月追いかけている担当者にとって、実にありがたい買い手グループかもしれません(笑)
つづいて、Bの買い手。こちらは、Aと対照的に購入までに要する時間(日数)かなり長いタイプです。
例えば、最近多くの企業が取り組み始めているLPからの離脱時にポップアップを出して、自社のメルマガやLINE公式アカウントなどに誘導するような囲い込み施策。囲い込み後は何度も販促メールが届くわけですが、これも効果薄。
こちらの買い手は、マイペースに自分の基準で購入判断を冷静に下す傾向を持つため、セールス系の情報への反応も薄いのです。売り込んだら速攻ブロックしているLINEユーザーにも、Bの買い手が多く含まれていると思います。
ただ、こちらが忘れた頃にやってきて購入に至っているといったこともあります。購入決断までの検討に多くの時間をかけている冷静な買い手なのです。
もちろん、サイト改善などが不十分でCVされないこともあるので、必ずしも買い手の性質だけで言いきれることではないのですが、サイト改善後でも、変わらずCVまでに時間を要す顧客がいるならば、それがBの買い手です。
すぐ購入するAよりも、なかなか購入しないBのほうが、常連さんになりやすい。この現象に疑問を感じる方のために少し具体的に説明をいたします(腑に落ちている人は、次の章まで飛ばしちゃってください)。
Bの買い手は、論理的で一貫性のある行動を期待できる
AとBを比較したとき、Bの買い手は、Aよりも多くの情報を精査して購入してくれたグループです。つまり、当人なりに確かな根拠を持って購入した論理的な考え方の持ち主。それゆえに、将来的にも根拠を重視した一貫性のある購買行動をとることが期待されます。
私は、このような買い手こそ良質な顧客=常連さんになっていただける可能性が高いと考えていて、注力顧客として設定すべきと伝えています。
Bの買い手から一度信頼感を得ることができれば、彼らは簡単に浮気したりしません。なぜなら、時間をかけて悩んだ末の自分の決断であり、その決断を肯定する傾向があるのです。すぐに別の商品にスイッチするようなことは、自分の決断を否定することに等しいのです。人間誰しも自分の行動を肯定したい気持ちはありますよね。
一方で、新規獲得では歓迎したくなるAの買い手。こちらは、常連さんづくりという視点では、実に難攻不落です。
Aの買い手は、商品購入までに多くの時間をかけず、勢いで決断していました。このタイプ、購入の決め手を自分の中で明確化できていないことが多い傾向があります。なんとなく勢いのまま買ってしまえるということは、根拠はそれほど重視していないということです。
常連づくりの最初の一手として重要なのはリピート促進ですよね。このリピート促進や定期購入への誘導には、買い手が期待しているポイントをしっかり訴求する必要があります。「期待しているポイント=自社製品の特徴」であるときに自社を選んでくれるということです。
例えば、化粧品であれば、有効成分を多く配合しているといったような訴求ポイントがありますが、それが買い手の根拠になってくれば、繰り返し購入する行動につながります。
ただ、このような根拠が、情報を受け取る側が論理的でないと効果も期待できません。根拠よりも、雰囲気や気分で購入してしまった顧客が、突然根拠を重視することはありません。
また通販ですと、初回は低価格で2回目以降は通常価格といった施策は多く見受けます。このときに、割安感だけで商品をよく吟味せずに飛び付いて購入する買い手もAの買い手です。
初回から2回目に引き上がらないときは、勢いで飛びつく顧客ばかりになっている可能性もあります。勢いで買えちゃうタイプは、勢いで浮気しちゃうということを忘れないでください。
では、ここからは面倒な買い手を常連さんに導く施策の中で、低コストに取り組めるLINEの施策をご紹介したいと思います。
あえて売り込まないという施策
まずこの施策を行う上で必要なのは、リターゲティング広告以外の接点で、Bの買い手とつながることです。
つながっていないとBに対してアクションを起こすことができません。ツールとしてはB2Cの商材はLINEが良いでしょう。B2Bであれはメールが効果的です。
次にBの買い手とどこでつながるかですが、私は、LP上もしくは、LPから離脱するタイミングをおすすめしたいと思います。
ここで、疑問もあると思います。LPにはAの買い手もたくさん訪れているじゃないか!という疑問です。
そうです。LPには、AとBの両方の買い手が訪れますので、 Bの買い手だけを絞り込むのは不可能なんです。なので、ここではAもBも決めずにまとめて接点を作ります。そして、ここまでは一部の企業でも行なっていることが多い施策だと思います。
肝心なのは、この後です。結論は、売り売りしない。以上です。
「え!じゃあAが買ってくれないじゃん!」
そんな声が聞こえてきそうですが、それでも売り込みません。理由は、Aの買い手もBの買い手と同じ施策で十分だからです。
A専用に何かを行う必要はありません。勝手に衝動的に購入します。おそらくリターゲティング広告でLPに再来訪したときに購入してくれるでしょう。もしくは、これから行うB向けの施策にも反応が得られるはずです。
つづいて、売り売りしない代わりにしなければいけないことです。それは、Bに対して購入判断につながる材料を提供し続けることです。Bの買い手は、しっかり自分の目と耳で判断して決断したい。Bが必要としているものは、その判断に必要な情報です。しかも自社製品の情報だけではなく、その商品ジャンル全てにおいて何が最適な選択肢なのか、その判断をするために必要な確かな情報なのです。
それは、いわばBにとっての仕事です。その仕事を手伝ってあげることがBにできる最善の取り組みです。加えてこの取り組みには初回購入に導くこと以上に意味があります。
それは、Bの仕事を手伝うことを通じた信頼関係です。これは、購入時だけでなく、購入後にも活かされるものです。ともすると、お試しではなく、最初から定期購入プランに入ってくれる可能性もあります。
LINEアカウント運用している企業さんは、ぜひ一度このような取り組みにチャレンジしてみてください。最初は自社製品の情報ばかりを送ってしまうかもしれませんが、できれば、自社製品を取り巻く市場まで視野を広げた情報提供がおすすめです。
常連さんというのは、商品やサービスに納得しています。買い手が納得するためには、材料が必要なのです。
常連さんづくりのアイデアやヒントをYouTubeで配信しています。皆さんのビジネスに応用できる裏技も紹介していますので、ご視聴やチャンネル登録してみてください。
【COMAKIマーケティングチャンネル】
www.youtube.com/@comakichannelbysundsdiginc9679
■リピート対策に関する質問はTwitterにてお答えします
Twitter:@COMAKI2014
■LINEで始める、毎月1万円からの常連さんづくり〜COMAKI
URL:https://comaki.sunds.jp/comaki_lp/
合わせて読みたい