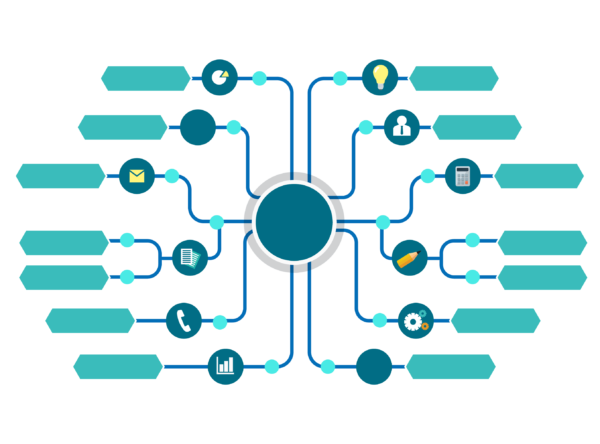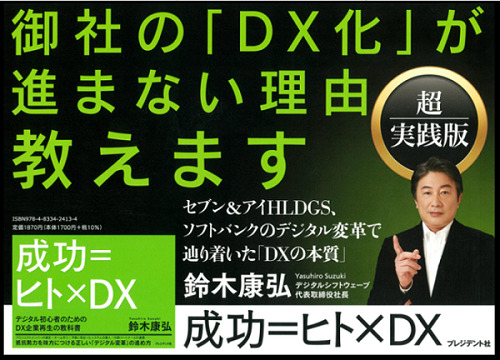
元セブン&アイHLDGSやソフトバンクでDX推進を第一線で実践していた鈴木康弘さんが「成功=ヒト×DX――デジタル初心者のためのDX企業変革の教科書」という書籍を発売しました。書籍の出版を記念して、企業の「DX化」が進まない理由を公開するウェビナーが行われましたが、当日参加できなかった方も多いと思いますので、コマースピック編集部でまとめさせていただきました。皆さんの参考になれば幸いです。
【登壇者】
株式会社デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長
一般社団法人日本オムニチャネル協会会長
鈴木 康弘さん
【モデレーター】
株式会社CaTラボ代表取締役
一般社団法人日本オムニチャネル協会理事
オムニチャネルコンサルタント
逸見 光次郎さん
この記事の目次
DXとはなにか?その本質と現状
経済産業省のDX推進ガイドラインによって定義されているDXとは
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」
といわれています。要するに、DXとは「デジタルによって仕事や生活が変革されること」であると鈴木さんは話します。
歴史の中で農業革命から産業革命、そして今は情報革命へと、技術の発展にともない革命が起きてきました。今まさに情報革命の真っ只中にいる上で起きているデジタルシフトは「既存のアナログ業務をデジタル化すること」であり、デジタル変革と称されるDXの中の一つの要素に過ぎません。デジタルシフトの一例として、流通業界におけるアマゾン・エフェクトや金融業界におけるフィンテック・エフェクトが挙げられています。しかし、デジタル変革(DX)とは、デジタルシフトにとどまらず、既存のビジネスを変革させていくことなのです。
「メディアによって『デジタル化』や『DX(デジタルトランスフォーメーション)』という言葉がはやし立てられ、DXを取り組まない企業は取り残されてしまうような風潮が生まれました。そうして、火に油を注ぐように、コンサル会社やシステム会社、広告代理店、人材紹介会社など、DXブームに乗って、様々な提案を始めた結果、あくまでデジタル化を目的とした『DXバブル』となってしまいました。そして、デジタル化を推進した企業の9割を超える企業が暗礁に乗り上げてしまっています」と鈴木さんは話します。
なぜ日本企業のDXが上手くいっていないのか
DXに取り組む企業が増えたものの、それに合わせて暗礁に乗り上げる企業が増加しています。ありがちな上手くいかないケースとして下記の5つが挙げられます。
- 経営者は掛け声ばかりで、全く進まない。
- 専任部門を設置しても、ノウハウ不足で停滞。
- マーケ部門は盛り上がるが、全社的には何も変わらない。
- システム部門に任せ、開発・ツール導入が増えるばかり。
- 外部委託で変革するも長続きせず、全社定着に至らずに自然消滅。
5つのケースに共通する要因は「ヒト、組織」であり、根本の要因は「他者任せ意識」なのです。
DXバブルによって、支援企業の多くが従来の提案内容の頭に「DX」という枕詞をつけるようになりました。こういったコンサル会社やシステム会社のようなDX支援会社は、デジタル改革(DX)ではなく「デジタル化」の提案となり、結果として企業を迷走させてしまいます。そして、DXを実現するために本当に必要なことは、デジタルマーケティングのノウハウやシステム開発のスキルではなく、変革をするスキルです。
「DXとは、Dgital(デジタル化)とTransformation(企業変革)が組み合わさってできている言葉です。デジタル化も企業変革もヒトが成し得るものであり、DXの本質は『ヒトの意識と行動の変革』である」と鈴木さんは話されていました。
DXを成功に導く5つのステップ
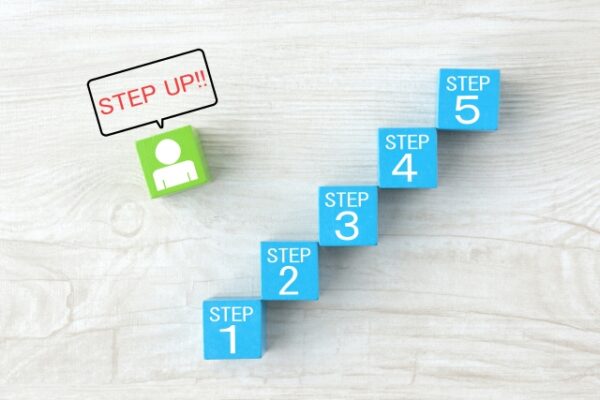
DXを成功に導くためには「DXの成功に近道はなく、一段一段ステップを踏み、全社改革を実行すること」だと鈴木さんは話されています。登っていくべき5段のステップを鈴木さんは下記のような形で示しています。
- 経営者の意識を変え決意を促す
- デジタル推進体制を構築する
- 未来を想像し業務を改革する
- 自社でITをコントロールする
- 変革を定着させ加速させる
このステップをどのようにして一段一段踏んでいくのか、その方法について鈴木さんは解説をしています。
1.経営者の意識を変え決意を促す
DXを成功に導くためには、まず経営者が「改革」の強い意識を持つことが欠かせません。しかし、社内からのDX推進の提言に対し、経営者が“NO!”と反対して、前に進めないことがしばしばあります。経営者を次の4つのタイプ別に分けて考えることで、どのように説得すれば、経営者の意識を変え、納得させられるのか攻略の糸口が見えてくるでしょう。
各経営者の攻略法としては、
- 創業型経営者タイプ
リーダーシップ&長期視点型
攻略法:「長期視点のHow」
- プロ型経営者
リーダーシップ&短期視点型
攻略法:「短期視点のHow」
- 2代目型経営者タイプ
マネージメント&長期視点型
攻略法:「長期視点のWhat」
- サラリーマン型経営者タイプ
マネージメント&短期視点型
攻略法:「短期視点のWhat」
と、それぞれのタイプがあります。(各経営者のタイプ別の説明や攻略法は鈴木さんの著書をご覧ください。)自社の経営者がどのタイプかを見極め、経営者の立場に立って説得をすることが大切だと、鈴木さんはお話されました。
経営者の役割として、会社の全体、一体性、未来にかかわる意思決定を行うことが挙げられます。そしてこの役割を果たすために、持つ権限として、事業方針の決定権、資金配分の決定権、人材配置の決定権があります。
なぜ、経営者の意識を変えなければならないのか。それはDXの成功には経営者が権限をフルに活かし、「改革」の意識を持つことが欠かせないからです。そのために経営者が強く意識しなくてはならない4つの要素があります。
- 時代の変化を強く意識
- 人任せにせず率先垂範で行動
- 全社を巻き込む変革の覚悟
- あきらめない心を持ち続ける
この4つの要素を強く胸に刻み込み、不退転の決意をすることが成功への第一歩となるのです。変革を行うことで社内から出てくる抵抗を抑えられるのは経営者のみであり、始めて半年や1年ですぐに結果を得られるものではないため、経営者の強い意志がDXの実現には必要不可欠となります。
2.デジタル推進体制を構築する
経営者がDXを推進する強い意志を持つことでこのステップへと進みます。デジタル変革のプロセスとして、
- 解凍(既存の事業や体制に揺さぶりをかけ過去を忘れさせる)
- 変革(向かうべき方向や考えを共有・実行する)
- 再凍結(共有された方向に向かい進み続ける)
の3ステップを実践する必要があります。このプロセスを歩むためにはデジタル推進に向けた体制を構築することが必要不可欠であり、デジタル変革の成否を決定します。そのため、リーダーやメンバーは慎重に選ぶことが大切です。なぜなら、ITに詳しい人やデジタルマーケティングに精通している人ではなく、変革のプロセスを推進するノウハウを持っている人がこの体制には必要だからです。
では、デジタル推進体制はどのような指標を持って構築するのでしょうか。鈴木さんは6つの極意を提示しています。
- デジタル推進リーダーは、経営者が一番信頼する人を任命
- 経営者が後ろ盾となり、社内の改革への抵抗に対処する
- メンバーは全社員を対象として立候補制で集める
- メンバー選定は、同質化を避け様々なスキルの人材を選ぶ
- メンバーは新しい風を期待し、外部からもオープンに招集
- スキル不足の場合、改革経験を持つ外部サポーターを頼る
「デジタル変革は既存のビジネスモデルや社内の体制を大きく変えるため、時には社内から批判の声が上がることや予期せぬトラブルに見舞われることもありえます。その際、指示を受けて招集されたチームでは逆風に耐えきれないため、自分自身の意志によって立候補したメンバーによって招集することが不可欠である」と鈴木さんは話しました。
3.未来を想像し業務を改革する

DXとはデジタル変革であり、業務をデジタルによって改革する必要があります。DXを推進する際に想像する未来は、業務改善ではなく業務改革を前提として考えることが大切です。改革と改善を混同することがありますが、業務改善とは過去の延長線上にある思考から社内の各部門や個人での視点に依存し、現状の課題からアプローチするものです。目指すべきは業務改革であり、未来の新天地を目指す思考でマーケットや全社横断的な視点を持って未来の業務を想像した上で行うべきものなのです。歴史のある会社では全社の業務を俯瞰して見られていないことがあり、どの部署でどのような業務を行っているのか、全社横断的な業務フロー図を作成してこそ初めて未来図を描けるようになります。
4.自社でITをコントロールする
デジタル変革において、システム構築の方法を変えていくことが大切です。従来、システムは現場から要件をヒアリングし、社内独自の運用に合わせてスクラッチで開発されていました。それでは、資金面やスピード面から時流に乗り遅れてしまいます。これからはクラウドツールに合わせて現場の業務を変えていく共創思考が欠かせません。各部署がどのようなシステムやツールを利用しているのか、業務フロー図と同様にシステム構成図を作成し、見える化することから始めるのが良いでしょう。類似した機能を持つ分析ツールや管理システムが部署ごとに異なることを発見でき、社内のITをコントロールできるようになっていきます。そうして、システムは「所有から利用」に変わり、システム開発からシステムプロデュースを行えるように変わっていくのです。
5.変革を定着させ加速させる
まず、DXを進めるにあたって当たり前に必要なこととして「やり抜く力(GRIT)」を持つことが挙げられていました。
GRITとは
Guts(ガッツ):困難に立ち向かう「闘志」
Resilience(レジリエンス):失敗してもあきらめずに続ける「粘り強さ」
Initiative(イニシアチブ):自ら目標を定め取り組む「自発」
Tenacity(テナシティ):最後までやり遂げる「執念」
の頭文字を取っている言葉です。
変革には抵抗がつきものです。その抵抗を前にしても、あきらめない心を持ち、変革を阻害する抵抗に対処することが、変革を定着させ加速させていきます。
抵抗の要因と対処方法
抵抗は個人からの抵抗と、組織からの抵抗に分けられます。
個人からの抵抗は
- 慣れた安全な状況が危うくなる
- 収入が減る心配や曖昧な状況への不安
といった理由が挙げられ、その末に自分が聞きたくないことを無視する人が出始めます。
組織からの抵抗は
- 新しい変革を嫌う組織風土による阻止
- 既得権益が損なわれることへの恐れ
- 自組織の資源が縮小されることへの驚異
を理由に発生します。
こういった理由により社内で発生する抵抗への対処方法も鈴木さんは解説しています。穏便なものから強硬なものまで上から順に6つの施策を挙げています。
- 教育とコミュニケーション=従業員に正確な情報を伝える
- 参加促進=反対する人を決定プロセスに参加させる
- 手助け=新しい環境への適応を助ける
- 交渉と合意=大きな勢力を持っている人に交渉する
- 策略と懐柔=戦略的または金銭的に抵抗を弱める
- 有形無形の矯正=抵抗者に直接行使する
抵抗する要因を知り、抵抗に適切に対処することで、変革を定着させ進歩させることができると、鈴木さんは話していました。
DX実現の先にある未来とは

新型コロナウイルスの影響でデジタル変革は加速しました。デジタル変革の先にある未来として、もたらされる変化は4つに分類することができます。
- ハイブリッド・ワーキング
- デジタル生産性の向上
- 優秀な人材の定義転換
- ヒト中心デジタル共創
この変化が具体的にどのような未来となるのか、イメージについても共有いただいております。
1.ハイブリッド・ワーキング
首都圏では緊急事態宣言など外出を控える動きが活発に行われる中で在宅勤務を行う人が増えています。同じ空間で労働を共にして一体感が生まれる「リアル・ワーキング」では、気軽な雑談から新しいアイディアが生まれ、直接会話をすることで深いコミュニケーションへと発展し、信頼関係を構築できる利点があります。一方、働く場所を選ばない「ネット・ワーキング」では移動時間の短縮により時間を効率化できる点や災害・パンデミックの際にオフィスに出ることなく事業継続が可能である点など、相互に利点を持っています。
デジタルの普及に伴い、リアルとネットの互いの長所を活かしたハイブリッドな仕事に変わっていくと鈴木さんは話していました。
2.デジタル生産性の向上
労働市場では2030年に7,073万人の労働需要に対し、労働供給は6,429万人ほどの予測であり、644万人の働き手が不足すると言われています。この人手不足を埋めるために女性やシニア、外国人などから働き手を増やしたとしても298万人の働き手が不足しており、生産性の向上によって補っていかなければならないとされています。
現状「壁」となっている時間や場所、組織や年齢、性別など様々な制約をデジタル変革によって取り払うことが、生産性の向上につながり、未来の労働力を補っていけるのです。
3.優秀な人材の定義転換
コロナ禍によるニューノーマルの加速や日本型の終身雇用システムの崩壊が始まったことで、劇的に社会が変わっていき、求められる人材が変わっています。これからは、社内外の知恵を結集し、自立した行動を取れる人材や複数の専門分野を持つマルチスキル人材が求められています。従来であれば、指示待ちのシングルタスク型人材であっても評価を得られていましたが、能動的に行動できる自立型マルチタスク人材が評価を受け、変革を可能にしていくのです。
4.ヒト中心デジタル共創
今までは業界や企業ごとに壁があり、それぞれが独立した機能を持っていました。業界・企業ごとに行われていた価値の提供は、デジタル変革によって壁を壊し、ヒトを中心に価値が提供されていくのです。
ヒトを中心に創造される新しい価値によって、人々の暮らしはより良くなっていくでしょう。こういった動きによって、民間だけではなく国を巻き込んだ「共創の世界」へと変わっていきます。
最後に:DX推進の実現可能性とは
DXバブルの中で、明確な変革のビジョンがないまま流行りの言葉に引っ張られてDXを実践しようとしている企業が多いことが本セミナーを通して伺えました。また、DX支援企業ですらもクライアントに対して、定常的な運用まで支援を実現できてはいない現実があります。会社としてDX化を実現するためには、まず経営者の並々ならない覚悟が必要であるため、本セミナー及び本著は経営者向けのものなのかと思う方もいらっしゃるかとは思いますが、DX化は経営者1人では行えず、立候補によって集められたチームが必要です。加えて本著には経営者をDX推進に向けて説得するための方法が具体的に解説されているため、DX化が必要とされる企業に属する幅広いレイヤーの方が読むべきであると感じられました。
自社のデジタル変革に課題を感じている方はぜひ「成功=ヒト×DX――デジタル初心者のためのDX企業変革の教科書」をお読みいただいてはいかがでしょうか。
また、自社のDX化でお悩みでしたら、デジタルシフトウェーブに相談してみるといいでしょう。
株式会社デジタルシフトウェーブ
https://www.digitalshiftwave.co.jp/contact/
合わせて読みたい