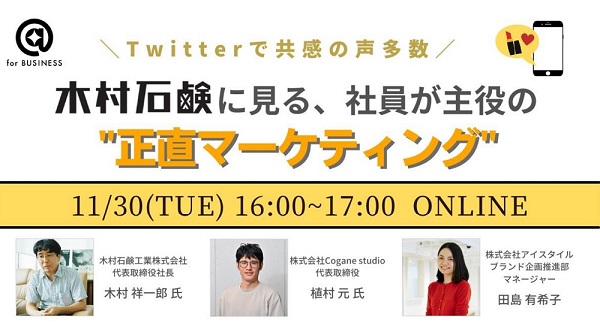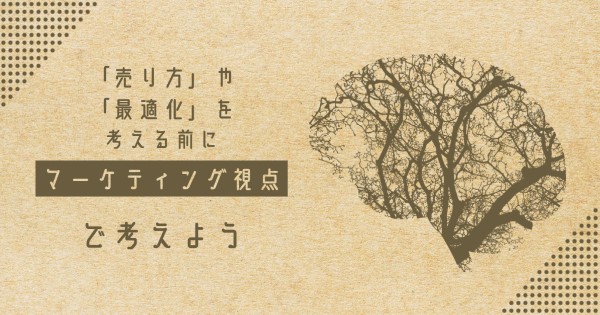
この記事の目次
売れないのには理由がある
スポーツの世界でよく引用されるフレーズで
『勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし』
という言葉があります。
やれば必ず勝てる必勝法はないけれど、やったら負ける必敗の法則は存在するので、負ける理由を研究し徹底的に対策をすることで、自分から負けに行くような事態は避けよう、というような意味で使われることが多いようです。
これは、ECでも同じことがいえます。
消費者の「なんとなく」が重なったり、たまたま有名人がSNSで紹介してくれたり、コントロール外の要因で一時的に急に売れることはあります。
一方で、日頃から売れない商品には必ず「売れない理由」があります。
数々のEC事業者様のネット販売をお手伝いしていますが、「売れない理由」は事業者自身にあることも少なくありませんでした。
その「売れない理由」は売り手目線で販売戦略を考えていることです。
つまり、売りたいモノを、売りたい売り方、売りたい金額で売ろうとしているのが原因です。
より具体的には、マーケティング視点の欠如、さらに具体的には
◯ブランド・アイデンティティの誤解
◯STP分析の不足
◯マーケティング・ミックスのズレ
です。
今回は、事業者自身が売れない理由を作ってしまったケースの実例を交えながら、最低限やってはいけない「必敗法」をご紹介します。
売りたいように売ろうとして失敗した焼肉店
オンライン販売に挑戦しようとして失敗した焼肉店の例を紹介します。
実店舗があるビジネスの例ですが、店舗を持たない純粋なEC事業者にも共通する部分があります。
事業者の概要
この事業者は、都内の一等地の空中階にある、10席強の高級焼肉店です。
プロの目利きで厳選した希少なブランド肉を骨付きのまま提携牧場から直接仕入れて、お店で加工して提供しています。なので、良い肉を最適な状態で提供できることが最大のウリです。さらに、あまり市場に流通しない珍しい部位も手に入りますし、そのような部位を美味しく食べさせる高い技術力も持っています。
また、お客様一組あたりに一人のスタッフがついて、それぞれの部位に最適な焼き方で調理しながら、肉の説明をしたり、美味しい食べ方を提案しています。
加工技術によりモノそのものにも高い付加価値があります。
ですがそれ以上に、目の前で調理して食べさせてくれるので、セルフサーブ型のように焼き方で失敗することがなかったり、加工方法や焼き方だけではなく珍しい部位についての知識も増えたりするため、そのサービスによる体験にも高い付加価値がありました。
ところが近年は、客単価が下がってきているのが主たる原因で売上が減ってきていました。
そして、「こちらからガツガツ売り込むのは安っぽくて嫌だ」と客単価を高めるための行動をシェフが嫌がっていました。
お店の特性から回転をあげることも難しく席数も増やせないためECを試してみることになり、わたしのところに相談がありました。
売り手目線が原因で付加価値を誤解して失敗したデリバリー
最初に始めたのはデリバリーです。
デリバリーをしたい事業者と、配達をしたい個人と、届けてほしい消費者をマッチングする黒字に緑色のロゴの例のサービスです。
デリバリーの消費者が求めているモノや、モノが消費される場面をよく考えずに、店舗のメニューをそのまま提供しようとして失敗しました。
お店での金額はサービスによる体験を含んだ金額です。
なので、スタッフによるサービスが提供できないデリバリーでは割高です。
そして、焼かれてから時間が経った焼肉は単純に美味しくありません。そして、説明なく珍しい部位を出されても、「珍しい」のが価値であり、とりわけ美味しいわけではないので、顧客の満足度は上がりません。
好奇心で一度注文する消費者はいましたが、リピートされませんでした。
次第に注文がなくなり実質的に辞めたのと同じ状態となりました。
マーケット分析をせずに進出したため失敗したEC
デリバリーの失敗を「調理済みのものを届けたから美味しくなかった。肉を届けて自分で焼いて焼きたてを食べてもらえば買われるはずだ。」と考えたようで、肉のECをすることになりました。
「目の前で焼いてくれる」「味だけじゃなくて情報も楽しめる」などのサービスによる付加価値は提供できませんので、モノだけでの勝負になります。
ところが、食品について、食べる前から質を感じてもらうのは難しく、価格面でも規模の利益が使える大手に完全に負けていましたので、まったく売れませんでした。
失敗理由の分析
一言でいうと、
マーケティングの視点が欠けていたから
です。
消費者が求めていて、市場で選ばれうるモノを作って売るのが本来です。
しかし、この事業者は、自分たちが売りたいもの、自分たちが売れるものを売ろうとしたために売れませんでした。
マーケティングの視点では、問題点は
◯ブランド・アイデンティティの誤解
◯STP分析の不足
◯マーケティング・ミックスのズレ
に分類できます。
ブランド・アイデンティティの誤解
彼らは自分たちを「おいしい焼肉店」と定義していました。
つまり「うちが美味しいからお客さんが来てくれる」と思っていました。
なので、デリバリーでもECでも「ウチの肉をウチの調理で売れば買ってくれる」と思っていました。
ところが、消費者は実際はサービスの付加価値が主な理由で来店していました。
このズレが原因で、商品に売れる理由がありませんでした。
この、自分たちが思っている「選ばれている理由」と消費者が「選んでいる理由」が一致していないのは、店舗での商売が比較的うまく行っている事業者が陥りやすい誤解です。
なぜならば、店舗への来客とデリバリー・ECで客層や求めているものが異なるためです。
ところが、純粋なEC事業者でも、自分たちが自信を持っていることが実は消費者にはピンと来ていなかったり、消費者が買ってくれている理由が思い込みで実際は違ったり、ということはよくあります。
STP分析の未実施
ECではSTP分析は欠かせません。
特に、店舗ビジネスの事業者がECに展開する場合は必須です。
なぜなら、店舗ビジネスの場合、物理的な場所によるセグメンテーションが必然的に発生してしまうため、同種の商品・サービスをより低価格で提供している事業者が世の中にどんなにたくさん存在していても、同じ商圏にいなければ関係がありません。
また、仮に近隣に存在していたとしても、需要がキャパを超えていれば席は埋まります。
なので、店舗ビジネスの場合は、運が良ければSTP分析をあまりちゃんとせずにもうまく行ってしまうことがあります。
一方で、ECでは所在地や席数などの物理的な制約がほぼなくなります。そのため、日本国内に対して販売しているほぼすべての事業者が競合相手になります。また、大規模事業者も零細事業者も同じ土俵で比較されます。
なので、EC市場をセグメントして、どこをターゲティングし、その中でどのようなポジションを取るかをよく考えなければなりません。
彼らは、「自宅で高級焼肉を(体験による付加価値がないのに)お店と同じ価格で食べたい人(デリバリー)」、「自宅で高級焼肉を(技術も設備もなく自分たちで焼くのに)お店と同じ価格で食べたい人(EC)」と存在しないセグメントを狙ったがために販売が伸びませんでした。
また、純粋なEC事業者でもSTP分析は常に必要です。
実店舗を出すのに比べて圧倒的に参入しやすいため、競争相手は刻々と変わります。
また、価格や売り方の変更も容易です。
そのため、STP分析は商品開発時に一度すれば良いものではなく、継続的に実施しなければなりません。
マーケティング・ミックスのズレ
彼らのデリバリー・ECにおけるマーケティング・ミックスは以下のようになっていました。
・Product:調理技術・設備が必要で焼いた直後じゃないと美味しくない肉を
・Price:体験を含めたのと同じ価格で
・Place(※):自宅で
・Promotion:注文アプリ・ECモール上で「お店の味を自宅で食べられる」という触れ込みで
売ろうとしていました。
※本来は販売(入手可能な場所)ですが、今回は「消費をする場所」に置き換えています
まず、Productが、Placeとの兼ね合いで魅力的ではありませんでした。
そしてPriceも体験込みの金額を体験無しで提供しているので割高です。
ECは「売れる商品」を作るところから始まる
彼らがECを成功させるためには、
◯ブランド・アイデンティティの見直し
◯STP分析の定期的な実施
◯マーケティング・ミックスの整理
をすべきでした。
ブランド・アイデンティティの見直し
彼らが自分たちを「おいしい焼肉店」ではなく「肉の仕入れと加工・調理のプロフェッショナル」と捉えていれば、違った売り方ができました。
つまり、独自の仕入れルートと目利きの能力、さらにどんな部位でも美味しく食べられるように加工・調理する技術を組み合わせて、他にはできないモノを提供することもできたはずです。
「質は十分だけれども理由があって値が下がっている掘り出し物を見つけてきて提供する」とか、「ブランド牛だけれども一般的には捨てられちゃう部位なのでお手頃価格で食べられる」とか、「ただ高い肉を買っても家庭の調理で台無しにしてしまう人が多いから、家庭で良い肉を美味しく調理できるように工夫した肉を販売する」など、独自性のある商品が作れたでしょう。
このように、売る商品ありきで売る方法を考えることに終止してしまったり、自分たちは「◯◯屋である」という枷を自分たちで掛けてしまって柔軟な商品開発が出来ない事業者が少なくありません。
今一度、自分たちが持っている資産・設備・技術・取引先など(ブランド・エクイティ)を整理し、何ができるのかを整理してゼロベースでECで売れる商品を作り直し、常に見直しをする必要があります。
STP分析の定期的な実施
次に、「誰に売るのか」を考える必要があります。
「自宅で美味しい焼肉が食べたい人」ではざっくりしすぎています。
ECで食肉を販売しているほとんどの事業者が競合となるためポジションが取れません。
規模の利益で安くできる大規模事業者なら価格でポジショニングできる可能性がありますが、ほとんどの事業者にはできません。
小規模事業者の場合は逆に生産量はそれほど多くできないため、市場は比較的小さくてもポジショニングができれば十分です。
そのため「めずらしい部位を食べてみたい」「ブランド肉をお得に味わいたい(自分が食べるだけだから見た目は悪くてもいい)」など、かなり絞った具体的なセグメントを設定しても問題ありません。
そのため、自分たちのブランド・エクイティを把握して、ゼロベースでできる商品を考え、その市場があるのか、ポジションを取れるのかを常に見直す必要があります。
マーケティング・ミックスの整理
この焼肉店のECおよびデリバリーは、消費される場所が自宅なのにProductもPriceも店舗で消費されることが前提となっていました。
そのために矛盾が生じ、売れない商品になってしまいました。
この焼肉店のECおよびデリバリーでは、自宅で自分(達)のために購入するという前提でマーケティング・ミックスを考える必要があります。
Productは、デリバリーなら調理してから時間が経過していても美味しいものである必要がありますし、ECなら自宅で素人がふつうの調理器具で調理しても美味しいことが条件になります。
そのため、デリバリーでは、肉汁や食感が重要だったり脂が多い部位などの焼き立てじゃないと美味しくないモノは適しません。そのため、肉自体にそれほど味を求めない濃い味付けで冷めても美味しく、ひとつの料理で満足できる食事となる、丼モノやお弁当だったりハンバーガーなどの定番メニューが無難でしょう。
掃除(可食部でも見た目を良くしたり食感を良くしたりするために切り取ること)で外した部位を使うなどして、ブランド牛を使っている料理だけれども「手頃な価格で食べられる」をウリとすることでファストフードなどとの差別化もできます。
ECでも、高火力の直火で一気にさっと火を通さないと美味しくない霜降りの部位などは適しません。弱い火力のフライパンなどで脂の多い部位を焼いてしまうと脂も肉汁も流れ出てパサパサになってしまいます。
ところが「焼肉店」であることにこだわらなければ、すき焼きなど、溢れた肉汁も料理となるような食べ方にしてもらうことで、よい状態で楽しんでもらうことができます。
Priceについては、体験がないぶん店舗よりも安く提供しなければなりませんし、同じセグメントに存在する他社との兼ね合いで見なければなりません。
次の観点のPromotionと兼ねて考えて、あえて提供先を絞ることで、「その対象者にだけ」は規模の利益があるところより安くするなども考えられます。
Promotionは、急激に生産量を増やすこともできないでしょうし、売れる商品を作るためには消費者の反応を見たり意見を聞いたりしながら改良することが必要ですから、案外オフラインの販促行動も十分に検討に値します。
そのため、店舗があるのなら来店者に申し込み用のはがきを渡すところから始めてもいいでしょう。純粋なEC事業者でも、営業所から一定の範囲の自分たちで届けられる範囲に限定してポスティングをする方法も考えられます。
商品づくりの段階ではいきなりECで売れようとせず、柔軟に発想することも必要です。
このようにして、あまり費用をかけずにテスト販売をして、その反応や感想を集めながら売れる商品を作るのが先です。
売れる商品ができてから、その商品でポジショニングが取れるECモールや広告媒体・手法を探して展開していくことをおすすめします。
または、新しい販売チャネルで取れそうなポジションを見つけたら、そこに合わせて商品を改良したり、新たな商品を作るのもいいでしょう。
まずは売れる商品づくりから
マーケティングの支援をしていると「商品ありきで、その商品をどうにか売れるようにするのがマーケティングだ」と考えられている事業者とよく遭遇します。
ですがそれは違います。
マーケティングは、売れる商品を作る活動です。
まず、ブランド・エクイティを見直すことで自分たちがどんな商品を作れるのかを考えてみましょう。
そして次に、市場が存在して、ターゲティングが可能で、ポジションが取れるところはどこなのかを探しましょう。
そして、そのポジションで選ばれる商品となるようにマーケティング・ミックスを考えながら売り物・売り方などを考えましょう。
皆さんのご商売がうまくいくことを祈っています。
合わせて読みたい