
はじめに:国・地域ごとに異なる越境EC
2017年11月に、私はアマゾンジャパンを退職し、当時越境ECの業界では売上最大手だった中国ECのプラットフォームであるNetEase Kaolaの日本法人の代表に就任しました。その時期は、Googleで「越境EC」という単語で検索をしても、検索結果に表示される記事やニュースはほとんどなく、日本から情報収集をすることができない状況でした。そのため、越境ECに関する情報は全て中国の本社から提供してもらう必要があったのです。
日本国内の越境EC、もしくはECを利用した海外進出という動きにおいても、アマゾンジャパンではグローバルセリングチームは解散されている状態です。そして、楽天市場では2016年6月にNetEase Kaolaと業務提携をすることで楽天出店者の中国進出にチャレンジしたものの、私の記憶が正しければ、まだまだ成功を収めたというところからはほど遠い状態でした。
あれから約5年が経ちました。NeEase Kaolaがアリババに買収された後、私がアメリカ越境ECのサポート企業である株式会社Picaroを設立したのが約4年前のことです。現在、Googleで「越境EC」と検索してみると、検索結果には100以上の検索結果が表示されています。様々な記事があり、広告を出稿している企業も多数あり、この5年間での市場の成長が伺えると同時に、名前が挙がってくるプレイヤーやプラットフォームが5年前のそれとは大きく変化しているのがわかります。
コロナの影響や、円安、日本の平均給与が相対的に下がっていることなどもあり、日本だけでビジネスをするのはリスクがあるという考えを背景に、ここ2年程は、越境ECの話題も非常に活発になっています。「越境EC」と一言でいっても、実はそこには地域ごとの特性、在庫の場所、オペレーション方法の違いなど、かなり複雑に分かれたグループがあります。越境ECのサービスプロバイダーと会話していても、どの越境ECのことを言っているのかがわからず、混乱してしまうこともあるでしょう。
そこで、第1回のコラムである今回は、まずは全体感を掴むためにも、地域ごとの越境ECの違いや、特徴、その界隈のサービスプロバイダーを簡単に紹介させていただき、まずはみなさんに全体像を把握していただければと思っております。なお、各地域のマーケットサイズなどについては、JETROからの情報や、他の方々が多数の記事を記載されているので、今回こちらのコラムからは割愛させていただきます。
オリジナル越境EC(海外から日本のサイトで購入)
まず「オリジナルの越境EC」です。これは日本のWebサイトに海外からお客様が訪問し、日本のWebサイトから海外へ、個人輸入という形式で、購入者が住んでいる自国に商品を送ってもらうことを指します。お客様が海外にお住まいであり、かつお客様が個人輸入の流れで日本の商品を自国に送るというのがポイントです。
最近はShopifyの人気と重なり、オリジナルの越境ECのビジネスが非常に活性化してきています。Shopifyで自社サイトを構築して多言語化対応をさせておき、デジタルマーケティングにより海外在住の方々へ訴求を行い、商品が購入されたら日本の倉庫から海外のお客様へ直接発送をします。
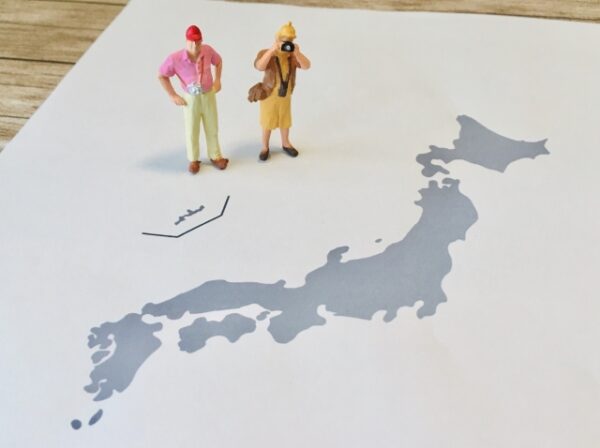
メリットとしては日本以外の方々へも商品を販売することになるので、マーケットサイズに限界がないことです。一方で、デメリットとしては、マーケティング活動をする地域や手法の選択と集中が困難であることと、送料でしょう。例えば中国へ販売したくても、中国から日本のWebサイトには通常の方法ではアクセスができないので、サイト構築には工夫が必要ですし、中国向けのマーケティングをしながら、他地域のマーケティングを同時に行うことは非常に困難です。また、購入者が個別に個人輸入する形となるので、送料を十分に下げることが叶わず、購入者側の送料が大きな負担になる点かと思います。
アマゾンジャパンでは掲載しているカタログを、日本語だけではなく英語や中国語で作成することで、アメリカや中国からアマゾンジャパンに商品を閲覧しに来たお客様に商品訴求をすることができ、スポンサー広告も英語や中国語での配信もできるようになっています。また、アマゾンジャパンのFBAプログラムに参加していれば、アマゾンジャパンが、販売者に代わって海外のお客様までの配送を全て行ってくれます。
楽天市場に関しては、十分な情報を持ち合わせていないので表現方法が適切ではないかもしれませんが、出店しているセラーで条件に合致する場合は、アメリカのWalmartで間接的に商品を販売できるようになっていると認識しています。
私が知る限り、このオリジナルの越境ECの領域においては、特に世界へボカン株式会社の徳田氏が業界を牽引されており、YouTubeチャンネルの登録者数も7,000人を越えています。最近販売された「はじめての越境EC・海外マーケティング」も非常に多くの方に読まれていると聞いています。ご興味がある方は、是非検索してみてください。
中国越境EC
上記のオリジナルの越境ECとは異なり、越境EC業界で最大の市場として「中国越境EC」が存在しています。これは細かく分けると非常に複雑になるのですが、極力シンプルにいうと、「一般貿易」と「保税区モデル」「オリジナル越境EC」という3つのモデルがあり、保税区モデルを使った中国でのビジネスが日本国内では「中国越境EC」と呼ばれていることが多いです。

保税区モデルとは、在庫自体は中国にあるものの、その在庫を管理している倉庫がある地域が、中国の法律上で別管理区域として管理されている形態のことです。オリジナルの越境ECとは、在庫が日本にあるのか、中国にあるのかという点が大きく違っています。更にこの「保税区モデル」においては、通関のプロセスや、CFDA(NMPA)、税率などの全てが、一般貿易とは異なっており、通関プロセスの簡素化や、低い税率といった特徴が挙げられます。
私個人が中国のビジネスを離れてから久しいので、最新の動向について不明な部分もあるのですが、現在はアリババのTmall Global(+NetEase Kaola)、テンセントのJD(京東)、Pinduoduoといったプラットフォームが市場をリードしており、ここにTiktokがどう参戦してくるのかが注目されている市場かと思います。
中国越境ECにおいて重要視しなければいけないのが、高いスマホ保有率、WeChat、Key Opinion Leader(KOL)、偽物対策です。まず中国でのスマホ利用者は10億人を超えています。そしてWeChatというスマホ上で利用されているコミュニケーションアプリは、日本のLINEと呼んでしまうと簡単過ぎるのですが、中国のモバイルインターネットユーザーのうちの83.7%が利用しているアプリで、全てを説明することは難しいのですが、何でもできてしまいます。
このWeChat上にミニアプリという形でショップを作ることが可能です。オニオングループはこのミニプログラム上に店舗を構え、設立から数年でニューヨーク市場にて上場をしています。また、KOLは日本ではインフルエンサーですが、中国のKOLは強烈です。1日の配信だけで、数十億の売上を作ってしまうKOLが何百人もおり、ライブの時間中はまさに「商品が飛ぶように売れる」という状態で、目の前で売上の伸びを見ているだけで興奮します。
そして最後に偽物対策ですが、これは非常に厄介な問題です。自社商品が売れれば売れるほど、偽物が出てきます。そしてその対応は簡単ではなく、メーカーでさえも、自分達が製造した商品と、偽物の区別がほとんどわからず、中身の成分検査をして初めてわかるというスーパーコピーレベルのケースが頻繁に発生していますので、事前の偽物対策は十分検討しておく必要があると思います。
中国越境ECのサポート企業としては、トータルサポートが必要な場合は、株式会社エフカフェや、中町秀慶氏がリードする株式会社unbot、元アマゾン時代の同僚が働いているInagora株式会社などがあります。また、カテゴリーに特化したサポート企業としては、元アマゾンの中山雄介氏が立ち上げた、日本酒及び冷凍冷蔵含む食品に特化した中国進出をサポートする合同会社オープンゲートや、美容に特化したライブコマースを使って中国に直接商品訴求ができる、上田直之氏の株式会社キレイコムなどが挙げられるかと思います。
東南アジア越境EC
そしてここ数年で盛り上がりを見せているのが、東南アジア市場です。この市場は中国のプラットフォーマーである、テンセントグループと、アリババグループが凌ぎを削っています。
2022年の6月時点での売上NO.1はShopee(テンセント(= JD)グループ)、そしてNO.2はLazada(アリババグループ)となっており、ここ数年ではShopee Japanや、Lazada Japanといった日本法人も立ち上がり、5年前の中国越境ECの盛り上がりと似たような活性化を見せています。
この市場の特徴は、中国のような仕組みとしての複雑性はないものの、複数の国に跨っていることで、微妙なマーケティングの違いが必要であることと、多数の言語をカバーしなければいけないという部分でしょうか。

東南アジアの中心というとファイナンシャルの観点からはシンガポールとなりますが、越境ECの市場としてはマレーシアやインドネシアが大きいです。日本のメーカーは、マレーシアを中心に他東南アジア諸国に進出するケースや、インドネシアを中心とした進出など、東南アジアへの進出方法は様々です。
また、興味深い話としては、特にシンガポールを中心としてマーケティングを考える際、裕福層へどうアプローチをするかというのが必ず議論に入ってきますが、この場合はお手伝いの方をどう巻き込むかが重要になるといわれています。シンガポールを中心とした東南アジアの裕福層の家には、住み込みのお手伝いの方がいる家庭が非常に多く、彼らの口コミから裕福層へ伝わり、そこから別の裕福層の方々へ波及するというケースが多いとのことです。
東南アジアにおいては、ShopeeやLazadaが自ら様々なサービスをメーカーに対して提供しており、日本に在庫を置いたまま現地で販売をし、受注があったら彼らが販売者の代わりに現地へ輸出し、購入者の手元まで届けるという、オリジナル越境ECと同じスキームでプラットフォーム上にて商品を訴求できるといったフルサポートサービスを提供しています。
なお、プラットフォーム以外で日本メーカーの東南アジアへの進出をサポートする企業としては、洞田潤氏のGDX株式会社や、場所はインドネシアですが長谷川智紀氏のBeautynesia、そしてトランスコスモス株式会社などが挙げられるかと思います。
アメリカ越境EC

次にアメリカ越境ECもしくはアメリカ進出があります。この市場は昔から巨大市場として存在しており、市場サイズとしては中国に次いで2番手となります。
ここ数年は越境ECの話題のメインは中国になっており、次に新興国としての東南アジアが盛り上がっていましたが、「アメリカ市場」と「アメリカ越境EC」は、実は中国越境ECよりも前からせどりや転売の界隈では大きな市場として存在しています。eBayを使った越境EC、もしくはアマゾンアメリカに商品ページを作成しておき、受注したら日本から発送するという越境ECモデルです。更にこれは越境ECではなく、アメリカ進出となりますが、アマゾンFBA(Fullfillment By Amazon)を使ってアメリカに在庫を持ち、現地の方々に販売をするといった手法に人気がありました。
最近ではJETROとアマゾンジャパンが協業してアマゾンアメリカ上に日本ストアを開設し、越境ECモデル、FBAモデルの両方をサポートしたり、中小企業機構も、アマゾンアメリカへの越境ECモデルのサポートを開始したりと、アメリカ越境ECも少しずつ盛り上がりを見せています。また、アマゾンアメリカ側もグローバルベンダーマネジメントチーム(GVMチーム)を中心に、日本企業のアマゾンを使ったグローバル展開を積極的にサポートしていると聞いています。
2022年5月には、これまでは全く日本のセラーに門戸を開いて来なかったWalmartが、日本からの出品を許可するようになり、Payoneerや当社経由でアカウントの開設ができるようになりました。Walmartへ出品するにはWalmartの出す基準をクリアした上で、事前に承認を取る必要があります。Walmartは本件で年内に来日するという話も噂であり、Walmartを使った日本からの越境ECも盛り上がりを見せつつあるのです。
なお、アメリカ越境EC並びにアメリカ進出に関して、物流面では株式会社グローバルブランドやアラウンド・ザ・ワールド株式会社、DHLなどがアマゾンFBAへの納品サービスを提供しており、FBAラベルの添付やImport Of Recordなどの代行をしてもらえます。また、FDAや英字ラベル作成サポートは、ロサンゼルスにあるGlobizzや、サンフランシスコにあるCosme Huntが提供しています。そして、納品後の現地での売上拡大、マーケティング支援に関しては、株式会社いつもや、当社Picaroのような、グローバルでアマゾンビジネスをサポートしている専門の会社が存在しています。
今回は第1回ということで、なるべく越境ECの全体感や、そこで活躍するプレイヤーがわかるような内容とさせていただきました。次回は最近話題になっているWalmart越境ECを含めた、アメリカ越境EC、アメリカ進出について、深堀していければと考えています。
株式会社Picaro:https://www.picaro.co.jp/
株式会社Picaro.ai:https://www.picaro.ai/
合わせて読みたい


















