
この記事の目次
はじめに:前回の振り返り
本連載のECの立て直しは、3つのフェーズに分けられると話しました。
【フェーズ1】「やろうとしていること」自体が正しいか(またはちゃんと考えられているか)
【フェーズ2】「やろうとしていること」と、そのための「手法、やっていること」が合っているかどうか
【フェーズ3】上記2つをベースに、自律的に動くメンバーや仕組み、運用を作っていく
連載の2回目である前回は、【フェーズ1】「やろうとしていること」自体が正しいか(またはちゃんと考えられているか)について、解説しました。今回の第3回では、【フェーズ2】「やろうとしていること」と、そのための「手法、やっていること」が合っているかどうかを説明していきます。
内容としては、【フェーズ1】の「やろうとしていること」で見直され、そのはっきりしたコンセプトを基に、マーケティング戦略を作っていくことに近いと思います。マーケティング戦略の策定自体が、「手法、やること」を決めていくことですので、今回ご紹介するプロセスで、「手法、やっていること」が合っているかどうかを検証、修正できるはずです。
極端な例ですが、高校生向けの商品なのに、経済紙に広告出しているような例、高校生が買わないような価格で売っている、やたら渋い大人好みにパッケージの例などはよく見ます。ここまでではないにしても、こんなトンチンカンなことをやっている会社多いです。なぜ、と訊くと、「考えていない」「少しは効果があるはず」「たまたま、知り合いがそのメディアに伝手を持っているから」といった理由が多いです。
フェーズ2のポイントについて
フェーズ2もフェーズ1同様に、チェックリストのようなものがあるわけではなく、基本の考え方に常に立ち返りながら、検討していくことになります。
「基本の考え方に常に立ち返りながら」というのは難しいようで、私の所属していた会社のメンバーも、支援している会社の方々も、苦戦されていました。そのため、このような考えで検討を行う訓練をした方がリードするか、逆に全く経験がない方がリードするくらいのほうがうまくいくように思われます。
複数でディスカッションして進める場合は、ホワイトボードの一番上に大きく「基本の考え方に常に立ち返りながら」や一旦決めたコンセプトを板書して、わかりやすくすることが、少しは効果があるようです。
フェーズ2のポイントとして、
- すべてはコンセプトに合っているか、ぶれていないかを常に気を付けながら考えていたか?
- ECサイト上で販売する商品ではなく、EC自体(取扱商品や物流、支払い方法、その他サービス、機能、ECサイトなどを含めた顧客に提供するすべての価値)のマーケティング戦略として考えていたか?
- ECを単純なチャネルやメディアと考えていなかったか?
の3点があります。それぞれ深掘ってみていきましょう。
すべてはコンセプトに合っているか、ぶれていないか

前回でも説明しましたが、うまくいかない理由の多くは、やりたい本当のことがぶれているためです。コンセプトが決まっていなければ、どうしようもありませんが、コンセプトを決めた自社の価値や大体の顧客像に、
- マーケティング戦略を決めていくこと
- 戦術を決めていくこと
- 各計画/施策を決めていくこと
上記の3つがずれていなかったかを考えなければいけません。
これは、全てにわたるので、ここで具体的に説明していくことは無理です。言えることは、もし、マーケティング戦略が事前に決めたコンセプトとずれていても、それのほうが良いと思ったら、コンセプトに戻って、コンセプトを検証し直すことです。コンセプトを変更したほうが良ければ、はっきり宣言して変えてしまいましょう。
逆に、決めていたコンセプトのほうがやはり良いのであれば、マーケティング戦略を考え直していくことです。実務上では、プロセスは行ったり来たりして、固まっていくことが多いといえます。危険なのは、なし崩し的な変更や、はっきり変更されたことが明示されないことです。結果、ぶれてしまいます。
戦術とマーケティング戦略がずれたら、マーケティング戦略を見直す?というわけにはいきません。考えられるすべての戦術がマーケティング戦略からずれていれば、マーケティング戦略の正しさを見直すことにはなりますが、それでは元も子もない段階にありますので、見直しではなく最初から考え直してしまうほうが混乱しないかもしれません。
ECサイト上で販売する商品ではなく、EC自体のマーケティング戦略として考えているか

実店舗の店舗開発も同様ですが、EC自体のマーケティングをしているかです。EC自体で提供する体験を自社の価値として考えなければならないのに、その中の一部である取扱商品を売るための手法ばかりに目が行っていないか見直す必要があります。
コンセプトで大まかに選んだECを利用する顧客がどの市場にいるかを考え、市場を細分化(Segmentation)し、EC自体で狙うターゲット(Targeting)を選定し、他のECまたは店舗や競合するものとのポジショニング(Positioning)からマーケティング戦略を構築するということです。
そして、EC自体のSTPを基に、4Pまたは4Cを決めていきます。
4P:「製品・サービス(Product)」「価格(Price)」「流通チャネル(Place)」「広告・販売促進(Promotion)」
4C:「顧客価値(Customer Value)」「顧客のコスト(Cost)」「顧客にとっての利便性(Convenience)」「顧客とのコミュニケーション(Communication)」
EC自体を中心に考える場合は、『売り手側の視点』から考える4Pよりも、『顧客側からの目線』から考える4Cのほうが、自社の価値であるEC自体をマーケティングするという観点的にも、用語的にもしっくりきそうです。
顧客価値(Customer Value)
「顧客価値(Customer Value)」は、EC自体が顧客に対してどのような価値を持つかです。特定の取扱商品だけでなく、ECサイトのデザイン/テイスト/機能、取扱商品の構成、支払い方法、配送方法などすべてが顧客価値となります。この顧客価値がターゲットに合っているかです。
顧客のコスト(Cost)
「顧客のコスト(Cost)」は、特定商品の価格だけではなく、取扱商品の構成で作られる価格帯及び送料やその他手数料なのです。
顧客にとっての利便性(Convenience)
「顧客にとっての利便性(Convenience)」は、チャネルがECだからではなく、自社のECをどこで見つけられるか、どこで/何で使えるかなどです。PC、モバイル、アプリ、ECモール、ミニアプリなどさまざまです。購入のしやすさ、支払い方法などを考えることもあります。
顧客とのコミュニケーション(Communication)
「顧客とのコミュニケーション(Communication)」は、EC自体をどう知らしめるかですが、広告、告知、オンラインやオフライン、対面やイベント、SNSなど、どのような方法、ツール、媒体、その他で顧客と接点を持つのか、その関係性についてです。
ECを単純なチャネルやメディアと考えていなかったか?
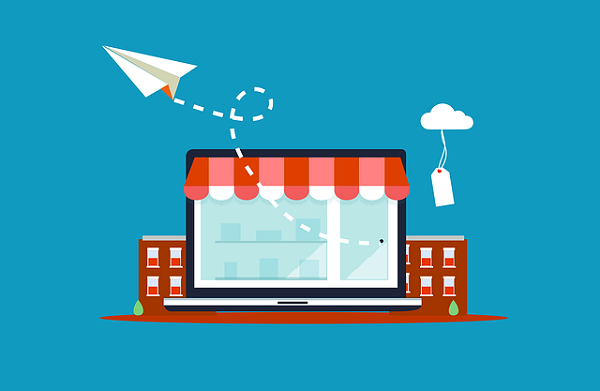
ECサイトはメディア、注文ツール、チャネルなどいろいろな機能を持ちます。どれかひとつの機能だけで収束するわけではありませんし、顧客も経営もそれ以上の役割を期待しています。ECはECサイトだけではなく、露出して、顧客に商品を届け、関係を維持するまでの全ての役割を持っています。
しかしながら、多くの企業がECを単純に新しいチャネルだと考えてしまいます。それだけではもったいないというのが正直な感想です。せっかく、コンセプトで自社の価値を顧客に届けるという考え方をしたわけなので、ECは自社の価値を顧客に届けるためのタッチポイントと考えると一番しっくりするでしょう。
自社の価値を顧客に届けるためのタッチポイント(顧客との接点)は、店舗も販売員も、店内ポップ、看板、DM、チラシ、交通広告、メルマガ、Webサイト、CS、ECサイト、物流、支払いなど、顧客と接点のあるすべてのものです。ECはそのいくつかを内包し、EC自体もタッチポイントと考えます。すると、店舗のある会社などでは、実店舗に加えて、EC自体を新しいタッチポイントとし、実店舗をどう内包するのか考えることができます。
ECをタッチポイントとしたときの考え方としては、まずは、既存客との新しいタッチポイントとして考え、既存顧客にECを使ってもらい、ECが育ってきたら、新規の顧客へECを活用していく流れです。
それぞれの考え方で、これまで/今「やっていること、方法」が、自社で考えたコンセプトではっきりしてきた「やりたいこと」に合っているか、検証を行い整理し、違っていればこの流れでちゃんと考え直していくことになります。
前回も今回も、見る人によってはきれいごととしか思われないのを承知で解説しています。当然、このようなことを考えなくても、改善できるようなことは沢山あります。しかし、やるべきことの中心に、前回と今回で解説したしっかりとした考えがないので、トンチンカンなことをやったり、正しいのだけれどつぎはぎだらけになったり、優先順位が無茶苦茶で効率が悪かったりと、立て直しの必要性を感じているわけです。
いろんなできることを調べ、検討していくことも重要ですが、ちゃんとしたコンセプト、戦略にそれらを当てはめていく工程がなければ、本当の成長を目指すことはできないでしょう。
次回は、【フェーズ3】上記2つをベースに、「自律的に動くメンバーや仕組み、運用を作っていく」というお話をしていきます。
合わせて読みたい


















