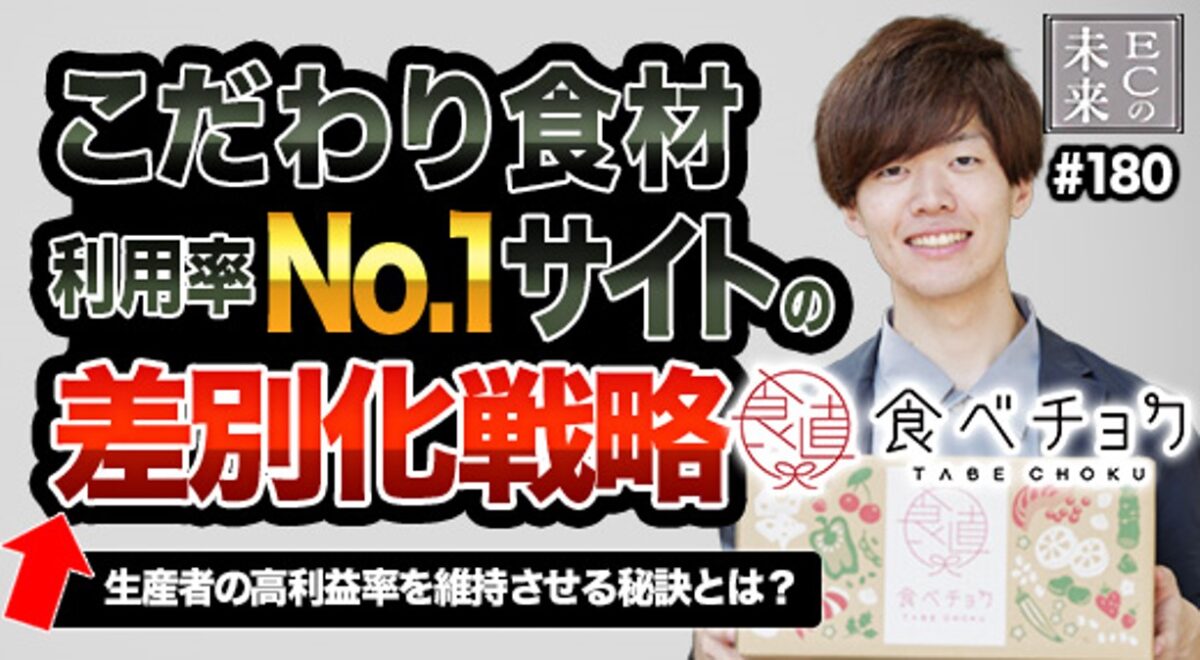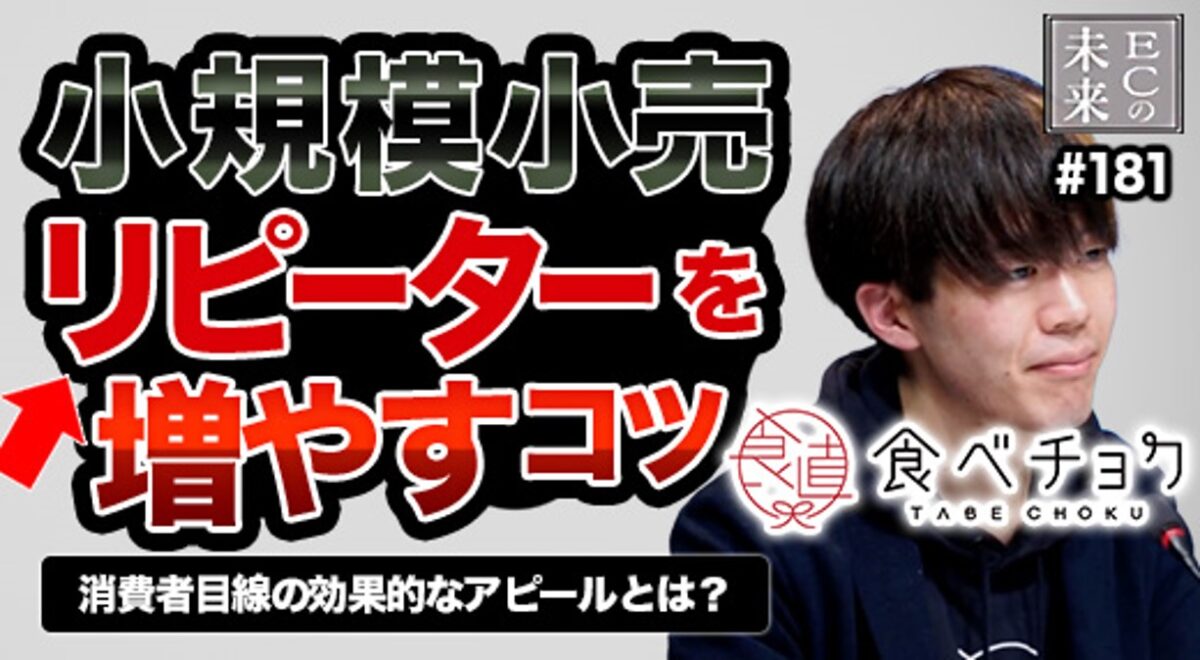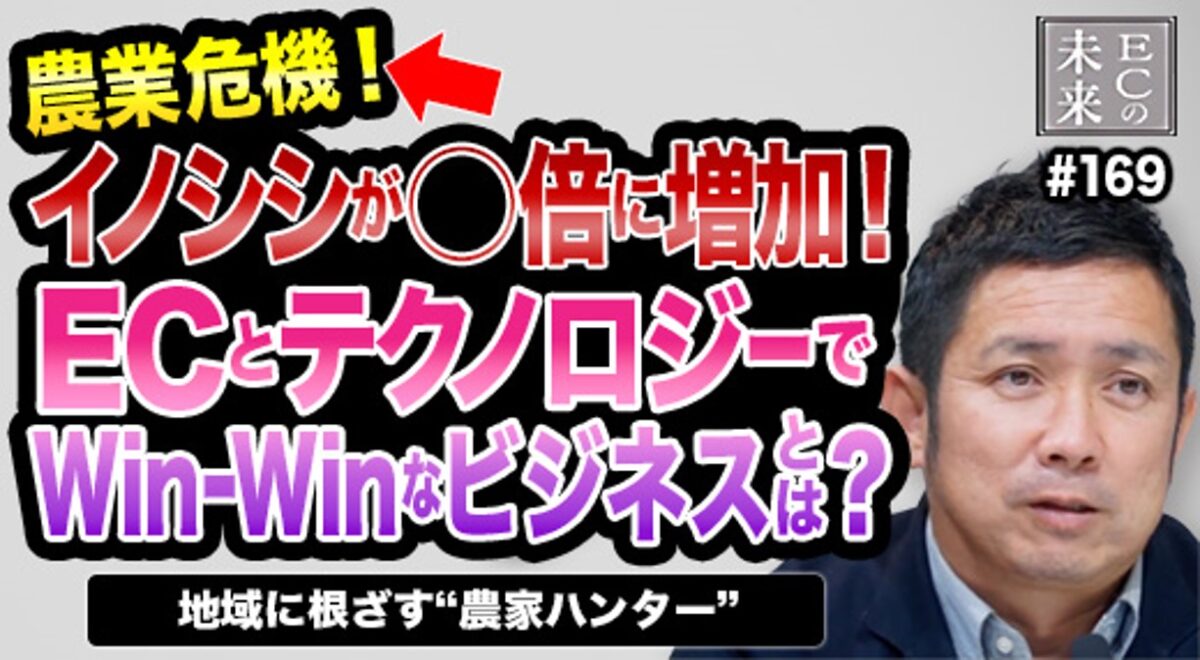【ゲストスピーカー】
秋竹 俊伸さん
株式会社早和果樹園 代表取締役社長
紀州有田みかんの専門店「早和果樹園」
【チャンネルMC】
柳田 敏正さん
株式会社柳田織物 代表取締役
ワイシャツ専門店「ozie(オジエ)」
この記事の目次
生産・加工・販売を自ら担う「6次産業」とは?
柳田さん:秋竹さんは6次産業を推進されていますが、まずは「6次産業」とは何かというところからお聞かせいただけますか?
秋竹さん:6次産業というのは、いわゆる造語です。一次産業は農業や漁業などの「生産」、二次産業は食品加工などの「製造」、三次産業は販売などの「サービス業」と定義されています。これらを「足したり掛けたりして6にする」という発想が6次産業です。
この概念は東京大学の名誉教授が考案し、アベノミクスなど政策面でも柱の一つとして位置づけられました。かつて農業者は一次生産と市場任せの販売しか行っていませんでしたが、自ら値付けをして販売することで、より強い農業を目指す取り組みが始まりました。
さらに、生産と販売の間に「加工」を加えることで、農作物の付加価値を高める動きが広がっています。つまり、生産から販売までを自ら完結させる“総合的な取り組み”が6次産業の考え方です。
柳田さん:昔はそうした動きはなかったのですよね。
秋竹さん:昔はできませんでした。私は和歌山県で柑橘を作っていますが、「売る」という行為は非常にハードルが高いのです。流通の問題があり、農業者が集まって築地市場に出荷していました。しかし、インターネットの普及によって情報が得やすくなったことで、「自分たちで加工しよう」「自分たちでチャネルを持って販売しよう」という流れに大きく変わってきています。
柳田さん:従来通り、JAなどに流通を任せるやり方を続けている方も多いのでしょうか?
秋竹さん:はい。従来のやり方を取っている農業者の方が圧倒的に多いです。柑橘や果物は地方が多いため、JAに出荷して流通させるのが最も理にかなった方法になります。一方で、直接販売は労力がかかりますが、各地で特に若い世代を中心に、自分たちで加工し販売する動きが少しずつ増えています。
柳田さん:基本的には「どれだけおいしいものを作るか」に朝から晩まで時間を費やしている中で、加工や販売まで担うのは時間的に厳しいですよね。
秋竹さん:そうですね。個別の農家が、昼は農作業、夜は販売準備をして、さらに加工の環境を整えるとなると非常に大変です。
加工業への挑戦、天候不順と相場崩れが生んだ転機
柳田さん:そもそも早和果樹園は、どのような経緯で6次産業に取り組み始めたのでしょうか。
秋竹さん:私たちはもともと寄り合いの組合でしたが、2000年に7戸のうち4戸に後継者ができたことをきっかけに、「法人化しよう」という話になりました。当時は農業法人がまだ全国的にも少ない時代でしたが、みんなで一生懸命みかんを作って頑張っていこうと法人化を決断しました。
ところが、天候不順や相場の乱れが起きると、どれだけおいしいみかんを作っても評価されない年がありました。生産量によって価格が大きく変動してしまうのです。ちょうど平成13年〜15年頃に天候不順が続き、傷がついて出荷できないみかんが大量に発生しました。せっかく会社にしたのだから事業を広げようと、そこで加工業に取り組むことにしたのです。
もともと6次産業という言葉は後から知りました。最初は「加工用の傷みかんがたくさん出たので、絞って売ってみよう」という単純な発想でした。ただ、どうせ作るなら普通のジュースではなく、“いいみかんだけを使ったジュース”を作ろうというのが始まりです。
柳田さん:そんなに簡単にジュースは作れるものなのですか?
秋竹さん:当時の社長は私の父ですが、ジュースを作ろうと言って研究所や加工業者の方々に話を聞きに行ったところ、周囲のほとんどから反対されたそうです。
柳田さん:順を追えばできそうにも思えますが、確かに簡単ではなさそうですね。
秋竹さん:反対されながらも、それでも「やってみよう」と踏み切りました。みかんの生産には時間がかかるため、1人で生産しながら加工を行うのはほぼ不可能です。そこで、生産はすべて私に任せ、父をはじめとする先代たちが加工事業に専念する形で動き出しました。
私はもともと、自分たちの畑でみかんを作って出荷することが使命だと考えており、10年ほど専業農家として働いてきました。加工事業が始まっても、当初はそれほど人手を必要としませんでした。
ただ、加工事業が軌道に乗ったタイミングで、私自身も徐々に加工のほうへ軸足を移していきました。現在もみかんを生産していますが、販売比率で見ると加工品のほうが多くなっています。社内には生産部を設け、若い後輩を雇って畑を任せています。加工事業は1年を通じて仕事があるため、私たちは年間を通して加工品の販売に取り組んでいます。
柳田さん:年間で考えると、加工品が中心のほうが安定しそうですね。みかんを作るのに、どのくらいの期間がかかるのですか?
秋竹さん:生産作業は一年中かかります。畑という財産を外に置いている以上、どうしても収入の上下は発生します。
「味の良さ」を伝え続けた試飲が導く、人気商品への道
柳田さん:加工事業が軌道に乗るまで、どのくらいの時間がかかったのですか。
秋竹さん:7年くらいかかりました。始めて1〜3年目は特に厳しかったです。
柳田さん:どのようにして事業が軌道に乗っていったのですか。
秋竹さん:自信を持って言えるのは、「試飲販売を続けてきたこと」です。どんなに味が良くても、知ってもらえなければ売れません。しかし「味が良い」という認知が広がれば、高価なジュースでも買ってもらえるようになります。10人中2〜3人がわかってくれる。そんな手応えを積み重ねながら、地道に認知を高めてきました。
また、関西圏だけでなく、東京で開催される和歌山物産展などにも出展し、販売エリアを広げていきました。そのなかでジュースだけが特に人気を集め、和歌山県外にもお客様ができ始めた頃に、「ようやく軌道に乗ってきた」と実感しました。
弊社のジュースはオリジナル商品ですので、ラベルを見て「このジュース、おいしいよ」と電話をくださる方が多かったんです。ジュースの認知がある程度広がった頃、私は総務を担当していましたが、事務所にはお客様からの電話がひっきりなしにかかってきました。
全てに対応していたら手が回らないため、カタログを作成したり、ネット販売を始めたりして、購入の受け皿を整えました。「おいしいからギフトに送りたい」という声にも応え、全国発送に対応したギフトセットを展開しました。ギフトを受け取った方がまた購入してくださるという循環が生まれ、直販の輪が少しずつ広がっていきました。
柳田さん:カタログやネット販売を始めたのは、狙ってというより電話対応の煩雑さがきっかけだったのですね。
秋竹さん:そうです。「お店はないの?」と直接訪ねてこられる方もいました。今では工場の下に店舗がありますが、当時はなかったため、お客様の動きに合わせて柔軟に対応してきました。
農業一筋で販売の経験がなかったので、最初は本当に手探りでした。お客様に説明しても「何を言っているかわからない」と言われることもありましたし、カタログがわかりにくいとお叱りの電話をいただくこともありました。そうした声を受け、買いやすい形へと改善を重ねていきました。
柳田さん:全国への広がりに影響を与えたのは、ECやカタログ販売の存在が大きかったのでしょうか。
秋竹さん:今となってはそうですが、当時はまだそこまでの規模ではありませんでした。
柳田さん:ECを始めたのはいつ頃ですか。
秋竹さん:2008年に自社サイトをオープンしたのが最初です。2010年には楽天市場にも出店し、この2つがきっかけで販路が大きく広がりました。
実は私は当初、自社サイトをメインにやりたかったのです。和歌山県内にとても売れている柑橘系のショップがあり、それを見た当時の社長(=父)が「楽天に出せば売れる」と言って、半ば強引に楽天市場への出店を決めたのが始まりでした。
柳田さん:なぜ自社サイトをメインにしようと考えたのですか。
秋竹さん:ネット販売を始めるときに、いきなりモールに出店して広告を打っても売れる商品ではないと感じたからです。
どちらかといえば、先ほどお話ししたように「すでに商品を知っているお客様の受け皿」を作りたかった。商品名で検索してもらえれば、基本的に自社サイトが上位に表示されますから、自社サイトを充実させた方がいいと考えました。
また、勉強したかったという理由もあります。自社サイト運営は自由度が高く、試行錯誤の余地があるので、面白くてのめり込んでいきました。こうして手探りで始めたECの取り組みが、いまでは会社の大きな柱の一つになっています。
おわりに:地道な試飲販売がブランドを育てた7年
秋竹さんのお話からは、天候不順や相場の崩れといった逆境を力に変え、農業法人として新たな挑戦に踏み出した姿が浮かび上がってきました。経営が安定しやすい加工業に着手し、試飲販売を重ねながら少しずつ認知を広げ、さらにカタログやECを通じて全国へ販路を拡大していった歩みは、まさに6次産業の体現といえます。生産者自らが価値を高め、顧客へ直接届ける仕組みを築くことは、農業の新しい可能性を示す大きなヒントとなるでしょう。
EC市場の真の発展に貢献をという想いで、「ECの未来」を運営しているサヴァリ株式会社は楽天市場・Amazonなどネットショップ運営代行をはじめ、モール通販を中心にECサポート・ECコンサルティングを行っています。EC運営に不安を抱えている事業者様は問い合わせてみてはいかがでしょうか。
■サヴァリ株式会社へのお問い合わせはこちら
https://savari.jp/contact/
あわせて読みたい