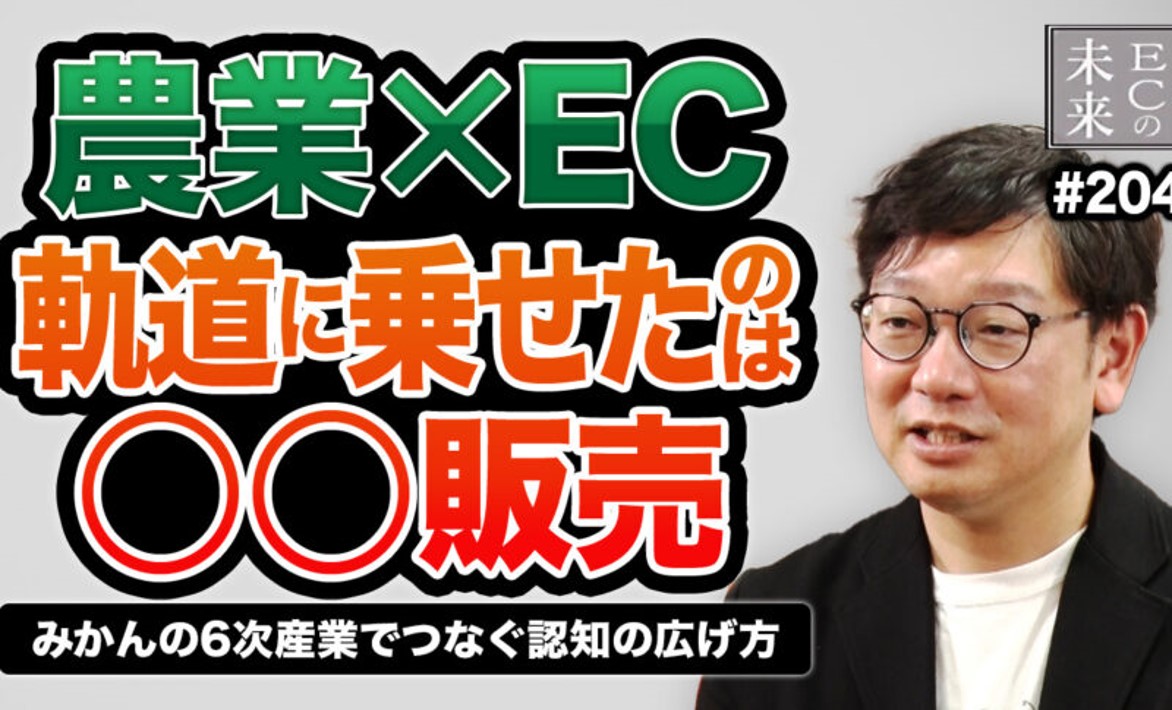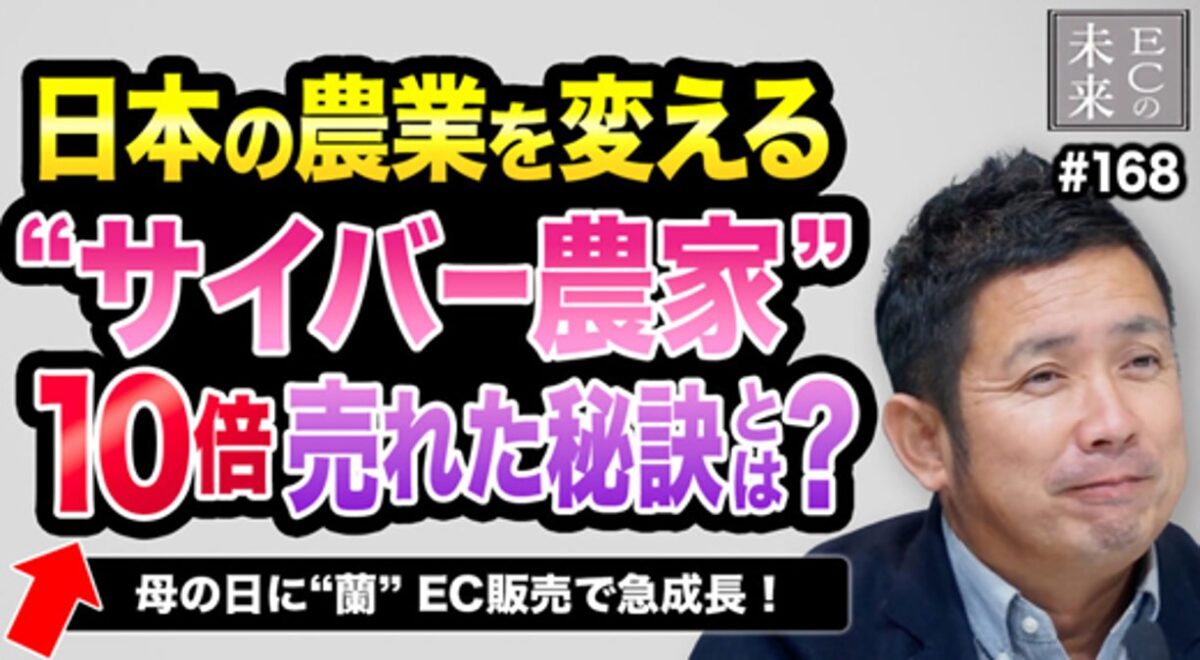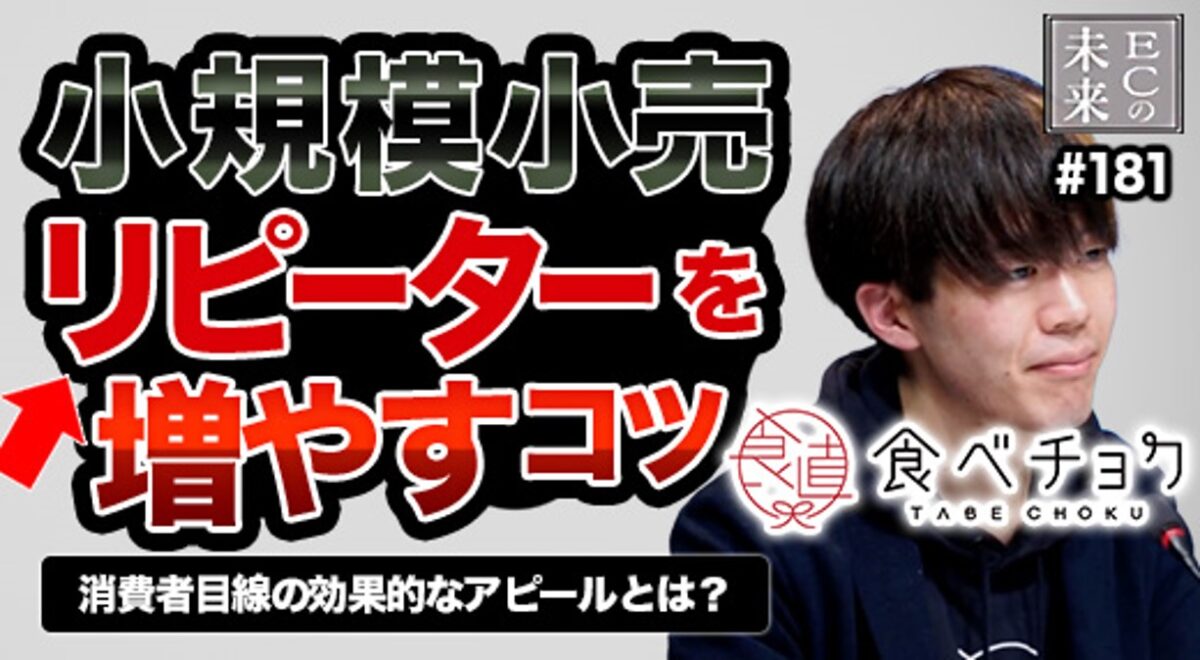【ゲストスピーカー】
秋竹 俊伸さん
株式会社早和果樹園 代表取締役社長
紀州有田みかんの専門店「早和果樹園」
【チャンネルMC】
柳田 敏正さん
株式会社柳田織物 代表取締役
ワイシャツ専門店「ozie(オジエ)」
この記事の目次
ジュースの人気が生果への波及効果に
柳田さん:早和果樹園ではみかんを育て、ジュースを製造されていますが、現在ではジュースの販売量が生果の販売量を上回っているそうですね。とはいえ、シーズンになれば直販でみかんも販売されているかと思います。
秋竹さん:はい、ジュースを販売していると、「このジュースの原料になっているみかんを食べてみたい」というお声を多くいただき、ありがたいことに、みかん単体で販売していた頃よりも生果への引き合いが強くなっています。
メルマガを1通配信すると、みかんはあっという間に完売してしまいます。「今回も買えなかった」というご連絡が私のところに届くことも非常に多いです。
柳田さん:いつでも満遍なく買えるよりも、「早く買わないとなくなる」という状況のほうが希少性が生まれるのかもしれません。直販であれば、自社の収穫量が多くても値下がりせずに販売できますよね。
秋竹さん:そうですね。直販は自社で値付けができます。ただ、果物という特性上、入荷時期がずれてしまうことも多いので、お客様からの要望があっても過注文にならないよう、ある程度受注を限定して様子を見るようにしています。
特に人気の高い“小さくて糖度の高いみかん”や、「この畑で採れました」と限定して販売しているみかんは、畑を見ているだけでは正確な収穫量の予測ができません。実際に収穫するまで、それが100ケースなのか50ケースなのかわからないのです。
また熟期があるので、収穫のタイミングがずれることもよくあります。100人に販売したくても、80人で一旦止めざるを得ないこともあります。直販に加えて市場にも出荷し、販売先を分散させながら対応しています。
柳田さん:みかんジュースを製造し、生果も自社で販売できる仕組みが整っていますが、ECサイトを立ち上げただけではリピーター中心になり、広がりは出にくいのではありませんか?
秋竹さん:おっしゃる通りで、ECサイトを作っただけでは絶対に売れません。リピーターが多いことは事実ですが、やはり「どう知っていただくか」という認知獲得の取り組みも欠かせません。
柳田さん:でも冬のみかんの場合、試食などで知ってもらうことは難しいですよね?
秋竹さん:そうなんです。みかんの販売期間は約1.5か月しかないため、試食に回す余裕はありません。みかんを購入してくださる方の多くはリピーターで、あとは口コミなどで“買いたい”と思ってくださった方が待っていてくれる状況です。
ですから、「ネットショップを作れば売れる」というわけではなく、長年かけて育ててきた関係性や信用の上に今の販売が成り立っているのだと思います。
BtoBの販路拡大が導く認知拡大戦略
柳田さん:一度サイトに来ていただかないと、メルマガなどのご案内をお届けすることができません。何かしら取り組まれていることがあるのだと思いますが、どのような施策を実施されているのでしょうか。
秋竹さん:Web施策で言えば、ライブコマースを始めるなどの取り組みもしていますが、それだけではなかなか難しいのが実情です。6次産業化を形にしていくためには、BtoBの取り組みが欠かせないと考えています。
当社はオリジナル商品を扱っているため、まずはお客様に認知していただき、そこからBtoCの購入につながる流れです。だからこそ、認知を広げることが最重要です。
BtoBで日本全国、さらには海外に展開し、みかんジュースが知られるようになると、そこで商品を知った方々が直販サイトに訪問して購入してくださいます。直販サイト向けに広告を打って新規顧客を獲得するというよりも、「ジュースそのものを広告」にして全国に届け、そこからお客様を育てていくイメージです。Webは、その受け皿であり、出会いをつなぐ役割を担っていると考えています。
柳田さん:つまり、BtoBの取引が増えることで売上が上がるだけでなく、商品ラベルを見たお客様がオンラインで検索し、直販につながる。そうした相乗効果を狙った方法ということですね。
秋竹さん:その通りです。BtoBが広告のような役割を果たしてくれています。BtoBでの販売をきっかけに直販サイトで売れ、直販サイトで人気が出れば、今度は「ネットで人気のジュースを卸してほしい」という依頼が来る。小売店の担当者の方もネットをチェックしてくれていて、「この画像を提供してほしい」とご連絡をいただくこともあります。
また、テレビで紹介されると、直販サイト以上に実店舗の売り場が動きます。翌日に大量の注文が入ったり、「売り切れたので追加を」とご連絡をいただいたりすることもあります。
当社は製造をアウトソースしておらず、自社の製造場を持っています。そのため、自分たちでしっかり作り、しっかり拡散し、受け皿となる直販サイトも自社で運営しています。SNSなども活用しながら、早和果樹園を知っていただくためのタッチポイントを増やすことを常に心がけています。
柳田さん:非常にうまいやり方ですね。ネット販売をされている方は多くいらっしゃいますが、ネットだけでは厳しい側面がありますし、逆にリアル販売だけでも難しい場面が増えていると感じます。
今の時代、ネットはどこからでもアクセスできる“受け皿”として機能します。ネットとリアルをうまく組み合わせながら、常にブラッシュアップしていくのが重要だとあらためて感じます。
カフェ・イベント・直売所、リアル展開で広がる「早和果樹園ブランド」
秋竹さん:最近はお客様の動きが変わってきていると感じています。どこかでジュースを飲んで「美味しい」と思ってネットで購入し、その後に「実際に和歌山へ行ってみたい」とお越しになるお客様が増えているんです。
例えば大阪からであれば、本社のショップまでは1時間ほどで来られますので、冬にはみかんの買い付けに来てくださる方もいます。「見てみたい」「食べてみたい」「お店に行ってみたい」というニーズが高まり、ショップの店長から「何か飲食を提供したい」という提案があり、パフェを提供するカフェを始めました。
このパフェをLINEで告知したところ、さらに来店が増えている状況です。本社敷地の前を借り、オープンカフェの開設も準備しています。リアルの拠点が増え、そこで直接みかんを購入いただけるようにすることで来店が生まれますし、たとえお店には来られない方でも、サービスエリアやネットで購入いただければ良い。商品に触れるタイミングを増やせばリピーターが増えるのではないかと考え、取り組んでいます。
柳田さん:本社の下にショップを設けたからこそわかった“人の流れ”ですね。白浜にも直売店を作られましたが、そのお客様が本社にも足を運び、熱心なファンになっていく。これは単にみかんやジュースの味が良いだけではなさそうです。
秋竹さん:味が良いだけなら、近所のお店やネットで購入しても事足りるはずです。だからこそ結果として表れるよう、しっかり育てていく取り組みを社内で進めています。
柳田さん:リアルイベントも開催されていますよね。
秋竹さん:はい、「みかん狩りイベント」です。ただのみかん狩りではなく、“びっくりするほど美味しい畑”で体験していただくイベントです。本来であればトップランクで販売される畑を完全開放し、収穫したみかんをお土産として購入していただけます。
本社では、さまざまなゲームを楽しんでいただけるイベントも開催しています。2019年には1,200名に参加いただき、リピート率も非常に高いです。コロナ禍で開催できていませんでしたが、今年はさらに参加者が増えるのではないかと見ています。
柳田さん:どこかで早和果樹園を知った方が、ネットという受け皿で商品に触れ、そしてリピートすることでファンが増えていくわけですね。商品が良く、受け皿があり、そしてリアルにも足を運びたくなる“何か”があるように思います。
秋竹さん:イベントは試行錯誤しながら作ってきました。例えばクローズドのイベントからオープンイベントに変えるなど、多くの方の動きを参考にしながらブラッシュアップしてきた経験があります。
柳田さん:最後に、今後どのように進めていきたいかお聞かせください。
秋竹さん:中長期的な視点でいえば、ありがたいことに新卒採用で毎年4〜5名が入社しており、若い人が増えています。私たちは元々農業者で、自分の家や組合の範囲でやってきましたが、今では外から入社した多くの社員が仕事に取り組んでくれています。店舗運営やLINEを使った集客施策などを進めてくれており、見ていて非常に面白いです。
果樹は野菜と違い、“みかんの木を育てる”ものです。木が実を育ててくれる。社員を木に例えるつもりはありませんが、若い人が育ってきていて、活躍の場をもっと与えたいという思いが強くなっています。
農家として、事業を拡大するのは自分たちも楽しいですし、魅力が出て地域の役にも立てます。ですから、リアル店舗を増やしたり、工場の規模を大きくしたり、この先5年ほどで一気に動いていきたいと考えています。
柳田さん:お店に来ていただければ、地域貢献にもつながりますよね。
秋竹さん:「地域貢献」「地方創生」といった言葉をいただくこともありますが、やはり取り組んでいる私たち自身が面白いと感じないと続きません。社員が増えてきて、「この人にはどんな仕事を任せようか」「次はどんなステージに進もうか」と考えているうちに、気づけばここまで来ていました。
有田は日本一のみかん産地ですので、この強みを活かせば、もっと面白い方向に進めるのではないかと常々感じています。
柳田さん:供給量も安定していますし、単純にそれだけを見てもまだまだ拡大できると感じます。やはり、みかんジュースの存在が大きかったですね。
秋竹さん:みかんジュースがなければ、ここまで来られなかったと思います。
柳田さん:6次産業化というテーマに加えて、オムニチャネルの仕組みが非常にうまく機能していますね。しかも最初から設計したのではなく、人の流れや気持ちを汲み取りながら自然とそうなり、今も拡大し続けている点がとても素晴らしいと思いました。
おわりに:みかんジュースが広げた、6次産業化の成功モデル
みかんジュースを起点に6次産業化を進めてきた早和果樹園は、直販とBtoBをうまく連動させながら全国へ認知を広げています。さらに直営店、みかん狩りイベント、カフェなどリアルな接点を増やすことで、ファンづくりにも成功しています。
若い社員が挑戦できる環境を整え、楽しみながら地域と共に成長しようとする同社の姿勢は、6次産業化に取り組む事業者にとってひとつの理想的なモデルといえるでしょう。
EC市場の真の発展に貢献をという想いで、「ECの未来」を運営しているサヴァリ株式会社は楽天市場・Amazonなどネットショップ運営代行をはじめ、モール通販を中心にECサポート・ECコンサルティングを行っています。EC運営に不安を抱えている事業者様は問い合わせてみてはいかがでしょうか。
■サヴァリ株式会社へのお問い合わせはこちら
https://savari.jp/contact/
あわせて読みたい