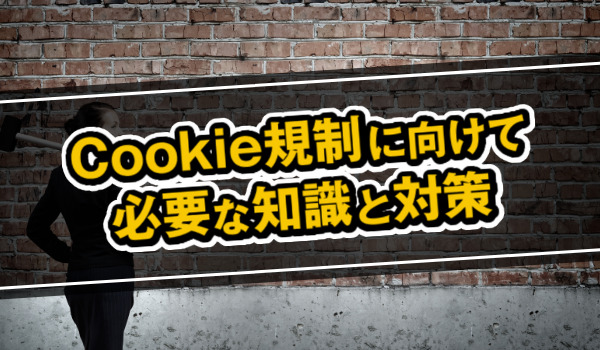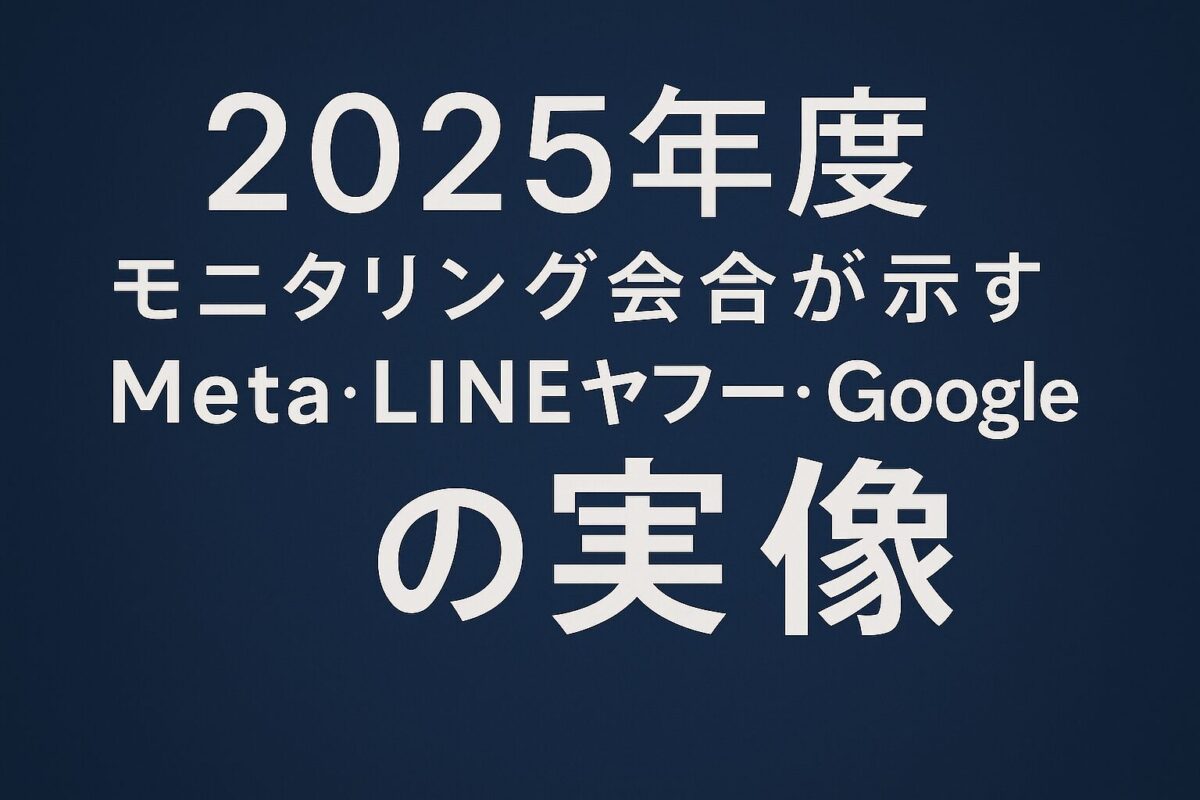
この記事の目次
EC事業者が感じる不安の正体
EC事業者にとって、デジタル広告は売上を左右する要となっています。しかし、審査が急に止まったり、掲載却下の理由が明瞭でなかったりする場面は少なくありません。広告主からの申立てがどのように扱われているのか、進捗はどう共有されるのかといった基本的な流れさえ見えづらいと感じる人も多いでしょう。
この不透明さは単なる運用上のムラではなく、制度面や仕組みが複雑に絡み合って生じている可能性があります。こうした疑問に応える目的で、経済産業省は特定デジタルプラットフォームに対し、透明性と公正性の観点から運用実態を確認するモニタリング会合を実施しています。
今年度の会合では、Meta、LINEヤフー、Google の三社が対象となり、苦情処理、審査の判断過程、国内管理人の役割などについて詳細なヒアリングが行われました。本稿では資料に書かれている内容をもとに、EC事業者が広告運用の背景として理解しておくべき“構造上の見えにくさ”を丁寧に整理していきます。
参照:2025 年度 デジタルプラットフォームの透明性・公正性に関する モニタリング会合 意見とりまとめ (デジタル広告分野)
苦情はどこへ行くのか――三社に共通する“進捗の霧”
苦情が分類されるまで
資料では、広告主からの申立てと一般利用者からの意見が混在する状況が共通して示されています。とくに表現に関する領域では、一般利用者が不快感を示す一方で、広告主が正当な表現として扱ってほしいと考えている場合があり、判断の難しさが背景にあります。
LINEヤフーは寄せられた申立てを「苦情として扱うべきもの」かどうか、法令や契約に照らして分類し、申立て内容を社内システムに記録していると説明しています。記録の内容には、申立ての具体的な説明や部署間のやり取りなどが含まれ、管理体制として一定の形を整えています。
Meta でも国内管理人が苦情を受け付け、本社と情報を連携する仕組みがあるとされています。しかし、この段階でどのような判断が行われ、何が本社に回されるのかは資料内の記述では十分には把握できません。
進捗が見えにくい理由
資料で目を引くのは、Meta の申立てのなかに「五週間以上、状況が動かなかった」という例が存在する点です。対応が進んでいるのかどうかを広告主側が把握しづらい状況が生じており、国内管理人と本社の役割分担が十分に説明されていないことが背景にあります。
Google に関しても、国内管理人が申立てを受け、本社と連携して対応していると説明されていますが、本社側での判断過程がどのように進むかについて詳細な情報は資料から読み取れません。苦情処理のプロセスが複数階層に分かれており、それぞれの段階でどのような基準が使われているかが十分に説明されていないため、広告主が自ら状況を推定することは難しいのが実情です。
分析が進まない構造
複数の意見が寄せられても、それらの共通点を抽出し体系的に改善へつなげる仕組みは十分に機能していないことが資料で示されています。LINEヤフーでは苦情の分類や記録は整備されているものの、複数の案件を横断的に分析し、継続的な改善に生かす取り組みは限定的であると整理されています。
Meta も同様で、分析や改善に向けた体制が存在すると説明はされていますが、その運用状況や具体的な成果などは資料から判断できません。Google でも慎重判断や申立ての扱いそのものに一定の基準が存在することは示されていますが、分析の体系化についての言及は限られています。
審査はどう行われているのか――基準の“多層化”が生む不確実性
審査体制の概要
Metaは、審査・認証の仕組みや担当チームの存在、電話認証などを紹介しています。また、画像検出モデルの運用や多言語対応があることも説明しています。しかし、これらが広告主にとってどのような影響をもたらしているのか、実際にどの程度の改善が進んでいるのかといった効果の説明までは資料内で確認できません。
Google については、広告審査の中で特定領域に「慎重判断」が存在することが示されており、誤情報や不適切な内容を排除するために慎重な運用が行われていると説明されています。ただし、どのような基準で慎重判断が行われるかについては詳細が記されていません。
判断過程の不透明性
審査の判断基準が明確に説明されていない点は三社に共通しています。Metaでは国内管理人と本社の役割が明確に区分されていないため、どの段階で審査が止まるのかがわかりにくい状況が発生しています。Googleも同様に、どのような判断過程を経て審査が行われるかを広告主が把握することは難しく、慎重判断の仕組みに関して説明が十分ではないと資料では整理されています。
LINEヤフーでも、一般利用者と広告主の意見が対立する領域では、判断に多層的な検討が必要になるとしていますが、実際にどのような基準で判断しているかについて具体的な情報は限定的です。
誤審査・判断揺れが生まれる背景
資料から読み取れるのは、審査の多くが「個別の事情」に左右されやすいという点です。複数の案件を集約して基準を整備するという流れが十分に可視化されておらず、広告主側から見ると判断基準が揺れやすいと感じる状況が生まれています。
なりすまし広告という異物――三社が抱える共通課題
広告主が受ける負担
資料では、著名人などを偽装した広告により、広告主側に問い合わせが増加するなどの業務負担が生じていることが明確に示されています。利用者が誤認することで広告主にも影響が及ぶため、なりすまし広告は広告主にとって無視できないリスクであることがわかります。
Meta の対策とその説明の限界
Meta は電話認証や顔認識モデルを用いた検出など複数の対策を説明していますが、それらがどれほどの効果をあげているのか、資料には具体的な検証結果が示されていません。会合では、こうした対策の実効性をより客観的に説明する必要があるとの意見が述べられています。
なりすまし広告の“根深さ”
なりすまし広告は広告主・利用者ともに影響を受けるため、プラットフォーム側が対応しても課題が残り続ける構造にあります。資料では、一般利用者の意見と広告主の意見が対立する場面が多いことが示されており、判断が難しい領域であることが改めて確認されています。
国内管理人の役割――期待と実態のギャップ
制度上の設計と実態
国内管理人は、プラットフォームの国内窓口として、苦情の受付や進捗管理、本社へのエスカレーションを担う役割を持っています。しかし資料を見ると、説明の抽象度が高く、どの程度主体的に状況を把握し、どこから本社に引き継がれるかについて詳細が示されていない場面が多く見られます。
国内管理人はどこまで権限を持つのか
Metaでは、国内管理人が本社に状況を共有しエスカレーションを行うと説明されていますが、その後の対応に時間がかかる場合があることが資料で確認されています。
LINEヤフーは、広告主と一般利用者の意見を同一部門が扱っていることが特徴で、判断に複数の視点を取り入れていると説明しています。
Googleは、国内で申立てを受け付ける体制を持ちつつ、本社との連携を行うと説明していますが、本社判断の過程は資料では十分には把握できません。
期待と現実の間にある距離
資料全体を通じて、国内管理人の役割は重視されつつも、実態がどこまで役割通りに機能しているかを測るだけの情報は限定的であることが読み取れます。会合では、国内管理人が進捗管理を強化し、広告主が状況を把握しやすくなる形で情報を提供する必要があると指摘されています。
プラットフォーム内部の判断ロジックはどこまで公開されているのか
“具体性不足”という共通課題
資料では、Metaの審査・認証体制の説明が改善の方向性にとどまっている点、LINEヤフーの分析体制が改善に十分に結びついていない点、Googleの慎重判断に関する説明が粒度として十分ではない点が、それぞれ課題として示されています。
説明の深さと簡潔さ
三社とも取り組みそのものは説明していますが、広告主が判断の背景を理解できるほどの具体的な内容に至っているケースは限定的です。プラットフォーム側で詳細な基準を内部に持っている可能性はありますが、資料には広告主向けに公開されている情報が限られている実態が示されています。
透明性への期待と限界
会合がプラットフォーム側に求めているのは、運用の詳細や基準を可視化することで、広告主が自身の状況を正しく把握できるようにすることです。ただし、資料内の説明では、その期待に十分に応えられているとは言い難い状況であり、透明性向上は今後も継続的な課題であると整理されています。
EC事業者が向き合う「広告運用の前提条件」
資料が示す実態
審査、苦情処理、分析、国内判断、本社判断――どの領域にも不確実性が残っていることが資料から読み取れます。これは広告主の努力では解消できない構造的な問題であり、プラットフォーム側の情報提供が限定的であることが背景にあります。
不確実性をどう理解するか
資料の事実だけに基づくと、広告運用には複数の層が存在し、そのいずれもが完全には可視化されていないことが明らかになります。審査が止まる理由、基準が揺れる背景、申立ての進捗が遅れる構造などは、資料内に点在する記述から読み取れる“現実”です。
広告主が採るべきスタンス
資料が示すのは、透明性が不十分な環境に対して広告主が“過度に透明性を期待しすぎない”姿勢が必要だという点です。プラットフォーム側が説明責任を果たすべき領域は多く残っているものの、現状では広告運用の判断が外的要因に左右されやすく、広告主が前提としてその不確実性を理解しておくことが重要になります。
透明性の行方を見守りながら、正しい理解を持つことから始める
2025年度モニタリング会合の資料を丁寧に読み解くと、三社それぞれが取り組みを進めてはいるものの、広告主にとって十分に透明とは言えない領域が多く残っていることがわかります。国内管理人の役割、審査体制、苦情処理の流れ、なりすまし広告への対処など、どの領域も発展途上にあり、さらなる改善が求められています。
EC事業者にとって重要なのは、こうした環境の中で広告を活用する際、正しく前提を理解し、自社の状況を適切に把握しながら向き合うことです。透明性を巡る議論は今後さらに重要度を増していくため、プラットフォーム側の発信と動向を注視し続ける姿勢が求められます。
あわせて読みたい