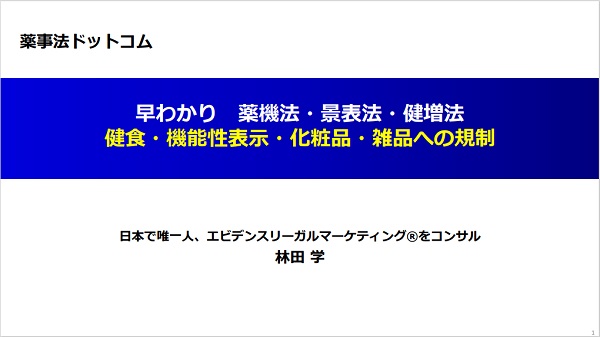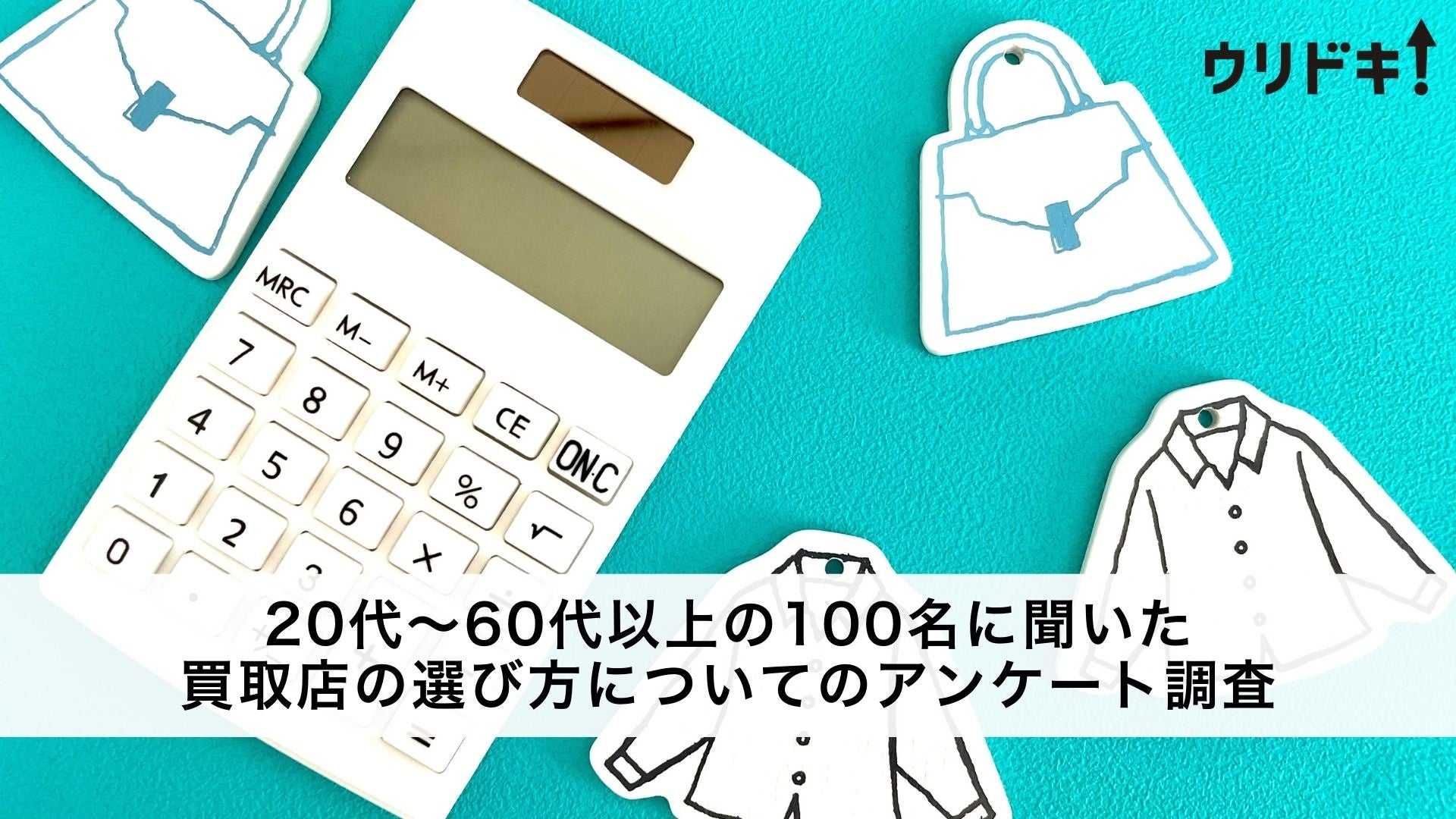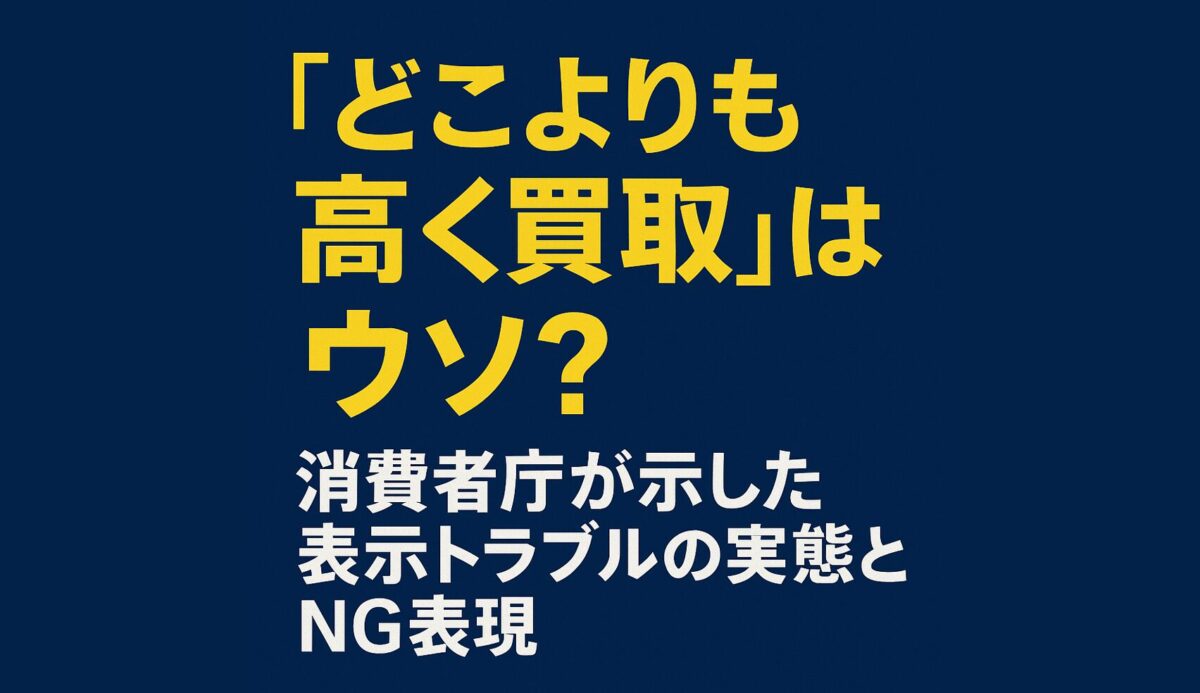
この記事の目次
はじめに
買取サービスの市場が拡大する中で、広告表示と実際のサービス内容のギャップによる消費者トラブルが増加しています。とくに「高価買取」「価格保証」などの表示が、根拠が不明確なまま用いられ、誤認を招くケースが問題視されています。
こうした背景を受け、消費者庁は令和6年度に買取サービスの広告表示に関する実態調査を実施し、令和7年4月に報告書を公表しました。調査では、広告表示の分析に加えて、消費者アンケートと事業者ヒアリングも行われ、表示に起因する誤認やトラブルの実態が明らかになっています。
本記事では、この調査結果をもとに、業界が直面するリスクや消費者庁の考え方を整理し、買取サービス事業者が今後とるべき対応を解説します。
調査実施の背景
調査の背景と目的
買取サービスを提供する事業者による広告表示については、近年、消費者からの苦情や相談が増加しています。特に買取価格に関する表示において、実際の取引と広告表示の間に乖離があり、消費者が混乱するケースが目立ってきました。これらの状況を背景として、消費者庁は景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)の適用対象となる買取サービスについて、広告表示の実態を調査し、消費者保護の観点から問題点を明確にすることを目的として、本調査を実施しました。
具体的には、「買取参考価格」や「買取実績価格」などの表示が適正であるか、「買取価格アップ」や「どこよりも高く買取り」といった比較広告の妥当性などを精査し、消費者が誤解する可能性がある表示についての現状を把握しています。
また、本調査は買取サービス事業者自身が表示内容をどのように決定しているのか、消費者の誤解や混乱を防ぐためにどのような対策を行っているかについてもヒアリングを通じて確認しました。
買取サービス市場の現状
買取サービス市場は近年拡大を続けており、調査時点(2023年度)の市場規模は約1兆3,000億円にのぼっています。特に市場規模が大きいのは「ブランド品」および「スマートフォン、ゲーム機器」などの電子機器であり、これらのジャンルにおいて市場競争が激化しています。
買取方法についても多様化が進み、従来の店頭買取に加えて、宅配買取や出張買取など、消費者が自宅にいながら手軽にサービスを利用できる形態が増えています。このような非対面型の買取サービスが拡大する中で、消費者が取引の実態を事前に確認しにくく、広告やウェブサイト上の表示を信頼して取引を進めるケースが多くなっています。その結果として、表示内容と実際の取引内容の乖離が消費者トラブルの一因となっていることが課題として指摘されています。
こうした市場環境を踏まえ、買取サービスを提供する事業者が消費者に対して適切でわかりやすい情報を提供することが、消費者保護および市場全体の健全化に必要であることから、本調査の実施に至りました。
実態調査の概要
消費者庁は、買取サービスにおける広告表示が消費者に誤解や不利益を与える可能性があるかを調査するため、次の3つの方法による実態調査を実施しました。
① 広告などのサンプリング調査
令和6年(2024年)12月に、買取サービスを提供している事業者の広告表示物をサンプリング調査しました。調査対象は、店頭やウェブサイト、チラシ、DMなど、さまざまな媒体での広告表示で、計50社から収集した広告表示物について内容を分析しています。
分析の主なポイントは以下の通りです。
- 「買取参考価格」や「買取実績価格」など、買取価格に関する表示が消費者に誤解を与える可能性がないか。
- 「買取価格アップ」「買取価格保証」「何でも買取り」「どこよりも高く買取り」といった表示の妥当性・根拠の明確性。
② 消費者アンケート調査
消費者アンケート調査は、買取サービスの利用実態および消費者の表示に関する認識を把握するために行われました。
- 調査対象: 20代~60代の男女、全国1,037名(直近3年以内に買取サービスの利用経験がある人)
- 調査方法: インターネットアンケート調査
- 調査期間: 令和6年(2024年)12月
調査の主な内容は以下の通りです。
- 買取サービスの利用頻度や利用形態(店頭・宅配・出張など)
- 広告表示(買取価格、価格保証、買取条件など)を見た際の受け止め方・理解度
- 実際にサービスを利用した際の表示と査定価格の一致度や満足度
③ 買取業者へのヒアリング調査
ヒアリング調査は、買取サービス提供事業者がどのように表示内容を決定し、どのように消費者に伝えているのかを具体的に確認することを目的に行われました。
- 調査対象: 買取サービスを提供する事業者14社(大手・中小含む)
- 調査期間: 令和7年(2025年)1月~3月
- 調査方法: 個別インタビュー形式(訪問またはオンライン)
ヒアリングの主な調査項目は次の通りです。
- 買取参考価格や実績価格、価格アップ表示の根拠や査定方法
- 消費者への説明内容や表示方法の決定プロセス
- 広告表示において注意しているポイントや、表示と実際の査定価格が乖離する場合の対応方法
- 消費者からの苦情・トラブル対応体制
これらの3つの調査を通じて、買取サービス業界における表示の実態と、消費者の認識や業者の対応状況が明らかになりました。
調査結果の詳細と消費者意識
本章では、調査で明らかになった買取サービスの利用実態と、広告表示に対する消費者の認識について、詳しく解説します。
買取サービス利用の実態
消費者アンケート調査(対象:直近3年以内に買取サービスを利用した1,037名)の結果、買取サービスの主な利用形態は以下のようになりました。
- 店頭買取:85.1%
- 宅配買取:27.3%
- 出張買取:16.1%
- オンライン査定:11.9%
多くの消費者が店頭買取を利用しており、その理由としては「直接査定してもらえる安心感」「即金性」などが挙げられました。一方で宅配買取や出張買取を利用する理由は「店舗に行く手間が省ける」「自宅で手軽に査定が受けられる」などの利便性が主な要因です。
消費者が複数の店舗を比較しない理由としては、「複数店で査定を受けるのが面倒」(57.6%)、「早く売却したかったから」(38.9%)、「査定価格に大差がないと思ったから」(27.1%)という回答が目立ちました。
各表示類型に関する消費者の認識
調査では、買取サービスの広告表示について消費者がどのように認識しているかを確認しました。主な表示類型に対する消費者の受け止め方は次の通りです。
①「買取参考価格・買取実績価格」の表示
消費者の約6割は「実際の買取価格に近い価格が提示されている」と認識。一方、約4割は「参考程度で、実際には大きく下がる可能性がある」と考えています。
②「買取価格アップ」の表示
約7割が「通常価格よりも明確に高く買い取ってもらえる」と認識している一方で、実際の査定時に条件が厳しく、表示どおりにならないケースへの不満が多く見られました。
③「買取価格保証」の表示
「提示された価格が必ず保証される」と約8割が認識しており、実際に店舗を訪れた際に条件付きだったケースで不信感を抱く消費者が多いことがわかりました。
④「何でも買取り」の表示
約6割が「どんな品物でも買い取ってもらえる」と認識していますが、実際には買取対象外の商品も多く、トラブルにつながる事例も報告されています。
⑤「どこよりも高く買取り」の表示
約5割の消費者が「他社より確実に高く買い取ってくれる」と考えており、実際にはその根拠が曖昧で、結果として期待を裏切られたとの回答が多数寄せられています。
こうした調査結果から、多くの消費者が表示内容をそのまま受け止め、実際の査定価格とのギャップに不満や不信感を感じていることが明確になりました。
買取事業者の表示実態と法的リスク
買取サービスを提供する事業者へのヒアリング調査(対象事業者14社)から、各表示類型に対する事業者の実際の対応状況および法的なリスクを整理しました。
各表示類型の実態とリスク
①「買取参考価格・買取実績価格」の表示
多くの事業者が、「買取参考価格」や「買取実績価格」を広告に掲載する目的として、「消費者の関心を引くため」や「自社の競争力をアピールするため」と回答しています。一方で、表示されている価格については「商品の状態や時期により大幅に変動する」「掲載時と実際の買取価格が乖離する場合がある」と多くの事業者が認めています。
法的リスク:実際に提示可能な価格との乖離が著しい場合、景品表示法の「有利誤認表示」に該当する可能性があります。
②「買取価格アップ」の表示
事業者の多くは、「買取価格アップ」の表示をキャンペーンとして実施していますが、「特定条件を満たした場合のみ適用」されることが多く、その条件はウェブサイトや店頭で細かく記載されています。しかし、消費者にはそれが明確に伝わっていないケースがあります。
法的リスク:「価格アップ」が条件付きであることを明示していない、または条件が不明瞭な場合、消費者に誤解を与え、「有利誤認表示」として問題になる可能性があります。
③「買取価格保証」の表示
「買取価格保証」と表示している事業者では、表示されている価格を保証する具体的な条件(状態・付属品の有無・査定期限)が存在しています。しかし消費者への説明が不十分である場合が多く、店舗訪問後にトラブルになるケースもあります。
法的リスク:「保証価格」が明示条件以外では適用されないことが消費者に十分伝わっていない場合、「有利誤認表示」として行政指導の対象となる恐れがあります。
④「何でも買取り」の表示
多くの事業者が「何でも買取り」と表示している理由として、「消費者に気軽に来店してもらうため」としています。しかし実際には買取対象外商品が存在し、これを明確に伝えないことが消費者とのトラブル要因となっています。
法的リスク:買取できない商品が明確に存在するにもかかわらず「何でも買取り」と表示することは、「優良誤認表示」に該当する可能性があります。
⑤「どこよりも高く買取り」の表示
一部の事業者が「どこよりも高く買取り」と表示していますが、多くの場合、「競合店の査定額が提示された場合に限りそれより高くする」との条件付きとなっています。
法的リスク:競合店の提示価格の証明が必要であることを明確に伝えない場合や、比較対象が曖昧な場合、「有利誤認表示」または「優良誤認表示」として指導対象になる可能性があります。
以上のように、各種表示について事業者側が明確に条件を提示・伝達していないケースが多く、これが法的リスクにつながる可能性が高いことが明確になりました。
買取サービスにおける景品表示法上の考え方
買取サービスにおいては、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)上、主に「優良誤認表示」と「有利誤認表示」の2つが問題になります。本章では、具体的な表示類型について消費者庁の見解を整理し、各事業者が注意すべきポイントを解説します。
景品表示法上の表示の基本的な考え方
① 優良誤認表示
「優良誤認表示」とは、商品の品質や規格、内容などが実際よりも著しく優れていると消費者に誤認させる表示を指します。
買取サービスの場合、例えば「何でも買取り」と表示していながら、実際には多くの買取不可商品がある場合、「優良誤認表示」に該当します。
② 有利誤認表示
「有利誤認表示」とは、価格や取引条件が他社や通常よりも特に有利であると消費者に誤認させる表示を指します。
買取サービスにおいて「買取価格保証」「どこよりも高く買取り」といった表示を用いる場合、実際には条件付きであり、その条件が消費者に明確に伝わっていない場合、「有利誤認表示」として指摘を受ける可能性があります。
各表示類型に関する具体的な消費者庁の見解と問題となる表示例
①「買取参考価格・買取実績価格」の表示について
参考価格が実際の取引価格と大幅に異なる場合、「有利誤認表示」に該当する可能性があります。消費者が「その価格で売れる」と誤認するような表示は、適正とは言えません。
②「買取価格アップ」の表示について
「買取価格アップ」が常に適用されるかのように表示され、実際には特定条件がある場合、その条件を消費者に明確に示さないことは「有利誤認表示」に該当する恐れがあります。適用条件や期間を明示しましょう
③「買取価格保証」の表示について
表示された価格が無条件で保証されるように誤解される表示は、「有利誤認表示」となる可能性が高いため、保証の対象条件を明示することが求められます。
④「何でも買取り」の表示について
買取不可商品が明確に存在するにもかかわらず、「何でも買取り」と表記することは、消費者の期待を裏切るものであり、「優良誤認表示」に該当する恐れがあります。
⑤「どこよりも高く買取り」の表示について
他社との価格比較を行う場合、比較対象や根拠を明確に示す必要があります。根拠や比較基準を示さずに用いる場合、「有利誤認表示」あるいは「優良誤認表示」として問題になります。
景品(次回利用クーポン、キャッシュバック、ポイント)提供の規制内容
買取サービス利用後に提供される次回利用クーポンやキャッシュバック、ポイントについても、以下の点に注意が必要です。
- 提供される景品類が景品表示法の「景品類の提供制限」に抵触しないよう、その価値や提供方法について適正な範囲内で設定すること。
- 景品提供条件を明確に表示し、消費者に誤解を与えないよう配慮すること。
以上のように、買取サービスの表示に関して消費者庁は各事業者に対し、景品表示法上の明確な基準と注意点を示しています。適切な対応を怠ると、行政指導や措置命令など法的措置を受ける可能性があるため、事業者は自社の表示方法を早急に見直す必要があります。
消費者庁の今後の取組
今回の調査結果を踏まえ、消費者庁は買取サービスに関する広告表示の適正化に向けて、以下の方針で今後の施策を展開することを明らかにしています。
① 表示の適正化に向けた業界への要請
調査で明らかになった通り、買取サービス業界では「買取価格保証」「どこよりも高く買取」など、消費者の誤認を招くおそれのある表示が多数確認されました。
これを受けて、消費者庁は以下の対応を進めるとしています。
- 不適切な表示に対しては個別に是正を求める
- 業界団体や主要事業者への周知と働きかけを強化
- 表示の在り方に関する明確なガイドラインの検討
とくに価格表示の根拠や適用条件、保証対象といった情報を明示する表示慣行の定着が求められています。
② 消費者への情報提供と注意喚起
消費者側にも「買取サービスの広告はすべて保証価格ではない」ことへの理解が不十分であることが判明したため、以下のような消費者啓発活動が進められます。
- 不当表示の例やトラブル事例の共有
- 国民生活センターや自治体との連携による広報
- 消費者庁ウェブサイト等を通じた啓蒙コンテンツの発信
これにより、消費者が買取サービスを利用する際に、表示内容をうのみにせず冷静に判断できるような「見極め力」の向上を目指しています。
③ 景品表示法に基づく行政措置の強化
重大な違反が認められる表示については、今後、消費者庁は景品表示法に基づく迅速な措置命令の発出も視野に入れると明記しています。
また、調査報告書の末尾には「明らかに不当な表示は、引き続き厳正に対処していく」との姿勢が記されており、実効性ある法執行を通じた未然防止を重視する方針が示されました。
おわりに
買取サービスの市場が拡大する一方で、広告表示と実際のサービス内容のギャップにより、消費者が誤解や不信感を抱くケースが後を絶ちません。今回の消費者庁による調査は、そのような実態を浮き彫りにし、事業者・消費者の双方に対する具体的な課題と改善の方向性を明示したものです。
買取参考価格や価格アップ保証などの魅力的なフレーズは、適切な根拠と明示があって初めて成り立つ表現です。景品表示法の視点では、表示が消費者に与える「印象」が重視されるため、いかに法的に問題がないつもりでも、結果として誤認を招く表現であれば指導や措置命令の対象となり得ます。
事業者にとっては、表示の透明性を高め、消費者からの信頼を得ることが、長期的な競争力につながります。今後、業界全体でルールの明確化と実務の標準化が求められるなかで、本調査報告書は重要なガイドラインとなるはずです。
一方で、消費者もまた、表示の裏にある条件や例外を読み取り、自らを守る判断力を養うことが求められます。買取サービスを巡る表示トラブルの未然防止には、事業者と消費者の双方の努力が不可欠です。
あわせて読みたい