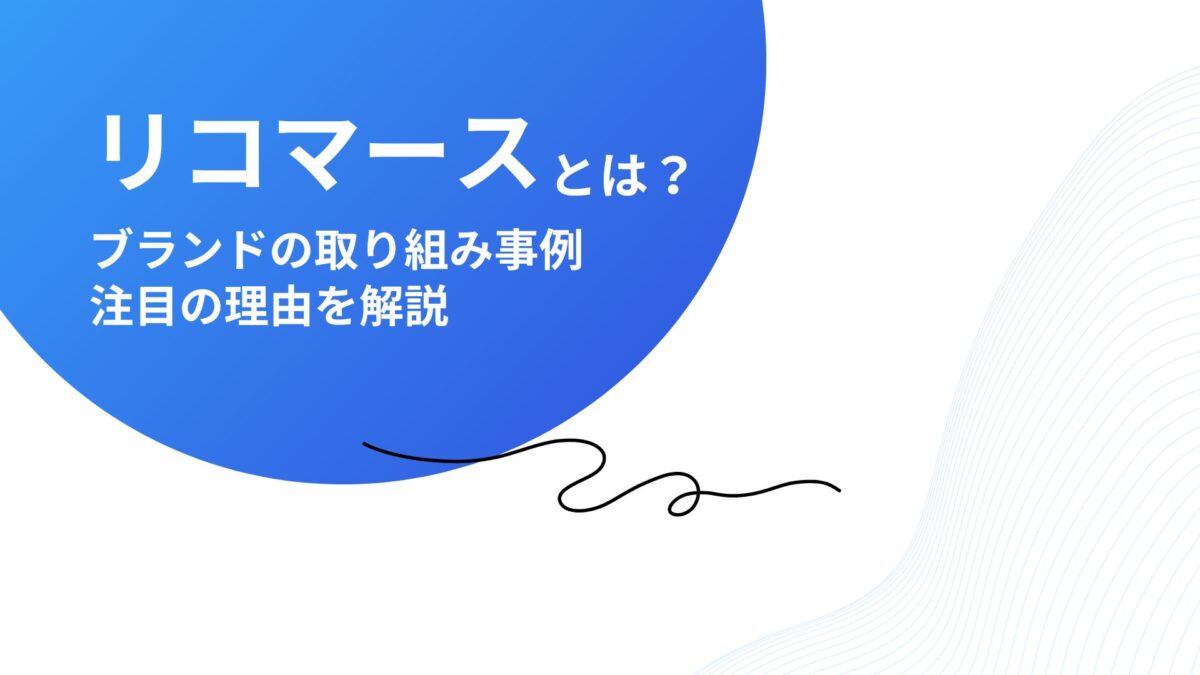本記事では、欧州を中心としたEC関連の最新トピックをお届けします。今回は、「TikTok Shopがドイツでローンチ後も低調なスタートを切っている実態」、「Amazon欧州責任者が語る中小企業支援と欧州市場の課題」、そして「再利用市場拡大を背景にECが循環経済を加速させているという調査報告」の3つのニュースを紹介します。
この記事の目次
ドイツで苦戦するTikTok Shop、認知度はあるも利用率は低迷
2025年3月末にドイツでローンチしたTikTok Shopは、2か月が経過した時点でも本格的な立ち上がりには至っていません。調査会社OMDによると、TikTok Shopの認知率は全体の34%と一定の浸透を見せる一方で、実際に購入経験のあるユーザーはわずか2.5%にとどまりました。特に若年層(18~29歳)での認知率は47%と高いものの、購買に結びついたのは3.7%と限定的です。
一方で、今後の購買意向を持つユーザーは全体の8%、30代では10.8%とポテンシャルの存在も示されています。TikTokの文化的文脈にフィットするブランドであれば、今後の展開次第では販売チャネルとしての活路が期待されます。
英国では急成長、ドイツとのギャップが鮮明に
TikTok Shopは2021年末に英国で欧州初展開を行いましたが、当初は期待外れのスタートとなり、欧州本土での展開も一時見送られていました。しかし、2024年にはライブコマースの活況を背景に大きく成長。出店するローカル事業者は20万社を突破し、取引量も急増しました。
これを受けてTikTokは、ドイツを含む欧州本土への展開を再始動。しかし現時点では、英国での成功事例のような目に見える成果は得られておらず、ドイツ市場での浸透には時間を要する可能性があります。なお、英国同様、TikTokはドイツでも出店者向けのフルフィルメント支援を計画しており、今後の成長に向けたインフラ整備も進められています。
日本におけるTikTok Shopの受容と可能性
TikTok Shopは2025年6月、日本でも正式にサービスを開始しました。ローンチからまだ日が浅く、現時点での利用実態や購買動向は限定的ですが、新たなECプラットフォームとして注目を集めつつあります。
ドイツでは「認知度はあるが、購買には至っていない」という傾向が報告されましたが、日本でも同様の課題が浮上する可能性は考えられます。今後、決済・配送などのインフラ整備や、販売者・消費者双方への運用支援体制の構築が、サービスの定着を左右するポイントになるでしょう。ECモールに依存しない新たな販路として中小ブランドの受け皿となるか、欧州の展開状況は日本市場の行方を占う上でも示唆に富んでいます。
参照:TikTok Shop yet to take off in Germany
欧州経済におけるAmazonの役割、「敵ではなく味方」と強調
Amazon EUストア担当VPのマリアンジェラ・マルセリア氏は、欧州経済に対する同社の貢献を強調し、「私たちは敵ではなく、ビジネスの成長を支えるパートナーです」と述べました。Amazonは欧州で127,000以上の中小企業(SME)の越境ECを支援し、輸出の手続きを簡素化。2024年にはEU域内のGDPに410億ユーロを寄与し、約23万人の雇用も創出しています。
また、欧州全体での広告収益の増加を背景に、同社の収益構造も進化を続けています。ECと実店舗の共存を予測するマルセリア氏は、「顧客はオンラインもオフラインも使い分けている」と指摘し、EC市場の拡大と従来型商業の共生が進む未来を展望しています。
単一市場化の遅れが中小事業者の越境ECを阻む懸念も
Amazonのマルセリア氏は、米国のような完全な単一市場と比較し、欧州では27の国が異なる規制で動いている現状に課題を感じていると述べています。Amazonのような大企業であれば対応可能ですが、小規模な出店者にとっては越境販売の障壁となっているのが現実です。法規制の違いに加え、複雑な手続きや書類対応が、中小企業の事業展開を困難にしていると指摘。これを背景に、欧州域内での制度統一や法整備の重要性を訴えています。
また、物価高に伴う消費者の節約志向にも言及し、日用品に重点が移る傾向や「Prime Day」「ブラックフライデー」などディールイベントへの関心が顕著であることを強調しました。
欧州EC市場の成長と制度整備の両立が今後の焦点に
Amazonは欧州においても強いプレゼンスを維持しながら、中小事業者の販路拡大や経済成長に寄与していることを強調しています。広告や越境ECを軸にしたビジネス支援は、SMEにとって大きな機会であり、Amazonが「成長の味方」として機能している構図が見て取れます。
一方で、国ごとに異なる規制体系や法的要件が欧州の足かせになっており、制度の統一化が喫緊の課題といえるでしょう。消費者側でも物価上昇を受けて「お得感」のある購買行動が加速しており、Amazonのようなプレイヤーがどのように価格施策や支援体制を整えるかが、今後のEC市場の成長に直結すると考えられます。
参照:European Amazon Boss: ‘We are an ally’
ドイツで進む「リコマース」浸透、消費者の半数以上が中古品を売買
ドイツにおいて、リコマース(中古品のオンライン売買)が消費者の間で急速に広まっています。調査によると、昨年は55%の消費者が中古品をオンラインで購入し、52%が販売経験を持つという結果が明らかになりました。取引される主な品目はファッション、書籍、家電などで、再購入の意欲も高く、77.6%が今後12か月以内に再び中古品を購入すると回答しています。
こうした消費行動は価格志向に加え、環境意識の高まりにも起因しており、安価で価値のある商品を持続的に活用したいという姿勢が読み取れます。eコマースを通じたリコマース市場の成長は、線形経済から循環経済への転換を後押しする重要な潮流となりつつあります。
大手企業もリコマース市場に参入、循環型経済の担い手としてECが台頭
リコマースの広がりに伴い、P2Pプラットフォームにとどまらず、大手小売企業の参入も進んでいます。IKEAは中古家具の専用マーケットプレイスを立ち上げ、Decathlonはスポーツ用品の中古販売支援を開始。Amazonも欧州での中古品販売を数十億ユーロ規模に成長させ、TikTok Shopも欧州本土での展開を視野に入れています。bevh(ドイツ通信販売協会)は、ECが「使い捨て文化」の対抗軸となり、価格とサステナビリティを両立させる購買行動を支えると主張します。
政策支援により、再生品やリファービッシュ品(整備済みのリユース品)、再利用品の明確な定義と表示制度を整備することで、さらなる市場拡大と消費者信頼の獲得が期待されています。
日本でも拡がるリユースEC、メルカリを軸に循環型消費が定着へ
ドイツと同様に、日本でもリユース市場はeコマースを通じて大きく成長しています。特にメルカリの存在は象徴的で、個人間取引(C2C)を中心に中古品の流通が日常化しています。フリマアプリ以外にも、ブックオフやセカンドストリートのような実店舗系リユース事業者がECを強化しており、書籍・衣類・家電など幅広いカテゴリーでオンライン売買が一般化しています。
環境配慮と節約志向の高まりを背景に、日本でも「サステナブル消費」としての中古品購買が市民権を得つつあります。政策面では、リユース推進に向けた明確な表示基準やデジタル管理の強化が今後の課題となるでしょう。
参照:‘Ecommerce is the driving force of the circular economy’
あわせて読みたい