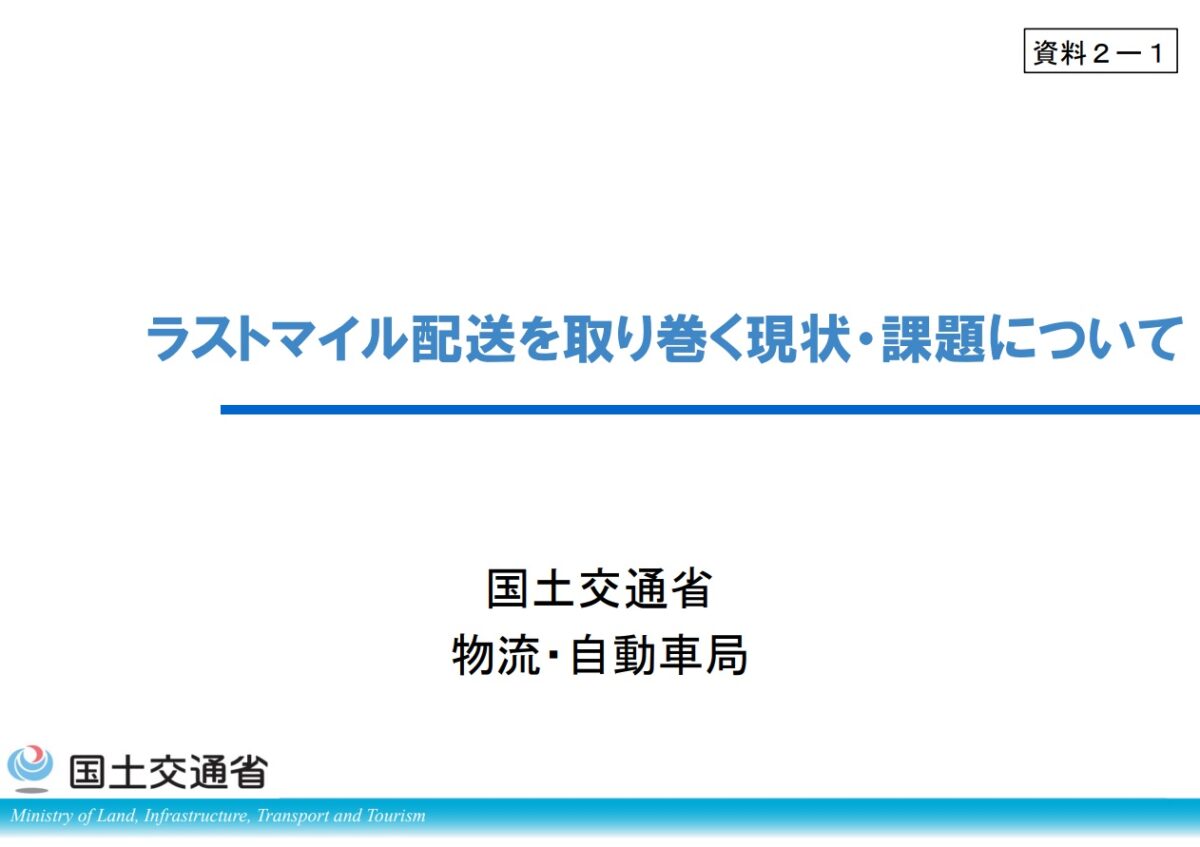
物流のラストマイルを巡る課題が深刻化する中、国土交通省は2025年6月26日、「ラストマイル配送の効率化等に向けた検討会」の第1回会合を開催しました。
本検討会では、置き配やドローン、自動配送ロボットの社会実装、さらには駐車規制の見直しまで、多岐にわたる施策の方向性が議論されました。EC事業に直結するテーマも多く、今後の制度設計や支援策の動向が注目されます。
この記事の目次
省庁横断の検討会が始動、ラストマイル課題に対応へ
国土交通省が設置した本検討会は、「物流2024年問題」や再配達率の高さ、マンション配送の非効率性といった、ラストマイルにおける社会課題を背景に立ち上げられました。第1回会合には、経済産業省、警察庁など複数の関係部局が出席し、現状と課題に関する説明のほか、各機関による最新の取り組みが紹介されました。
国交省は「ラストマイル配送」の定義を、最終的な配送先である個人宅や事業所までの区間とし、そこに発生する非効率やコスト増、再配達による環境負荷などを重点課題としています。特に、都市部を中心に顕在化する課題に対し、省庁横断での対策立案・政策検討の場として、この検討会が活用される意義は大きいといえます。
今後は、ECや宅配に関わる業界関係者からのヒアリングや、技術・制度面の論点整理を経て、秋頃には一定の取りまとめが予定されています。議論の行方は、配送現場の効率化やインフラ整備だけでなく、EC事業者の販路設計やサービス提供にも影響を与える可能性があります。
置き配の普及を阻むマンション課題に対応へ
国土交通省が示したデータによると、都市部では不在再配達が依然として多く、配送効率の低下やドライバー負担の増大が課題となっています。特にマンション居住者の置き配利用率が低いことが注目されています。
例えば、玄関前への置き配を許可している人の割合は戸建てで約63%であるのに対し、マンションでは約37%にとどまります(2023年国交省調査より)。背景には、防犯面の不安やマンション管理規約の制約、住民間での合意形成の難しさなどがあり、個人の意思だけでは置き配が進みにくい現実があります。
これに対し、国交省は東京都港区などでの先行事例を挙げつつ、管理組合・管理会社との連携支援や、置き配に関する住民向け説明ツールの提供などを通じて、置き配の利用促進を後押しする考えを示しました。国としての介入によって、個人の宅配体験を改善するだけでなく、配送事業全体の効率性向上につなげたい狙いがあります。
さらに、議論の中では、置き配が社会インフラとして定着している海外とのギャップも暗に意識されています。たとえばアメリカでは、Amazonをはじめとする大手事業者が置き配をデフォルト設定としており、オプトアウト方式(手渡し希望者が選択)を採用しています。中国でも都市部を中心に置き配ロッカーやスマート宅配ボックスの普及が進んでいます。
一方、日本ではオートロック付き集合住宅が多く、共用部での荷物管理に関する規制や心理的なハードルが存在します。置き配のルール設計には、プライバシー・セキュリティの確保と物流効率のバランスが不可欠であり、制度と技術の両面からのアプローチが求められています。
今後の検討会では、置き配を「個人の判断」に委ねるだけでなく、「合意形成をどう支援するか」「標準的な置き配対応をどう設計するか」といった実務的な制度整備の方向性が注目されます。
ドローン・配送ロボの実装が進展、制度整備も加速
ラストマイル配送の効率化に向けては、ドローンや自動配送ロボットといった新たなモビリティの社会実装も進められています。第1回検討会では、過疎地域におけるドローン配送の実績や、都市部における配送ロボットの運用状況が共有されました。
特にドローンに関しては、2022年の航空法改正により「レベル4飛行」(補助者なしでの有人地帯上空の目視外飛行)が可能になったことが転機となりました。長崎県五島市では、民間企業が医薬品をドローンで配送するサービスを展開しており、商用化の先行事例として注目されています。さらに、東京都檜原村や北海道上士幌町などでは、山間部を対象とした生活物資の定期配送にも取り組んでいます。
今回の検討会では、多数機同時運航(1人の操縦者が複数機を操作)についても、制度整備の進展が報告されました。運用ガイドラインや航空法の解釈通達の見直しにより、将来的にはAIによる自律飛行や、地域内の定常的なドローン物流ルートの実現も視野に入っています。
自動配送ロボットに関しては、2023年4月から新制度のもとで道路使用が可能となり、現在は10都府県26市区町村で実証・運用が進行中です。最大3時間、4km程度の配送が可能とされており、食品デリバリーや宅配便再配達の代替手段としてのニーズが高まっています。
今後は、これらの技術を単なる「代替手段」にとどめず、地域のインフラの一部として持続的に機能させる制度・コスト設計が求められます。配送網の“ラスト100メートル”を担う存在として、法整備・道路環境・住民理解の三位一体の取り組みが不可欠です。
農村の物流維持と都市部の駐車対策を両輪で推進
農村部では、人口減少や高齢化により、これまで地域物流を担っていた事業者が撤退・縮小するケースが増加しています。特に医薬品や生鮮食品といった日常生活に不可欠な物流が滞るリスクが深刻です。
農林水産省は、こうした地域に向けて「スマート農業実証プロジェクト」を通じ、ドローン・小型EV・電動カートなどの導入を進めるとともに、農産物・生活物資をまとめて配送する「共同配送」のモデルづくりを進めています。2024年度には10地域を新たに追加し、自治体・事業者・住民が連携した持続的な配送網の構築を図っています。
一方、都市部では物流ニーズの増加により、貨物集配中の駐車スペース不足が大きな課題となっています。荷さばき中の車両が路上駐車として取り締まられるリスクがあるほか、駐車場所を探す時間が配送効率を下げ、周辺住民とのトラブルにつながるケースもあります。
警察庁は、駐車許可制度の全国統一運用(2024年7月施行)や、貨物車専用駐車枠の整備によって、現場の柔軟な運用を後押ししています。こうした取り組みの結果、貨物車の駐車可能区間は平成29年度比で約2万8千メートル拡大しました。
ただし、制度整備だけでは不十分との声もあり、今後は民間施設の荷さばきスペースの開放や、配送タイミングの分散化、動態管理との連携など、より複合的な対応が求められます。
今後の検討スケジュールと議論の見通し
検討会では、今後の進め方についても共有されました。2025年7月中には第2回検討会を開催し、ラストマイル配送を巡る直近の情勢について、関係業界などからのヒアリングが実施される予定です。
第2回以降の会合では、事業者が直面している現場の課題や、先進事例の紹介を踏まえながら、制度整備や技術導入におけるボトルネックを洗い出していく見通しです。また、ヒアリングを通じて、国の支援が必要とされる領域や、地域特性に応じた政策設計の方向性も明らかにしていくとしています。
その後、8月以降に第3回・第4回の検討会が予定されており、これまでの議論を踏まえた論点整理や取りまとめ案の提示が行われる見込みです。これにより、秋頃には具体的な政策提言やガイドライン案の提示がなされる予定です。
物流・EC事業双方に影響、今後の動向に注目
ラストマイル配送を取り巻く課題は、都市部・地方部ともに複雑化しており、単一の対策では解決が困難です。今回の検討会では、置き配の普及やドローン・配送ロボットの導入、駐車規制の緩和など、多面的なアプローチが打ち出され、国が横断的に対応を進める姿勢が明確になりました。
EC事業者にとっては、配送の効率化がもたらすコスト構造の変化や、ユーザーへの提供価値の再設計にもつながる可能性があるため、今後の制度設計の行方を注視する必要があります。配送の現場に関わるすべてのプレイヤーが共通の課題を共有し、連携を深めることが、持続可能な物流インフラの構築につながっていくでしょう。
あわせて読みたい
















