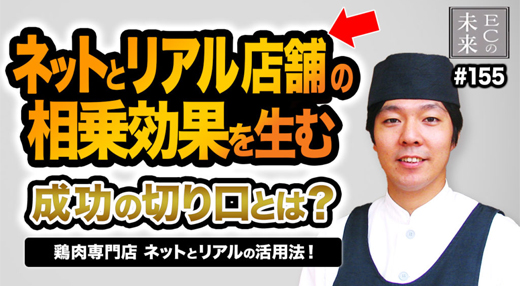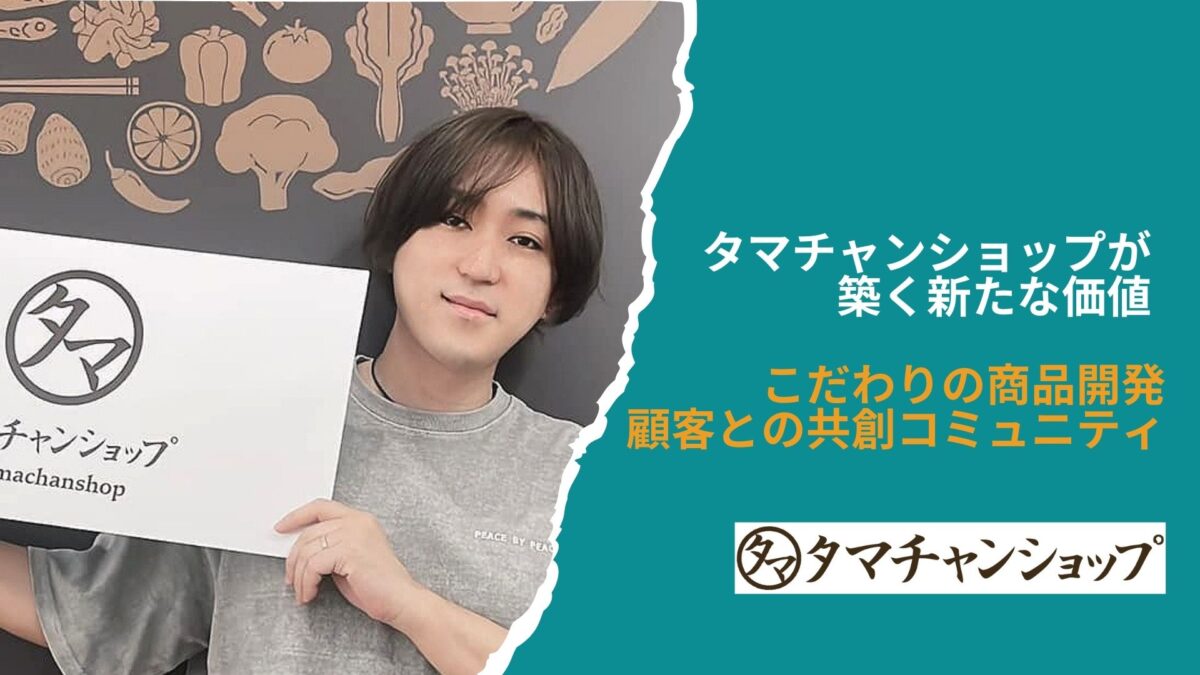【ゲストスピーカー】
須田 健久さん
株式会社須田本店 代表取締役
鶏肉専門店「水郷のとりやさん」
【チャンネルMC】
柳田 敏正さん
株式会社柳田織物 代表取締役
ワイシャツ専門店「ozie(オジエ)」
この記事の目次
商品の特徴を意識した商品開発と販売方法
普段の食事向け、メディア向け、珍しいものなど300アイテムを販売
柳田さん:「水郷のとりやさん」では、焼き鳥や唐揚げだけでなく、鶏肉を基点にした商品バリエーションが充実していますが、こだわりをお聞かせいただけないでしょうか?
須田さん:鶏肉専門店ですから、鶏肉の商品しかありませんが、アイテム数としては300商品以上あります。その中でも普段から食べる料理、特別な日に食べる料理などと分けて商品開発を行っています。
最近出した麻婆豆腐の素を開発した経緯としては、私の幼馴染にミシュラン二つ星を獲得した中華の料理人がおります。何か一緒に美味しいものを作れないかという話になり、「通販で本格的な中華が食べられる」をコンセプトに商品開発を行うことにしました。
辛味がしっかりありますが、商品のコンセプトページでしっかり伝えることで、それを食べたいと思った人が買ってくださって、イメージと合っているからレビューの評価が高いのだろうと感じています。
柳田さん:「美味しい」と伝えるのではなく、具体的な味を伝えているということがポイントですね。
須田さん:そうです。メディアでよく取り上げていただく商品としてはレバーパテがあります。焼き鳥店「バードランド」のお客様が、ワインを飲みながらレバーのパテを食べているのを見たとき、衝撃を感じました。水郷のとりやさんで働く前に、バードランドで修行をさせていただいたのですが、和田社長に「地元でもこの美味しさを広めたいので同じようなレシピで作っていいですか?」と尋ねたところ快諾いただき商品化しました。
バードランドの味を崩すことなく、品を下げることはしないというこだわりを持って提供しています。水郷のとりやさんのレバーパテは、地元の醤油を使っていて、新鮮なレバーしか使っていません。さらに丁寧な下処理の手順を定めているため、あまり大量に作ることができないのです。そのため、通販では期間限定販売とさせていただいています。
それを見て「なかなか手に入らないレバーパテ」という切り口でメディアに取り上げていただくことが多いです。一方店舗では、せっかくお越しいただいた方に売り切れをお伝えするのは心苦しいため、毎日ご購入いただけるようにしています。
また、「水郷どり丸ごと1本」という商品は、12種類の部位を一度に楽しめる、つまり鶏の命を丸ごといただくというコンセプトが珍しく、取材にきていただくことがあります。
商品開発においては、普段食べるもの、大量に作れるもの、なかなか売れないけどメディアに取り上げていただけそうなもの、他にないものというように数パターンに分けて考えています。
柳田さん:商品の特徴を意識して商品開発をしているということですね。
須田さん:なんでも作ってなんでも売っていくというのでは、何も売れなくなってしまいますから。
期間限定販売のお問い合わせには丁寧なコミュニケーションを
須田さん:弊社の場合は、例えばレバーパテをもう少し多く作ることもできますが、その代わりに他の作業ができなくなってしまいます。美味しいものが作れなくなるのであれば、製造量を維持してしっかりと美味しいものを作ることに重きをおいています。
その代わり、販売期間以外の日にもお問い合わせを受け続けて、次回の入荷時にご連絡をするなどお客様とのコミュニケーションを大切にしています。
柳田さん:通販では月に2〜3日の販売期間であれば、お問い合わせが殺到しそうですね。
須田さん:毎月100件ほどのお問い合わせを常にいただいている状況です。例えば毎日10個ずつ販売するというような販売方法もありますが、弊社では1か月分を2〜3日で予約販売する形が合っていると感じています。
柳田さん:毎日販売の場合は、接触頻度を上げる意味で効果があると思いますが、「この日に販売しますから見てください」という水郷のとりやさんのような販売手法が良いケースもあります。水郷のとりやさんでは、実店舗を訪れれば購入することはできるのですね。
須田さん:地元を大事に思っていて、商売をして地元に来てもらいたいという想いがあります。だからこそ、実店舗でしか購入できない商品を作ったり、イートインでしか食べることのできない親子丼を提供したりと、実店舗に足を運んでもらうためにどうすればいいかを模索しています。また、実店舗に来ていただければ弊社の良さや世界観を伝えやすいので、実店舗に来てもらうための仕掛けは意識して行っています。
鶏肉を中心にネットとリアルが循環するビジネス設計
柳田さん:須田さんの中では、ネットとリアルのどちらを優先していますか?
須田さん:弊社の場合は、通販を始めたから実店舗を維持できた面があります。通販に助けられたという意味で当然大切にしていますが、あくまで商売のツールの一つでしかありません。
商売としてどちらを大切にするかという優先順位はなく、通販と実店舗の二つをうまく融合して回していくということが重要ではないでしょうか。
柳田さん:通販に合わせて、実店舗の戦略を変えたとお聞きしましたが、地元の人からの評価も上がったのでしょうか。
須田さん:通販を行い、地元の人が以前よりも実店舗に来てくれるようになりました。そこで気がついたことは、自分たちがやっていることをきちんと伝えなければ買ってもらえないということです。以前のお店は開けていれば、宣伝をしなくても地元の人が買いに来てくださっていましたが、なぜ買ってくれるのかをよくわからないままに商売をしていた部分がありました。
通販では美味しさやどういった鶏を扱っているのかなどをしっかり説明しなければ買っていただけません。実店舗にもポップを充実させたり、鶏舎の様子を掲示したりと通販で学んだことをリアルに活かしています。
一方、通販では対面販売の雰囲気を出せるよう、メールのやりとりは多めにしたり、電話対応を積極的に行ったりしています。
柳田さん:Webページで実店舗への来店を促しているのですか?
須田さん:本店サイトでは常に左上に店舗の案内を載せています。「食べて美味しかったから行ってみよう」と思っていただき、お客様に直接会ってお話ができるのが嬉しいです。
柳田さん:商品を基点に話が弾むのは、専門店ならではの売り方ですね。
須田さん:バードランドの和田社長は茨城県のご出身で、茨城の地鶏を美味しく食べてもらうために、生産組合に掛け合い「奥久慈しゃも」を有名にされました。そのコンセプトが好きで、私も地元の鶏や農家を大事にしたいと思っています。そのためには、地元に来て鮮度の良い食材を食べていただき、商品や地元の観光名所を基点に話が弾み、帰って取り寄せていただく循環ができるのが良いなと考えています。
地元の農家と共に繁栄を目指して
須田さん:弊社は2021年で創業100年でしたので、鶏肉の価値をより高めるための取り組みとして職人が鶏をさばいているところを見学できる新しい工場を作りました。
柳田さん:鶏肉をさばいているところを見せるというのは珍しいですね。
須田さん:そうですね。弊社は職人が手ばらしをしており、これは鶏肉屋さんならではの強みです。大きな処理場とは異なり、職人が一羽一羽まな板の上に鶏をのせてさばいていくという鶏肉屋さんの原点が見えるようになることで、より価値を高めたいと思いました。副次的な効果としてお客様に見られるため、作業場がとても綺麗になり、衛生面でも品質を高めることができました。
また、新しい工場に合わせて出荷場も建設し、繁忙期の出荷に耐えうるようにしました。これまでは父の日やクリスマスなどの繁忙期前には一週間ほど実店舗を閉めて全国の出荷作業のみに取り組んできました。本来の営業日に休業しているため、せっかく楽しみにご来店いただいたお客様が何も購入できずに帰られてしまうというのがとても嫌で、今回実店舗を開けたまま繁忙期の出荷作業にも耐えられるよう整備しました。
今年の父の日は、工場と出荷場の完成後、初めての繁忙期でしたが、これまで三日間休業していた実店舗をオープンしたまま、出荷作業を無事終えることができました。お越しいただいたお客様をお断りすることなく、商品が不足することもなく、繁忙期を越えられ、お客様に残念な思いをしてもらうことなく商売ができていることを嬉しく思っています。
柳田さん:これまでの繁忙期は、通販を優先させざるを得ない状況にあったけれども、今回解消されたということですね。父の日とクリスマス、どちらがより忙しいのですか?
須田さん:断然クリスマスです。クリスマスがなかったら全国の鶏肉屋さんは立ち行かなくなるのではないかというくらいの勢いがありますね。今回は父の日に予行演習ができました。8月頃からクリスマスに向けて鶏を育てる準備が始まります。
柳田さん:最後に今後の展望をお聞かせください。
須田さん:通販で全国のお客様からご注文をいただけるようになっているので、その強みを活かしていきたいと考えています。地元に足を運んでもらうためのツールとして、そして販売だけではなくコミュニケーションツールの一つとしても通販を活用していきたいです。
いずれは、東京などの都心部に焼き鳥屋を出店して、千葉までは行けないけれど、ここで食べられるという拠点を作っていけたら面白いなと思っています。東京や大阪など都心部でも水郷のとりやさんの焼き鳥が食べられるようになれば、地元で養鶏をしている人が「東京の店で俺の鶏が食えるんだよ」と言えるようになり、農家の価値を高めることができるのではないでしょうか。
養鶏も農業も担い手不足が課題になっていますが、自分が育てた鶏を価値のあるものとして生まれ変わらせてくれる存在になれたら、養鶏を始めようと考えてくれる人が増えるのではないかと、そうなれば鶏肉屋さんとしては嬉しいですね。
柳田さん:素晴らしいですね。具現化できるように心からお祈りいたしております。本日はお話をありがとうございました。
おわりに:地元の鶏を基点につなぐECと実店舗の相乗効果
通販があったからこそ、実店舗を維持できた過去がある一方で、ネットもリアルもツールの一つでしかなく、うまく循環させることを意識しているというお話は印象的でした。鶏肉専門店であり、地元の鶏を生かすことを軸にして事業に取り組んでいるからこそ、目先の数字にとらわれない仕掛け作りができているのではないでしょうか。通販のコミュニケーションを対面に近づけ、実店舗のポップなどは通販で学んだことを反映する、また今後も都心部での出店を目指していくということで、ネットとリアルの相乗効果を生む事業の形を実感できる回だったと思います。
EC市場の真の発展に貢献をという想いで、「ECの未来」を運営しているサヴァリ株式会社は楽天市場・Amazonなどネットショップ運営代行をはじめ、モール通販を中心にECサポート・ECコンサルティングを行っています。EC運営に不安を抱えている事業者様は問い合わせてみてはいかがでしょうか。
■サヴァリ株式会社へのお問い合わせはこちら
https://savari.jp/contact/
あわせて読みたい