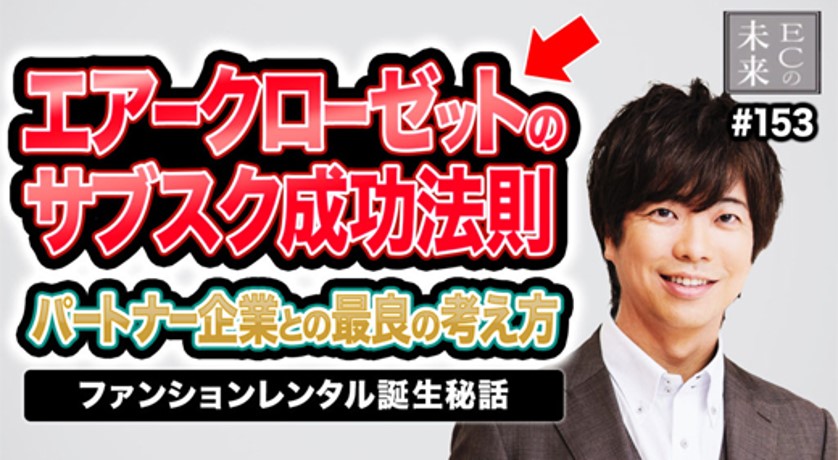【ゲストスピーカー】
須田 健久さん
株式会社須田本店 代表取締役
鶏肉専門店「水郷のとりやさん」
【チャンネルMC】
柳田 敏正さん
株式会社柳田織物 代表取締役
ワイシャツ専門店「ozie(オジエ)」
この記事の目次
町のお肉屋さんが楽天市場に出店
柳田さん:鶏肉を加工して販売されていて、楽天市場でも非常に好調と伺っています。ECを始めた経緯についてお聞かせいただけないでしょうか?
須田さん:私で4代目になります。初代の頃は、農家さんから生の鶏肉や卵を仕入れて、東京の市場に卸すことから始まりました。2代目のときに、鶏の飼育を始め、3代目のときに育てた鶏を一般のお客様向けに加工・販売するようになりました。
私自身は大学時代、旅行が好きだったので家業を継ぐという意識はあまりなく、旅行代理店で働こうと思っていました。ところが大学4年生のときに、その当時阿佐ヶ谷にあった「バードランド」という焼き鳥屋で食事をしたときに衝撃を受けたんです。当時の私は、焼き鳥と言えば赤提灯でサラリーマンがネクタイを緩めて愚痴をこぼすようなイメージがあり、あまり良い印象を持っていませんでした。
しかし、バードランドでは、ワインを片手におしゃれな人たちが焼き鳥を楽しんでいて、「焼き鳥にはまだ可能性がある」と強く感じました。そして、その翌日には「修行させてください」とお店に直談判し、卒業後に修行に入ることに。私はバードランドで修行した新卒第1号になりました。
柳田さん:須田本店は当時から焼き鳥に特化していたんですか。
須田さん:私の父の代では、まだ「ワンストップショッピング」の時代で、今のスーパーのような店舗でした。ブルドックソースやマヨネーズ、アイスクリーム、お菓子などが並ぶ中で、焼き鳥や唐揚げを販売していた、いわゆる「町のお肉屋さん」です。
そんな中、私がバードランドで修業をしていた2001年に、父が楽天市場に「水郷のとりやさん」というネットショップを出店しました。
柳田さん:お父様がECを始めたきっかけは何だったのでしょうか?
須田さん:当時、地方にも大型スーパーが進出し始めていて、個人の肉屋が価格競争で生き残るのは厳しい状況でした。商圏の人口も減っていく中で、新しいチャレンジが必要だと考えていたようです。そんなとき、2001年の元旦に掲載された日経新聞の記事で楽天市場の存在を知ります。
また、ちょうどその頃、同じ町の豚肉屋が通販で売上を伸ばしているという話も聞き、「豚屋ができるなら鶏屋もできるだろう」と、ECを始めたようです。まずはパソコンを買うところから始めて、楽天市場に申し込んで、「水郷のとりやさん」が誕生しました。
柳田さん:鶏肉の中でも当時の主力商品は何だったのですか?
須田さん:当時は生の鶏肉が中心でした。ただ、それだけでは競争が厳しかったので、店舗で提供していた唐揚げなどの加工品も一緒に販売するようになりました。
柳田さん:生の鶏肉をネットで買うというイメージはあまりありませんからね。
須田さん:そうですね。現在では加工品の比率が高まっていますが、当時はまだ加工品の取り扱いが少なく、楽天市場でも鶏肉ジャンルでは、生肉が主流でした。そのため、そこを狙ってスタートを切ったんです。
柳田さん:順調にいきましたか?
須田さん:最初はまったく売れませんでした。すでに出店していた鶏肉専門店は、自社で鶏を生産・処理して販売しているような大規模店でした。私たちはそのような店舗から仕入れて販売しているイメージに近く、同じ価格帯では勝負になりません。利益がでず、苦しい時期が続きました。
両親は50歳を過ぎており、昼間は実店舗の営業、夜はネットショップの対応という生活で、昼間はお問い合わせの返信すらできず、深夜2〜3時まで作業し、朝6時からまた店に立つという生活を3年ほど続けていました。ちょうどその頃、私がバードランドでの修行を3年で終えて、家業を継ぐために実家に帰り、ECの運営も引き継ぐことになりました。
柳田さん:修行は最初から3年と決めていたんですか?
須田さん:自分の中で「3年やって覚えられなかったら、それ以上やっても無理だろう」と思っていたので、とにかく必死でした。バードランドのスタイルを学びながら、焼き鳥の可能性をどう広げられるかを常に考えていました。
焼き台を任せてもらえるようになってからは、社長が何を見て焼いているのか、どういう点に注意しているのかを意識しながら、自分の感覚を磨いていきました。
EC・実店舗、両軸で進めた鶏肉専門店のブランディング
柳田さん:バードランドでの修業を3年で終えて帰られてから、まず何に取り組まれたのですか?
須田さん:私は焼き鳥の修行しかしていなかったので、ECについては全くの素人でした。そこで、父が参加していたECの勉強会のようなグループで、3か月ほど見習いとして学ばせてもらいました。インターネット上でどうやって商品を販売しているのか、どんな商品ページを作っているのか、受注業務の流れなどを吸収してから、家業に戻ったんです。
柳田さん:実際に学ばれて、最初にご自身で起こしたアクションは何でしょうか?
須田さん:インターネット通販「水郷のとりやさん」というのを引き継いで、まず数字の見直しをしました。当時、メルマガの読者数は一定数いたのですが、購入にはつながっていませんでした。そこで、「まずは味を知ってもらおう」と考え、「1,000円ポッキリトリ逃がすなセット」の販売をはじめました。今では、楽天市場で「1,000円ポッキリ」は一般的ですが、最初に始めたのはうちではないかと思っています。
柳田さん:そのネーミングは、誰が考えたのですか?
須田さん:私が考えました。
柳田さん:キャッチーで良いネーミングですね。
須田さん:とにかく「一度食べてもらうこと」を重視しました。
柳田さん:実店舗のほうも手伝っていたのですか?
須田さん:もちろんです。焼き鳥を焼きながら店頭にも立っていました。ECは当初、私と妻で対応していたのですが、スピードが命なので、専任スタッフを雇って体制を整えました。お問い合わせには即返信、電話応対も丁寧にという基本を徹底しました。
とはいえ、昼間は店頭で親子丼を作ったり焼き鳥を焼いたり、実店舗と通販の両立でかなり忙しい日々でした。
柳田さん:実店舗のほうでは、何か変化があったのでしょうか?
須田さん:2004年に家業に戻って以降、ECでは「鶏肉専門店」としての軸を明確にしていました。当時、魚屋がプリンを売るような「なんでも屋」的なショップも多くありましたが、うちは鶏肉一本に絞り、それに共感してくださるお客様がついてくれました。
一方、実店舗はというと、調味料やアイスクリームなど、鶏肉以外の商品も並ぶ昔ながらの「町のお肉屋さん」だったんです。ネットで「鶏肉専門店」として認知された方が来店されると、「イメージと違う」とギャップを感じるようになっていました。
そこで2006年、実店舗を「鶏専門店」として全面改装しました。地元の調味料や醤油のみを扱い、鶏肉以外は基本的に置かない。さらに、改装前はテイクアウトのみでしたが、焼きたてを味わっていただきたいと考え、イートインスペースを設けたんです。焼き鳥や親子丼をその場で楽しめる、“鶏を満喫できる場所”に生まれ変わらせました。
柳田さん:今では珍しくありませんが、当時としてはネットを見て店舗を訪れるお客様も多かったのですね。ECでは鶏肉専門店、実店舗ではスーパーのようなスタイル。そのギャップを感じたからこそ専門店に改装し、イートインも設けたと。結果として、お客様の反応に変化はありましたか?
須田さん:正直、最初は地元のお客様には受け入れられづらかったです。「ここでイートインはちょっと……」という反応や、「ショーケースに衝立を立ててほしい」といった要望もありました。田舎ではカウンターで食事する文化がまだ根付いていなかったんですね。
ただ、週末になると東京方面から親子丼を目当てに来店されるお客様が増え、他県ナンバーの車が駐車していると話題になるように。少しずつ、「ああいうスタイルもありなんだ」と地元の方にも認知され始めました。
親子丼は都内にもおいしいお店がたくさんあると思いますが、2時間かけて車で来てくださる方もいて、「ここが一番おいしい」と言ってもらえることもあります。
そうした声を聞くたびに、イートインを設けて専門性を高めたことは、ECでのブランドイメージと実店舗のギャップをなくし、結果的に相乗効果につながったと感じています。
柳田さん:なるほど。たしかに「スーパー的な店」ではメディアも取り上げづらいですもんね。
須田さん:そうなんです。食べるスペースがなければ“食べているシーン”も撮れないので、メディアにも訴求しづらい。でも、イートインを設けてからは、タレントさんが来店して焼き鳥を食べる様子などを撮影できるようになり、取材依頼も増えていきました。
商品開発で意識する”おいしい”と”楽しい”
商品化の原点は「自分のおいしい」
柳田さん:飲食の世界って、どんなに工夫しても“おいしくない”と成立しませんよね。通販で商品を購入した人が実店舗に足を運ぶのも、やはり「おいしい」と感じたからだと思います。
須田さん:そう言っていただけるのは本当にありがたいです。ただ、僕自身、“おいしい”の基準を明確には設けていないんです。しょっぱいのが好きな人もいれば、甘いのが好みの人もいる。だから僕が考える“おいしい”は、自分が食べて「おいしい」と思うかどうかだけなんですよ。
万人にとってのおいしさを追い求めると、商品開発が難しくなってしまうんです。なので「これは自分が食べておいしい。誰かにも食べてもらいたい」と思えるものだけを商品にしています。もちろん、鮮度など、誰が見ても重要な要素についてはしっかりと基準を設けています。
柳田さん:つまり、「須田さんのおいしい」を信じて出しているということですね。
須田さん:そうです。スタッフが「これはおいしくない」と言っても、僕が気に入っていれば商品化します。逆にスタッフが「おいしい」と言っても、自分がおいしくないと感じたら出しません。
柳田さん:でも、それをお客様にどう伝えているんですか?「おいしい」って感覚的なものなので、言葉だけでは伝わりにくいのでは?
須田さん:「おいしい」という言葉は基本的に商品ページには書きません。その代わり、「甘い」「しょっぱい」「辛い」といった味の特徴や、「どんな調理法か」「どのような風味か」といった具体的な情報を伝えるようにしています。
たとえば、最近出した麻婆豆腐の素は「四川の山椒の辛さが効いた麻婆豆腐」と明記しています。麻婆豆腐といっても、甘口もあれば北京風もある。その中で、うちのは“四川風”というコンセプトで、自分が食べて「うまい!」と思ったものを商品化しました。
専門店ならではの”楽しんでもらう”商品づくり
柳田さん:焼き鳥は、やはり焼きたてが一番おいしいんでしょうか。
須田さん:もちろんです。焼きたてで、しかも部位や厚みが均一に串打ちされている焼き鳥が、最もおいしく仕上がります。ただ、それだけでは面白くない。そこで生まれたのが、「水郷どり丸ごと1本」という商品です。
これは、長さ27センチの串に、鶏の12部位を1本に刺して焼いたものです。おいしさを追求した商品ではなく、それぞれの部位の違いを“楽しんでもらう”ことを目的に開発しました。
柳田さん:かなり変わり種ですね。それ、うまく焼けるんですか?
須田さん:正直言って難しいです。部位によって厚みも火の通りも違うので、焼き鳥屋に言わせれば「そんなのうまく焼けるわけない」と言われるかもしれません。でもこれは「鶏肉専門店として、鶏1羽を丸ごと味わう」という体験を楽しんでもらう商品なんです。
説明書も同封していて、「これがソリ」「これはセセリ」と部位を確認しながら会話が生まれるような、コミュニケーション型の焼き鳥を目指しています。
柳田さん:その商品は冷凍ですか?
須田さん:冷蔵と冷凍の両方あります。焼き上げたものを冷蔵・冷凍し、湯煎や電子レンジで温めてすぐ食べられるようにしています。
柳田さん:会話が生まれるレシピって、すごくいいですね。
須田さん:うちのコンセプトは「鶏料理を通して、お客様の食卓に笑顔を届ける」こと。なので、「え、なにこの焼き鳥?」「説明書がついてる!」「これがソリ?ソリってなんだろう」と興味が会話に広がっていく。そんな商品を意識して作っています。
柳田さん:僕も焼き鳥好きですが、12部位ってそんなにありましたっけ。
須田さん:ありますよ。例えばハツ(心臓)は1羽に1つですし、ソリはモモ肉の付け根にある筋肉のかたまり。もともと、日本ではモモ肉としてまとめて売られていた部位ですが、バードランドで修行していたとき、恵比寿のロブションのシェフが来店されて「ソリはないんですか?」と。フランス料理では非常に重要視される部位なんです。
ただ、一般のお肉屋ではソリを切り取ってしまうとモモ肉の形が崩れてしまい、売れにくくなってしまいます。でも、うちは他の商品に回せる加工ラインがあるので、ソリを切り出して焼き鳥に使えるんです。
柳田さん:専門店ならではの発想ですね。
須田さん:そうですね。「鶏肉をどう楽しんでもらえるか」を常に考えて商品開発をしています。たとえば麻婆豆腐やチキンカレーにも、鶏肉の専門店としてのこだわりを込めています。
麻婆豆腐は鶏ひき肉と鶏ガラスープで、チキンカレーは鶏の弾力を楽しんでもらえるように、煮込まず香辛料をまぶして焼いた鶏肉を使います。その代わり、ルーには鶏白湯スープを使ってコクを出す。こうした工夫で、鶏肉専門店ならではの商品に仕上げています。
柳田さん:須田さんのお話を聞いていると、「自分が食べておいしい」と思うものと、「誰かに楽しんでもらいたい」という視点がすごく自然に融合している印象があります。
須田さん:ありがとうございます。それを目指してずっと商品を作ってきました。お客様と商品を軸にして会話が生まれたり、思い出ができたりすると、本当にやっていてよかったなと思います。
柳田さん:多くの人は「食品はおいしくなければダメ」と思いがちですが、須田さんのように“楽しさ”や“会話”からアプローチするのも、素敵な切り口ですね。
おわりに:鶏肉へのこだわりがファンをつくる
焼き鳥の可能性を感じ修行に励んだり、鶏肉を楽しんでもらえることをコンセプトに置いた商品開発を行ったりと、須田さんの鶏肉へのこだわりが強く感じられました。鶏肉専門店として成長したECに合わせて、実店舗も専門店へと改装したことで、自宅で楽しんでいた「水郷のとりやさん」を、リアルでも楽しめるようになり、わざわざ遠方から実店舗まで足を運ぶほどのファンが生まれました。ブランディングの重要性と共に、ECと実店舗の相乗効果が感じられる回だったと思います。
EC市場の真の発展に貢献をという想いで、「ECの未来」を運営しているサヴァリ株式会社は楽天市場・Amazonなどネットショップ運営代行をはじめ、モール通販を中心にECサポート・ECコンサルティングを行っています。EC運営に不安を抱えている事業者様は問い合わせてみてはいかがでしょうか。
■サヴァリ株式会社へのお問い合わせはこちら
https://savari.jp/contact/
あわせて読みたい