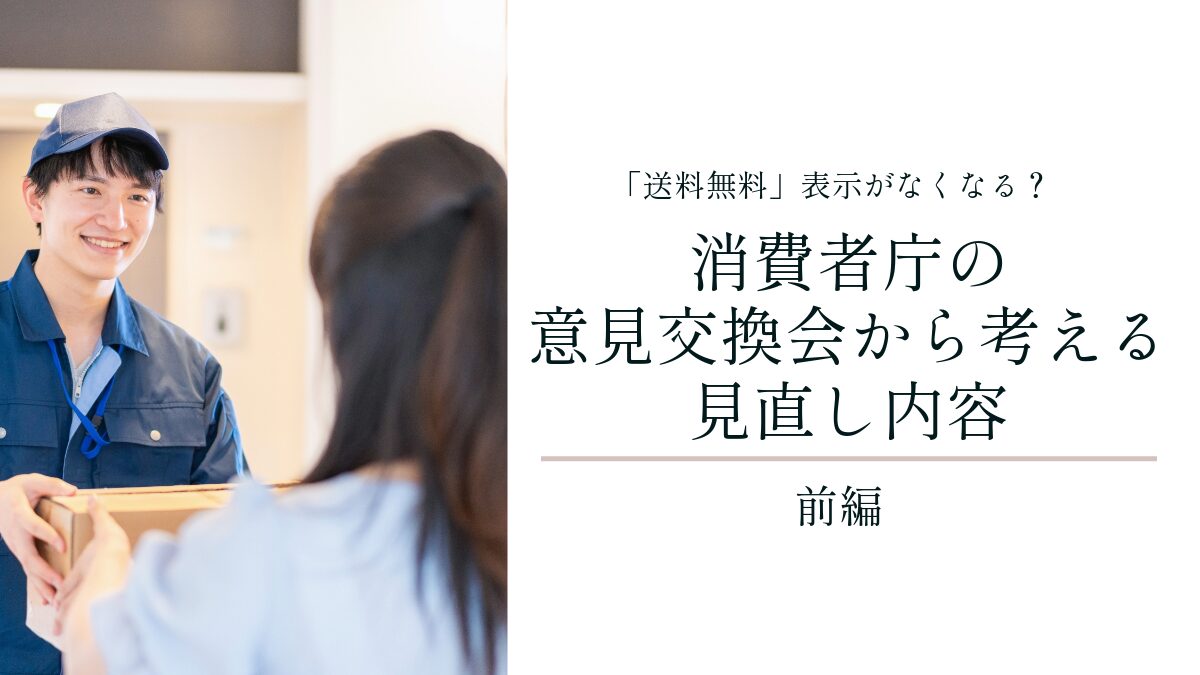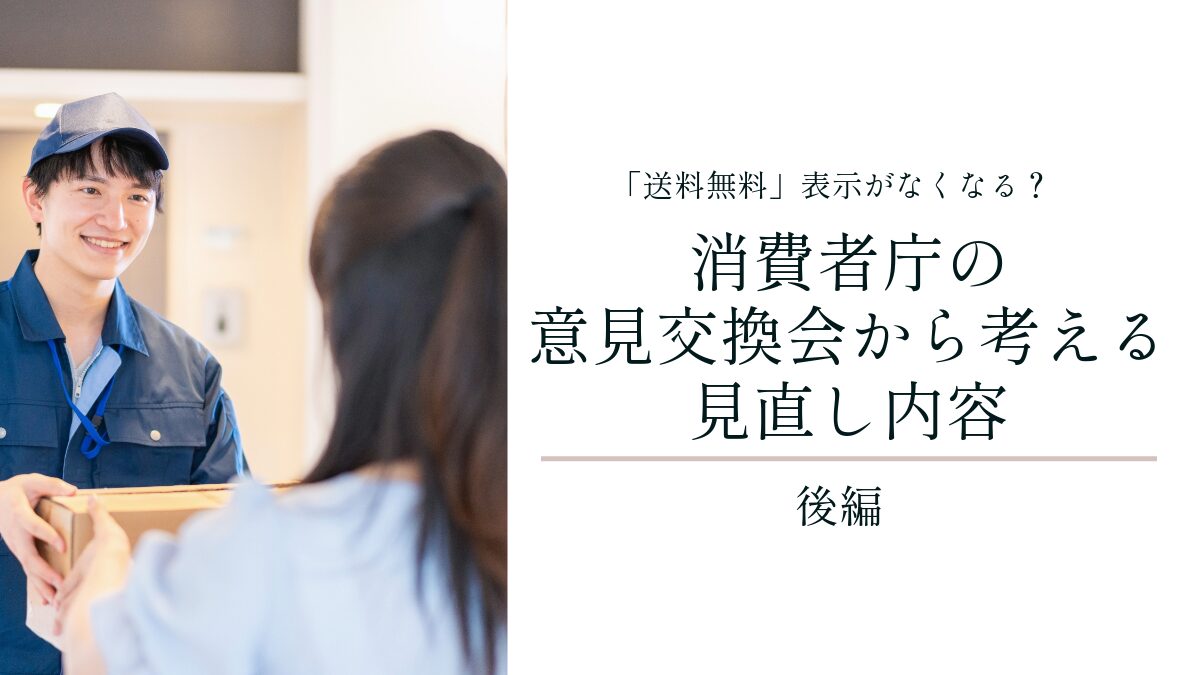
ECサイトのマーケティング施策として定番の「送料無料」表示。しかしこの表示が今のように使えなくなる可能性があります。消費者庁では現在、2023年6月23日から『「送料無料」表示の見直しに関する意見交換会』を開いており、2023年11月8日には第9回が開催されました。各回、物流業界、通販業界、消費者団体など関係業界の各団体の代表者が招かれ、意見交換が行われています。本記事では、第7~9回までの意見交換会から要点をまとめるとともに、全9回の内容を振り返り、「送料無料」表示が今後どうなるのかを考えます。前編をご覧になっていない方はこちらを参照ください。
各回の詳細は以下のページに記載されている情報をご確認ください。
消費者庁HP:「送料無料」表示の見直しに関する意見交換会
この記事の目次
全日本交通運輸産業労働組合協議会(交運労協)他の意見【2023年9月22日 第7回意見交換会】
第7回の意見交換会では、全日本交通運輸産業労働組合協議会(交運労協)、全日本運輸産業労働組合連合会、全国交通運輸労働組合総連合から、物流業界で働く人々を代表した意見が発表されました。
交運労協は、物流の危機的状況に対する消費者の理解喚起と行動変容を訴えています。貨物自動車運送をはじめとするすべてのキーワーカーが正当に評価される社会を創るため、物流を担う労働の価値の再評価、「価値」を「価格」に反映することを求めています。
「送料無料」表示については、物流の背後にある「労働」への想像力を欠如させる結果になっているとの考えで、景表法適用により「送料無料」表示を禁止する要望を挙げたのです。
ヤマト運輸株式会社・佐川急便株式会社の意見【2023年10月6日 第8回意見交換会】
第8回の意見交換会では、ヤマト運輸株式会社、佐川急便株式会社から、宅配大手からの意見が発表されました。
ヤマト運輸としては、ECが発展していくなかで、物流、EC事業者、購入者を含め全員で解決していかなければならない課題があるとの認識で、「送料無料」表示の問題に限らず、背景を理解した上で支援をしていきたいとの姿勢です。
佐川急便からは、物流業界の2024年問題への対応事例が説明されました。
「送料無料」表示に対する見解としては、佐川急便は、「送料無料」表示が荷受人の誤解を招くことは一部あるとした上で、「送料は当社(出荷人)が負担」という表示が望ましいが、出荷人に対して現時点で佐川急便として要望を出すことはないという考えです。
ヤマト運輸は、このテーマのみで捉えるのは難しいとして、EC事業者にとって売りやすく、購入者にとって買いやすくなることを考えていくなかで、それを支援していくスタンスは変わらないという姿勢です。
消費者団体からの意見【2023年11月8日 第9回意見交換会】
第9回の意見交換会では、4つの消費者団体からの意見が発表されました。
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS)
NACSの意見では、「送料無料」は消費者にとって魅力的であるものの、表示によって配送事業者の存在および人件費、輸送のためのインフラや輸送に使われるエネルギーなどの必要性について、思い至ることができなくなる懸念もあるとしています。
また、エネルギー価格の高騰、賃金上昇などで運送業界の経費が上昇するなかで、「送料無料」の継続は事業者にも大きなリスクとなり、結果的に力の弱い立場への過度な圧力につながる心配があると意見しました。
NACSでは、「持続可能性」「地球規模」「弱い立場の人や社会全体のため」を考えて商品やサービスを選ぶ「エシカル(倫理的)消費」を推奨しています。消費者が実情を正しく認識し、エシカル消費につなげるためにも、「送料無料」表示はやめ、少なくとも「送料は当社負担」など、「運ぶ・届ける」で発生する負荷を消費者が認識できる表現に改めてほしいと要望しています。
主婦連合会
主婦連合会の意見では、「送料無料」表示の在り方について、「透明化」すべきとの立場です。消費者から見ると、「送料無料」は販売事業者による販促のための「サービス」「キャンペーン」のように捉えられていますが、実際に送料を誰が負担しているのかは消費者からはわかりません。そこで解決策の一例として、但し書きとして誰が送料を負担しているのかを記す方法を提案しています。
また、社会の大切なインフラを疲弊させないため、環境負荷を減らすために、消費者の意識改革・行動変容は必要としています。
その上で、送料表示や消費者の意識改革・行動変容と、運送業界の待遇改善や担い手不足の解決は別の問題として対応策を立てるべきとの考えです。取り組みの優先順位としては、EC事業者・元請けの大手運送会社・下請けの運送会社、それぞれの間で不当な契約が起こらないようにルールが徹底され、そのルールの遵守が担保されてから、「送料無料」の見直しに取り組むことを提案しています。
一般財団法人日本消費者協会
日本消費者協会では、「物流改革に向けた政策 パッケージ」について、消費者に対しては、意識改革・行動変容を促す取り組み、再配達に向けた取り組み、物流に係る広報の推進に向き合わなければいけないと受け止めています。
他方、ECなどによる宅配便の物量はトラックが運ぶ荷物全体に占める割合は低く、宅配便と送料無料表示に焦点が向けられることで、本来、改善・改革が必要な企業間物流の課題解決が遅れることのないようにしなければならない、との考えです。
そして第1~8回の意見交換会を踏まえた受け止めとして、まず、「送料無料」表示の法規制によって得られる効果は限定的としながら、「送料無料」表示を行う事業者は、その根拠について説明責任があるとしています。また「送料無料」表示が、商品購入に係るサプライチェーンで起こりうる負の影響を見えにくくする可能性には留意すべきとの考えです。
運送事業者に支払う運賃・料金と消費者向けの送料については、再配達を減らし無駄・無理のない物流に協力するために消費者ができることはいろいろあり、事業者はそのための技術導入・技術開発などサービス向上を目指すべきと提案しています。
消費者の意識改革・行動変容については、「より安い価格や利便性」から「適正価格と持続可能性の尊重」へと、サステナブルな社会実現のために重視すべき価値観の転換が必要で、自分でできることを行動に移すことで2024年問題へ能動的に協力できることを消費者団体として広報していく姿勢です。
公益社団法人全国消費者生活相談員協会
全国消費者生活相談員協会の意見では、「送料無料」表示について、消費者がその内部事情を正確に理解しているわけではないものの、「送料無料」だからといって多くの消費者が物流を軽視しているわけではないと考えています。また、消費者は物流業界が無料でサービスを提供しているという認識ではなく、販売店などの負担によりその分安いと理解して選択する傾向にあると推測しているのです。
一方で、「送料無料」表示が物流業界にとって課題であること、気持ちに沿わないものであることを今回の議論で理解した上で、消費者に誤解されない別の表現があるならば修正も必要なのではないかとしています。その場合、「〇〇無料」とする同種のケースが他にないか、他業界、多方面の検討もすべきではないかとの考えです。
また、「送料無料」表示をなくしただけで再配達の減少や労働環境の改善がすぐに実現することは難しいと考え、今すぐできることの実施が重要として、いくつかの取り組みを提案しています。
「送料無料」表示は変わるのか?第1~9回の意見交換会を踏まえたまとめ
【後編】で紹介した第7~9回の意見交換会では、物流業界から1団体と大手宅配2社の意見、消費者団体から4団体の意見が発表されました。
第1~9回の内容を振り返ると、EC業界としては、やはり「送料無料」表示の見直しはできるだけ避けたいものといえるでしょう。「送料無料」表示は効果的なマーケティング施策のひとつであり、表示の変更には手間もコストもかかります。
一方で、EC業界が成り立つために欠かせない物流業界の意見は無視できません。物流業界のなかでも、特に中小規模の事業者や、現場で働くドライバーの方々にとっては、「送料無料」表示は非常にネガティブに受け止められていることが、意見交換会で出た意見からわかります。
2024年問題に対して関係する業界が協力していく必要があるなか、そういった物流業界の人々の気持ちを無視することも避けるべきです。意見交換会のなかでも、EC業界の意見のなかの前提として、物流がECにとって不可欠であること、そのサービスへの感謝は繰り返し述べられています。
ただ、同時にEC業界の意見として出されているのが、実際に「送料無料」表示を見直すとして、その目的が何であるのか、目的の達成を測る基準は何なのか、実際にどの程度の効果が見込まれるのかは、見直しを行う前に明確にしておくべきということです。
また、「送料無料」表示の見直しだけで物流の諸問題が解決するわけではなく、より直接的な効果が見込まれる施策の検討・実施も必要です。そういった施策のほうが効果的であれば、それは「送料無料」表示よりも優先されるべきですし、実際に効果が見えれば物流業界の協力も得られやすくなるでしょう。
さらに、「送料無料」表示には、物流の仕事が軽んじられている印象を受けるという、気持ちの面での問題もあります。これには、表示の変更という対応もありますが、もっと直接的に消費者の意識変容を促すようなコンテンツやメッセージを届けるという対応も考えられます。この点は、意見交換会に参加した消費者団体も認識しているところで、協力した取り組みが必要でしょう。
第1~9回の意見交換会を踏まえて、「送料無料」表示が見直されるかどうかという点では、EC業界と物流業界の主張がまだ平行線といった印象です。もし見直されるとすれば、「送料弊社負担」といった表現が有力ですが、それがどの程度の強制力を持つかによって、普及具合も大きく変わります。
いずれにせよ2024年問題は差し迫った問題であり、EC業界としては、そのなかで「送料無料」表示が問題視されているという認識を持った上で、物流業務の効率化や再配達の削減など、物流の諸問題を解決するための対策を積極的に打ち出していく必要があります。
合わせて読みたい