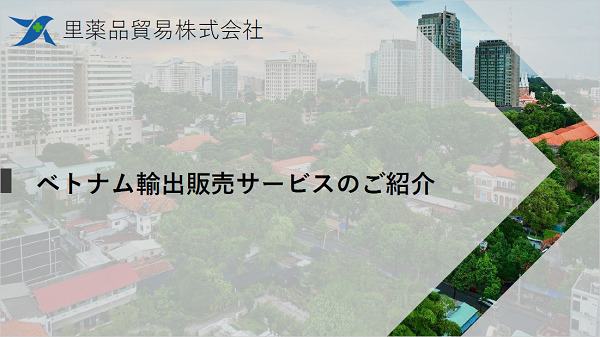筆者の過去のコラムでは、Eコマースを中心にベトナムでどのように物販を開始するのかをご紹介してきました。しかし、一部の方々からは、ITは不慣れなのでFacebookの細かな対応ができないという意見もいただきました。また、ネットで小さく小売をやるのではなく、卸販売で大きく展開できないのかというお問合せもいただきます。
特に自社製造工場を持っている企業、日本国内で販売できないロット(例:古いパッケージの在庫)を抱えている企業では、とにかく大きく販売したいというニーズがあります。
一方、現在ベトナムではAEONやマツキヨなど日系小売大手が進出し、徐々に現地での存在感を高めてきています。これはメーカーにとって非常に良い環境ができつつあるということです。
しかしながら、ところ変わればビジネスも変わります。ベトナムにおける卸販売は日本とは多少ルールが異なります。今回は筆者がベトナム現地で実際に行なっている卸販売の経験を踏まえ、具体的な進め方を説明していきたいと思います。
1)代理店(ベトナム国内の輸入販売会社)とベトナム商工省の輸入許可が必要
以前のコラムでは、越境ECにおいては日本から小さな単位で発送し、オーダーが多くなってきたら一般貿易に切り替えるのが定石とご説明しました。しかし、卸販売においてはテスト販売的なことは許されず、小ロットであれ、期間限定であれ必ず代理店との一般貿易契約および、ベトナム商工省への輸入許可申請が必要となります。
ベトナムには、中国やラオスあたりから模造品が大量に持ち込まれているため、政府や小売店は対策として、代理店が保有する商工省発行の輸入許可証を提示することを必須としています。大手小売チェーンではさらにメーカーと代理店の契約書や、輸入した際のインボイスまで求めることがあります。
この点に関してはネット販売側も徐々に厳しくなってきていて、大手ネットショッピングモールでは同様の資料の提出を求められるようになりました。
というわけで、仮にAEONやマツキヨとの繋がりや内示があったとしても、代理店が決まっていて、商工省の輸入許可申請の目処が立っていなければ、一切具体的な話に進めません。
2) ベトナムにおける代理店との付き合い

ベトナムにおいての商品の販売ルートは特段日本とは変わらず
①メーカー → 小売店 → 消費者
②メーカー → 代理店 → 小売店 → 消費者
このようなルートになります。しかし前述したように日本から輸出した商品を小売店で販売するために代理店は必須なので、必然的に②となります。
代理店との付き合いにあたっては、最初に方針を決める必要があります。
A.代理店に商品を買い取ってもらい、その後の卸販売も全てお任せ
B.代理店は輸入手続きのみ、卸販売はメーカー主導で行う
Aの方が簡単で且つ売上を早く回収できるから良いに決まっている、と思った方は多いのではないでしょうか。しかしベトナムにおいてAで開始し、代理店からわずか1〜2回の注文が来ただけで終わってしまったというケースが後を絶ちません。
多くのベトナム企業や個人は日本商品の代理店になることに対して非常に前向きです。例えば、儲かっている飲食店(フォー屋さんなど)のオーナーがサイドビジネスとして代理店を始めることはよくあります。
100万円程度の初期投資はできるので、とりあえず数十ケースを購入し近所の小売店などに卸販売をかけていきます。フォー屋を繁盛させた信用を駆使して、100万円分の在庫なら1〜2ヶ月で売り切ることもできます。商品が日本製というのも売りやすい理由です。
ここまでの状況を日本のメーカーが知ると「いい代理店を見つけた。この調子で代理店を増やせば販路も拡大できて、倍々ゲームで売上が伸びていくぞ」と一瞬夢を見ることになります。しかし、メーカーに2回目の発注はなかなかきません、催促してもまだ早いと断られてしまうのです。何故かというと、小売店に卸販売したものの、消費者が購入しないからなのです。
実はベトナム人は非常にコンサバな消費行動を取ります。例えば炭酸飲料。日本であればコンビニには毎月のように新製品が登場しますが、ベトナムは10年経っても、コカコーラ、ペプシ、セブンアップ、ミリンダ、スティングという同じラインナップなのです。新商品を試すことに躊躇するという特徴がベトナム人にはあるのです。
他にも、ポップなどの販促物がなく、商品が消費者の目に届かないことや、販売員が商品の説明をできないなどの理由で、次第に商品は忘れ去られて埃をかぶっていきます。最悪なのはここからで、消費期限が迫ってくると最後は半額以下で叩き売ってしまうのです。店頭での叩き売りならまだしも、ネットに出品して叩き売りをされてしまうこともあります。こうなるともはや商品の価値は暴落し、このベトナム市場では2度と売れない商品となってしまいます。
フォー屋さんの例に限らず、中堅の代理店でもやることは大体同じです。小売店に卸すだけで、ブランド価値の向上や小売店向けの販売支援はほとんど行いません。これでは商品が売れなくて当たり前です。
こういった理由があるので、筆者としては、メーカー側が主導して代理店を動かしながら着実に売上を作っていくBをお勧めしています。
3)小売店開拓と販売支援

ベトナム小売の8割はパパママショップと呼ばれる個人商店といわれていて、AEONやマツキヨなどの小売チェーンはベトナムの経済成長に合わせてこれから伸びていくと考えられています。そう考えるとAEONの進出タイミング(2014年1月ホーチミン1号店 開店)は非常に早かったといえるでしょう。
ベトナム系や外資系の小売チェーンもあります。例えば通信会社大手のFPTホールディングス傘下の薬局チェーン「ロンチャウ」は2019年時点では200店舗でしたが、2022年中には700店舗にまで拡大します。
それでは、AEON、マツキヨ、ロンチャウなどに商品を卸していくにはどうしたら良いのか説明していきたいと思います。まずAEONやマツキヨなどの日系であれば、日本本社でのお付き合いを活かして、ベトナム現地にいる日本人の責任者の方へ繋いでもらうのが近道です。これを我々は「上からいく」と言ったりします。逆に「下からいく」場合ですが、代理店(前章のBとして進めている前提)のベトナム人スタッフにお願いして小売チェーンの本社代表番号に電話して、バイヤーに繋げてもらえないかを交渉します。しかし、大抵の場合、本社代表電話から前に進むことはありません。
上からも下からもだめだったときは「横からいく」という手があります。横というのは同業者です。競合商品だと同業者からの依頼は嫌がられることがありますが、商品ジャンルが異なれば、快くバイヤーさんを繋いでもらえることが多いです。例えば筆者が化粧品を扱っているとき、日本酒を扱っている日本人の方にコンタクトを取ったのです。
「○○さん、あのスーパーとあの薬局に卸されていますよね。もし可能であれば担当バイヤーの方をご紹介いただけないでしょうか」
このように「横からいって」小売店のバイヤーさんに繋がることもあります。
バイヤーさんに繋がると商品の紹介をし(新型コロナウィルスの影響もありいきなり初めから会わないことが多いです)その後販売価格と卸販売価格の交渉となります。筆者の立場としては代理店ですので、メーカーの担当者と事前相談したうえで価格交渉に臨みます。卸価格は小売価格の65%〜70%に収まるのですが、毎回議論になるのは小売価格です。小売店は他の小売店より少しでも安く売りたいと考えるので、少しでも高く(メーカー希望小売価格に近い価格)売りたいメーカー側との交渉になるのです。
そして、もう一つ大きな交渉のポイントになるのが、メーカー側からの販売支援です。その中でも最も重要なのが販売員の派遣です。メーカー専任の販売員を店舗に配置することで、商品に関する細かな質問に答えることもできるようになるので(小売店側の店員が的確に回答する事はほぼ不可能)実際に売上が伸びるのです。そのため、仮に卸価格でメーカー優位に進んだ場合、販売員は多めに派遣するなどして調整をします。販売員と併せてノベルティの提供やイベント協賛金を払うこともあります。
筆者の意見としては、メーカーと小売店の歯車が噛み合わないと絶対に販売は伸びません。販売開始後もメーカー(または代理店)は最低でも月に1回は店舗を見て、改善点を探し小売店と協議して施策を打っていくべきでしょう。卸しただけで商品が売れることはありません。一方、苦労しながらも海外の店舗で自社商品が売れていくという感動を得ることもできます。是非日本のメーカーにはベトナム卸販売に挑戦してもらいたいです。
最後に
今回はECから離れ、卸販売について説明させていただきましたが、実際に卸販売に向け動くというのはハードルが高いと思います。そこで弊社では卸販売を一括代行するサービスをご用意していますので、お問合せください。
▼お問合せ先 - 里薬品貿易株式会社
https://satoyakubou.co.jp/
合わせて読みたい