
代表取締役社長 青栁陽介さん(写真右)
おもちゃ事業部 事業部長 小林志苑さん(写真左)
0歳から借りられる知育玩具やおもちゃのサブスク・レンタルサービスを行う「キッズ・ラボラトリー」では、2021年1月のサービス開始から順調にサービス登録者数を増やし、2021年12月には累計で3,000名を超える方が利用しました。代表取締役社長の青栁陽介さんと事業部長の小林志苑さんに、着実に成長を続けるキッズ・ラボラトリーについて、マーケティングや顧客対応など事業を拡大する上で実践している具体的な内容を幅広くお伺いしました。
この記事の目次
サービス立ち上げ背景とお客様の属性
――まず、キッズ・ラボラトリーの事業立ち上げの背景やどのような属性の方にご利用いただくことが多いのか教えていただけますか?
青栁さん:知育玩具の事業の立ち上げに至った背景として、私の子供が長期入院により外に出ることが難しい時期がありました。そのとき、こんなサービスがあったら良いなと思ったことを今やっています。また、おもちゃのサブスクはアメリカやフランス、台湾など海外では当たり前に利用されているため、いずれ日本でも普及するだろうと思ったこともきっかけの1つです。
小林さん:ご利用いただくお客様の属性は様々ですが、年齢層は広く0歳から8歳くらいまでのお子様にお使いいただいています。ご家庭にないおもちゃをお送りしているのはもちろん、当社のおもちゃコンシェルジュがご家庭やお子様の成長に合わせて選定をしています。
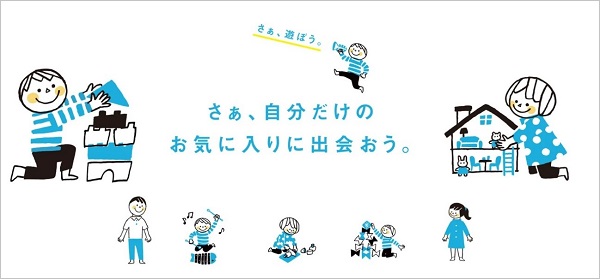
おもちゃのサブスクをお客様が知るきっかけは?
――既に海外では習慣化している知育玩具のサブスクサービスですが、キッズ・ラボラトリーの利用者数が伸びていることからも徐々に認知が広がっているように思います。新規のお客様から認知を得るためにどのような取り組みを行っているのでしょうか。
青栁さん:お子様の年齢によって認知を得る場所は異なります。例えば、お子様が生まれる前であれば産婦人科の待合室にあるデジタルサイネージに打ち出すことで認知を得られるでしょう。競合さんのサービスは出稿しているのですが、当社では費用対効果が合わないため出稿していません。そのため「世の中に知育玩具のサブスクサービスがある」という点は、他社に認知を任せていることになりますね。
また、オンラインでは比較サイトやブログが非常に多く、アフィリエイトによる集客が多く行われている業界です。しかし、お客様はサービスを比較するコンテンツも見られますが、お申し込みの決め手になるのは実際に利用したお客様が発信したコンテンツ(UGC)であることが多いです。そのため、競合さんと違い、積極的に広告を実施していない当社では、本物の情報を届けられるように、お客様の声や実際に遊んで楽しんでいるお子様の動画に気づいてもらえるような仕組みづくりをしています。
SNSを活用した認知拡大方法
――知育玩具など教育に関係する内容を深く調べる親御様は多そうです。SNSについて、サービス立ち上げ当初のお考えや実際に動いた上でのご状況を教えていただけますか。
青栁さん:サービスを立ち上げる際にSNSの活用は重要だと考えていました。20~40代の女性の利用数が多いInstagramはSNSで認知を広げる上で欠かせないと思い、最初から力を入れています。サイト内の様々な場所にお客様がInstagramに投稿しやすいような導線設計をして、自然と自ら投稿してみようと思える仕組みを作っています。その後、サービスを運用するにつれて、Instagramのフィードに他社のアフィリエイターのコンテンツが増えてきました。するとInstagram内のコンテンツにPR感が出てきてしまったので、それを薄めるために、並行してYouTubeやTwitterにも力を入れるようになりました。
それぞれのSNSの特徴として、Instagramはポジティブな発信が多く、YouTubeは比較検討で活用され、Twitterでは普段吐き出せない心の吐露のような言葉の投稿が多い印象です。Twitterでポジティブな傾向が強い投稿を調べたところ、ある特定のハッシュタグを付けて投稿していることがわかりました。このハッシュタグが付いている投稿に、botのような動きにならないよう毎日手動で「いいね」ボタンを押し続けています。結果、最近ではTwitter経由の流入が増えるようになりました。
広告による集客状況について
――各SNSを活用して、徐々に集客につなげているかと思います。広告による集客も行っているかと思いますが、効果の方はいかがでしょうか?
青栁さん:アフィリエイト広告は当社の場合、1件あたりの成果報酬を競合さんよりも低く設定しています。しかし、競合企業の中には1件あたりの成果報酬を1.2万円と設定されているところもあり、当社の設定金額を大幅に上回っていることも少なくありません。料金では見劣りしますが、アフィリエイターの方々が競合サービスと当社のサービスを比較する中で、世界観や品質を気に入っていただき、記事として取り上げていただけることが多いように感じています。結果として、アフィリエイト広告でも、まずまずの成果が出ているかと思います。
お客様の層としてiPhoneユーザーが多いこともあり、最近ではCookie規制の影響によりリターゲティング広告やリマーケティング広告、Facebook広告の効果が大幅に下がっています。こういった背景からInstagramに出している広告も減らしています。TikTokは色々と試してみましたが、動画から直接LPに遷移する形ではなかなか費用対効果が合わず苦しみました。一方で、Twitterは「いいね」ボタンの施策効果もあり、上手くいっているかと思います。

お客様の満足度を高める取り組み
――Cookie規制による影響が大きく出ている一方で、アフィリエイト広告やTwitterのように効果的な運用ができている面があることに安心しました。新規でお申し込みいただいたお客様が長く継続していただいたり、UGCを投稿したりするにはサービス面の魅力が欠かせないかと思います。その点についてはいかがでしょうか。
小林さん:競合さんと比較し、最もお客様に寄り添ったサービスを提供している自信があります。好きになっていただけないと継続されませんし、SNSにアップもしていただけません。お客様とのコミュニケーションやサービスの世界観など、いろいろな点を工夫しています。
お客様対応の点ですと、忙しく働いている親御様のために、LINEの問い合わせは朝7時から夜23時まで対応することで、回答を待つストレスをできるだけ減らせるように工夫しています。
毎日数百件のお問い合わせをお客様からいただきますが、親御様がお子様と楽しい時間を過ごすための対応であれば、個別対応をスタッフの判断で行っても問題ないと伝えています。例えば、お申し込みを検討しているものの、当社で導入していない決済手段を希望していたお客様に対して、1ヶ月分無料のクーポンをお出ししました。こういった判断を現場のスタッフがすぐにできることは、お客様にとっても嬉しいことだと思います。
他にも、お子様の誕生月には心を込めたバースデーカードを別送します。原価がそれなりにかかるバースデーカードですが、親族以外から初めてもらうお祝いのメッセージになるかと思うので、喜んでいただけるような贈り物になればという想いでお送りしています。
サービス面ではおもちゃの選定や品質についてもこだわりを持っています。おもちゃをお送りする前に、お客様が既にお持ちのおもちゃの情報をお伺いしています。その情報から教育方針や好みがわかるため、機械的に決まったおもちゃをお届けするのではなく、おもちゃコンシェルジュがお客様に合わせておもちゃを選定してお送りしています。今お伝えした内容は複数行っている取り組みの一部なので、ぜひサービスを活用いただけると嬉しいです。
事業立ち上げ後に感じる立ち上げ前とのギャップ
――お客様にとって喜ばれることを優先している取り組みが多いことをお話の中で感じられました。最後に、この事業を立ち上げる前と今とのギャップについて気づいたことなどあれば教えていただけますか。
青栁さん:リピート通販やサブスクサービスが簡単に黒字化しやすいという話は信じない方が良いと思います。2年かけても黒字化することは簡単なことではありません。事業を伸ばしていく上で、最終的に勝ち残るには資本力が大事なことはもちろんですが、諦めずにやり続けることが大切です。やり続けるために、借り入れできるならお金はできるだけ多く借りた方が良いと思います。最初に立てた事業計画は、事業の状況や実際に事業を進めてみてわかったことに合わせて動きながら調整していかなければなりません。
当社の場合、おもちゃを仕入れて、選定してからお届けし、返却いただいた後にクリーニングを行うまで全ての工程に人の手がかかります。お客様が増えれば、ここにかかる人の手がその分増える労働集約型のビジネスモデルです。実際やってみた感想として、正直、そんなに儲かる商売ではありませんが、何のためにこのサービスをローンチしたのか原点を忘れずに、お客様に喜んでいただけるようこれからも頑張っていきたいと思います。
インタビューを通して:手間暇やこだわりが世界観を作り、お客様から愛される
取材の前までは、お客様の傾向に合わせて提供するおもちゃを仕組み化し、業務を外部に委託しながら効率良く事業を拡大していると思っていまいた。しかし、実際は完全にその逆の運用をしています。お話を伺うことで、キッズ・ラボラトリーを通じて親御様とお子様が楽しい時間を過ごすために必要な取り組みであることがわかります。
集客やお客様対応など緻密に考え抜かれた施策は、お客様にとって一貫した世界観を提供するためにこだわりを感じられます。物流や同梱物に関するより詳しい内容については、株式会社富士ロジテックのD2C/eコマースコラムによってまとめられていますので、ぜひそちらもご覧ください。
本取材は株式会社富士ロジテックによる協賛で行われています。
▼株式会社富士ロジテックのD2C/eコマースコラム
https://fujilogi.net/pages/voice
▼キッズ・ラボラトリー
https://kids-laboratory.co.jp/
合わせて読みたい

















