
この記事の目次
ステップ2:通信販売(ダイレクトマーケティング)への拡張
地域の製造小売ビジネスが成長するために必要なステップとして、次の3つが挙げられます。
ステップ1:リアル店舗の顧客データを活用して再成長
ステップ2:通信販売(ダイレクトマーケティング)への拡張
ステップ3:デジタルコマース・マーケットプレイスへと拡大
前回のコラムでは、ステップ1について解説いたしました。今回はステップ2についてお伝えいたします。
通信販売(ダイレクトマーケティング)への拡張にあたって、次の3つを意識するといいでしょう。
①通販(ダイレクトマーケティング・オフライン)はリアル店舗の顧客から
②アトリビューション(購入理由)がわかれば、ダイレクトマーケティングが可能
③通販事業をサポートするための運用デザインとシステム選定のポイント
それぞれについて説明いたします。
①通販(ダイレクトマーケティング・オフライン)はリアル店舗の顧客から
ロイヤルカスタマーはダイレクトマーケティングも利用してくれる
古きメーカー通販の時代(関西の大手上場メーカーの事例など)を思い起こすだけでも、製造・小売企業が通販(ダイレクトマーケティング・オフライン)に参入する方法にはいろいろなやり方があります。初期段階として、工場直売会、直売店舗を基点としたリアル販売と、通販のハイブリッド展開をお勧めしています。
その理由の1つは、新規顧客とリピート顧客の獲得に掛かるコストです。リアル店舗の顧客リストから、通販への引き上げが可能になります。顧客の価値と商品が合っていれば、CPOが3,000円以下に下がるはずです。それで、一気に利益ベースが良くなるでしょう。
ただし、商品開発は必要になります。なぜなら、店舗で販売しているものが、そのまま通販で売れるわけではないからです。1品単価や平均購入金額、送料などの費用と利益のバランスを考えなければなりません。贈り物(自家消費は、自分などへの贈り物です。「ケ」であろうが「ハレ」であろうがどちらでもです)などで、ご利用いただくような商品開発も必要になってきます。
仕組み(多くは、スタッフと売上計上などの評価制度)を整えて、余裕が出てきたら、通販単独での投資(広告などになりますが、オフラインだけでは大変です。どうしてもデジタルのチャネルを活用することになります)を始めるという形で実施されていくと、会社として事業として良くなっていきます。
②アトリビューションがわかれば、ダイレクトマーケティングが可能
そのためには、SNSを活用する
「アトリビューション(購入理由)」は、顧客が商品やサービスを購入する際に影響を与えるさまざまな要因や要素を指します。これは、購入行動がどのように形成されて、どの要因が購入の決定に寄与したかを理解しようとする概念です。アトリビューションは、購入行動においてどの要因がどれだけの影響を持っているかを評価するプロセスを指します。
その中で、製造・小売企業が一番身近で、ローコストで活用できるものが、リアルでは顧客との会話ですし、アンケートです。デジタルでは、InstagramなどのSNSや、LINEになります。初期のSNSの機能(コミュニケーション&コミュニティ)と特徴(ローコスト)を活用して成長したのは、D2Cビジネスです。そのため、D2Cはモデルではなく、チャネルといえるでしょう。
SNSでは、創業者、経営者、プロダクトマネージャー、スタッフが自らの視点・スタイルで顧客とコミュニケーションすることが基本です。顧客とのコミュニケーションから生まれる、アトリビューションの事例を展開して共感する顧客候補と出会っていくことがコミュニティマーケティングです。このフェーズで、これを実施することで、デジタルマーケティングへの参入するための準備ができていきます。
価値=自分にとってのベネフィット(個人によって千差万別で未来での体験・評価です)を想起していくこと
アパレル・ファッションでは、着こなしであったり、コスメではメイクアップされたパーソナルカラーコーディネートであったり、スキンケアでは五感で感じる表現のワードであったり、サプリメントでは、改善された状態からのプラス要素であったりします。
これだけではなく、その結果として、どのように周りから見られていたという体験や、時間を、コミュニティで共有できていたこと、感じたことを、信頼と透明性をベースに表現することが、「顧客中心」の商品の価値としての、証拠(エビデンス)となり、口コミと影響力を発揮します。
③通販事業をサポートするための運用デザインとシステム選定のポイント
通販ビジネスをするためには、顧客データ、商品データを管理把握して、顧客をセグメントして、コミュニケーションをして注文をいただき、注文を処理(決済と出荷)して、顧客にお届けして、ご利用いただき、評価を得ることが必要です。そのためにも、システムには次のような機能が備わっていなければなりません。
一般的な「通販業務システム」機能
- 商品管理機能
- 顧客管理機能
- 注文管理機能
- 在庫管理機能
- 支払・決済管理機能
- 配送管理機能
- 問い合わせ管理機能
- キャンペーン機能
ここではシステム選定にあたっての3つのポイントについて説明します。
ポイント1:通販業務は、データエントリーと注文処理の正確性と効率化
注文管理機能などのポイントは、アナログだということです。紙の注文・申込書からの転記入力になります。正確なデータ入力が重要になってくるので、二重入力で確認をします。それは、同じデータを二回入力して、その結果を比較することで、タイプミスや入力エラーを減少させることが基本です。
これを、顧客にセルフでしてもらうことが、デジタルコマースですし、だからこそ、ここでのスタッフのUIの知見がカートでのフォーム設計に活かされてくるのです。そして、他で登録しているデータを連携して呼び出すことが、Amazon PayなどのID連携の顧客視点での導入メリットになります。
可能であれば、顧客カードや、商品部分は、商品コードとバーコードスキャンを導入してデータ入力の正確性を向上させることができます。
アプリケーションの入力フィールドにおいて、ユーザーが以前に入力した情報(例: 名前、住所、電話番号)を、オートフィル機能として、 顧客の情報(IDとなるkeyデータ)や以前の注文履歴から、注文フォームを自動的に補完する機能を導入することで、注文処理の効率を向上させることができます。
ここでは、類似データ候補や、重複排除、グレー・ブラック情報など顧客情報の気付かない管理ポイント機能の有無、そして、顧客別の有効なキャンペーン情報や、レコメンド情報が提示できるかを確認するようにしましょう。
明確なプロセスドキュメントを更新して、運用すること
標準手順(プロセス)の作成をします。これは、業務システムの標準機能を活用することをお勧めします。なぜならそれが一番効率的なワークフロープロセスとして設計されているはずだからです。
データエントリーや注文処理の標準手順を文書(マニュアル)化し、関連するスタッフにトレーニングを提供します。これにより、品質一貫性が保たれるということは、ムダ・ムリ・ムラがなくなるために効率化も強化されるということです。
イレギュラー・トラブルシューティングガイドを、準備拡充すること
イレギュラー処理や、予期せぬ問題は必ず発生します。その場合の手順をまとめたイレギュラー・トラブルシューティングガイドを用意して更新して、スタッフが問題を解決するのに役立てます。これは、先々デジタルコマースを展開する場合に、顧客のセルフサービス機能とFAQへと引き継がれていきます。
ポイント2:店舗と倉庫と工場との、在庫確認と各場所からの出荷業務の簡素化と効率化
在庫管理機能として、在庫(さまざまな場所:店舗A・店舗Bそして倉庫や、工場での生産在庫など)を可能な限りリアルタイムで把握できるようにし、在庫切れのリスクを減らしたり、分散出荷をしたり、荷合わせ出荷のために最も遅い出荷日での発送予定などを設定しましょう。
これは、デジタルコマースをする際や、オムニチャネルコマース(店頭受取や、店頭発送)を実施する際により重要になってきますので、拡張性(カスタマイズではなく、追加設定など)のある業務システムを選定する必要があります。
業務効率化のためには、自社倉庫出荷であっても、3PLを活用する場合であっても、注文処理からピック・パック・シップ業務までのフルフィルメント業務に添って、最適な処理バッチを作成できるかがポイントです。
100件の注文データがあったとします。
A商品 50件 20セット/時間・人 ワークタイム:2.5時間
B商品 30件 10セット/時間・人 ワークタイム:3.0時間
A+B商品 20件 5セット/時間・人 ワークタイム:4.0時間
トータル9.5時間の場合に、どのように出荷バッチを生成して指示票を出すかがポイントになります。標準ワークタイムをベースに、1週間分の予定出荷件数などがわかると、さらに効率化と、平準化を求めるアイディアと工夫は店舗・工場・バックオフィスのスタッフが、多能工として考え出していくことができます。(Amazonのように、ピーク時には1日あたりのお届け可能数を設定して顧客に提示することも重要な購入体験です。)
業務システムとして、ピッキング票や一体型の発送伝票の印字システムがあれば、WMS機能を別システムとして持つかは倉庫ロケーションの複雑性と、ロボット化をするかどうかがポイントです。
ポイント3:店舗で、バックオフィスで顧客を知って、見て、対話することができること
日本の通販業務システムには、顧客の購入履歴データしかありません。
Aさん ○○年○○月○○日 ++商品 ●個 ****円 ▲**円引 ???クーポンを利用
で、クレジットカードで購入した程度のデータです。
この程度のデータを、RF分析などで分析したところで大したインサイトは出ません。顧客を「木」という集まりの「森」として俯瞰しているだけです。
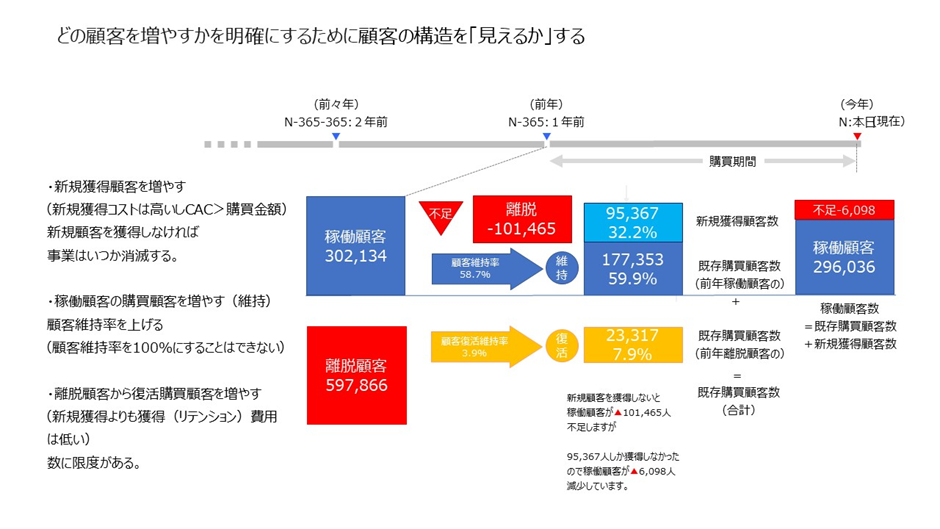
ここでは、顧客の行動データや、価値観などを留めておくことが重要な機能ですが、CRMシステムとして外部システムで実装することのないようにします。なぜなら、業務システムの顧客データを「正」にするためです。顧客データの機能として下記に挙げられるものが必要になります。
顧客情報管理:一番のコア機能でここが「正」
顧客の基本情報や購入履歴、問い合わせ履歴などを管理する機能です。顧客情報を一元管理することで、顧客との関係性を深め、顧客のニーズに合わせたサービスを提供することができます。
カスタマーサポート:顧客を知るためのハブ機能
顧客からの問い合わせやクレームなどの管理、対応履歴の管理など、カスタマーサポートに役立つ機能になります。顧客の相談や、判らないことへの問い合わせ、応対処理してほしい課題に迅速かつ適切に対応することができ、顧客満足度を向上させることができます。
その詳細データは、各外部コミュニケーション・オペレーションシステム(電話ならPBX・LINE)に保持されています。リンククリック(問合せレコードなど)でポップアップすることでUIを解決します。
データ分析:外部システムを活用して目的を持ってテーマ分析
顧客データを分析し、顧客の嗜好や傾向を把握することができます。顧客のニーズに合わせたサービスを提供することができ、顧客との関係性を深めることができます。
この顧客データを活用して施策の目的に応じた分析・抽出(and・orだけではなく、notが重要)できることが必要になります。これは業務システムに求めないで外部のシステム(マーケティングオートメーションなど)で実装する時代です。
業務システムでは、売上をもたらしてくれる、顧客のセグメント別のコホート情報などの基本的な情報を時系列で、ウォッチ・アラートが出ることで充分です。(固定的なデータ分析で充分だということです)
マーケティング支援:外部システムからの情報を連携して活用
DM発送やキャンペーン管理など、マーケティングに役立つ機能があります。CRMシステムからLINEなど配信ツールを利用することで、顧客が求める情報を提供することができ、顧客のニーズに合わせたサービスを提供することができます。
このデータを見ることで、Aさんにとって必要な、商品のご案内、有効なキャンペーン・オファー情報を提供できること、そしてその反応と結果がコミュニケーションのポイントだからです。
外部連携:通販業務システムにコミュニケーション&マーケティング機能のすべてを求めない
デジタルコマースへチャネルを増やしていくときには、コミュニケーションにおけるタッチポイントとの連携が必要になりますので、これらの機能のデジタル拡張領域を外部のシステムで追加実装します。
次回のコラムについて
「ステップ2:通信販売(ダイレクトマーケティング)への拡張」について、説明させていただきました。次回は「ステップ3:デジタルコマース・マーケットプレイスへと拡大」について解説します。
※本記事は執筆にあたって株式会社東計電算にご協力いただいています。
合わせて読みたい

















