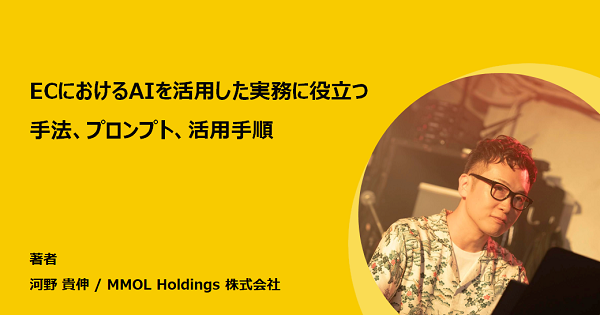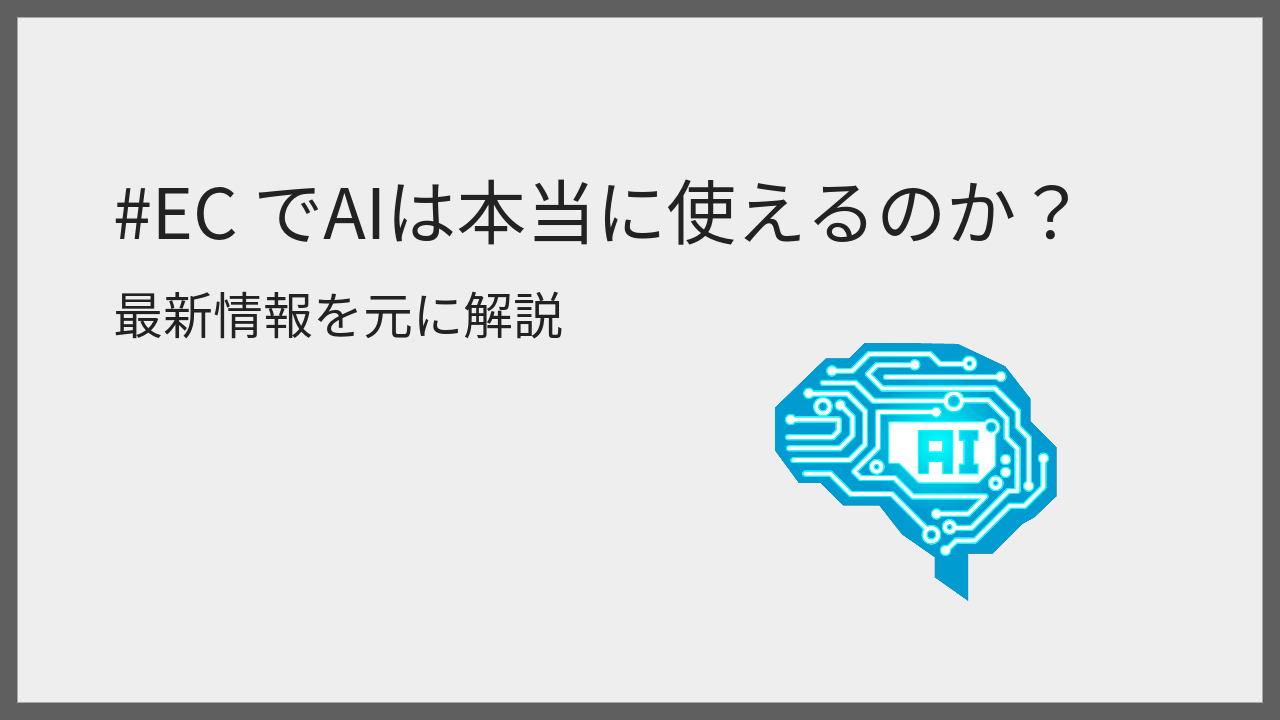ChatGPTを筆頭に注目を集めている生成AIは、業務を効率化できる手段のひとつとして活用が進められています。生成AIでできること、できないことに加え、具体的な生成AIサービスの特徴と、EC事業での活用イメージをご紹介します。
この記事の目次
生成AIとは?
生成AIは、人が作り出すようなコンテンツを生成できるAIのことで、ジェネレーティブAI(Generative AI)とも呼ばれます。従来のAIは既存の情報を整理したり、分類を学習したりして結果や予測を導くことに長けていたのに対し、生成AIはさまざまな情報を組み合わせて新たなコンテンツを生成できるのが特徴です。
生成できるコンテンツは、文章(テキスト)、画像、音声、音楽、動画、プログラムコードなど多岐に渡ります。クリエイティブな分野にとどまらずニュース記事や広告の作成など幅広い活用が期待されている技術です。
生成AIを活用してできること
生成AIはコンテンツ生成や文字起こしができます。手間のかかる定型業務に生成AIを活用することでEC事業を効率化させましょう。
問い合わせ対応を効率化できる
コールセンターを構えて、消費者からの問い合わせ対応を行っているEC事業者では、文字起こしAIを活用して、コールセンターの応対を記録することができます。応対の分析や改善、振り返りに活用することで、問い合わせ対応の品質向上が期待できます。
また、生成AIを活用したチャットボットを活用すれば、カスタマーサポートの効率化や24時間対応によるサービス品質の向上を期待することも可能です。
コンテンツの生成を代行できる
ECサイトに掲載する商品名やキャッチコピー、SEO記事などのコンテンツを作成することも可能です。生成AIで作られたコンテンツをそのまま活用するのが難しい場合でも、アイデアのヒントになるかもしれません。
生成AIではできないこと
生成AIでは、人の感情を読み取ったコンテンツ生成やオリジナルコンテンツの生成は難しいです。
人の感情を読み取った応対やコンテンツ生成は難しい
キャッチコピーを作ったり、会話ができたりする生成AIですが、人間のように思考しているわけではないため、。入力されたテキストのパターンやキーワードに基づいて感情を推測することはできますが、文脈やニュアンスを完全に理解するのは難しいです。回答として正しいとしても、状況によっては相手を不快にさせてしまう可能性があり、人の手による検証や編集が欠かせません。
オリジナルコンテンツをつくることは難易度が髙い
生成AIは膨大なデータからパターンを学習し、その特徴に基づくコンテンツを生成しています。そのため商品や消費者にぴったりと合う0→1のオリジナルコンテンツを作成することは困難です。
生成AIのサービスとEC事業での活用イメージ
ここからは具体的な生成AIのサービスと、EC事業での活用シーンをご紹介します。
【テキスト生成AI】ChatGPT
ChatGPT(チャットジーピーティー)はOpenAI社が開発した自然な会話ができるチャットサービスです。生成AIが精度の高い回答をすることが話題になり、また無料で利用できることから多くの利用者に活用されています。
ChatGPTは「GPT」という言語モデルがベースになっており、Web上にある膨大な情報を学習し、複雑な語彙や表現を理解できます。さらに2023年9月にはChatGPTの音声・画像認識機能が発表され、画像生成AIと統合することで画像の生成もできるようになりました。
メールアドレスを登録するだけで無料で利用できますが、月額20ドルでより機能が充実したChatGPT Plusが利用できます。
ChatGPTのEC事業での活用シーン
ChatGPTのAPIを活用したチャットボットを作成すれば、シナリオに沿って回答するチャットボットよりも、顧客満足度の高い問い合わせ対応が実現します。また細かく指示を出したり、入念にチェックを行ったりなど、誤った情報を公開しないよう慎重に活用する必要はありますが、SEOコンテンツやFAQの作成にも活用できます。
【テキスト生成AI】Gemini
Gemini(ジェミニ)は、2023年12月にGoogleから発表された生成AIです。テキストや画像、音声、動画を用いて、チャット形式でタスクを実行できるもので「マルチモーダルAIモデル」と呼ばれます。ChatGPTと似ていますが、ChatGPTは蓄積したデータから回答しているのに対し、GeminiはGoogleの検索エンジン上の情報から回答しているという違いがあります。Geminiは基本的に無料で、上位版のGemini Advancedは月額2,900円で利用できます。
GeminiのEC事業での活用シーン
Geminiを活用して、記事コンテンツのアイデアを提案してもらえば、SEO対策に役立ちます。また、提示したWebページや手書きメモの要約、議事録の作成などを行うことで、日々の業務の時間短縮にもなります。
【文字起こし生成AI】Whisper
Whisper(ウィスパー)は、OpenAIが発表した文字起こしAIで、日本語の音声も高い精度で文字起こしができるとして知られています。複数人が同時に会話をしていてもそれぞれの内容を識別できる他、翻訳を同時に行うことも可能です。
WhisperのEC事業での活用シーン
会議の議事録作成や、消費者や開発者へインタビューを行った際の文字起こしに活用することで、作業工数を削減できるでしょう。また字幕の生成も可能で、PR動画などの作成の際にも活用できます。
【キャッチコピーの生成】Catchy
Catchy(キャッチー)は、OpenAI社のGPT-3が搭載されたAIライティングアシスタントツールです。テンプレートにテキストを入力するだけで、記事作成やリライト、メールの返信文などを自動生成できます。無料から利用でき、日本企業が提供するツールのため問い合わせがしやすいのも特徴です。
CatchyのEC事業での活用シーン
商品紹介文の作成や、問い合わせメールの返信文などを自動作成することで作業工数を削減できます。なお、さまざまな文章の作成が可能ですが、ユーザーレビューを生成して掲載することは禁止されています。
【画像生成AI】Stable Diffusion
Stable Diffusion(ステーブルディフュージョン)は、Stability AIが開発した、ユーザーが入力したテキストを基に自動で画像を生成するAIです。2022年8月にオープンソースで公開されました。利用料は無料で、商用利用も可能。作成枚数に制限がないため、画像生成AIのなかでも特に注目を集めています。利用にあたっては、Stable Diffusionを搭載しているサービスを利用するか、お手元のPCにインストールするかのいずれかの方法があります。
Stable DiffusionのEC事業での活用シーン
Stable Diffusionを使って、商品の使用例や着用例を作成すれば、モデルの採用や撮影にかかるコストを削減できます。Stable Diffusionで作成した画像は商用利用可能ですが、他のモデルを追加学習する際にはライセンスに制約がかかる場合があるため確認が必要です。
【画像生成AI】Midjourney
Midjourney(ミッドジャーニー)は、2023年7月に一般公開された画像生成AIです。芸術的な画風が特徴で、クリエイター向けの画像生成AIといわれることもあります。Discord上で操作する必要がある他、生成したい画像に関するキーワードは英語で入力する必要があるため、Stable Diffusionに比べて使いづらいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。なお、以前は無料で利用できましたが、2024年4月からは有料版のみの提供となっています。
MidjourneyのEC事業での活用シーン
Midjourneyは文字を表示できるため、ECサイトや商品ブランドのロゴの作成に活用できます。Midjourneyの芸術的な画風が合うECサイトやブランドにおすすめです。
【アイコン生成】Canva AI
Canva AI(キャンバエーアイ)はテキストを入力するだけで、イメージに合う画像を生成してくれるサービスです。無料登録をすれば画像編集ができるデザインツールと、画像生成AI「Magic Media」を利用できます。日本語に対応しており、操作も簡単で手軽に利用できる生成AIとなっています。Canvaで生成された画像は商用利用できますが、著作権を得ることができない点には注意が必要です。
CanvaのEC事業での活用シーン
記事コンテンツのヘッダー画像や、ECサイトの装飾に用いる画像の生成に利用できます。先述の通り、著作権を得ることができず、画像を独占して使うことができないので、企業ロゴやブランドロゴの生成は避けたほうがよさそうです。
【動画生成AI】Make-a-Video
Make-a-Video(メイクアビデオ)は、2022年9月にMetaが発表した動画生成AIで、テキストや画像、既存の動画から新しい動画を生成することができます。EC事業の日常業務に活用するにはまだ物足りない状況ではありますが、テキストから動画を生成する技術は、テキストから画像を生成するのに比べて高度だといわれており、今後の活用が期待されています。
【動画生成AI】Phenaki
Phenaki(フェナキ)は、Googleが開発した動画生成AIです。テキストと画像を組み合わせたり、長めのテキストから動画を生成できたりするのが特徴です。Make-a-Videoと同様に、実務で活用するにはさらに改善が必要ですが、今後の発展が期待されています。
生成AIを利用する際の注意点
手軽に短時間でコンテンツを生成できる生成AIは、非常に便利で事業の幅を広げてくれる可能性を秘めていますが、情報を組み合わせて生成しているという特性ゆえに、フェイクコンテンツを生成してしまうこともあります。
生成AIでコンテンツを作成する際には、正しい内容が生成されるよう適切な指示を与えた上で、人の手による検証や編集を欠かさずに行うようにしましょう。
ECモールでの生成AI活用
2024年3月に楽天市場より「RMS AIアシスタントβ版」の提供が開始されました。RMS AIアシスタントβ版は、店舗運営に関わる次のような機能を備えています。
- 商品の説明文生成や商品画像の加工
- ユーザーへの問い合わせ対応用の文章生成
- 自店舗の売上傾向などのデータ分析・解説
- 店舗運営に関する疑問を解消するためのAIチャットボット
また同年4月には、AIの基礎知識やRMS AIアシスタントβ版の利用方法、活用事例を学ぶことができる「楽天AI大学」の提供を開始し、EC事業者へのAI利用を促しています。
参考:「楽天市場」、AIを活用した店舗運営の効率化や生産性向上を推進・支援
現時点で他のECモールから生成AIの活用を促す機能などは発表されていませんが、Amazonではかねてより不正レビュー対策にAIを用いるなど、AIの活用が進んでおり、今後生成AIに関する機能や取り組みが発表される可能性も考えられます。
おわりに
生成AIを使って、人が行う業務を代替するには適切な指示出しが必要になるため、慣れるまでは取り扱いにくさを感じることがあるかもしれません。また、動画生成AIなどは更なる技術発展が期待される部分もあります。その一方で、生成AIはうまく用いることで、アイデアを広げ、業務効率を大幅に改善できる技術です。少しずつ業務に取り入れて業務改善を重ねることで、競争力を高めEC事業の売り上げアップにつなげていきましょう。
【卒業生が選んだ】おすすめプログラミングスクール比較 | プロリア プログラミング
https://www.interspace.ne.jp/media/programming/
トレンドをキャッチアップ!AIに関する情報が得られるメディア・ブログまとめ
https://freelance-hub.jp/column/detail/686/
合わせて読みたい