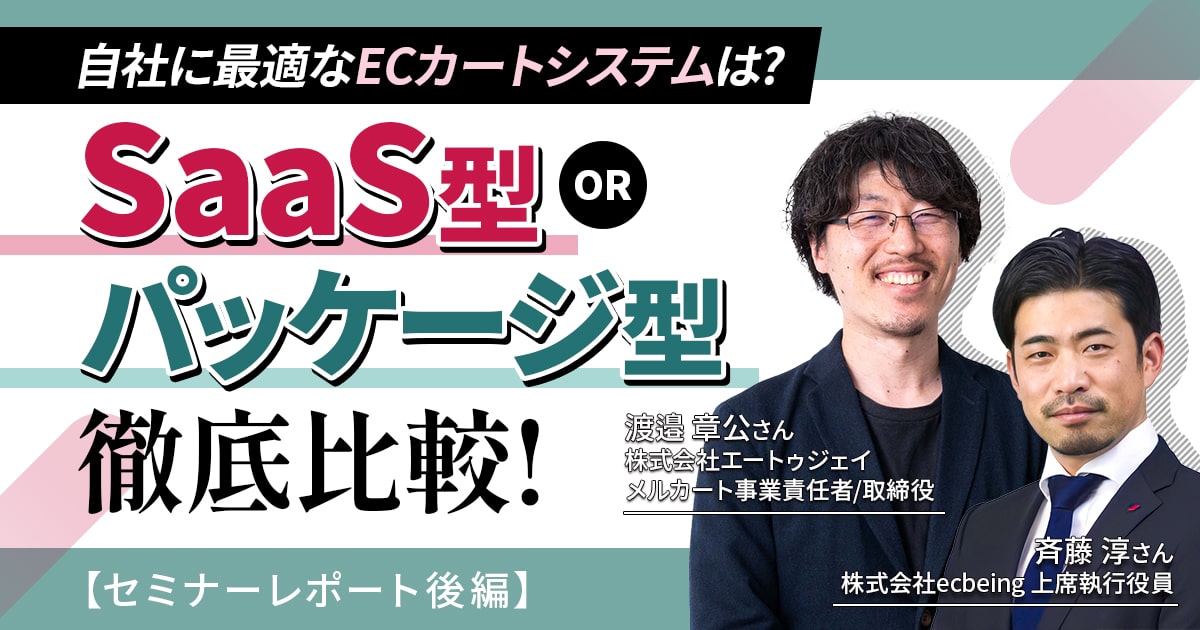【ゲストスピーカー】
望月 卓郎さん
株式会社ヤッホーブルーイング コンシューマー部門 事業統括
クラフトビールよなよなエール公式サイト「よなよなの里」
【チャンネルMC】
柳田 敏正さん
株式会社柳田織物 代表取締役
ワイシャツ専門店「ozie(オジエ)」
この記事の目次
商品数や価格で勝負できないからこそ、「面白い」を意識
柳田さん:「よなよなエール」といえばEC起点でありながら、コンビニやスーパーでの販売、イベントの開催、さらにはビアレストラン「YONA YONA BEER WORKS」の展開など、リアルの場にも積極的に取り組まれてきました。ECを起点にリアルとの接点を増やしている理由や、よなよなエールのブランディングについて教えていただけますか?
望月さん:首都圏にいらっしゃる方やEC業界の方の中には、「よなよなエールはよく見かける」と思ってくださっている方もいるかもしれませんが、私たち自身はまだまだ認知度が足りないと感じています。例えば、沖縄の「オリオンビール」は日本人の多くが知っているブランドですよね。あれくらいの認知度があれば、売上ももっと伸ばせるのではないかと考えたりもします。
ECを始めた2010〜2012年頃は、まだ完全に無名の状態でした。流通に乗せるのも非常に難しく、代表もよく話していますが、採用されない苦しい時代の中で“背水の陣”で始めたのがECなんです。
ちょうど楽天市場のオープン時期と近かったこともあり、EC経由で購入してくださるお客様が徐々に増えてきました。その中に、メーカーである私たちが自由にメッセージを発信し、それを喜んでくださるお客様が見えてきました。
楽天市場で少し売れるようになってきた頃の「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」では、売上はそこまで多くなかったにもかかわらず、お客様投票で非常に多くの票をいただいたのが印象的でした。それを見て、「これは面白がってくださっているお客様がいる」と感じたんです。
そうした方々に、ネット上のやりとりだけでなく、「当社のビールを飲んでよかった」「面白い体験ができた」と思っていただける機会を増やしたい。それが当社のマーケティングの一つの目的でもあります。
そのためには、やはり“直接会う”のが一番早いと考えました。当時は直営店もなかったので、当社のビールを扱ってくれているパブにお客様をお呼びして、新商品発表会を開催してみたんです。45名限定でメルマガを出したところ、すぐに満席に。そして当日、夕方にお店に向かうと、すでに行列ができていました。
やはりメーカーの人間と直接話すことで、お客様にはより興味を持っていただけますし、ブランドへの愛着も深まると実感しました。対面イベントは製品に対する関心だけでなく、ブランドへの熱量を高めるんだと、社内でも改めて強く共有された経験です。
柳田さん:「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」の投票といえば、メールマガジンで投票をお願いする形式でしたよね。あの投票で多くの票が入ったというのは、ECで面白いことをやっているだけでなく、ビールのクオリティが高い証拠でもあります。社長の井出さんも個性的な方ですよね。
望月さん:今でも代表のカラーは強く出ていますが、当時の商品ページや企画は本当に“ぶっ飛んで”いて、今見返すと恥ずかしいくらいです(笑)。
柳田さん:でも、そういう企画があったからこそ、商品が良いだけでは実現できない“イベントの即完”が生まれたのだと思います。
望月さん:当時、商品ページは私が作っていたのですが、設定がとにかくユニークでした。たとえば代表の井出は「てんちょ」というニックネームで、「働かないてんちょ」という設定なんです。2か月に1回しか出社せず、来ても「みんな元気にやってる?午後、釣り行く人いる?」と言い出して、「いやいや、仕事ありますから帰ってください」という寸劇をページ内で展開していました。
これは、私たちが扱える商品数が少ないことにも起因しています。現在も30アイテムほど、ビールに限ると10種類ほどしかありません。組み合わせ商品でバリエーションを出している状況です。メーカーである以上、値引き競争も避けています。つまり、ECの王道である「商品数を増やす」「価格で勝負する」といった戦略が取れません。だからこそ、「どうすれば最後までページを見てもらえるか」を本気で考えて、毎回ページをつくっていました。
よくやっていたのは、「新商品がまもなく完成します」というタイミングで、井出がマジシャンの格好で現れるという演出です。私は倉庫番という設定で、軽井沢の寒い倉庫でウトウトして目覚めると、商品が一部なくなっていて、それを井出が持っていった、というようなストーリー仕立てのページを作っていました。仕事としてこういうページを作っていて、「なんて楽しい仕事なんだ」と感じていましたね。
大規模イベントも社員の手で創り、お客様の“好き”を実感
柳田さん:社員が楽しそうに仕事をしているブランドがリアルイベントを開催すると、「面白そうだし、新商品も飲めるなら行ってみたい」と思うお客様は多かったのではないでしょうか。とはいえ、初めてのイベントで45名規模というのは、少しハードルが高く感じます。
望月さん:実際、私たちも「集まるのかな?」と心配していたのですが、想像以上のスピードで席が埋まりました。45席のパブといっても、小さめの店舗よりはやや大きい程度ですが、当日は井出がスライドを使って新商品の紹介をしたりして、「これが“働かないてんちょ”か!」「今日は新商品を樽で持ってきたので飲めます」「おおー!!」と会場が盛り上がる瞬間が何度もありました。
楽しかったですね。お客様の反応を間近に見て、これはいける、もっと広がるかもしれないと強く感じたイベントでした。
柳田さん:やはりリアルイベントで盛り上がると、スタッフ側にも「これは手応えがある」という実感が生まれますよね。
望月さん:その通りです。イベントの場では「おいしいね」「ありがとう」と直接言っていただけるので、スタッフのモチベーションも一気に上がります。
ECの現場って、画面越しのやりとりが中心ですし、裏方の仕事も多く、配送トラブルなどの対応で大変なことも少なくありません。そういう中で、お客様が「いつも飲んでますよ」と笑顔で声をかけてくださる。それが本当に励みになるんです。ですので、イベントはお客様のためだけでなく、社員にとっても非常に意味のある取り組みだと感じています。
柳田さん:そこから、イベントにも本格的に力を入れるようになったのですね。かなり熱量を注がれているようにお見受けします。
望月さん:そうですね。私はもともと、オートバイメーカーの「ハーレーダビッドソン」さんのイベント運営をとても尊敬していたんです。ファンが集い、ブランドの世界観を“体感”できるイベントを、初期は社員主導で全て運営していたんですよ。
だからこそ、お客様と直接向き合う姿勢や細やかな気配りが行き届いていて、非常に高い熱量を感じました。その影響もあり、当社でもイベントはある程度の規模になるまでは社員の手で企画・運営する方針をとっていました。
ただ、来場者が1,000人規模になるとさすがに大変で…。プロジェクトメンバーとして社内から約50名の希望者を募り、台本の作成からアーティストの選定まで、すべて自分たちで進めて、3〜4日間にわたるイベントを開催しました。イベント終了後は、全員が完全に疲れ切っていましたね(笑)。
あまりに急激に拡大してしまうと、どうしても“行き届かなくなる部分”が出てきます。そこで現在は、1to1の接点を大切にした、適度なサイズ感のイベントがちょうどよいのではと考えるようになっています。
リアルもオンラインも、“一緒に飲む”で意向度をアップ
柳田さん:お客様同士の交流を重視するようになった背景には、何かきっかけがあったのですか?
望月さん:はい。よなよなエールを「好き」と言ってくださる理由を調査したことがあるのですが、その結果、キーワードとして「仲間」「関係性が深まる」「顔が見える」といった点が浮かび上がってきました。
たまたまですが、当社にはニックネーム文化がありまして、イベントでもお客様にニックネームを書いた名札をつけていただいています。
私は「もっちー」という名札をつけているのですが、「あなたが“もっちー”なんですね」と声をかけていただいて、そこから自然に会話が始まる。そんなやり取りが、関係性の質を一段も二段も深めてくれるんです。
その経験から、意図的に“お客様同士が対話できる仕掛け”をイベント内に組み込むようにしています。
柳田さん:たしかに、同じ商品が好きな人同士なら、それだけで会話が広がりますよね。
望月さん:そうなんです。当社は「大規模な飲み会」を開催する会社だと冗談交じりによく言われるのですが、私自身が入社して気づいたのは、ビールというお酒は“理由がなくてもハッピーになれるし、仲良くなれる”存在だということでした。
もちろん一人で楽しむ方もいらっしゃいますが、同じ商品が好きな人同士であれば、「おいしいよね」「来月、新商品が出るらしいよ」と、自然に会話が弾みます。
ですから、お客様同士が交流するイベントが盛り上がるのはある意味“必然”。ビール会社がイベントをやるなら、こういう形で発展していくのは、ごく自然な流れだったのかもしれません。
柳田さん:大手企業になると開催が難しい面もあると思いますが、そもそも“交流”を目的としたイベントをお酒の会社が開催するケースはあまり多くないように思います。
望月さん:そうですね。たとえば日本酒の業界では「蔵開き」といった工場見学イベントがよくあります。当社の工場見学も人気ですが、私たちの場合は「その場でどう楽しんでもらうか」という感覚を特に大切にしている点が違うかもしれません。
柳田さん:確かに、多くの酒造メーカーのイベントは商品認知が主な目的かもしれません。その中で、ヤッホーブルーイングさんのように、まず自分たちが盛り上がって、お客様にも喜んでもらい、次の接点につなげていくというのは、なかなかできることではないですよね。一番盛り上がったイベントは、やはりコロナ前の「超宴」でしょうか。
望月さん:はい、「超宴」は盛り上がりました。ただ、その後コロナ禍でリアルイベントができなくなり、本当に苦しい時期が続きました。
そんな中、「オンライン超宴」という新たな形に挑戦してみたところ、2日間で延べ10,000人に参加いただき、リアルを超える勢いを感じることができました。
柳田さん:リアルでも1日5,000人規模とのことでしたが、オンラインで同じ人数を相手にするのは、もっと大変だったのでは?
5,000人の熱量を画面越しに感じるのは難しそうですし、放送局のような運営になりますよね。
望月さん:出演は社員が担当しましたが、配信の裏側は専門会社に協力いただきました。
この2年間でオンラインスキルも格段に上がりましたが、10,000人規模のイベントは頻繁にはできません。現在はより密度の高いコミュニケーションが可能な、数十人〜百人規模のイベントを数多く実施しています。
商品などのテーマについて全体で触れた後、ブレイクアウトルームでお客様と社員が分かれて会話を楽しむような構成にしています。リアルほどではないにせよ、「楽しんでもらえている」という実感はあります。
柳田さん:ECに取り組んでいる企業だからこそ、こうした柔軟な対応ができたのかもしれません。小売や卸の企業が「お客様を集めてオンラインイベントをやろう」と考えるのは、なかなか難しいのではないでしょうか。
リアルイベントができないなら諦めよう、となってしまいそうな中で、オンライン開催のアイデアはどこから出てきたのでしょう?
望月さん:当社には早くからイベント専任の部署がありまして、現在は6〜7名が在籍しています。そのメンバーたちが、「リアルが無理ならオンラインでやろう」と自発的に動き始めました。
コロナが始まった直後から「今、自分たちにできることは何か?」を真剣に考えて、インターネットラジオ番組や複数のオンラインイベントを試行しました。それが現在まで継続されている形です。
柳田さん:イベントチームがあることも大きいと思いますが、それ以上に「お客様とつながり続けたい」という強い気持ちが根底にあると感じます。
オンライン開催って、恵比寿で45名を集めた最初のイベントよりも、むしろハードルが高かったのでは?
望月さん:確かに、リアルイベントは対面なので、場の空気や反応から満足度が見えやすい。でも、オンラインはトラブルも予測しづらいし、慣れていないと本当に大変です。
柳田さん:それでも、挑戦して成功された。1回成功すれば、以降は継続開催の基盤ができますよね。
望月さん:はい。お客様が「コンビニで飲んだことがある」という状態から、「ヤッホーブルーイングのビールが本当に好き」と感じてもらえるようになるには、接触方法のバリエーションと、意向度を高めるタッチポイントが必要です。
その中でも、「一緒に飲む」という体験を共有できるイベントは、意向度を一気に引き上げる効果があります。
ですから、イベントには確かな意味があると確信しています。収支としては赤字ではありますが、「イベントを企画・実行するチーム」「コンテンツを磨き続けるチーム」「カスタマージャーニーを描くチーム」など、お客様の“好き”を育てる体制は、他社と比べても充実しているのではと感じています。
おわりに:EC発ながら、“人と人”のつながりで築くファンとの関係
お客様との交流イベントに力を注ぐヤッホーブルーイングの取り組みからは、「ビールを売る」こと以上に、「お客様との関係性を育む」ことに重きを置いてきた姿勢が伝わってきました。
流通に商品を並べてもらうことさえ難しかった時代から、ファンの声に耳を傾けながら着実に歩んできたその軌跡には、真摯なマーケティングと温かい人間味がにじみ出ています。
リアルイベントやオンライン施策も、認知拡大や売上向上といった短期的な成果を目的とするのではなく、「お客様と一緒に楽しむ」という純粋な想いが根底にあることが印象的でした。
顧客との距離を縮める工夫の数々は、商品や価格だけでは語れないブランド価値をどう築くか。そんな問いへのヒントが詰まっているように感じられます。
EC市場の真の発展に貢献をという想いで、「ECの未来」を運営しているサヴァリ株式会社は楽天市場・Amazonなどネットショップ運営代行をはじめ、モール通販を中心にECサポート・ECコンサルティングを行っています。EC運営に不安を抱えている事業者様は問い合わせてみてはいかがでしょうか。
■サヴァリ株式会社へのお問い合わせはこちら
https://savari.jp/contact/
あわせて読みたい