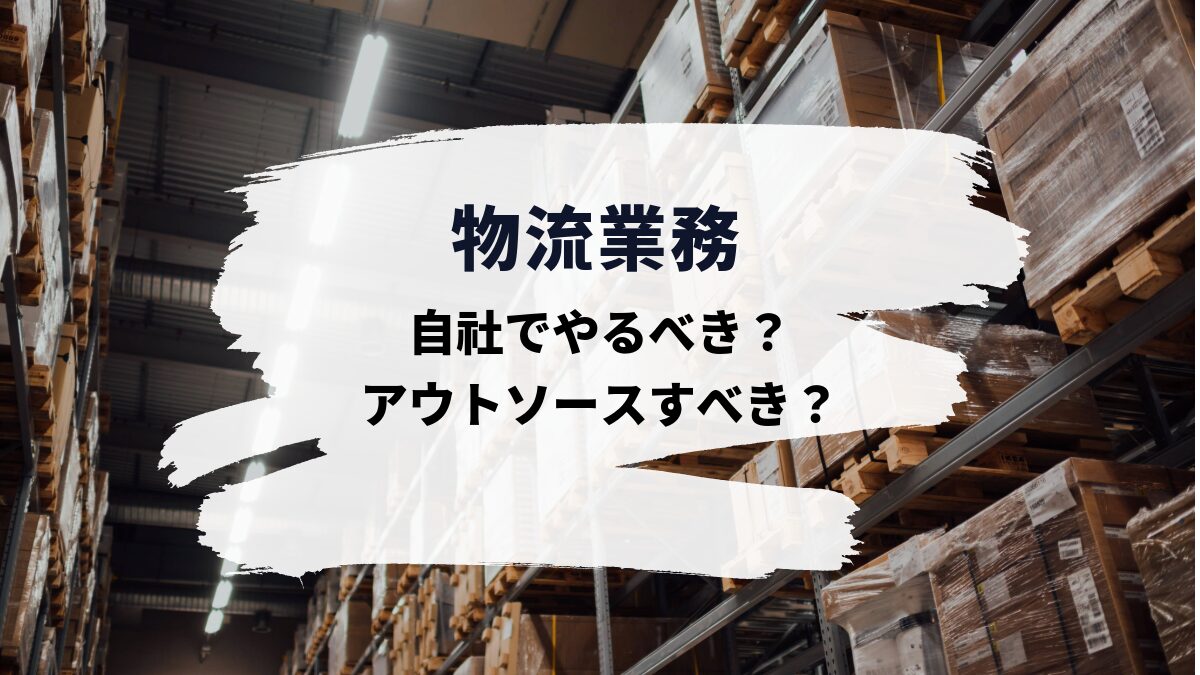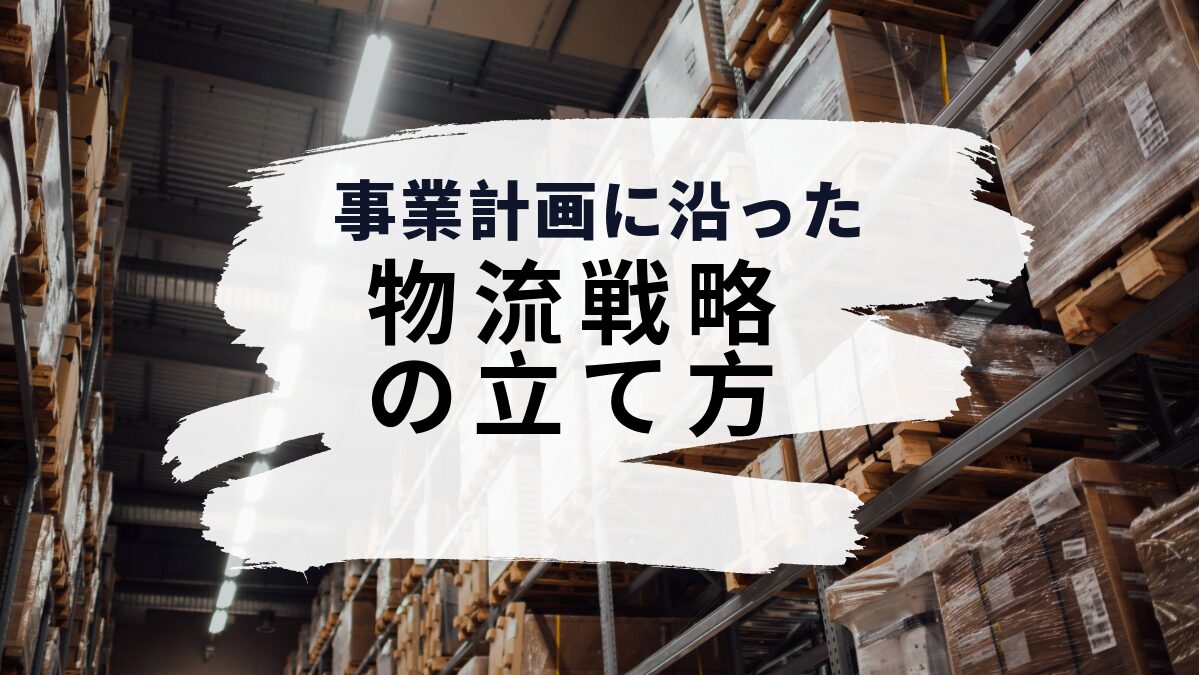
アマゾンや楽天といった企業が日本でECサービスを開始し、他社も次々と参入し本格的に拡大していった2000年以降のEC市場の成長とともに、近年では物を届ける業務である物流の重要性もより一層高まってきています。物流力を高めることで欠品をなくし、遅滞なく届けられる状況を作ることは今や当然のこととして、販売価格を安くするために現場で改善や機械化を進めていたり、配送リードタイム短縮を実現するための物流ネットワークの整備といった施策を講じたりと、顧客サービスレベルの向上の手段として物流が位置づけられるようになっていったのです。
このように物流をただの「運ぶ」活動と捉えるのではなく、事業成長の鍵を握る戦略的な要素として捉えることが重要となり、特にEC事業者は効率的でコストパフォーマンスの高い物流システムの構築が競争力の源泉となります。ただ一方で物流戦略ってどうやって立てるの?という疑問もあるかと思いますので本コラムでは、事業計画に沿った物流戦略の立て方について解説していきます。
この記事の目次
物流戦略を立てる必要性
物流戦略を立てる必要性は、上記でも記載した通り競合との差別化を図ることにより、事業の成長の下支えに直結します。物流コストの削減、納期の短縮、サービス品質の向上など、物流戦略を通じて達成したい目標は多岐にわたります。これらの目標を達成することで、顧客満足度の向上とともに、コストパフォーマンスを高めることが可能となり、結果として事業の拡大に寄与します。
では物流戦略を立てるうえで何を考えていけば良いのか。一般的に物流戦略の中に必ず含まれる主要な項目を5つ考えていきましょう。
1.必要時期と売上規模の設定
物流戦略は事業計画と整合している必要があります。言い換えると現時点から何年後にいくらの売上を実現しているのか、そのために必要な物流機能とはどういった内容になるのかを考える必要があるということです。いつ、どんな規模を目指すのかを社内で合意するところから物流戦略の立案は始まります。
2.倉庫立地の決定
いつ、どれぐらいの規模の物流機能が必要になるかを定めたら次に考えるべきことは商品を保管する倉庫の立地についてです。拠点の場所は特に配送効率に大きな影響を与えます。消費者に近い場所に倉庫を置くことで配送時間とコストを削減できる一方で、地価や人件費の高い地域ではコストが上昇する可能性があります。従って、事業の対象地域と配送コストを考慮して最適な立地を選定することが重要です。
3.必要能力(保管・入出荷)の算定
次に事業計画に基づいて、将来の売上予測に合わせた倉庫の保管能力や入出荷能力の算定を行っていく必要があります。閑散期・平常期・繁忙期の状況を整理しながらその繁閑の需要の差にも対応できる柔軟性を持たせつつ、過剰な能力による無駄なコストが発生しないように計画することが求められます。その基準となる必要能力を定めていきます。
4.目標とする売上高対物流費
必要能力を試算することと並行して目標とする売上高に対する物流コスト比率を定めていきます。事業の収益性を保つためには、売上高に対する物流費の割合を適切に保つことが重要です。業界平均や競合との比較を行い、目標とする物流費の割合を設定し、その範囲内で物流戦略を立案します。この目標物流費は仮に自動化の投資をする状況において特に重要となるため、必ず定めておきましょう。
5.実現するサービスレベル
コストを突き詰めて行き過ぎると顧客に対するサービスレベルや担保すべき品質が置き去りになってしまうことがあります。配送速度、返品・交換サービスの充実度といった内容も含めて最終的に顧客に提供するサービスレベルを定義していきましょう。そこで顧客満足度を高めるためのサービスレベルとかけるべきコストを設定し、コストとサービスレベルのバランスを定めながらそれを実現するための物流戦略を策定します。
物流戦略策定の進め方
上記5項目はあくまでも代表的な項目ではありますが、物流戦略には必ず含める必要がある項目です。では次に物流戦略を立てる際の具体的な進め方についてみていきましょう。進め方は極めてシンプルです。
STEP1:現状把握
まずは自社の物流の現状を正確に把握するところからスタートします。直近の物量や物量の増減の推移、物流コストの内訳や推移、作業ミスの件数や内容、納品の実績、顧客からのフィードバックなど、現場で取得できているデータに基づいて現状の把握を行っていきましょう。
STEP2:目指す姿の策定
現状把握ができたら次にいつまでにどういう状態を目指す必要があるのかを定めていきます。いわゆる目指す姿や、やるべき姿といった内容になります。上記でご紹介した主に物流戦略に含む5項目についてまずは考えてみるといいでしょう。
STEP3:課題の抽出と対策定義
現状と目指す姿の策定ができたら次にその目指す姿に向けて現状とのギャップ、つまり課題を抽出していきます。例えば現状は売上高対物流コスト比率が8%だけど5%を目指したい、としたときに3%の開きがある、というような内容ですね。その課題に対してどのように解決していくかの対策を具体的に整理していきます。
STEP4:実行計画の立案
STEP3で具体的な課題や対策が定義できたら次はそれを戦略を実行に移すための詳細な計画を立てていきます。これらの計画には具体的なスケジュールや、必要な投資などが含まれてきますのでメーカーやベンダーといった対外的なコミュニケーション、情報収集が必要となってきます。
STEP5:プロジェクト化
実行計画が立案できたらその内容を社内で合意し、いよいよ実行に向けてプロジェクト化をしていく段階に入ります。
結び
物流戦略は、事業計画において非常に重要な位置を占めます。特にEC事業者においては、物流の効率化とコスト削減は直接的に競争力に影響します。物流知識がない方でも、上記のポイントを踏まえ、戦略的な視点で物流を考えることで、事業の成長を支える強固な物流システムを構築することが可能です。物流戦略の立て方を一つひとつ丁寧に進め、事業計画の実現に向けて、その第一歩を踏み出しましょう。
▼株式会社CAPES
https://capes.jp/
合わせて読みたい