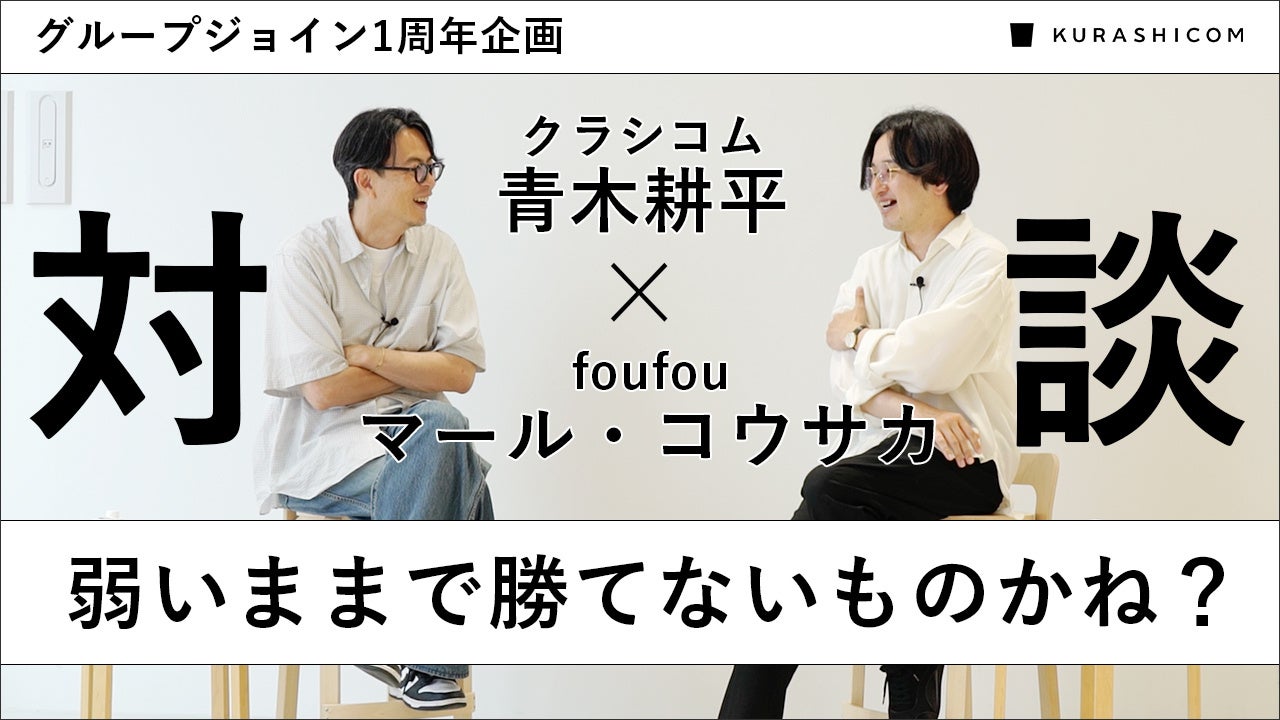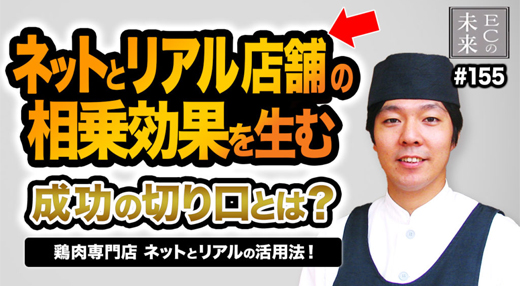【ゲストスピーカー】
青木 耕平さん
株式会社クラシコム 代表取締役社長
北欧ビンテージ雑貨店「北欧、暮らしの道具店」
【チャンネルMC】
柳田 敏正さん
株式会社柳田織物 代表取締役
ワイシャツ専門店「ozie(オジエ)」
この記事の目次
半分以上が割れた荷物の中で、残った食器を顧客リストに
柳田さん:多くの人が「北欧、暮らしの道具店」の成功から、青木さんにはスマートな立ち上げのイメージを持っているかもしれませんが、創業期は試行錯誤を重ねられたと伺っています。まずは、創業に至ったきっかけをお聞かせいただけますか?
青木さん:高校卒業後、私は進学せずにさまざまなアルバイトをしていました。学歴や職歴、人脈といったものは何も持っていなかったのですが、30歳を迎える頃に「インターネット」という新しい産業が登場しました。
誰もが経験していない産業ができたことで、その末端に潜り込むチャンスが生まれ、ようやく社会の中で働いて身を立てることができるようになったのです。それが20代後半のことでした。とはいえ、インターネット産業の中にもすでに多くのものを持っている人たちがいて、自分がいくら自己研鑽しても太刀打ちできないだろう。当時はそう思っていました。
そんなときに『金持ち父さん貧乏父さん』という本に出会います。そこには「最も良いのは投資家になること。そのためにビジネスオーナーになるべきだ」と書かれていました。「従業員として出世を目指すのは、あまり得をしない生き方だ」とも。今ではその考えに共感していませんが、当時の自分にとってはとても都合のいい話でした。というのも、自分が従業員として出世できる見込みはないと思っていたからです。
「なるほど、起業すればいいのか。雇われる側で成功するのは難しいけれど、雇う側に回ればチャンスがあるのか」。そう考えるようになり、いつか起業しようと決めました。
その後、6〜7年ほど経った34歳のとき、『ウェブ進化論』という本に影響を受け、「インターネットでビジネスをしてみたい」と思うようになります。そこで思いついたのが、賃貸不動産やその一部スペース、たとえば倉庫などを貸したい人と借りたい人が直接やり取りできるマーケットプレイスをつくるというアイデアでした。そうして立ち上げたのが、「クラシコム」です。
何とかサービスを立ち上げたものの、まったく利用されず、資金が尽きてそっと閉じることに。振り返ると“失敗”とすら言えない、何も起きなかった事業でした。それでもある程度の投資はしており、手元に残った資金は150万円ほど。2006年頃のことです。
その事業は妹が少し手伝ってくれていたのですが、彼女は以前スウェーデンを訪れて以来、また行きたいと話していました。会社があと数か月で潰れるだろうという状況の中、最後の“罪滅ぼし”として、ストックホルムへの社員旅行を決行することにしました。
とはいえ私も商売人です。ただお金を使って帰ってくるのはもったいない。旅の途中で、「現地で何かを買って日本に持ち帰り、ヤフオクなどで売れば、交通費くらいは取り戻せるのでは?」と考えるようになったのです。
そこで、ビンテージの北欧食器をクレジットカードの限度額まで購入し、日本へ持ち帰ることにしました。はじめは「旅費を回収できればいい」といった、低い志での挑戦でしたが、準備も調査も不十分だったうえに、割れ物を国際物流で送った経験もなく、結果として半分以上が破損してしまいました。それでも、約40%は無事に残っていました。「残った商品を使って、次につながることができないか」と考えるようになります。
もともと私は、通販ビジネスに興味を持っていました。というのも、通販は顧客リストが蓄積されていくことで、1年目より2年目、2年目より3年目と、事業基盤が強くなっていく構造があります。やればやるほど仕事がしやすくなる。そんな仕事はあまり多くありません。
柳田さん:それはまさに事実ですが、中小企業や個人事業主で通販をやられている方には、その感覚はあまりないかもしれません。「売れそうだから売る」といった姿勢の方が多く、リストを積み重ねることに意義を感じている人は少ない印象です。
青木さん:ピーチ・ジョンの創業者である野口美佳さんの著書『男前経営』にも、「顧客リストこそが資産の中心であり、それを積み上げることで事業が伸びていく」と書かれていました。素人ながらに「これは面白いビジネスだな」と感じていたんです。
スウェーデンから持ち帰った食器は、国内での需要がとても高いのに供給が少ない、まさに“ボーナスタイム”のような商品でした。手元の商品をただ売っても利益にはなりませんが、「再入荷時にお知らせが欲しい方はこちら」といった形でメルマガ登録を促せば、先に顧客リストを作れるのではと考えたのです。
次回仕入れのアイデアはまだありませんでしたが、とりあえずクラシコムという会社を紹介する場として、そして顧客リストを作る場として、ヤフオクではなくECサイトを立ち上げることに。
柳田さん:壊れた食器も販売されたのですか?
青木さん:いえ、販売したのは割れていない40%の完品だけです。ECの良いところは、売れた後も商品ページが残り続ける点です。私はそこに目をつけ、「再入荷の可能性がある商品です。ご希望の方にはメルマガでお知らせします」といった形で、登録を促しました。
実際に販売してみると、初日で半分以上が売れてしまいました。「ビンテージの北欧食器って、こんなに人気があるんだ」と驚き、本気で取り組んでみようと思ったんです。
まずは、定期的に商品を仕入れられるサプライチェーンの構築に力を注ぎました。そうした取り組みの積み重ねが、今の「北欧、暮らしの道具店」につながっていきます。
“売り方”より“仕入れ方”。持続可能な仕組みを構築
柳田さん:さらっとお話されていますが、食器の破損はかなりのダメージになったのではないでしょうか。
青木さん:本当に、膝から崩れ落ちるような失敗でした。郵便局の方が、すごく渋い顔をしながら荷物を届けてくださって。「これは何かあったな」と思いながら受け取った箱を揺らすと、ジャリジャリという音がして……。開けなくても、中の食器がほとんど割れているのがわかる状態でした。
当時、クレジットカードの限度額まで使って、100万円近くを仕入れに使っていたんです。にもかかわらず、銀行口座には25万円程度しか残っておらず、「これはどうしたものか」と途方に暮れたことを、今でも鮮明に覚えています。
柳田さん:そこからよく、メルマガリストを集めるという方向に切り替えられましたね。
青木さん:需給のバランスに違和感がある商材だと気づいたことが大きかったです。つまり、日本で一番売る人になろうとするのではなく、日本で一番“持ってこれる”人になればよい。勝負すべきは販売力ではなく、供給力だと気づいたのです。
売るほうは比較的簡単で、難しいのは仕入れること。だからこそ、これは自分に向いているのではと思いました。私は、派手な販促や売り込みが得意なタイプではありませんが、地道に積み上げるような仕事は得意です。
さらに、顧客リストの重要性についてはすでに理解していたので、供給力とリスト構築、この2つの考えが自分を導いてくれたように感じます。
柳田さん:青木さんをご存じの方の中には、「売り込みが下手」という印象をお持ちでない方も多いと思いますが、確かにご自身から積極的に前に出るタイプではない印象ですね。
青木さん:そうなんです。自分からガツガツいくのは得意ではなく、「欲しいと思ってくれた方に、ちゃんと届ける」というスタンスでやっています。
柳田さん:どちらかというと、深掘りして仕組みを作るのが得意な印象です。仕入れの仕組み構築も、まさにその延長ですよね。
青木さん:まさにそうです。最終的には、現地の素人の方にお金を預けて、ほぼ自動的にビンテージの北欧食器が送られてくるという仕組みをつくりました。
具体的には、採用や評価、インセンティブの設計を行い、北欧各国にバイヤーを配置。届いた商品を出すだけで良い状態をつくりました。この仕組みは、数か月で整えました。
柳田さん:数か月で構築されたんですか?
青木さん:はい。2回目にスウェーデンへ行った際には、現地でバイヤーを募集し、その場で採用まで行いました。そして、次回からは自分が現地に行かなくても仕入れが回るようにすることを目指しました。
最終的には、北欧3か国で10名弱のバイヤーを採用しました。中には直接会ったことがない方もいました。
柳田さん:会ったことのないバイヤーまでいたんですね。
青木さん:基本的には、バイヤーの方に送っていただいた商品が売れた場合に、その粗利の一部をお返しするという仕組みを設けました。売れなければ報酬が発生しないので、みなさん真剣に人気商品を探してくださいます。
また、商品の破損リスクに対しても対策を講じています。もし商品が割れた場合は、残った商品に原価を再配分するルールにしました。そうすることで、丁寧に梱包・発送してくださるインセンティブが働きます。
さらに、10名のバイヤーにはランク制度を設け、実績の高い人から優先的に仕入れ予算を配分する形にしています。たとえ機能しないバイヤーが混ざっても、予算が多く割り振られることはありませんし、売れなければ報酬も発生しないため、非常にリスクの少ない構造になっています。この仕組みをベースに、紹介や問い合わせを通じてバイヤーの輪を広げていきました。
柳田さん:このような仕組みは、何かモデルとなるような事例があったのでしょうか?
青木さん:はい。徳島県の上勝町に「株式会社いろどり」という会社があります。お刺身の飾りに使われる“つまもの”と呼ばれる葉っぱを、町のお年寄りたちが山で採取し、ネットを通じて料理店に卸すというビジネスを手がけている会社です。
テレビでもよく取り上げられていて、葉っぱを販売した報酬で、息子や孫に家を買ってあげたというおばあちゃんのエピソードが話題になっていました。
この事例を見て、「知識や経験がない人でも、自律的に働ける仕組みを作ることができる」と感じました。そこで、北欧の蚤の市などでビンテージ食器を探し、それを私たちに送ってもらう仕組みを、同じように構築できたら面白いのではと思ったのです。
ブランディングの前に、仕組みを磨いた7年間
柳田さん:そこからエッセンスを受けて、数か月で仕組みを構築されたのですね。
青木さん:そうですね。私はテレビや本などからインスピレーションを受け、それを自分流にアレンジするのが得意なんです。誰もが知っている話題の情報に影響されやすいタイプで、ベストセラー本やテレビ番組を見て「すごい、これやりたい」と思うんですよね。
柳田さん:多くの人は「すごい」で終わってしまいますが、青木さんは実際にやってしまうのが素晴らしいです。
青木さん:やってみないとどうなるかわからないじゃないですか。良さそうに見えても、実際にやってみると全然違う結果になることもありますし、そこからの学びがとても大きいと思っています。だから、やってみるのが一番なんですよ。
そして今日のテーマでもある“ブランディング”についてですが、実は多くの方がブランディングの話から入りたがる一方で、私たちはその“前段”にあたる部分、効率化や堅牢な仕組みづくり、生産性の向上といった部分に、最初の7年ほどの時間を費やしてきたんです。
柳田さん:これは非常にいい話ですね。多くの人は、まず売ることを考えてから仕組みをつくろうとします。でも私も、逆の順番が正しいと思っていて。裏側のオペレーションがしっかりしていれば、どれだけ売れても対応できますし、少人数でも効率よく運用できるんですよね。
青木さん:私たちが幸運だったのは、販売にあまり困らない商品を扱っていたことです。むしろ、継続的に需要に応じて安定的に仕入れることのほうが課題でした。
つまり、売ることよりもまず“入荷を安定させる”ことに取り組む必要があり、自然とサプライチェーンやオペレーションの構築に力を入れざるを得なかった。その結果として、土台から固める文化が会社のカルチャーとして根づいていったのだと思います。
これは「まずオペレーションを整えよう」といった意思決定ではなく、「やらないと売るものがない」という状況だったので、必然的にそうなったんです。そうした中で社員も増えていき、組織としても“まずは足元から整える”という考え方が自然と根付いていきました。
希少で人気のある商品を、一つひとつ丁寧に仕入れて販売する。一見するとスケールしづらいビジネスに思えるかもしれませんが、そうした環境でスタートしたからこそ、まずは土台を徹底的に整えるという“癖”のようなものが、会社のDNAとしてしっかりと刻まれていったのだと思います。
おわりに:売る前に、土台を築く。ブランドを育てた“仕組みと思考”
残った食器で顧客リストを作るという行動から始まった「北欧、暮らしの道具店」の歩みには、失敗を次につなげる行動力と実行力が根底にあると感じます。売ることよりも先に、仕入れやオペレーションの仕組みを整えたことで、効率的で再現性のあるビジネスモデルが構築され、それが企業カルチャーとして自然に根づいていきました。
ブランディングの前段にあたる“土台づくり”に時間を惜しまず取り組んできた姿勢は、短期的な成果を追いがちな事業者にとって、持続可能なブランドを育てるヒントになるのではないでしょうか。
EC市場の真の発展に貢献をという想いで、「ECの未来」を運営しているサヴァリ株式会社は楽天市場・Amazonなどネットショップ運営代行をはじめ、モール通販を中心にECサポート・ECコンサルティングを行っています。EC運営に不安を抱えている事業者様は問い合わせてみてはいかがでしょうか。
■サヴァリ株式会社へのお問い合わせはこちら
https://savari.jp/contact/
あわせて読みたい