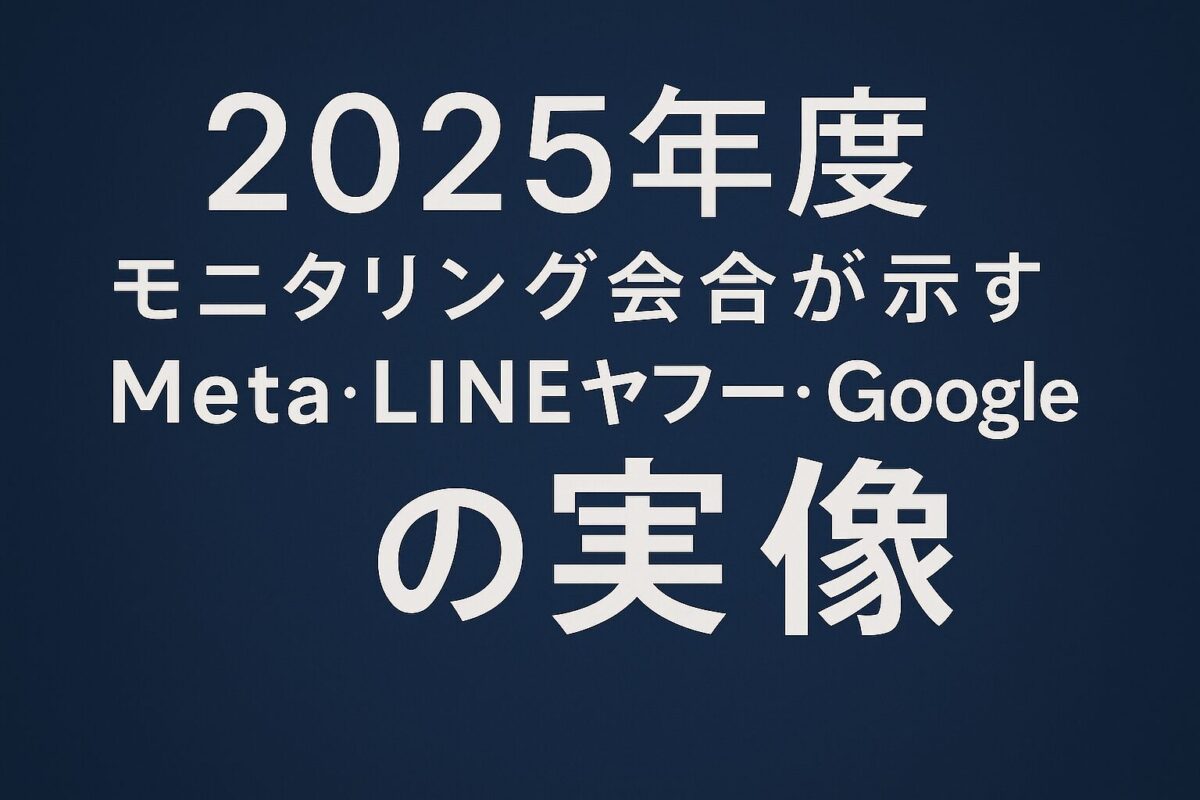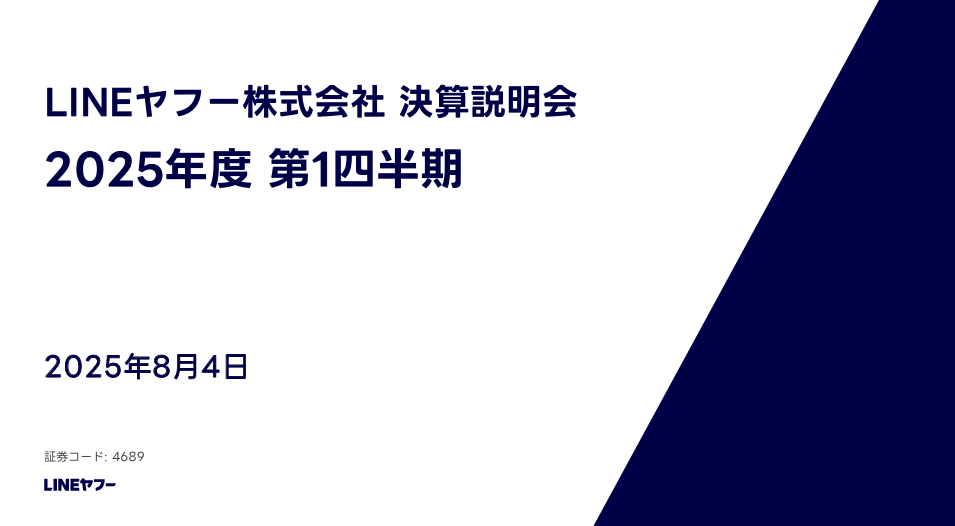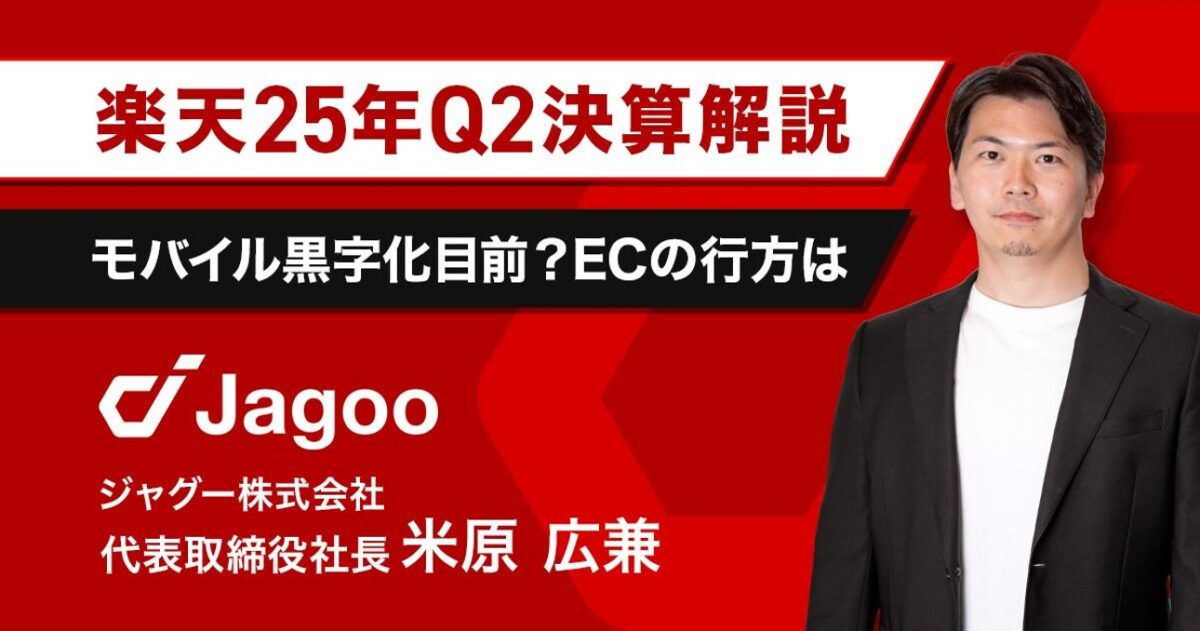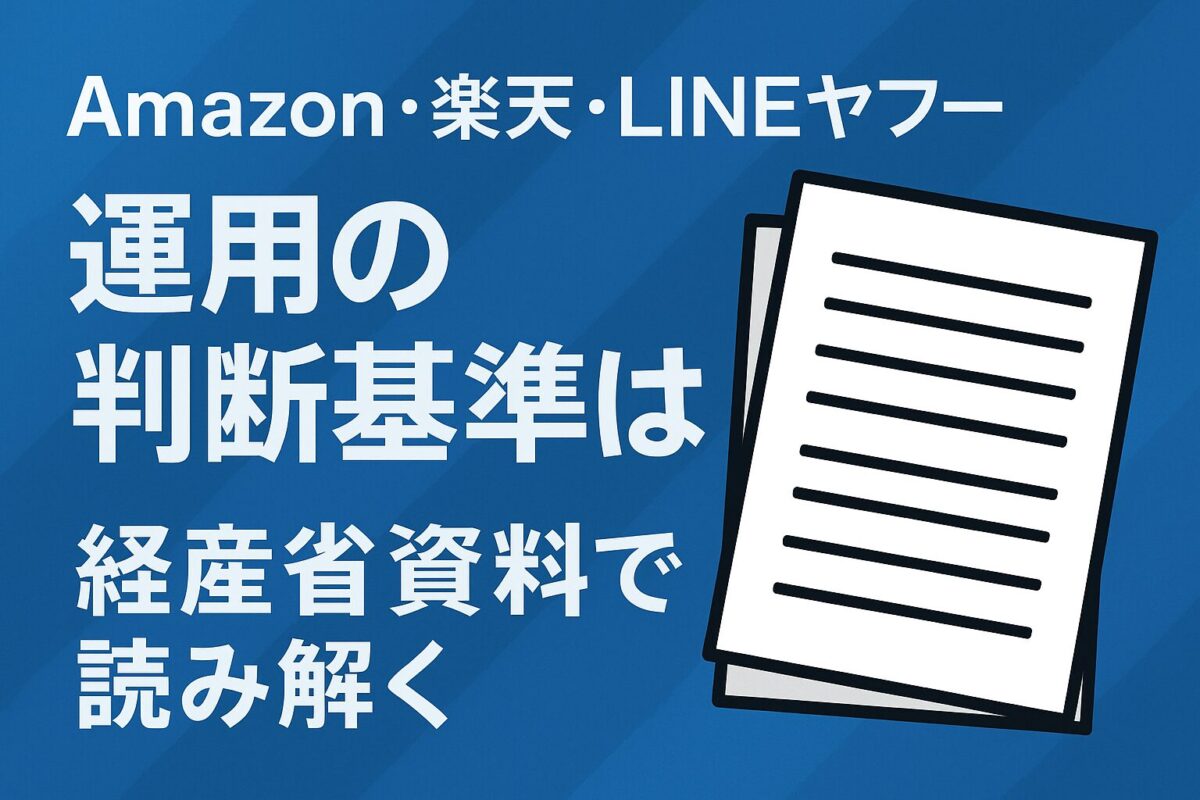
ECモールを運営する事業者にとって、日々の売上は単なる数字ではありません。検索順位のわずかな変動が流入を左右し、レビュー1つの扱いで転換率が変わり、アカウントやSKUの停止は事業そのものに影響します。
しかし、こうした“事業の命綱”にあたる領域の多くは、モール側の判断基準が十分に見えていないことが少なくありません。
なぜ検索順位がここまで落ちたのか。
なぜ補てん額がこの数値になったのか。
なぜ売上金が留保されたのか。
なぜこの通知が突然届いたのか。
EC事業者にとっては日常的な疑問ですが、モール側の説明は断片的で、背景にある判断の流れまでは十分に共有されているとは言えません。
こうした“理由の見えにくさ”を解消するために、経産省はモニタリング会合を通じて、Amazon、楽天、LINEヤフーの三社から運用の実態をヒアリングし、その内容を資料としてまとめています。
今回の記事は、この資料に記載された情報をもとに、三社の判断基準や運用体制を整理し、EC事業者が“理解できる理由”に近づくための視点を提供するものです。判断の透明性は一朝一夕で実現できるものではありませんが、資料を読むと、三社とも内部の体制整備や説明改善に向けて動き始めていることがわかります。まずは、その全体像を丁寧に解きほぐしていきます。
参照:2025 年度 デジタルプラットフォームの透明性・公正性に関するモニタリング会合 意見とりまとめ (オンラインモール分野)
この記事の目次
Amazon:判断の裏側にある「運用設計」と経産省資料が示した実態
Amazon に関する提出資料は、三社の中で最も分量が多く、扱われているテーマも幅広いです。EC事業者が日々向き合う悩み(検索順位、手数料、補てん、レビュー、不正対策など)の多くが Amazon の資料の中で具体的に説明されています。
資料を丁寧に読み込むと、Amazon の運用は「判断の理由をどこで作り、どの段階で確定させるのか」という点が比較的読み取りやすく、他社との差が浮き上がります。ここでは、資料に記載された事実だけをもとに、その構造を整理します。
情報提供・苦情の扱い:一次情報がどの経路を通るのか
資料によると、利用者や事業者から寄せられた情報は、まず内部で仕分けされ、必要に応じて担当部門に回付される仕組みになっています。初期の仕分け工程では、機械学習による分析が行われ、その後に人手による確認が加わります。
特に印象的なのは、Amazon がこの仕組みを「定期的な分析が行われる」という形で説明していることです。単に問い合わせに回答するだけではなく、集まった情報が一つのデータとして扱われ、運用改善に反映される位置づけになっています。
この構造は、「声が本当に届いているのか」という事業者側の不安に対する回答になり得るもので、資料を読む限り、Amazon は一次情報の扱いをかなり体系立てて運用していることがわかります。
補てんの仕組み:原価データはどこまで使われ、どこまで共有されないのか
補てんに関する資料の記述は、事業者が誤解しやすいポイントを丁寧に分解した内容になっていました。
補てん額を算定する際には、事業者が原価データを提出するケースと提出しないケースがあります。提出した場合、Amazon はそのデータを補てん額の計算にのみ使用し、直販事業部門や他の部門には共有されないという説明が明記されています。この点は、資料の中でも特に強調されていました。
事業者側が「データを渡すと直販で活用されるのでは」という懸念を持ちやすいため、Amazon が“どこに共有されないか”を明確に示した意味は大きいです。資料ベースでここまで踏み込んで書かれている例は三社の中でも珍しく、補てんというセンシティブな領域における“線引き”の一つといえます。
手数料カテゴリーの適用:基準は存在するが、事業者には伝わりにくい理由
手数料カテゴリーの決定は事業者にとって重要なテーマです。資料では、カテゴリー適用に関する問い合わせが多かった背景や、説明の改善を進めていることが述べられています。ただし、資料中にはカテゴリーの詳細な判断基準そのものが開示されているわけではありません。Amazon内部では一定の判断基準が存在しているものの、その基準が事業者にどこまで伝わっているかは別問題です。
今回の資料は「説明内容を改善していく」という方針が中心で、事業者が期待する「具体的な判断条件」までは踏み込んでいません。このため、カテゴリー適用に対する誤解が生まれやすい構造は、依然として残っていると読み取れます。
レビューの扱い:偽造レビューの特定方法と削除判断の流れ
レビューの取り扱いについても、Amazon の資料は比較的具体的です。とくに偽造レビューと正当なレビューを切り分ける際のプロセスが説明されています。資料によれば、レビューが投稿された商品が「どの出品者から購入されたものか」を Amazon が把握した上で、偽造品の可能性がある場合は人の判断が介在します。これは、完全に機械的に処理しているわけではなく、機械検知→人手確認→対応判断の三段階で運用されていることを示しています。
レビューは検索順位や販売力に直結するため、誤った削除や見逃しを避ける仕組みとして、この多段階チェックが機能していると資料から読み取れます。
検索結果の決定:Amazonは “自社優遇はしていない”と説明
検索順位について、Amazonは資料の中で「自社商品の優遇は行っていない」と説明していました。EC事業者にとっては最も気になるポイントですが、この説明は“そう説明している”という事実を示すものにとどまり、優遇があり得ないことを証明する内容になっているわけではありません。資料で具体的に書かれているのは、検索ロジックを変更するときの進み方です。
ロジックをいじるには、
- 技術部門
- 担当部署
- 法務部門
の合意が必要で、現場が勝手に調整できる仕組みではないと説明されています。属人的な変更が起きないように、複数の部署が関わる体制になっているという意味です。
ただ、この仕組みは「個人が勝手に変更することはできない」という説明にはなっても、「会社として自社商品を優先しよう」と決めた場合にそれを止める根拠になるわけではありません。資料の範囲で読み取れるのは、あくまで“優遇していないという Amazon の主張”と、“変更には複数部署の承認が必要”という体制の説明です。
EC事業者として知っておくべき点は、「優遇しない」という説明と、「優遇できない仕組みになっている」という証明は別物だということです。今回の資料は前者に該当し、後者まで踏み込んだ内容にはなっていません。
不正対策:国内だけで完結しない“国際的な脅威モデル”
資料では、不正対策において Amazon が“日本市場に限定しないモデル”で運用していることが示されています。海外で発生した新たな不正手口も日本の対策に反映され、国内だけを見て判断しているわけではありません。
これは、Amazon の対応速度や精度が高い背景にある仕組みであり、他の二社とは異なる大きな特徴です。日本市場だけで判断基準を作るのではなく、世界的な不正傾向を踏まえた上でルールが設計されている点は、資料から明確に読み取れます。
楽天:検索順位・不利益措置・売上金留保の“判断の流れ”が見える資料
楽天の提出資料は、三社の中では中程度の分量ですが、扱われているテーマは事業者にとって重いものばかりです。検索順位がどう決まるのか、不利益措置の判断はどこで行われるのか、売上金留保はなぜ起きるのか。いずれも店舗運営に直結する内容であり、資料の記述にも核心的な情報が含まれています。
今回の経産省資料を読むと、楽天がどのような基準やフローで判断を行っているのかが、これまでよりも明確に整理されていました。とはいえ、内部基準そのものが細かく開示されているわけではなく、「説明の改善」と「方向性の提示」が中心になっている印象です。
検索順位の決定:非公開のロジックと、公開できる“方向性”の切り分け
楽天の検索順位は、店舗側にとって最も納得しづらい領域の一つです。資料の説明によれば、検索順位は複数の要素から総合的に決定されますが、具体的なロジックの開示は行われていません。
資料では、検索順位に影響する可能性がある要素として、売上、レビュー、転換率など複数の指標を挙げています。これらは日々の店舗運営で自然と意識される項目であり、「なぜこの店舗が上位にいるのか」を理解するための基礎にはなります。ただし、どの指標がどの程度重視されるのか、どのタイミングで影響が反映されるのかといった詳細は非公開です。資料の説明は、あくまで“方向性”の提供にとどまっています。これは三社共通の課題ですが、楽天も例外ではありません。
不利益措置の判断:事業者がどこに気をつければいいのかが見える内容
楽天の提出資料の中で、事業者にとって最も実務に直結するのが不利益措置に関する説明でした。アカウント停止やSKU単位の停止、契約に関わる判断など、事業に大きく影響する領域が整理されており、普段の運営で「ここがわからない」と感じる部分に対するヒントが含まれています。
資料では、違反の疑いがある場合にどのように確認が進むのか、どこで人手の判断が入るのかが説明されていました。自動的に処理されるケースと、人が内容を見て判断するケースの違いが示されているため、事業者としては「すべてが機械的に決まっているわけではない」ことを理解できます。
一方で、どの程度の違反で停止に至るのかといった細かな線引きまでは資料では示されていません。つまり、具体的な基準は明らかになっておらず、事業者が状況を見極めながら理解する必要がある領域が残っています。この“線引きが見えない”ことが、これまで不利益措置に対して不安が生まれやすかった要因とも言えます。
資料にはもう一つ重要なポイントがありました。それは、通知内容の改善を進めているという説明です。理由がわからないまま措置だけ届いてしまうことが多かったという声を踏まえ、どこまで説明するかの方針や文面の改善が始まっていると記載されています。EC事業者にとっては、判断理由が少しでも見えるようになることが、運営の安定につながるため、ここは実務的に大きな前進と捉えられます。
売上金留保と通知:仕組みの説明と、改善の方向性
売上金の留保は、楽天で店舗を運営するうえで最も影響が大きい領域の一つです。日々の仕入れや支払いに直結するため、突然留保が発生するとキャッシュフローにすぐ影響します。提出資料では、この留保がどのような場面で起こり得るのか、そしてどのように解除されるのかという“基本的な流れ”が整理されていました。
資料では、留保が発生する背景として、取引の安全性に関わる状況や、注文・配送・決済に関する一定のリスクが確認されたケースなどが例示されています。具体的な項目名までは開示されていませんが、「問題が疑われる場面で一時的に売上金が押さえられる」という前提だけは読み取れます。また、留保が発生した後の扱いも、状況の確認→必要な対応→留保解除という流れで進むと説明されており、店舗側がどの段階で何を求められるのかが基本的に整理されていました。
ただし、事業者が最も知りたい「この条件なら留保が起きる」といった線引きは資料の範囲では示されていません。例えば、注文キャンセルが一定水準を超えたら留保に当たるのか、何件のトラブルが発生するとリスクと判断されるのか、そうした細かな基準までは開示されていないため、事業者側としては“どこからリスクと見なされるのか”を事前に把握しにくい構造が残っています。
資料ではもうひとつ重要な点として、通知文面の改善が挙げられていました。これまで「理由がよくわからないまま売上金だけ留保される」という声が多かった背景を受け、留保が発生した理由や確認が必要な内容を、よりわかりやすく記載する方向性が示されています。通知のタイミングや表示方法についても改善を進めていると記載されており、事業者が状況を把握しやすくする取り組みが始まっていることが読み取れます。
とはいえ、完全な透明化には至っていません。通知の届き方や表示タイミングが案件ごとにばらつき、説明が不十分に感じられるケースも残っているため、事業者側が“なぜ今回留保が起きたのか”をその場で判断しきれない場面は今後も想定されます。資料の範囲で言えるのは、「仕組みと流れはこれまでより説明されるようになったが、基準そのものは依然として見えにくい」という点です。
LINEヤフー:理由説明・検索・不利益措置の“線引き”をどう見せていくか
LINEヤフーの資料は、検索順位の決定、不利益措置の通知、理由説明といった領域が中心です。三社の中では、理由説明に関する記述が最も多いのが特徴で、事業者から寄せられる「理由がわからない」という声を意識した内容になっています。
検索順位の算定:現場調整不可の体制と、多段階チェック
資料によれば、検索順位の算定は複数の要素から構成され、現場レベルで操作できるものではありません。システム変更は法務部を含む複数部署で合議され、恣意的な調整が行われない体制が敷かれています。
LINEヤフーの検索運用は、Amazon と同様に“現場判断の排除”が基盤となっており、変更のプロセス自体に一定の統制が働いています。とはいえ、事業者側が知りたい「なぜ今回は順位が落ちたのか」という粒度までは資料の範囲では明らかにされていません。
不利益措置と通知:理由説明をめぐる“開示・非開示”の線引き
LINEヤフーは、不利益措置に関する開示の考え方を、三社の中でも比較的丁寧に整理していました。通知文面の内容や、どの範囲まで理由を説明すべきかといった方針が資料の中で示されており、これまで「理由がわからないまま措置だけが届く」という声が多かった背景を踏まえた対応が進んでいます。
資料では、説明不足への改善方針が示される一方で、理由を詳しく伝えすぎると悪質者への情報提供につながりかねないという課題も整理されていました。開示と非開示のバランスをどう取るかが難しく、実際にどの措置で理由を開示するのかといった具体的な基準までは資料には示されていません。
事業者にとっては、説明の丁寧化は大きな前進になりますが、開示の線引きが完全に明らかになったわけではなく、改善の途中にある領域だと理解しておく必要があります。
苦情・意見の扱い:データは届いているが“見えにくい”構造
事業者や利用者から寄せられた声については、社内でどのように処理されるのかが資料の中で説明されていました。具体的には、受け付けた内容はまず Salesforce 上で記録され、CS 部門が一次確認を行います。その後、必要に応じて安全対策部門・法務部門・政策企画部門へ Slack を通じて共有され、個別の事案ごとに検討が進むという流れが整理されています。
ただ、Amazon のように“分析結果をどう改善に生かしているか”まで踏み込んだ説明は示されていません。フローそのものは明らかになっている一方で、事業者から見ると「送った意見がどの程度改善に反映されているのか」が見えにくく、声が届いている実感を持ちづらい点が残ります。
三社の“判断基準”をどこまで理解できるのか?資料から見える着地点
経産省資料をもとに三社の運用を丁寧に読み解いていくと、「判断基準は確かに存在している」という点は共通しています。検索順位、不利益措置、補てん、手数料、通知……。どの領域も、内部には一定のフローが存在し、複数部門の合意や人手による確認が入る構造が整っています。
一方で、事業者が知りたい「なぜ今回はこのようになったのか」「どの項目が影響したのか」といった“個別の理由”までは、資料の中でも十分に示されていません。三社とも、悪質者への過剰な情報提供を避ける意図があるため、一律の透明化が難しい領域であることも読み取れます。
今回の資料を踏まえると、EC事業者が意識すべき視点は大きく三つです。
① モールごとに“判断の軸”が異なることを理解する
Amazon は内部統制とデータ分析が軸にあり、楽天は措置と通知の整理に重きを置き、LINEヤフーは説明の範囲と線引きを重点的に扱っています。同じ「検索」「措置」であっても、考え方が全く同じではありません。
② 事業者の声がどこに届いているかを把握する
Amazon のように“分析”と明記している企業もあれば、フローは存在しても可視化されにくい企業もあります。声が届いているかどうかを推測するのではなく、資料から読み取れる範囲で“どの窓口がどの工程につながっているか”を理解することが重要です。
③ 透明化は進んでいるが、完全ではないことを前提にする
三社とも説明改善を進めているものの、判断基準そのものがすべて公開されるわけではありません。だからこそ、変化が発生した際には早期に確認し、必要であれば複数経路で問い合わせを行うなど、事業側のアクションも引き続き求められます。
資料に書かれている情報だけを丁寧に読み込むと、三社の判断が「不透明だからわからない」のではなく、「存在しているが構造が複雑で伝わりにくい」という現実が見えてきます。今回の整理が、EC事業者にとって“判断の理解”に近づくための一助になれば幸いです。
あわせて読みたい