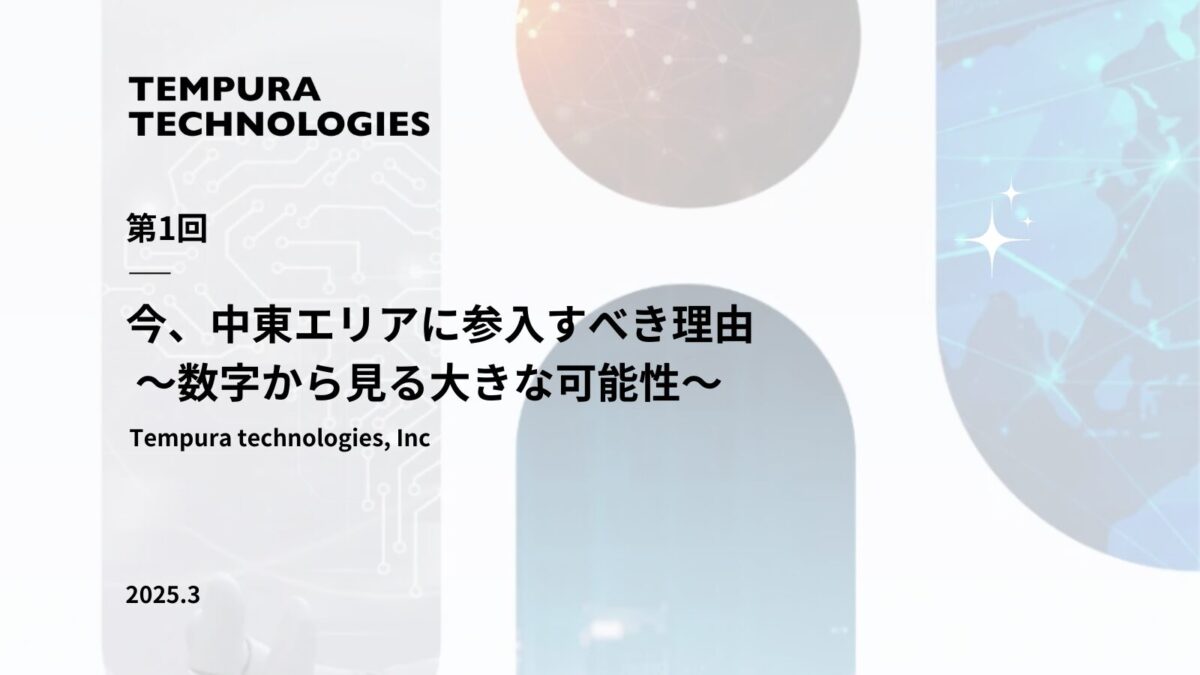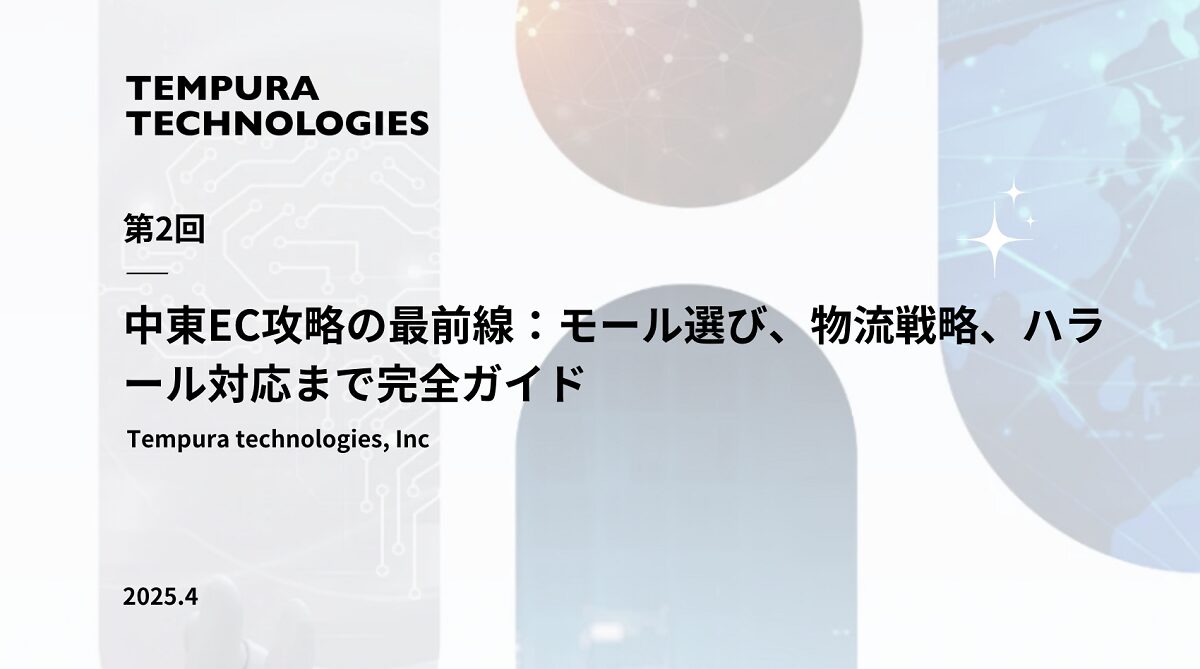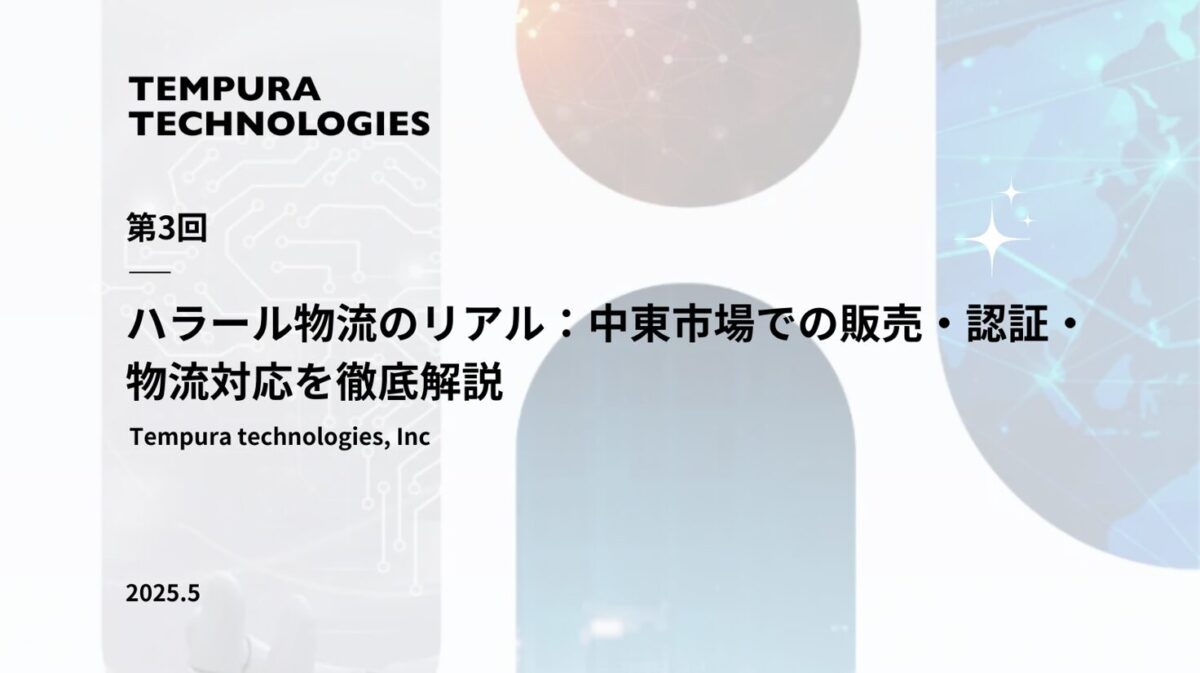
コマースピック読者の皆様、こんにちは。Tempura technologies株式会社の上田です。
一部読者の皆様よりハラール認証製品の物流に関して質問を頂戴しましたので本稿では、中東を中心にハラール認証製品の販売・流通構造や物流の特徴、カテゴリ別の対応の違い、そして現場でよく聞かれる誤解の解消について実例を交えて解説します。
ご存じの通り中東市場では、イスラム教の教義に沿った「ハラール」認証製品が重要な地位を占めています。マレーシアやインドネシアなど東南アジアの事例も比較対象としながら、ハラール物流への実務理解を深めることを目的とします。
上田 剛大
Tempura technologies株式会社
共同創業者 / 取締役
2020年にSansan株式会社へ中途入社し、個人向け名刺管理アプリeightの新規ソリューションのBizDevとして従事。その後、2022年にTempura technologiesを共同創業し、web3やAIを活用したソリューションを提供。自社プロダクトとしてロイヤリティプラットフォームやマーケットプレイスを構築し、エンタメ、化粧品、日用品、電化製品メーカーの海外支援(GMV最大化)を支援。現在はドバイ子会社設立と韓国企業への出資も踏まえTempura technologies Groupとして主に中東エリアへの海外支援を注力している。
会社ホームページ:https://tempuradao.xyz/
中東のハラール市場規模と流通構造
中東は世界でも有数のハラール製品市場であり、食品・飲料分野だけでも消費規模は数千億ドルに上ります。とりわけ湾岸アラブ諸国(GCC)は人口こそインドネシアなどに比べ少ないものの、一人当たりの所得水準やGDPが高くハラール食品の需要が旺盛です。また自給率が低いため、食料の大部分を輸入に頼っていると言われ、ハラール認証を受けた海外製品が市場を支えています。サウジアラビアでは国内食品消費の約85%を輸入に依存しており、現地の輸入業者や卸売業者が海外メーカーからハラール認証済みの商品を仕入れて国内の流通網へ供給しています。
伝統的に、中東の食品流通は輸入代理店や卸売業者がハブとなり、そこから各地の小売店や市場(スーク)へ商品が行き渡る仕組みでした。しかし近年は大型スーパーマーケットやハイパーマーケット(例:UAEのルル、サウジのパンダなど)の台頭により、流通構造に変化が生じています。これらの大規模チェーンは中間業者を介さず海外から直接調達するルートを持つ場合もあり、従来型の卸売中心モデルに加えて新たなチャネルが拡大しています。
中東の消費者にとって、「ハラール」であることは日常的に当然視されています。豚肉やアルコール飲料の一般向け販売自体が禁じられている国も多く、市場に出回る食品・飲料はすべてハラール対応が前提です。ただし、輸入品や加工食品については信頼性の高い認証が重視され、消費者も商品パッケージのハラールマークや政府機関の認可表示を確認する傾向があります。東南アジアでは消費者が自ら認証マークを探す志向が強い点で、中東との対照が見られます。
ハラール物流の要件と認証制度
ハラール製品を扱う物流(サプライチェーン)には、宗教上および法規上の特有の基準が求められます。宗教的な観点で最も重要なのは、禁じられた物質(ハラーム)との接触を避けることです。豚由来成分や酒類などハラーム品とハラール品が接触・混載しないよう、倉庫では保管エリアを区分けし、輸送時も専用コンテナや仕切り、梱包で物理的接触を防ぎます。また、以前に非ハラール品を扱った倉庫・車両をハラール品向けに使う際には、宗教に則った清浄化(洗浄)を行い、汚染リスクを除去する必要があります。
法的な要件は国によって異なりますが、中東諸国ではこれまで、製品そのもののハラール認証が重視され、物流業者の認証までは求められないケースが多く見られました。しかし近年、物流段階にも認証を広げようとする動きが活発化しています。インドネシアでは2024年から物流事業者へのハラール認証義務化が始まり、マレーシアではMS2400という国家規格に準じたハラール物流認証制度が運用されています。UAEでは政府がハラール国家マーク制度を整備し、ドバイには専用のハラール産業特化ゾーンやジュベル・アリ港の施設が設置されています。サウジアラビアでもSFDA(食品医薬品庁)が主導するサウジ・ハラールセンターが輸入製品の認証・検査体制を強化しています。
誤解されやすいポイントと現場での実態
ハラール物流に対しては、以下のような誤解がしばしば聞かれます:
- 「一般の物流と完全分離しなければならない」:実際には、既存の倉庫や車両内でゾーニングやラベル・仕切りなどの管理を徹底することで、同一インフラ内での運用が可能です。
- 「保管・輸送は非常に手間がかかる」:確かに認証維持や分離管理にはコストがかかりますが、アレルゲン管理など他の品質管理体制と重ねることで効率化が可能です。また、ハラール対応を専門とする物流会社の活用も有効な選択肢です。
食品分野
中東、とりわけUAEやサウジアラビアでは、食品とくに動物由来の製品にハラール認証が法律上必須です。牛や鶏などの肉製品は、イスラム法に則った屠畜証明やハラール証明書の提出が求められます。さらに、ゼラチンやコラーゲンなどの加工食品も対象に含まれ、「Halal」表記をする場合には出荷証明が必要です。
一方、野菜や穀物などの非動物性製品には法的な義務はありませんが、商習慣上では認証取得が事実上の標準となっています。中東の流通・小売では、ハラール認証がある製品を優先する傾向が強いため、取得の有無が実質的に市場参入の条件になっているケースもあります。
物流面では、ハラール品と非ハラール品の物理的分離が基本。輸送コンテナや倉庫でのゾーニングが必須となり、非ハラール品の取り扱い履歴がある設備は清浄化が必要です。仮に豚由来製品に接触すれば、当該食品は「不浄(ナジュス)」として廃棄対象になるため、輸送業者・サプライヤーの管理精度が問われます。
医薬品分野
医薬品は、食品とは異なり中東諸国において法的にハラール認証が義務付けられていません。これは医薬品が命や健康に直結し、イスラム法でも「代替がない場合は禁忌成分の使用も容認される」という考え方があるためです。
ただし最近では、植物由来カプセルやアルコールフリー製品などの開発が進み、自主的にハラール認証を取得する製薬・サプリメント企業も増加中です。これにより、「安心して使える」というブランディングや販路拡大の効果を見込むケースも出てきています。
物流においては、医薬品は密閉状態で流通するため、食品ほどの厳格な分離管理は行われません。ただし、認証品を扱う場合は、混載リスクを防ぐためのルール整備や清浄管理が推奨される場面もあります。
化粧品分野
化粧品においても、ハラール認証は法的義務ではなく任意です。とはいえ、UAEではESMAが「UAE.S 2055-4」などの基準を設けており、希望企業に対して認証スキームを提供しています。また、サウジアラビアではSFDAが化粧品成分の輸入審査を行い、豚由来成分は基本的に禁じられています。
香水などに使われるエタノールについても、宗教的な判断基準によって許容される範囲が異なるため、成分の表示や処方設計には注意が必要です。
物流面では、基本的に食品のような厳格な管理は不要ですが、製造段階でのライン分離や原料管理は重要です。たとえば、石鹸やリップクリームなど身体に直接触れる製品に対しては、消費者の信頼を得るためのハラールマーク表示や成分情報の開示が求められる場面もあります。
電化製品(美容家電)
電化製品、特に美容家電に関しては、ハラール認証は不要です。これは、製品が口に入るわけではなく、宗教上の禁忌と関わることが少ないためです。UAEのMoIAT(旧ESMA)やサウジのSASOなども、家電については安全・品質基準の適合性を重視しており、ハラール性を問うことはありません。
ただし一部では、マーケティング上の理由からハラール相当のロゴや表示が使われるケースもあります。たとえば、美顔器に付属するジェルがハラール認証済みである場合などです。このような事例では、製品本体ではなく付属消耗品が認証対象になるため、メーカー側も誤解を与えない表現が求められます。
物流や在庫管理においても、基本的には特別な配慮は不要ですが、ハラール認証済みの付属品が含まれる場合には、食品や化粧品と同様の対応が望まれることもあります。
| カテゴリ | ハラール認証の必要性 | 物流・在庫管理上の対応 | 備考・実務的ポイント |
|---|---|---|---|
| 食品 | 法的義務あり(特に動物性食品) | 非ハラール品と物理的に分離。 清浄化が必須 | 商習慣上も認証が事実上の参入条件。ハラールマークの有無が重要視される |
| 医薬品 | 義務なし(任意) | 密閉状態で流通前提。分離は法的義務ではないが推奨される | ハラールサプリなどの開発が進行。マーケティング目的で自主的に取得する企業もあり |
| 化粧品 | 義務なし(任意) | 製造段階での成分管理やライン分離が重要。物流面での分離は任意 | UAE・サウジで基準整備済み。動物由来成分表示やアルコール使用に注意 |
| 電化製品(美容家電など) | 不要 | 原則不要。ただし付属品(ジェルなど)にハラール品が含まれる場合は留意 | 本体は対象外。ロゴ表示は誤解を招かないようマーケティング的に配慮が必要 |
おわりに
ハラール物流は、単なる宗教対応ではなく、サプライチェーンの透明性・品質・信頼性を高める仕組みとして進化しつつあります。販売商品ごとに異なりますが中東への販売=ハラール認証が必須というわけではありません。特に中東では、ハラール製品が日常的な消費財であり、その信頼構築のためには物流も重要な役割を果たしますがカテゴリ別の違いを正確に把握し、必要に応じたハラール認証と物流体制の構築を行うことで、企業は中東をはじめとする世界最大規模のムスリム市場への確かな足がかりを築けること間違いありません。また、直近の中東市場に関して話を聞いてみたいなどあればこちらのリンクより日程調整していただければ嬉しいです!
▼中東市場に関して話を聞いてみる▼
https://cal.com/gota-ueda-upijc0/60分-mtg
あわせて読みたい