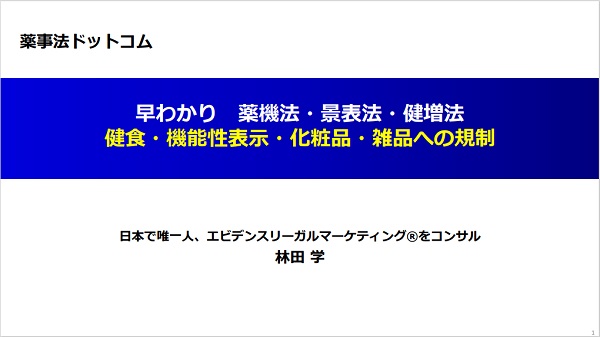前回は化粧品の「機能的ベネフィット」と「その差別化方法」について解説しました。今回は、その双璧となる「情緒的ベネフィット」について解説します。
前回記事:化粧品ビジネスを始めたい!機能的ベネフィットとその差別化方法とは!?
松崎 淳
株式会社天真堂 取締役
2014年に医薬部外品、化粧品、健康食品のOEMを展開する株式会社天真堂に営業としてジョイン。取締役となった現在も、EC通販をメインとする化粧品会社や、スタートアップおよび異業種から参入する企業に対し、商品企画、事業立ち上げ支援など、OEMの枠を超えたサポートを行っている。
情緒的ベネフィットとは
機能的ベネフィットが、その名の通り商品やサービスの機能を通じて得られる便益なのに対し、情緒的ベネフィットは「感情」「気持ち」を通じて得られる便益(ベネフィット)となります。
テーマパークへ行く際、「絶叫系コースターに乗りたい」「時速100キロを体感したい」という目的で訪れる方はほぼいらっしゃらないでしょう。恐らく、「作品の世界観を楽しみたい」「非日常に没入してわくわくしたい」「卒業記念に友達との思い出を作りたい」など、感情を主に置いた目的で訪れるのではなないでしょうか。
化粧品も同様に、「保湿したい」「キメを整えたい」「毛穴をケアしたい」といった機能的な面だけでなく、感情によるベネフィットの提供が重要であり、購入と継続の意思決定に大きく関与していると考えられます。
化粧品における情緒的ベネフィットの設計方法
企画段階で、具体的にどのように設計すれば良いかについて触れさせていただきます。
①タイミングで考える
大きく分けると、「購入前」と「購入後」の2つのタイミングが考えられます。
「購入前」について言い換えると「広告を見て何を感じてもらうか」ということになります。つまり、「第一印象で何を感じてほしいか」です。
ビジュアルとして捉える部分になりますので、パッケージデザインがウェイトを占めます。一方で、中身で表現する方法もあります。色を付ける、手に取ると伸びる、カプセルを分散させている、キラキラと輝いているなど、目から入る印象で感情に訴えかける処方を開発することも可能です。
「購入後」は、さらにいくつかのタイミングに細分化できます。具体的には、「届いたとき」「初めて使ったとき」「継続して使っているとき」で生み出される感情を言語化します。
「届いたとき」は通販に限定される感情ですが、箱を開けて初めて商品を手にしたとき、どのように感じてほしいかという観点です。また、配送資材や同梱物もそこに関与するため、可能であれば商品開発のタイミングで並行して検討できると良いでしょう。
続いて「初めて使ったとき」です。商品を購入するという行動の裏には、何かしらのニーズ(悩み)が存在します。そのニーズに対し、初回の使用で「この商品は良さそう」と感じていただくために、見た目、使い心地、効果感だけでなく、香りについてもしっかりと考えて設計しておくことが重要です。例えば、「ほっとする」「高揚する」「やる気が出る」「人に会いたくなる」といった具合です。(簡易的に例を上げていますが、「香りでほっとする」とはどんな気持ちだろう、と深堀っていきましょう。)
※「しっとりした」は感情ではなく感想です。「しっとりする」→「肌が整って明るくなる」→「翌朝の乾燥を感じない」→「メイク乗りが良くなる」→「通勤、通学、人に会うのが楽しみになって、”わくわくする”」といった具合に言語化してみてください。
「届いたとき」「初めて使ったとき」でポジティブな感情が生まれていれば、あとは「継続して使っているとき」です。継続する前提は、前述した「悩みの解決」(良くなってきている、という感情)が生まれているという点になりますが、それだけでは「同等の効果のある他社商品」でも換えがきくため、有名商品や安価な商品にスイッチされてしまいます。
続けていただくためには、そのブランド、商品を所持していること、使っていること自体にポジティブな感情を生むような商品設計をしておくことがポイントになります。(例えば、ブランドプロミスに共感できる、環境に優しくて使っていることに罪悪感がない、パッケージが可愛くて使うたびに気分が上がる、など)
※商品だけでなく、SNS、同梱物、メルマガでの情報発信やコミュニケーションも深く関係するため、マーケティング、CRMチームと連携してアイデア出しすることも有効です。
②処方から考える
レチノール、ビタミンC、ナイアシンアミドを〇〇%配合。これらを見て、何かしらの感情(期待感)が生まれたのではないでしょうか。このように、処方からメッセージを伝え、何かしらの感情を生み出すことも可能です。
入れる成分、入れない成分(無添加)だけでも、情緒的ベネフィットを提供することができます。例えば、国産の天然由来成分のみで作られた処方、あえて合成成分に拘って作られた処方というだけでも、感じ方は異なるのです。
肌に触れる製品のため、当然ながら使用感(こっくり、さっぱり など)でも生み出される感情は異なります。
上流から設計する
情緒的ベネフィットは、商品開発の段階で言語化しておくべき重要な要素ですが、単体で考えるものではありません。
会社(事業)の目的→ブランドの目的→製品の目的→だからこんな「機能的ベネフィット」「情緒的ベネフィット」を提供する→それに基づいて開発をする、という順で設計されている必要があります。
上流が言語化されていないと、そもそもどんなベネフィットを提供するのかを検討することができません。さらに言うと、「可愛いけれど効果がもの足りない」「効果はあるけど持っていても気分が上がらない」といった矛盾を起こすことになり、数多ある商品の中で埋もれてしまうことになります。
情報に溢れ、価値観も多様化している時代だからこそ、上流の目的をしっかりと設計し、感情という目に見えない価値までユーザーに提供することが重要であると言えるのではないでしょうか。
さいごに
いかがだったでしょうか。
今回は、情緒的ベネフィットの説明と設計方法、また市場において存在感を示すための重要性について解説しました。
これから化粧品ビジネスを始めたいという企業様、ご担当者様にとって、少しでもお役に立てば幸いです。
あわせて読みたい