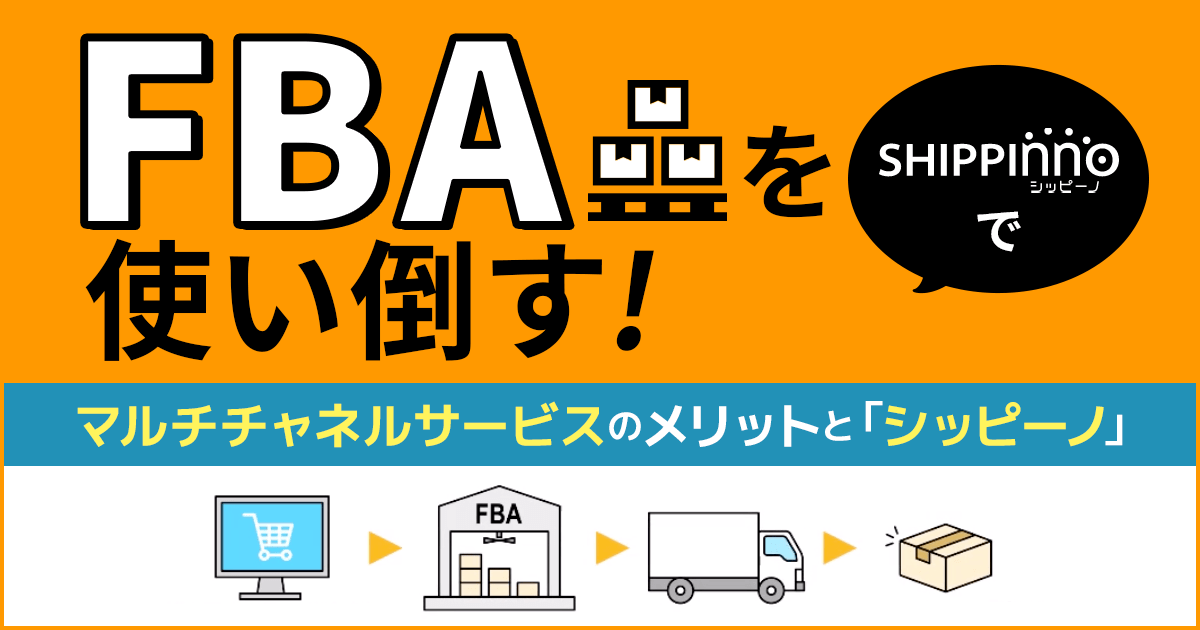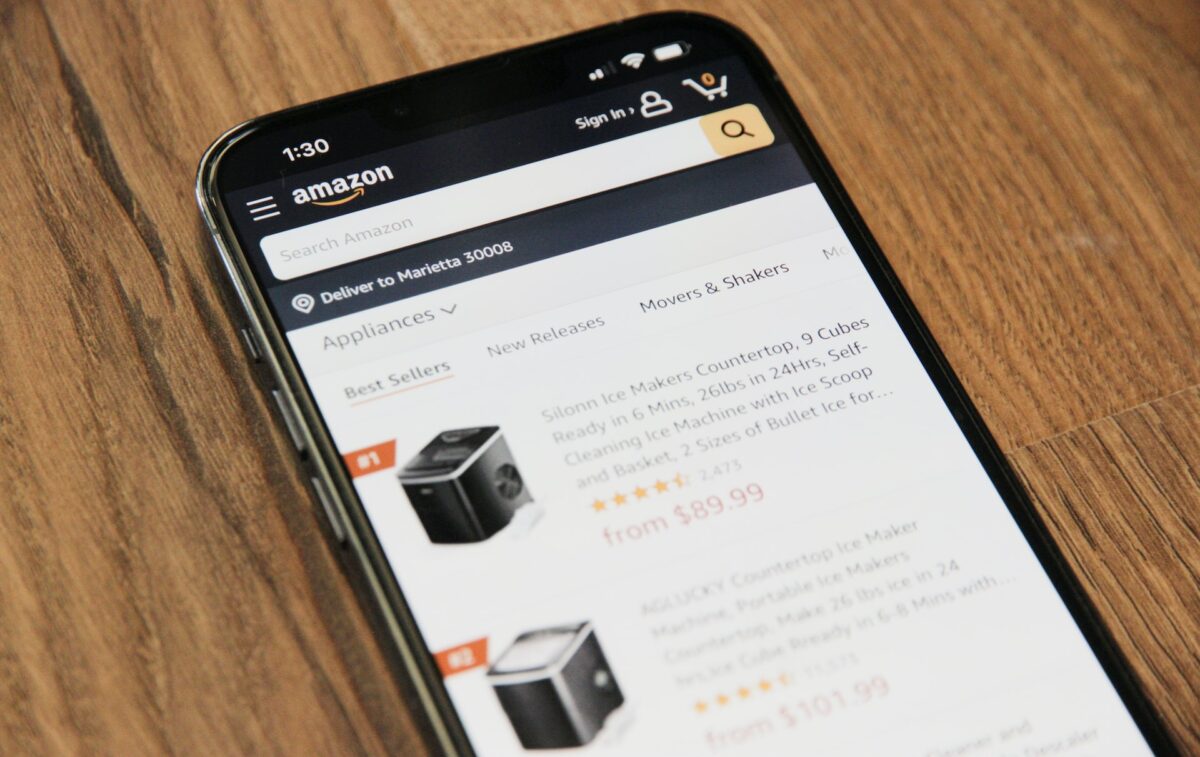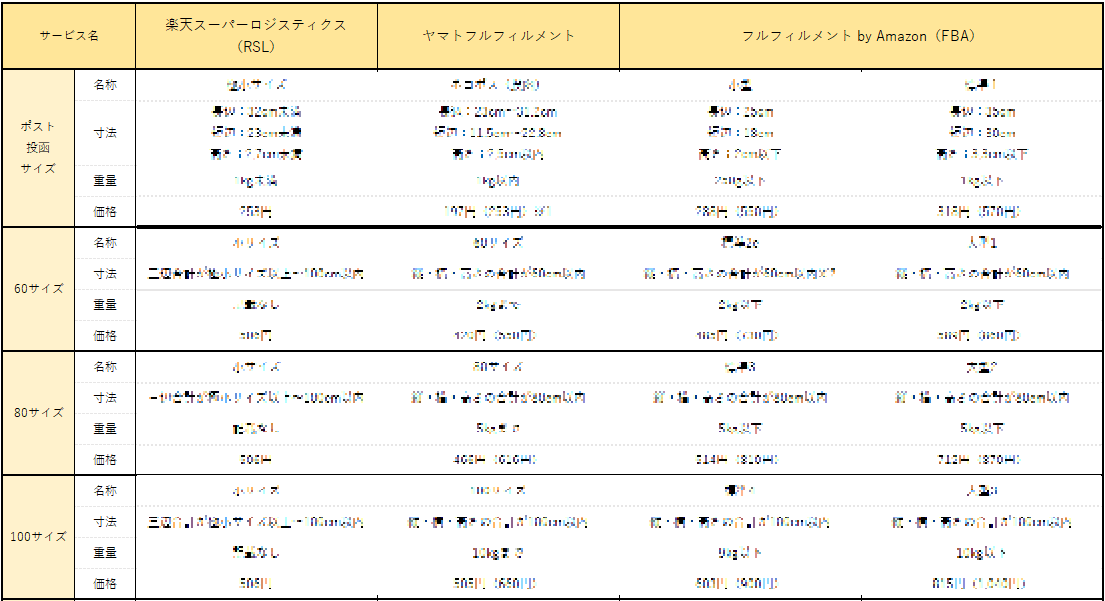この記事の目次
はじめに
コロナ禍の影響でオンラインで商品を販売したり購入したりするのが当たり前になりました。そのため世界中でEC運営のためのプラットフォームや便利なツールが続々と登場しています。
EC事業をやったことのない事業者にとっては、今こそ挑戦すべきタイミングかもしれません。そんな中でもAmazonのFBAを使ったEC運営が注目されており、これからECに挑戦される方もAmazonのFBAを使うことを検討されているのではないでしょうか?
「ECプラットフォームやツールが多すぎて何が何だかわからない」
「AmazonのFBAという言葉を何回か聞いたことがあり、何がそんなに良いのか気になっていた」
「AmazonのFBAを使ってEC運営しようとしているが、社内向けに説明が必要なため情報収集している」
本日の記事は、ECに挑戦しようと検討されていてAmazonでの出品について情報収集されている方に向けて書いていきます。
記事を書く私は、事業者向けにAmazon出品のサポートをさせていただきながら自社でもAmazonを使ったEC運営を行っています。すでにAmazonに出品中の方も、これから出品する予定の方にも有益な内容になるかと思いますのでぜひ最後までご覧ください。
AmazonのFBAが向いている事業者の特徴と、FBAを使わない場合の注意点
結論からお伝えすると以下のような特徴に当てはまる方が、AmazonのFBAを使ったEC運営に向いています。
特徴①:倉庫など商品を長期間に渡って保管する場所を持っていない
特徴②:自社で発送業を行うのが難しい
特徴③:大量の見込み客を継続して獲得することが難しい
それぞれ詳しく解説していきます。
特徴①:倉庫など商品を長期間に渡って保管する場所を持っていない
商品は注文が入るまでは、どこかに在庫を保管しておくことになります。さらに食品のような繊細な商品を販売するならば管理方法も考える必要があるでしょう。そのような保管機能を自社で用意できない場合はAmazonのFBAを利用することをおススメします。
AmazonのFBAでは国内外に専用の物流センターを持っており、取り扱う商品も多岐に渡ります。一般的には自社で倉庫を持っていないのであれば外注できる業者を探して契約し、管理方法を共有するところまでを、実際に商品を販売する前に完了しておく必要があります。
さらに海外向けに販売するのであれば現地まで行く必要があり、英語など外国語でのコミュニケーションがマストです。
AmazonのFBAを使用していれば、そんな保管業務を全てお任せすることができますし、保管の品質もとても高いです。また在庫の状況はネット上からいつでも確認できて、返送や廃棄が必要な場合はリモートで依頼することができます。
特徴②:自社で発送業務を行うのが難しい
商品を運ぶ配送手段も保管機能とセットで考えることになるでしょう。
自社で発送業務を行う場合、ヤマト運輸や佐川急便などの配送会社を利用するところが多いです。注文情報をもとに出荷作業を行い、配送会社と連携しなければなりません。発送業務は時間との戦いで、注文が多くなると対応が追いつかなくなります。また、梱包が雑になったり、誤出荷のリスクも高くなるでしょう。
こちらもAmazonのFBAを使うことでAmazonが用意した車両とスタッフを使ってお客さんに商品を配送することができます。出荷作業などもAmazon側で対応してくれるため不要です。
皆さんもAmazonで買い物をしたことがあるかと思いますが、Amazonの配送はとても早く丁寧ですよね。
人手不足の日本においてAmazonのようなレベルで物流を組める会社は極小だと思います。また①でお話したAmazonのセンターに商品を預ける際の物流はヤマト運輸か日本郵便が使用できます。
ヤマト運輸か日本郵便のどちらかをAmazon上で選択しておき、専用のラベルを添付して支店まで持ち込むか引き取り依頼をかければOKです。
特徴③:大量の見込み客を継続して獲得する方法がない
そもそも商品はお客さんに見つけてもらわないと注文が入りません。
「ECはいつでもどこからでも注文してもらえるから便利」と思われているかもしれませんが実際にはそこまで単純ではありません。たしかにリアル店舗と違ってインターネットで商売することで自由度は上がりますが、それゆえに参入しているライバルも多いです。
とりあえずネット上でサイトを立ち上げれば勝手にポンポン注文が入るということはありません。結局はリアル店舗と同じでメディア露出、広告、有名人とのタイアップなどをすることになります。
すでに会社もしくは商品に強いブランド力がある場合を除いて、見込み客となる大量のユーザーに自分たちでアプローチする手段が必要です。もちろん瞬間的なものではなく継続的な集客です。
Amazonのようなプラットフォームを利用することで、膨大なAmazonユーザーにアプローチすることができます。さらにFBAを利用することで、Primeマークがつくため商品を選んでもらいやすくなります。
巨大なモールを利用することは「相乗り商売」とも呼ばれていて、すでに大量のユーザーがいるところに商品を投下するほうが集客の難易度は楽です。「手数料がもったいない」と思われるかもしれませんが、Amazonで一生販売しなくても大丈夫です。
軌道に乗るまでAmazonの力を借りて、認知度がついてから自前のサイトやSNSで販売することに切り替える方はたくさんいます。コロナによる自粛生活は終焉を迎えつつありますが、ネットで買い物をする習慣は今後も継続しますので、EC運営は長期的な目線で計画してみてはいかがでしょうか?
AmazonでFBAを使った場合に知っておくべきメリット、デメリット
もちろんAmazonのFBAにもデメリットもあります。
AmazonのFBAのことをあまり知らない方も多いと思いますので、改めてAmazonのFBAにおけるメリットとデメリットを整理してみたいと思います。
AmazonのFBAを使うメリット
- 商品の出荷や在庫管理を委託できる
- ユーザーからの注文はAmazon側でリアルタイムに処理してくれる
- Prime会員のユーザーに対しては最短で翌日出荷で発送できる
- ユーザーからの問い合わせや返品対応の一次受付をAmazonが対応してくれる
- Amazonが対応している地域であれば同じオペレーションで海外向けにも販売できる
オンラインで商売をしたことがない方であればECを立ち上げるだけでも一苦労かと思いますが、本当に大変なのは運営の部分になります。商品出荷やカスタマーサポートなど、運営に関係する作業は人力で行わないといけないものが多いからです。
AmazonのFBAを使うメリットをまとめると、「EC運営における煩雑な作業をプロに任せることができる」という点です。もちろん委託するわけなので手数料はかかりますが、月額会員費用(税込5,390円)を除く多くの手数料は「注文1件ごと」にかかる仕組みのためキャッシュフローも安定しやすいでしょう。
Amazonに限らずEC運営を自社でやり切るには人手がかかるのはもちろん、新しい従業員への教育やミスのあった作業へのフォローをやり続けることになります。さらに月によって売上に波があったとしてもコストは一定なため、売上の少ない月は利益が赤字になったり手持ちの資金がピンチになったりする可能性が高くなります。
AmazonのFBAを使うデメリット
- 月額会員費用(税込5,390円)と注文1件に対して手数料がかかる
- 問題の所在が不明になりやすい
先ほどお話したようにEC運営の一部をアウトソーシングできる反面、Amazon内でのコストがかかるので自社ですべて対応することに比べると利益率が下がるかもしれません。
またEC運営の一部をアウトソーシングできるのは便利ですが、1つの商品にいろんな立場の人が関わることになるので商品破損などの問題が発生したときに「どこで何があったか?」がわかりにくいです。
例:ユーザーからの連絡で商品の破損がわかった場合
- 自社の従業員がヤマト運輸に持ち込む過程で落とした
- ヤマト運輸のドライバーがAmazonセンターに運ぶ際に落とした
- Amazonセンターの従業員が商品の取り扱い中に落とした
- Amazonの配達員がユーザーに配送する際に落とした
- ユーザーが荷物を受け取って自宅で落とした
こんな感じで商品破損にしてもいろいろな可能性が考えられ、それらすべてを探偵のように追いかけることは不可能でしょう。
Amazonに出品する上で知っておくべき仕組み
さらにAmazonで出品する上では知っておかないといけない仕組みがあります。
Amazon内でのオペレーションやルールは基本的にAmazonが決めるため、私たちのように出品する側が自由にアレンジすることができません。例えばAmazon内では時代背景やトレンドに対応するため、特定の条件を満たした商品を出品禁止にすることがあります。
さらにサイトのデザインや機能はAmazonが決めたものになっていて、「〇〇なユーザーをターゲットにした▲▲のようなブランディングを。。。」といったことができません。
またAmazonのようなモールでは「相乗り」という現象が起きます。簡単にいうと皆さんの商品を買ってくれたユーザーが「中古品としてAmazonで出品する」ことができる仕組みです。
つまり皆さんがオリジナルで作ったはずの商品を他の人も販売できるため、Amazon内での価格相場が変動するわけです。Amazonに対して特別な申請をすることで相乗り禁止にすることもできますが、初めてAmazonを利用されるのであれば先に頭に入れておいてください。
こんな感じで型に囚われず自由に販売していきたい方にとっては堅苦しさを感じるかもしれません。とはいえ現状のAmazonの業績やユーザーからの支持を考えると「結局はAmazonが決めたやり方が正しかった」という風にも考えられるかもしれませんね。
Amazonでは後からFBA⇆自己発送を切り替えることもできる
ちなみにですがAmazonで出品する方法にはFBAを使わない方法もあって「自己発送」と呼んだりします。
ここまで読んできた方のなかで「FBAが便利なのはわかったけど、後になってから自己発送の方が良かったなんて後悔したくないな」と思われている方がいるかもしれません。AmazonではFBAと自己発送のどちらで開始したとしても途中で切り替えることができます。
「テストでやるだけだから自己発送で始めて、本腰を入れてやるときになってからFBAに切り替えよう」
「人手がいないからFBAで始めて、従業員が増えたら自己発送に切り替えよう」
そんな感じでどちらで始めても大きなリスクはないので安心してください。とは言いながらもFBA→自己発送への切り替えのときだけ注意点がありますので共有しておきます。
①FBA在庫の処理
自己発送に切り替えたいと思った時点でAmazonセンターに未発送の商品が残っている場合は皆さんで返送もしくは廃棄依頼をかけて対応します。
AmazonのFBAを使用した場合、365日を超えた商品については「長期保管手数料」という固定の手数料が発生するルールになっています。長期保管手数料の対象になった商品はセンター内に保管されている間は毎月請求されます。
返送もしくは廃棄せずに放置しておくと長期保管手数料が延々とかかり続けてしまいますので注意しましょう。
②未発送の予約販売
予約販売をしている場合、すでにユーザーが購入して発送日だけ待っている商品はそのままにしておくことになります。①のことがあるので予約販売があったことを忘れて商品を廃棄してしまっては大変なことになりますので気をつけましょう。
③返品の発送先を登録
最後に簡単な事務手続きとして「返品の発送先」をAmazon上で登録してから自己発送に切り替えてください。
FBAの場合はユーザーからの返品はAmazonセンターに自動的に戻されて、不良品などでなければ在庫されて次回の販売を待ちます。一方で自己発送はAmazonセンターを使いませんので、自社もしくは指定した場所まで戻す必要があり、そちらの住所を事前にAmazon上で設定しておく必要があります。
上記3点のようにFBAから自己発送に切り替える際には、事前に対応することがあるので切り替えでトラブルがないようにしたいです。
最後に
以上のようにAmazonのFBAを使うことで事業者は物流業務や管理業務を軽減して、商品開発やマーケティングに集中することができます。大量の人員や自由に使える保管場所を持っていない事業者であるほど、FBAのメリットによる恩恵を大きく実感することになるでしょう。
今回の記事を書きました当社ではAmazonのFBAのサポートはもちろん、自己発送でのAmazon出品についてもお手伝いすることができます。本記事を読んでもっと個別の相談に乗ってほしいなどがありましたら、ぜひお気軽にご連絡頂ければと思います。
■株式会社Lorem
https://lorem-co-ltd.com/
合わせて読みたい