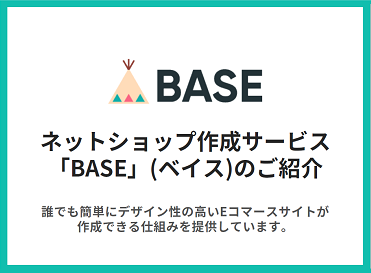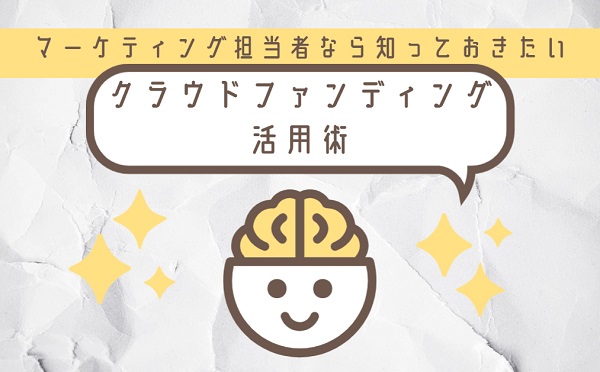
この記事の目次
令和の起業術、スモールビジネス(スモールプロジェクト)のススメ
昭和の起業とは
1955年~1973年の高度経済成長下の日本においては大きく変化・発展していく生活様式にとって、足りないもの、必要なものがたくさんありました。だから、世の中の人々は足りないものを満たしてくれるモノやサービスにお金を払い、ビジネスとして発展していきます。
この時代に起業するために必要だった能力は資本力(お金を集める力)です。集めた資本を使って足りないもの、必要なものを作って売る、もしくは買ってきて売ることがビジネスになりました。銀行から、大企業から、資本家から出資してもらえる「環境を持っていること」が起業するための前提条件だったのです。
令和の起業とは
一方、現代に目を移すと、衣食住はもちろん、余暇を彩るエンタメや趣向品なども選びきれないほどに満たされています。どんなモノやサービスが新しいビジネスになるのか、「これだ!」というものがなかなかわからないから、資本家はどこへお金を投資すべきか頭を悩ませています。世の中の変化のスピードはとても早く、新たなサービスや技術がどんどん世に出てきて私たちの生活はより豊かに便利になっていきます。その変化を捉え、形にしていくスピード感も令和の起業家には求められるでしょう。
現代の起業に必要な能力は発想力(アイデア)と発信力(顧客や資本家に「知ってもらうこと」)だといえます。社会を豊かにするためのおもしろいアイデアを持っていて、それを多くの人に知ってもらうことができれば、誰でも起業できるので、昭和の起業と比べハードルは下がったといえるでしょう。あとは行動力ですね。
コストを抑えてツールを活用する
インターネットが普及し、誰もが情報発信できるようになったことで、商品やサービスを知ってもらうチャンスが、(昭和に比べると)誰にも等しく、与えられるようになりました。
そして、上手に活用すれば「資本力」がなくてもビジネスに挑戦できる、それをサポートしてくれるツール・システムとなるサービスが増えてきたことも令和の起業家たち、イントラプレナーたちにとって追い風となっています。
これらのツール・システムの共通点は手数料ビジネスであることです。売上を立ててから手数料を支払うキャッシュフローとなっているため、資本力のない起業家にとって手元資金が少ない状態でもビジネスをスタートする機会を得ることができます。その代表的なシステムの1つが「クラウドファンディング」なのです。
クラウドファンディングの活用
クラウドファンディングとは
もともとの語源はcloud(群衆)とfunding(資金調達)を併せた造語です。インターネットを通じてアイデアに対してお金を集める仕組みとしてアメリカで生まれました。
クラウドファンディングにもいろいろな種類がありますが、ここでは私たちがニュースやテレビCMなどで耳にすることの多い購入型クラウドファンディングについてお話しします。
「クラウドファンディング=資金調達」と認識している人が多いのですが、お金の流れを見ると「予約販売」といった方が適切かもしれません。モノやサービスを購入する決め手として、そのモノやサービスのストーリーや「誰が売っているのか(ヒト検索)」が重要視されるようになり、それを伝えやすい仕組みとしてクラウドファンディングの仕組みに注目が高まっています。
ゼロ次流通という考え方
一般的に商品・サービスの流通フローとしては上図破線右側の製造以降になります。クラウドファンディングは製造の一段階前の「0次流通」にあたり、このことから様々な活用ができるのです。

テストマーケティング
飽食の現代において、顧客のニーズを見つけることはとても難しいです。そんな中、クラウドファンディングの仕組みを活用すると、リスクを抑えて市場にニーズを問うことができます。商品やサービスのアイデア、ストーリーをクラウドファンディングプロジェクトとして発信し、その商品・サービスを「買いたい」かどうか、直接顧客に判断してもらうのです。「買いたい」と思った顧客は「支援」という形で、その商品やサービスを予約購入します。「買いたい」と思う顧客が少ない(ニーズがない)場合は「支援が集まらない」という結果が得られます。
また、先にもお話ししたように予約販売と同じお金の流れなので、顧客の注文数が確定してから生産数を決めることができます。商品が市場に受け入れられず、ニーズがなかった場合でも、最小ロットの生産で対応することで在庫リスクを最小限に抑えることが可能です。
資金調達
先に説明した通り、クラウドファンディングを活用することで販売数量を確定してから生産数を決めることができます。商品販売の場合、リターンの発送スケジュールを予め調整しておくことで発注・支払いをクラウドファンディングの入金後にすることが可能です。
厳密にこの場合は資金調達ではなく、クラウドファンディングを活用しキャッシュフローの順番を変えるといった方が正しいかもしれません。リターンの内容を工夫し、原価のかからない(極端に安い)サービスや商品を設定することで、資金調達に充てることもできます。
ECプラットフォームの活用
BASE
最近では、商品やサービスを販売するプラットフォームで初期費用を抑えてスタートできるサービスが増えてきています。その中でも、BASEは実務を運用するためのアプリも充実していておすすめです。
販売ページの作成から商品・サービスの販売スタートまで初期費用ゼロで作り上げることができ、販売実績に応じて手数料がかかるシステムになっています。事業の立ち上げから実際に商品が売れるまでの間に維持費もかからないので、リスクを抑えてEC事業に参入することができます。
CAMPFIREとの連携
BASEはクラウドファンディングポータルのCAMPFIREと資本業務提携しています。「CAMPFIRE連携」というアプリが実装されており、BASEのアカウントでそのままクラウドファンディングプロジェクトの立ち上げを行うことができます。「新商品を開発するための資金を集めたい」「新規の顧客を開拓したい」「自身のビジネスの宣伝をしたい」そんなときにスムーズに0次流通を活用できるようになっています。
プロジェクトの終了後は、BASEページへのリンクボタンを設置することができるので、プロジェクトページはランディングページのように働いてくれます。
スモールビジネスのススメ
昭和の起業であれば、資本的に大きなリスクを伴うので、練りに練った失敗しないビジネスモデルを世に出していく必要がありました。しかし、令和の起業においてはアイデアの良し悪しは顧客に判断してもらい、リスクを抑えたトライ&エラーを繰り返しながら事業を進めていくことができます。
初期費用・ランニングコストを抑えて、小さなチャレンジを繰り返す中からスケール可能性のある事業を見つけ、形にしていくことが令和の起業のコツなのかもしれません。
BASE×CAMPFIREを実践した事例の紹介
実際にクラウドファンディングを活用し、ブランドを立ち上げた事例を紹介します。
お芋のスイーツ専門店 おもいもの-OMOIMONO-

お芋のスイーツ専門店 おもいもの-OMOIMONO-(https://omoimono.base.shop/)というスイーツブランドです。このブランドはクラウドファンディングを活用しスイーツの予約販売を行い、初期費用を調達しゼロ円起業を実現しました。立ち上げから一年間はコストを抑えてBASEでのネット通販のみで展開しコツコツとファンを獲得しています。二年目の現在は駅前催事出店や商業施設の催事出店などの固定費のかからない販路での展開を進行中です。
催事での販売計画は当初予定の3倍とスイーツの生産が追いつかない状況になっており、今後はOEMなど商品の大量生産をすすめています。
まとめ
クラウドファンディングの活用術について解説させていただきましたがいかがでしたか?リスクを抑えてブランドを立ち上げられるクラウドファンディングはアイデアを形にしようと思っている事業者さまに最適な手法かと思います。
クラウドファンディングを活用したいとお考えの事業者さまはお気軽にご相談ください。
▼アンノウン株式会社へのご相談はこちら
https://crowdfunding.unknown-osaka.com/
合わせて読みたい