
古くから日本で愛されている「日本酒」ですが、その製造や販売には許認可が必要なことをご存知でしょうか。免許を取ることが困難であることや、従来の商習慣が残る日本酒業界には新しいことが起きづらい状況があります。今回は株式会社RiceWineのCOOである渡辺毅志さんに、世界を見据えて販売している日本酒ブランド『HINEMOS』(ヒネモス)のこれまでと今後の成長を、日本酒業界のお話を絡めて伺いました。
この記事の目次
日本酒業界のトレンドとは
――製造や販売に際して、それぞれ免許が必要な日本酒ですが、まず、この業界の商慣習や直近の動向について教えていただけますか?
渡辺さん:酒類全体の市場規模が3兆円ほどある中で、日本酒業界に限ると5,000億円ほどの規模といわれています。日本国内での消費量は縮小傾向ではあるものの、海外への輸出量は増加しているのです。国を挙げて日本の特産食品を海外に輸出する動きがある中で、日本酒もそれに漏れず輸出が進んでいます。輸出が活発に行われているものとして果物や和牛に並び、日本酒の輸出額は400億円規模に成長しています。
輸出量が増えている背景に、世界的に日本食が流行っていることが理由の1つに挙げられます。和食がユネスコ無形文化遺産に認定されたことや寿司やラーメンのような知名度の高い日本食がますます認知されることで、日本食のそばにある日本酒も受け入れられているのです。また、新型コロナウイルスの影響で、海外の方が日本を訪れて日本酒を楽しめないことも輸出増加の要因の1つと考えられます。
別の観点では、海外の高級なフレンチやミシュランを獲得しているような飲食店でも日本酒が注目されています。例えばフランス料理ですと、この数十年でバターや生クリームを使ったこってりした味わいから、その土地の素材を活かした薄味で繊細な味わいが好まれるようになりました。そこで、繊細な味わいを引き立てるために、食中酒として日本酒に注目が集まり、ワインリストの中に日本酒が並ぶようなことが起きています。
国内の日本酒市場と商慣習
――海外での認知・輸出額がともに伸びているのは良い傾向ですね。一方で、国内の動向についてはいかがですか?

渡辺さん:日本では、紙パックに入っているイメージの、いわゆる普通酒と呼ばれる日本酒の消費量は減っています。しかし、「純米大吟醸」のようにスペックが定められた、いわゆる特定名称酒と呼ばれるお酒の消費量はコロナ以前まで伸びていました。居酒屋のメニューで単に「日本酒」や「熱燗」と書いてあるようなお酒が喜ばれる時代から、銘柄を指定して楽しむ、酒蔵の個性や味わいを楽しむ、こだわって日本酒を飲むという行為に消費者の嗜好が移っているようです。
国内で日本酒全体の消費量が減っているのは、若者の酒離れや、日本酒以外のお酒の選択肢が増えていることが原因とよくいわれています。ハイボールやレモンサワー、ストロング系のチューハイの名前が日常的に楽しまれて支持を集めている一方で、日本酒がその中で存在感を少しずつ失ってきてしまっている、というのが現状です。
日本酒産業を取り巻く環境は他の酒類と比べて特殊です。例えば、一昔前までは製造方法によって酒税が異なり、味わいではなくお酒のスペックのみで値段が決まっていくような時代もありました(いわゆる級別制度、1992年に撤廃)。戦後の混乱の中で日本酒の安定的な供給に寄与したという評価もありますが、一方で蔵ごとの個性が打ち出しにくいというデメリットがあったと思います。
制度が廃止されてからは酒蔵が個性を打ち出して多様な日本酒が生まれる土壌が生まれ、獺祭さんや十四代さんのような全国的に有名になったブランドがいくつも生まれてきています。しかし、級別制度が撤廃されてからはまだ30年ほどの歴史であり、今ではビール、ウィスキー、ワイン、缶チューハイなど多様なお酒の選択肢が消費者に与えられていて、日本酒産業が十分に盛り返すことができる構造がある、というわけではないと思います。
HINEMOS立ち上げの背景
――今のお話を受けて、日本酒業界でブランドを新規で立ち上げるのはハードルが高いように思いました。「HINEMOS」がどのような背景で立ち上がったブランドなのか教えていただけますか?
渡辺さん:私たちが起業をする際に大切にしていたことは、「日本から世界に誇れるプロダクトを創ること」を念頭に置いていました。例えば寄木細工や発酵食品など・・様々な日本ならではの伝統産業を調べていく中で、一番可能性を感じられたのが日本酒です。
免許が取りづらいことや、流通が硬直化していることなどイノベーションが起きづらい構造にある日本酒業界において、まっさらな私たちが新たに挑戦することは、消費者にとっても新しい価値が提供できる余地があるのではないか、と考えたのです。
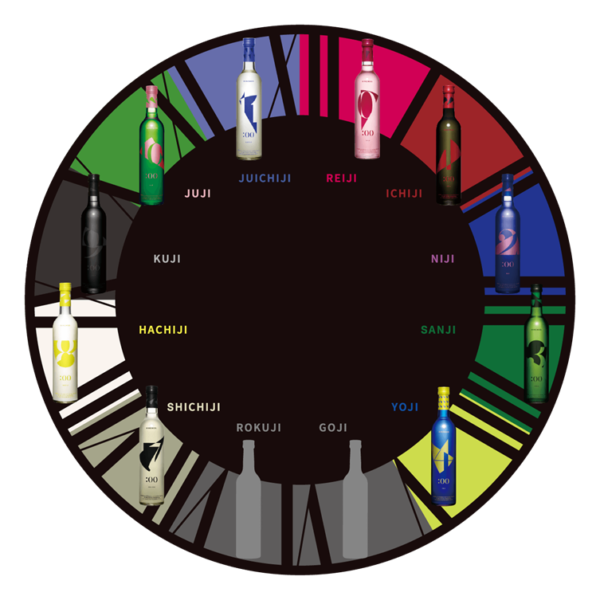
――日本酒は製造や販売に際して免許が必要だとお話されましたが、ブランド立ち上げのときは、どのような流れでHINEMOSを作られたのでしょうか?

渡辺さん:2021年4月には、日本酒の製造免許は輸出を目的とし、国内で販売しない場合に限り、新規で発行する制度が整備されました。しかし、国内で販売することを目的にする場合には、原則新規での発行を受け付けていません。そのため、スタートアップがいきなり日本酒を自社製造することは非常に難しいのです。
まずは、弊社の代表が地元の商工会に問い合わせをするなど地道なアプローチにより、私たちの想いに賛同してくれる酒蔵を探しました。最初は委託醸造という形で、神奈川県の井上酒造さんにご賛同いただき、HINEMOSを作ってもらうことができ、ブランドをリリースできることになったのが、2019年4月のことです。
――委託醸造は自社のコンセプトを酒蔵さんにお伝えして、日本酒を作ってもらうOEMの形かと思います。今では自社で製造していますが、新規発行されていない製造免許をどのようにして取得したのですか?
渡辺さん:製造免許を取得するにはM&Aにより酒蔵を買収したり、廃業する酒蔵から譲り受けたりと様々な方法がある中で、私たちは既存の酒蔵に移転してもらうことで、自社製造を実現しました。
委託醸造先の井上酒造さんで杜氏(酒造りの責任者)をしていた現弊社社員の湯浅の実家が森山酒造という酒蔵で、その酒蔵の後継者でした。将来的には自分の実家の酒蔵を継ぐ予定だった湯浅は井上酒造さんで修行をしていたのですが、実際に自分の酒蔵を継ぐことを考えたときに、設備の老朽化や、酒蔵の立地が都市部から離れていてアクセスが悪いことなどがあり、費用面、人的確保の面や物流の面などからビハインドな要素が多くあったのです。
そんな中、HINEMOSの味やデザイン、売り方など多くの面で今までの日本酒業界のプレイヤーとアプローチが違うことに興味を持ってもらいました。弊社の代表や私たちと湯浅が同年代ということもあり意気投合します。最終的に、愛知の山奥にあった湯浅が継ぐ予定だった森山酒造が小田原に移転することを弊社が資本面などで全面的に支援して、我たちと一緒に立ち上げた酒蔵で製造を行うようになりました。
大手企業が中小規模の酒蔵にM&Aを持ちかけて製造免許を取得する事例は複数ありましたが、スタートアップでそれを実現するのは資金面やパートナー選定の面で困難さがあると感じていました。HINEMOSが自社製造をこのスピードで実現できたことは、ただただご縁に恵まれた話だと思います。

自社製造ならではの強み
――杜氏の湯浅さんは変わらず、OEM(委託醸造)から自社製造に切り替わったことで、どんな変化があったのでしょうか?
渡辺さん:日本酒をオンラインで販売しているベンチャー企業、D2Cブランドの多くはOEMで製造しているかと思います。その中で、自社製造を一気通貫して行うことで、バリューチェーンの川上から川下までを意識した企画を出すことで差別化を行えるようになります。例えば、父の日や母の日など季節の限定商品を作るとき、企画を持ち込んでOEMで生産してもらうのと、社内で企画から生産まで行うのはスピード感が違ってくるでしょう。

渡辺さん:杜氏の湯浅は清酒専門評価者という日本に150人ほどしかいない国が認定している唯一の日本酒の資格を所有しています。日本酒の品評会で審査員を務めるなど、若くして相当な舌と経験を持っているのです。そういった杜氏が社内にいるのか社外にいるのかで、提案できる企画の内容やコミュニケーションの質が変わります。
また、最も異なる点として、OEMの場合、製造できる量や時期に制限がありました。日本酒業界特有のことですが、寒仕込みといって冬の寒い時期だけ製造をしていることが多く、急遽製造量を増やすなどの柔軟な対応が難しいのです。これは委託していた井上酒造さんでも同様のことでした。なので、大手の酒蔵ではない限り、例えば売れ筋の商品を在庫状況に合わせてたくさん作ったり、また消費者の好む味わいをもとに製造の度に味わいを調整したりといった、一般的な製造業では実現できるようなPDCAを素早く回すことが難しいと感じていました。
弊社では、移転した森山酒造は冷蔵倉庫の中に酒蔵を建てました。そのため、春夏秋冬いつの季節でも日本酒を作れる「四季醸造」という製造体制を小規模ながら実現しました。これで極端な在庫切れを起こす心配がなくなり、また季節の限定商品を年間のスケジュールではなく、月単位の製造スケジュールで作れるようになったので、企画・製造ともに機動力がかなり上がっています。
また、お客様から頂いた声をもとに商品の改良・改善も月単位で行うことができるようになりました。高い商品レビューをいただき続けていることは、日々の地道な改善活動が肝だと感じています。
日本酒の販売方法と効果的な販売施策
古くからの慣習とEC化が進みづらい理由
――自社製造によりバリューチェーンの全工程がスピードアップしたのですね。次に日本酒ならではの販売方法やHINEMOSとして反響が合った取り組みを伺えますか?
渡辺さん:一般的に、酒蔵は酒問屋や酒屋に卸し、飲食店や小売店などの流通に乗せていきます。卸が前提の業界であったことから、そもそも日本酒をオンラインで積極的に販売しているプレイヤーがまだまだ少ないと感じています。
また、ECモールなどでオンライン販売しているプレイヤーは酒蔵ではなく酒屋が多いです。大手の酒蔵を除き、酒蔵が直販するためにEC人材を確保することや、専業のスタッフを雇用することの難易度は高いと感じます。また、既に酒屋や問屋に卸している商品を自社で売ること自体、今までの流通経路を飛び越えてしまうことになるので、なかなか積極的に取り組みにくいという業界の慣習があることも理由として考えられるでしょう。
新規参入である私たちにはそのような制約が一切ないため、初めからD2C/ECでの販売ありきの商品展開を実行できていることが、日本酒業界の中では稀有なことと感じています。
成果につながった販売施策

渡辺さん:販売する上でHINEMOSが重点的に取り組んでいることを2つご紹介します。まず、ギフトについてです。企画から、製造、販売までの全工程を内製化している中で、物流業務も社内で対応しています。そのため、オプションでリボンやメッセージカードを付ける、といったことも柔軟に対応できるのです。加えて、母の日やクリスマスなど季節ごとのギフト商戦には限定商品を販売するなどの企画も自社で完結して行うことができるため、結果として今までの日本酒ECでは満たせなかったサービスとしてお客様の支持を集めることができていると感じています。
もう一つの取り組みがポップアップストアです。HINEMOSを知っている人に向けた取り組みではなく、まだHINEMOSを知らない方や、そもそも日本酒を購入する意識がなかった人向けに認知や購入機会を広げる取り組みとして始めています。
そのためには、人流の多い場所でポップアップストアを開催する必要があります。しかし、実績のない中ではご協力いただける商業施設が少なかったのが正直なところでした。初めはポップアップストアが出店できる場所を知人から紹介いただくところからはじめ、その実績をもとに商業施設の方への営業を重ね、実績を積み上げていきました。結果として、2021年には首都圏の主要ターミナル駅(池袋や恵比寿、上野など)の駅構内でのポップアップを実現しました。今では商業施設からお声がけいただけるようになっています。

渡辺さん:実際にやってみると費用対効果が良い施策として継続できることがわかりました。また、一般的に日本酒の販売量が一番多くなるのは12月です。ポップアップストアも例に漏れず12月が最も売上が高くなりますが、この時期は寒仕込みで冬に集中して日本酒を仕込む酒蔵にとっては製造の繁忙期でもあり、通常であれば販売に人員を割くには難しい時期です。私たちも立ち上げや日々の運営に苦労がないわけではないですが、都内に専属の販売スタッフを設けるなど工夫を凝らすことで、多くの消費者の方に日本酒を手に取るきっかけを提供できています。
また、ポップアップストアでは客層として若い女性にご来店いただくことが多く、それを目の前で感じられることは相当の励みになっています。若い女性に支持をいただいていることは、HINEMOSがブランドとして他の酒蔵とは異なる強みを持っていると感じています。
強みを活かして、世界にブランドを届けていく
――最後にHINEMOSが今後拡大する上でどのようなところに力を入れていくのかお伺いできますか?
渡辺さん:現在実施しているポップアップストアを更に展開することやECでの販売を増やすことに加えて、最も重要な動きは海外展開だと考えています。コロナ禍における特殊な状況やアルコールをECでは販売できない国があるなど、海外に向けて販売するのは高いハードルがあります。
ただし、国内では製造から販売まで一気通貫して実行している酒蔵だからこそ、世界中の消費者に対しても同様に、それぞれの国に合わせた方法を整えることで、新しい日本酒の価値を提供していけると信じています。私たちと共に日本を代表するブランドを創りたい方の参画をお待ちしています。
インタビューを通して:唯一無二の日本酒ブランドを世界に届けていく
日本国内で着実に認知を拡大し、売上を伸ばしているHINEMOSはブランド立ち上げから世界を見据えて販売を続けています。自社で製造を行っているアドバンテージや世界に展開することを最初に決めた上でつくられた商品のコンセプトなど、唯一無二の日本酒ブランドとして日本を代表していくのではないかと感じられました。
業界の慣習にとらわれず、日本酒を通じて新しい価値を提供しているRiceWineでは、現在採用を強化しているようです。世界からの需要が伸びている日本酒業界で、国内外に向けて新しい施策や取り組みに挑戦できる環境は伝統ある酒蔵とは違ったチャレンジングな機会が広がっています。気になる方はぜひ下記よりご応募してみてはいかがでしょうか。
▼株式会社RiceWine 求人情報
https://ricewine.co.jp/jobs
合わせて読みたい
















