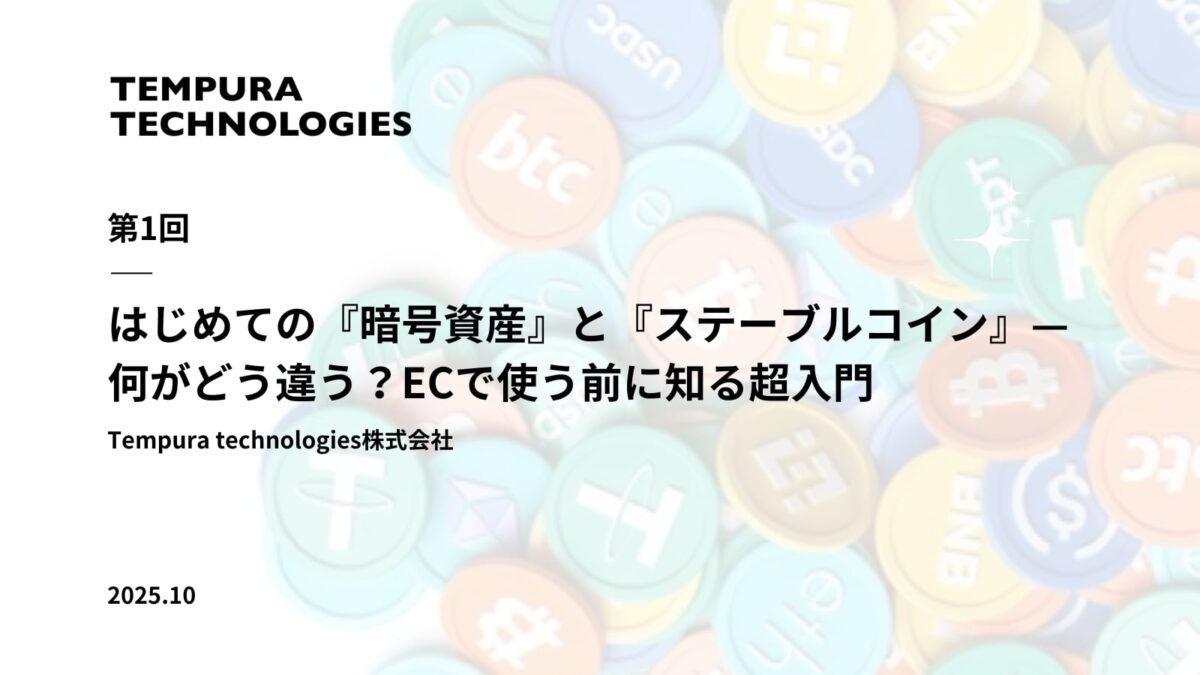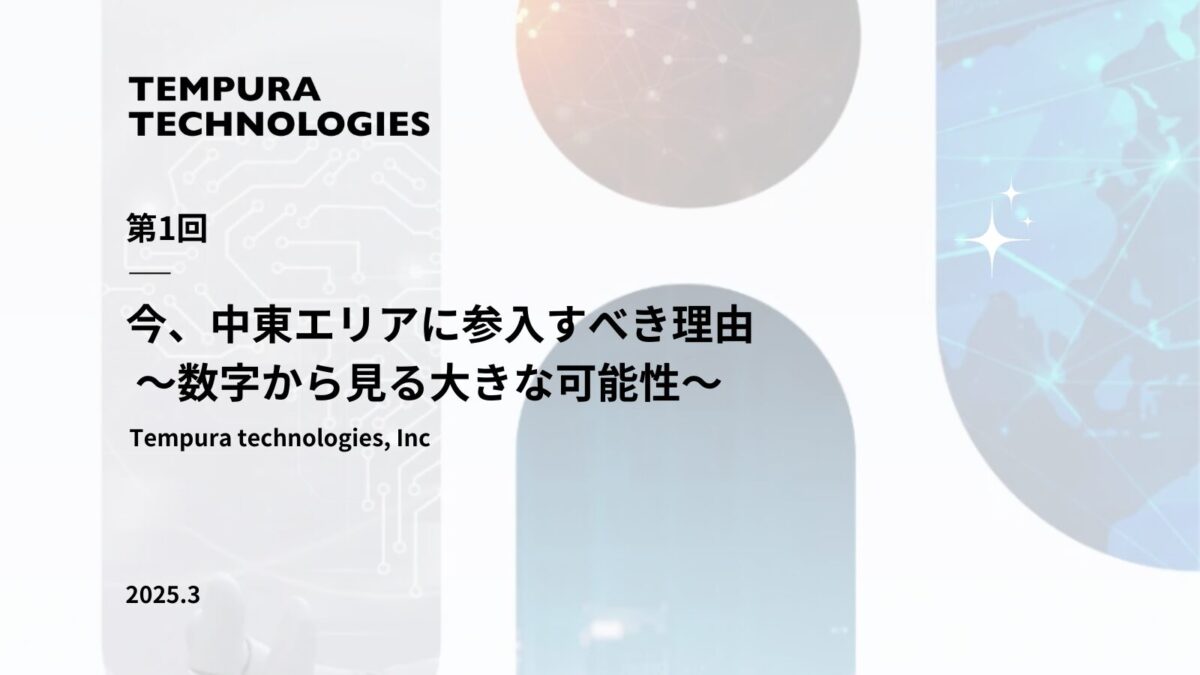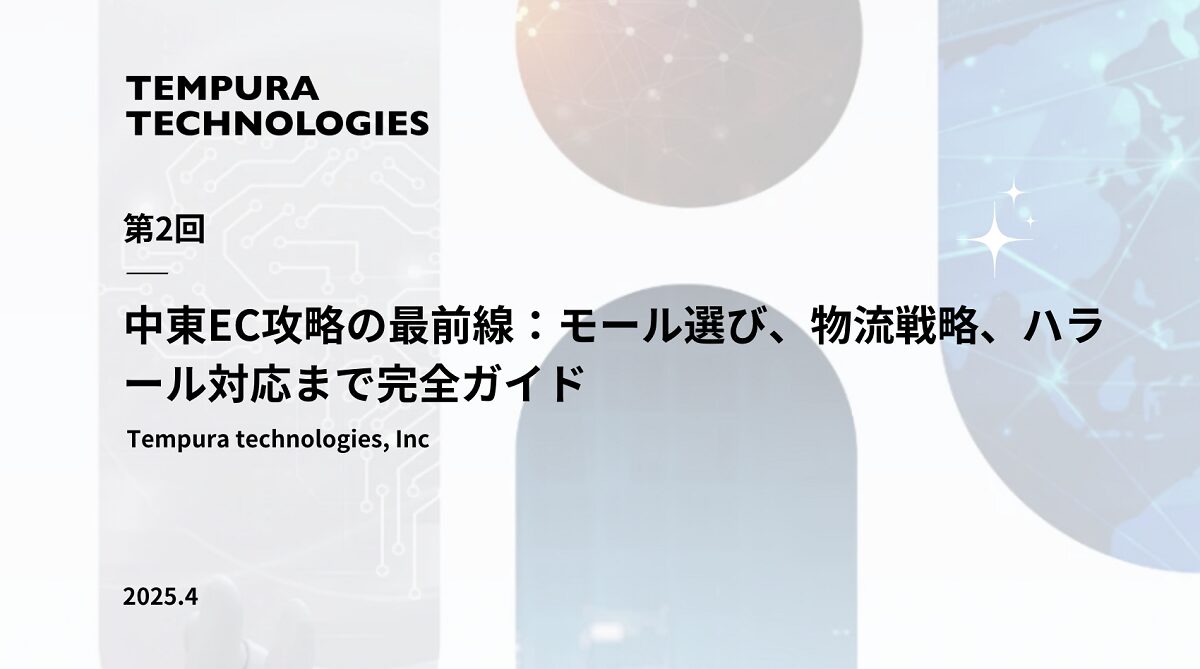海外向けECは、広告、在庫、値付け、CSのすべてが日々の為替に触れています。昨日は勝ち筋だった施策が、翌日には同じCPAでも利益が伸びない。価格の“ブレ”がユーザーの購入率(CVR)をゆさぶり、薄利多売のモデルでは気づかないまま粗利が削られることすらあります。本稿は、難しい金融ヘッジに頼らなくても、価格の見せ方とお金の受け取り方をそろえるだけでリスクを小さくできるという話です。キーワードはステーブルコイン。USDC、USDT、JPYCを“投機の道具”ではなく“商いの道具”として捉え直し、越境ECの現場で使い分ける視点を整理します。
上田 剛大
Tempura technologies株式会社
共同創業者 / 取締役
2020年にSansan株式会社へ中途入社し、個人向け名刺管理アプリeightの新規ソリューションのBizDevとして従事。その後、2022年にTempura technologiesを共同創業し、web3やAIを活用したソリューションを提供。自社プロダクトとしてロイヤリティプラットフォームやマーケットプレイスを構築し、エンタメ、化粧品、日用品、電化製品メーカーの海外支援(GMV最大化)を支援。現在はドバイ子会社設立と韓国企業への出資も踏まえTempura technologies Groupとして主に中東エリアへの海外支援を注力している。
会社ホームページ:https://tempuradao.xyz/
為替がCVRに与える影響(価格の“ブレ”問題)
「最初に見た価格」が基準になる
ユーザーは初回に見た価格を強い基準として記憶します。翌日また同じ商品を見たとき、表示が同じでも決済直前の実質金額が上がっていると、わずかな違和感が最後の一押しを止めます。購入を保留し、比較サイトやSNSを回り始めるだけで離脱は高まり、広告のクリックは稼げてもコンバージョンが伸びないというねじれが生まれます。反対に安く見える日はCVRが一時的に持ち上がりますが、在庫補充や原価管理、次回プロモの設計にしわ寄せが来て、LTV設計が不安定になります。短期のCVRと中期の収益性を同時に崩すのが、為替による“ブレ”の厄介さです。
「表示通貨」と「受け取り通貨」のズレがブレを増幅する
このブレを加速させる典型が、サイトの表示通貨と実際の受け取り通貨のズレです。米国向けにドル表示なのに、着金は円で受ける設計だと、同じ受注でもその日のレートで粗利が変わります。ユーザー体験は一定に見えても、事業側では「思ったより儲かっていない」「急に利幅が出た」といった揺れが起こり、値付けやクーポン投下の判断が後追いになります。たとえば広告の最適化でCVRが0.3ポイント上がっても、週末の円安で粗利が同幅下がるなら成果は相殺されます。最前線のチームは改善しているのに、財務の指標では成果が見えづらい——この認知のズレが、社内の意思決定速度をさらに落とします。
“ものさし”をそろえ、換金の「窓」を固定する
対処は拍子抜けするほどシンプルです。まず、表示通貨と受け取り通貨をそろえます。米国ならUSD表示×USD相当の着金、GCC(湾岸協力会議加盟国。サウジアラビアやUAEなど中東6か国の経済圏)ならUSDまたは現地通貨表示×同通貨の着金に統一するだけで、ユーザーの価格体験と事業側の計算が同じものさしに乗ります。次に、換金の“窓”を決めます。たとえば毎日11時に本社の基軸通貨へ集約する、もしくは1,000USD相当を超えたタイミングで自動換金するなど、ルールを先に固定すると、広告、在庫、会計の判断が同じ前提で回り始め、日々のレートに振り回されにくくなります。返品・返金時の基準レートもあらかじめ明文化しておくと、CSの対応が安定し、レビューやSNSでの不信感の拡散も抑えられます。
通貨選択の考え方(USDC/USDT/JPYCの使い分け)
USDC:ドル基準市場で“価格のものさし”を固定する
USDCは米ドルに連動する代表格で、1コイン≒1ドルという直感性が意思決定を単純化します。米国や“ドル基準”の地域に売るなら、USD表示→USDC受領という直列の設計がもっとも扱いやすいでしょう。カートの割引、バンドル割、送料無料ラインなどの価格ルールをドルで固め、着金もドル相当で受けることで、広告の入札と在庫の発注点が一つの指標で語れるようになります。日次で円に替えるか、週次で一括かはキャッシュフローとボラティリティ許容度で決めるだけです。
USDT:対応先の広さを活かして受け口を拡張する
USDTは対応先と流通の厚みが強みです。B2Bの回収や一部地域では「まずUSDTで」という相手が少なくありません。その場合は、受け口としてUSDTを許容しつつ、社内では日次でUSDCや本社通貨に集約する運用にしておくと、通貨在庫が積み上がらず、評価損益の管理も簡素化できます。複数通貨が同時に流入しても、終点をそろえてしまえば会計は落ち着きます。
JPYC:円建て会計の“最終着地”をシンプルに
JPYCは日本円に連動するタイプで、本社会計が円建ての企業にとって強力な“最後の一手”になります。仕入、物流費、給与など円支出が多いなら、最終的にJPYC(または円)へ集約して評価の軸を円に置くのが合理的です。海外向け販売で表示がドルでも、表示USD→受け取りUSDC→当日中にJPYC(または円)という二段導線にしておけば、ユーザーのわかりやすさと社内の統制を同時に満たせます。返金は原則として受け取った通貨で行い、端数はクーポンで吸収するなどの細則をCS台本に織り込んでおくと、オペレーションはさらに滑らかになります。
“技術の細部”は内蔵化し、事業は運用の型に集中
現場で迷いがちな点は、チェーンやウォレットなど技術の細部をどこまで理解すべきかという問題です。実務では、どのネットワークが最も低コストか、どのルートが最短かといった選定は決済パートナーに委ね、事業側は“運用の型”に集中するのが得策です。販売国では現地の見え方に合わせ、最後は本社の帳簿に合わせる。ステーブルコインは、その二層を結ぶ輸送レーンだと考えると腹落ちしやすくなります。
ステーブルコイン決済導入におけるメリット
受け取りコストの構造を「数千円→数十円」オーダーへ
ステーブルコインの導入は、為替の揺れ対策に加えて、受け取りコストの構造を軽くします。海外から銀行経由で円を受け取る場合、受取手数料と為替関連のチャージ、さらに中継銀行の費用が毎回かかります。B2Cの小口売上が積み上がるモデルでは、この“件数×定額”が月次の利益をむしばみます。ステーブルコインでの受け取りは、基本的にネットワーク利用料が中心で、混雑や相場に左右されるとはいえ、1件あたりの体感コストは数十円から百数十円に収まる場面が多く、銀行受取の数千円規模と比べるとオーダーが一段違います。小口を数多く回収するほど差が効いてきて、同じ広告費でもキャッシュ・コンバージョン・サイクルが短くなるため、在庫の回転や再投資の速度にまで波及します。
ほぼ即時の着金がオペレーションを軽くする
スピードの面でも効果は大きく、着金はほぼ即時です。広告費を投下してから現金化できるまでの時間が縮むと、在庫補充の判断が早まり、機会損失の削減につながります。返品や返金の運用も、基準レートの決め方と記録の残し方を最初に設計しておけば、むしろ銀行振込よりも透明で再現性のあるプロセスになります。
ルールの文書化で“毎日の迷い”をなくす
社内の統制という観点では、販売国ごとの表示通貨、受け取り通貨の原則、集約通貨と換金タイミング、返金レートの基準をA4一枚にまとめ、ダッシュボードには例外フラグを立てるだけで十分です。重要なのは、ルールを現場が毎日使える言葉に落とし、手順を定刻で回すことです。多くの場合、仕組み自体より運用の徹底が成果を左右します。
30日導入プランで小さく始めて素早く検証
導入時の現実的な進め方は、30日プランが役に立ちます。最初の一週間で通貨ポリシーを文書化し、次の一週間で米国など一市場を対象にUSD表示×USDC受領のテストを走らせます。三週目で返品・返金の細則をCSに展開し、最後の一週間でレポート形式を固めます。テストは一つのSKUから始め、広告の入札単価とコンバージョンの推移、着金コスト、返品時の対応時間を日次で記録します。四週目の終わりに、銀行受取とのコスト差と、カート離脱率の変化を見比べると、意思決定に必要な材料がそろいます。
まとめ
価格のものさしがそろえば、ユーザーは迷いにくくなり、事業も計算しやすくなります。越境ECでは、まず表示通貨と受け取り通貨を一致させ、USDCとUSDTで“現地の見え方”に合わせ、最後にJPYCや円へ日次で集約して“本社の帳簿”に合わせる。換金のタイミングと返金レートの基準を最初に決め、毎日同じ手順で回す。銀行受取の定額コストをデジタルのネットワーク費用へ置き換えれば、為替のブレと受領手数料という二つの痛点は小さくなります。最初の一国、最初の一SKUからで十分です。運用の型を小さく始め、早く検証し、静かに広げていく——それが“やさしい”為替対策の近道です。
▼暗号資産・ステーブルコインに関して話を聞いてみる▼
https://cal.com/gota-ueda-upijc0/60分-mtg
あわせて読みたい