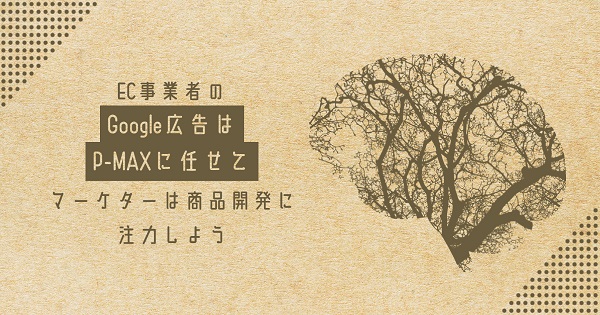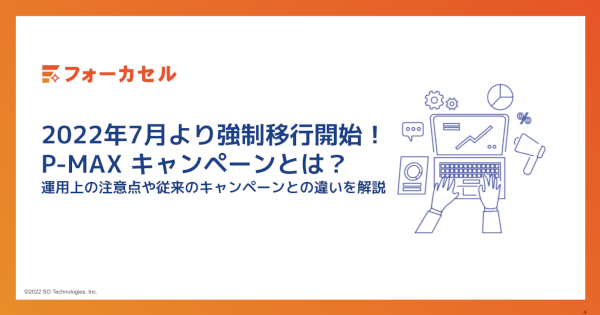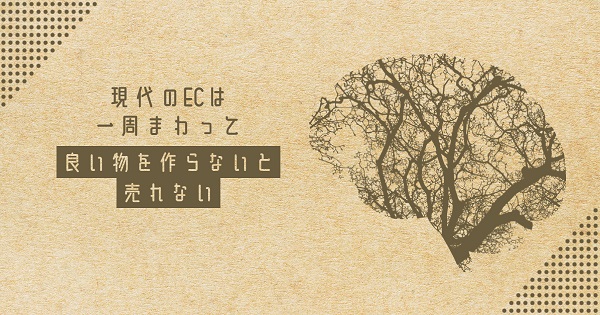P-MAX(Performance Max)は、Googleが提供するGoogle広告の自動最適化型キャンペーンです。検索、YouTube、ディスプレイ、Discoverなど複数のチャネルを横断的に配信できる一方、長らく「ブラックボックス」と言われてきました。 今回は、広告運用の現場で感じてきたP-MAXの課題と、最近のアップデートで見えてきた“攻略の糸口”、そして実際の運用で成果を出すための考え方を紹介します。
佐藤 裕二
アドペグラム
EC企業を中心に、Google・Meta・Microsoftなど複数媒体での広告運用を支援。商品点数が多い総合通販や、単品・定期通販、ブランド系ECまで支援領域は多岐にわたり、粗利率と連動した運用戦略の設計を得意とする。「広告のチカラで、ECの利益構造を変える」をテーマに活動中。
この記事の目次
P-MAXのこれまでの評価と課題
登場当初のP-MAXは、機械学習にすべてを任せる“全自動キャンペーン”という位置づけでした。確かに一定の成果は出るものの、運用者からは以下のような声が多く聞かれました。
- 成果は出るが、なぜ出ているのかわからない
- 学習が不安定で、構成変更でリセットされる
- 配信先やキーワードが見えず、改善余地を見出しづらい
私自身も「運に左右される広告」という印象を持っていました。しかし2025年、状況は大きく変わりました。
アップデートで見え始めた“攻略ポイント”
Googleは段階的に、P-MAXの「中身」を開示し始めました。特に大きな変化は次の2点です。
- クエリの可視化
- どのようなクエリで配信されているか、ユーザー意図が見えるようになりました。この仕様変更によって、除外設定はもちろん、新たなキーワードの発掘も可能になりました。
- インプレッションの多いクエリに特化したアセットグループの作成で成果改善に繋げることもできるようになりました。
- チャネル別レポートの追加
- 検索、YouTube、Display、Discover、Gmailといった配信面別の成果を確認可能になりました。この仕様変更によって「実はYouTubeからの購入が多かった」や、さらに深ぼって「セール動画は購入される一方で、それ以外の動画は購入につながっていない」などの詳細まで分析できるようになりました。
- DiscoverやGmailなどの成果が良い場合、デマンドジェネレーションで配信面を選択して配信をするなども施策として考えることができるようになりました。
これらのアップデートにより、P-MAXは「どのクエリが成果につながり」「どのチャネルが効率的か」を把握できるようになりました。
すると、これまで感覚的に行っていた設計が、データドリブンに検証できるフェーズへと移行しました。
例えば、
- 検索クエリからは「どんな意図で購入しているか」
- チャネル別成果からは「どこに予算を集中すべきか」
が見えるようになり、運用者は学習構造そのものを設計する発想を持てるようになりました。
こうした“見える化”を活かして成果を上げた事例の共通点が、次に紹介する「勝ちパターン」です。
実践で見えた勝ちパターン
複数のEC案件で運用を重ねる中で、成果を安定させるための「勝ちパターン」が見えてきました。
①キャンペーン分割の考え方
目的や商品特性に応じて、学習を分ける設計が有効です。たとえば以下のように構成します。
- 新規獲得用:「新規顧客設定」を使い、顧客以外へのリーチ拡大
- 売筋商品専用:売筋商品のみに限定して売上の最大化
- 商品単価別:高単価商品は別キャンペーンでROASを最適化
これにより、キャンペーンごとの学習方向が明確化し、最適化速度が上がるという効果があります。
②シグナル設定の工夫
検索テーマと顧客データを組み合わせることで、AIが“誰に見せるべきか”をより正確に学習します。たとえば、
- 検索テーマ:「マットレス 通販」「高反発ベッド」など購買意図の強い語句
- 顧客データ:購入者リストやGA4のオーディエンス
これにより、P-MAXが「良い顧客像」を学びやすくなり、配信精度が上がります。
③除外キーワードによる指名対策
P-MAXの課題の一つが「ブランドワード」。新規獲得キャンペーンに自社指名検索が混ざると、数値が過大評価されることがあります。そのため「ブランド名を除外キーワードに設定」することで、純粋な新規獲得のパフォーマンスを可視化します。
事例1:寝具ECでの改善例
ある寝具EC企業では、もともと検索広告のみで運用していました。
P-MAX導入後、月間CV数が2.3倍・ROASが25%改善という結果を得ました。
ポイントは以下の2点です。
- 高単価商品のみでキャンペーン分割
- 売筋商品のみでキャンペーン分割
商品数が6,000を超えるサイトだったので、全商品を1つのキャンペーンで配信すると「インプレッションの出ない商品」があったり、「売筋商品のインプレッションが少ない」などの問題が発生するため、売りたい商品をメインにキャンペーンを分けて配信を実施。結果、CV数が安定しROASの改善にもつながりました。
事例2:高級インテリアECでの改善例
ある高級インテリアEC企業では、もともと店舗販売のみで、広告も店舗への来店促進目的で運用していました。
ECの開始と同時にP-MAX導入、月間CV数が20件・ROAS800%という結果を得ました。(目標:CV数10件/ROAS500%)
ポイントは以下の2点です。
- 顧客データを使用したシグナル設定
- 指名ワードの除外
元々店舗での知名度が高かったため、指名ワードは「店舗を探している人が多い」という想定で除外を実施。結果、CVRが高くなりROASも安定しました。
限界と注意点
P-MAXのブラックボックスは完全に解消されたわけではありません。AIの学習ロジック自体を操作することはできず、私たち人間の仕事は「AIが正しく学ぶ環境を整えること」にあります。
つまり、これからの広告運用者は「設定をする人」ではなく「学習を設計する人」へと役割が変化していくでしょう。
今後の展望
今後は、AIによる自動生成クリエイティブや、ユーザー意図をリアルタイムで読み取る“AIモード”での広告配信など、さらに自動化が進むと予想されます。
ただし、AIが最適化を担っても、「誰に・何を・どう届けたいか」という戦略設計は人間にしかできません。
P-MAXを正しく理解し、事業戦略と同期させること。それが、EC成長を支える広告運用に求められる新しい力だと感じています。
さいごに
P-MAXをはじめとする自動化の進化は、EC広告運用の在り方そのものを変えつつあります。“人がやるべきこと”は減っていくように見えて、実は「学習を設計し、利益を最大化する判断」はこれまで以上に重要になっています。
アドペグラムでは、今回の記事のような広告運用ノウハウや最新トレンドを発信しています。「自社ECのP-MAXをもっと活かしたい」「広告の数字を利益構造に結びつけたい」と感じた方は、ぜひ下記サイトも併せてご覧ください。
あわせて読みたい