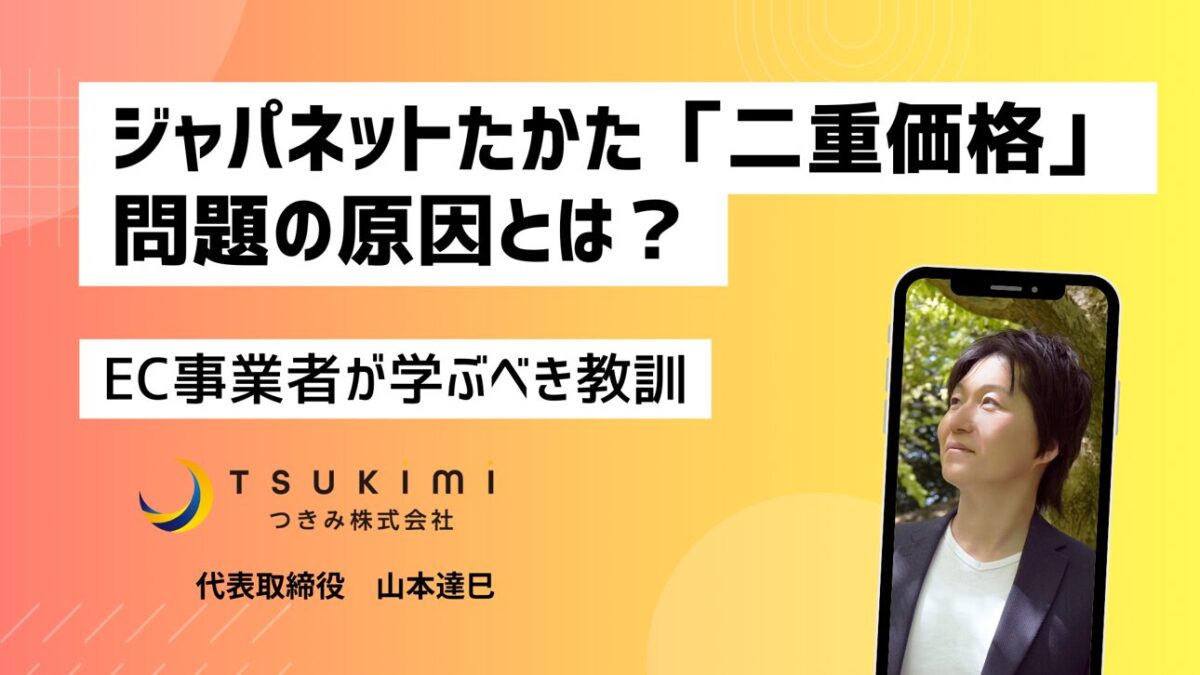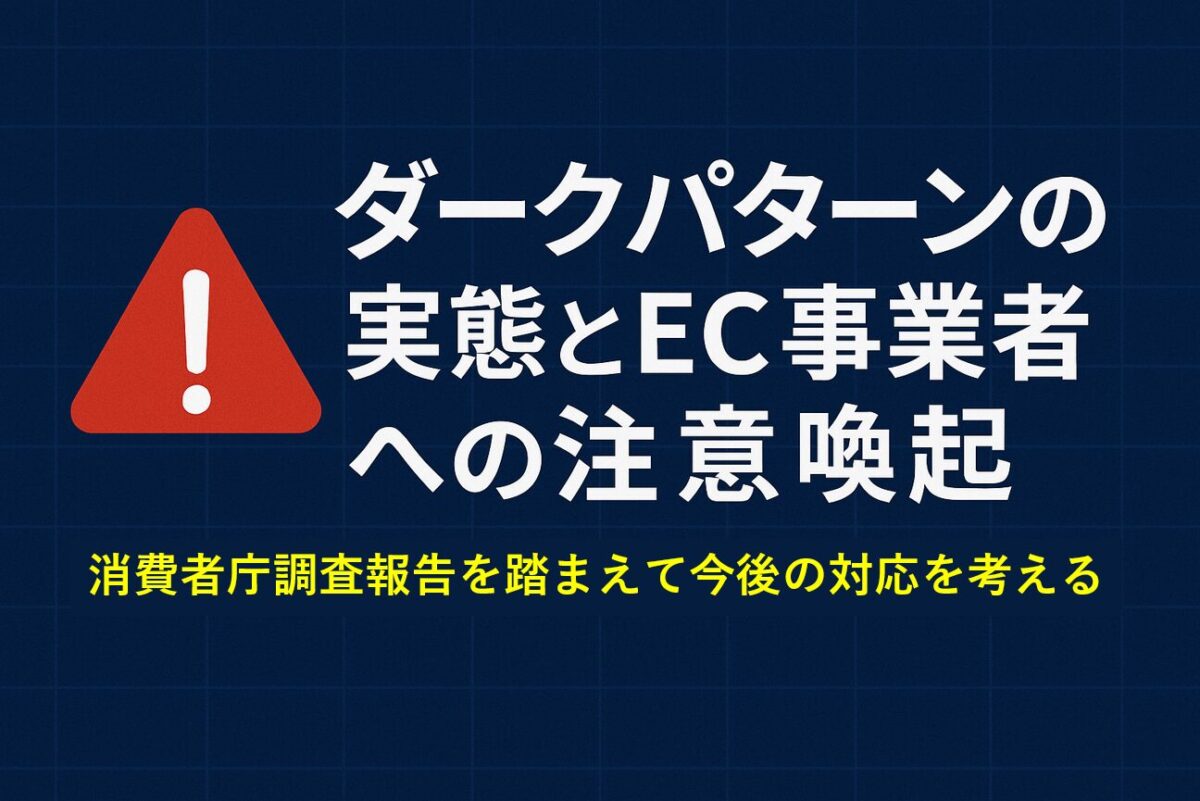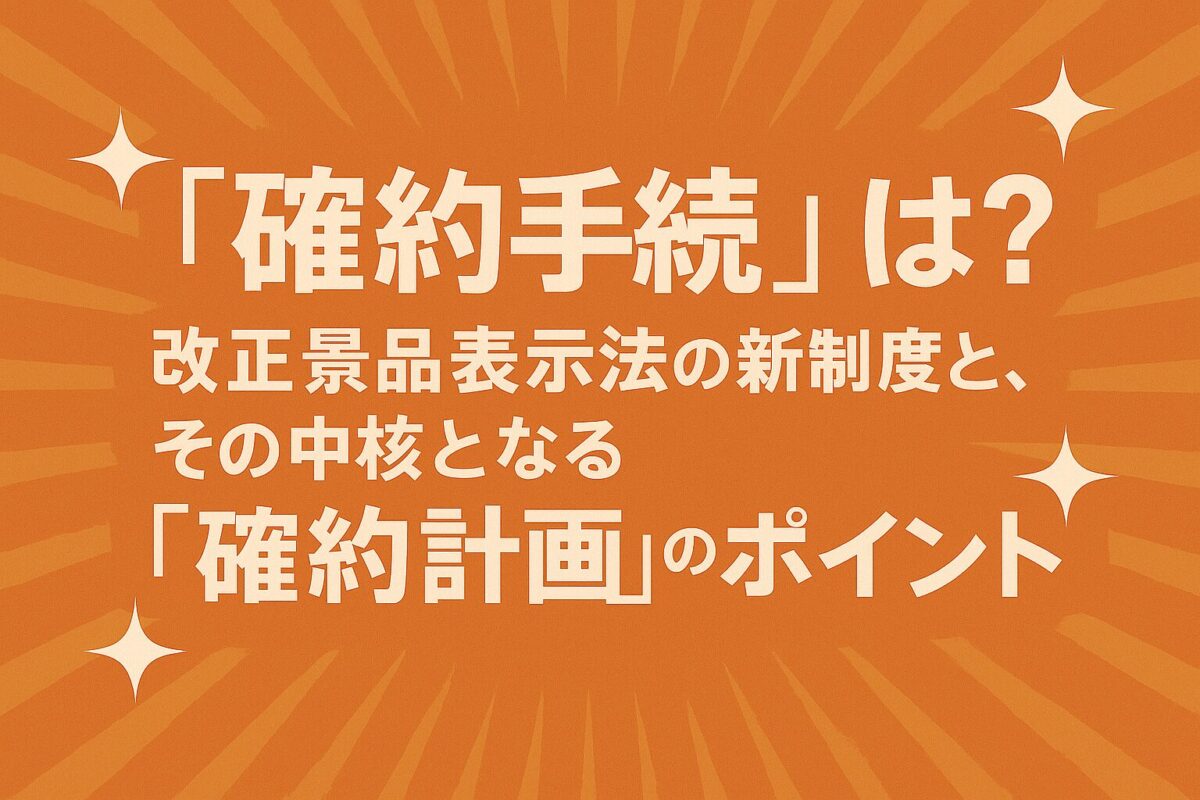
この記事の目次
新たに始まった「確約手続」とは
2024年10月1日、改正景品表示法に基づく「確約手続」が施行されました。これは、事業者が景品表示法第4条(不当表示の禁止)や第5条(不当な取引条件表示の禁止)に違反する疑いがあるときに、行政処分を受ける前に自ら問題を是正するための制度です。
制度導入の背景
近年、ECやデジタル広告の拡大に伴い、消費者が誤認するおそれのある表示や、実態と乖離した口コミ・レビューの利用などが相次ぎ、景品表示法違反の調査件数が増加しています。従来は違反が確認されれば措置命令や課徴金納付命令といった「事後的な制裁」が中心でしたが、この方法では是正までに時間がかかり、被害が拡大する懸念が指摘されていました。
確約手続は、こうした課題に対応するために導入されました。事業者が自主的に是正計画(確約計画)を作成し、消費者庁の認定を受けることで、行政と事業者が協調して問題を迅速に解決し、消費者の合理的な選択を守ることが狙いです。
従来制度との違い
- 従来:違反認定 → 措置命令/課徴金命令 → 公表
- 確約手続:違反疑い段階 → 通知 → 事業者が是正計画を提出 → 認定 → 公表(行政処分なし)
従来の流れと異なり、確約手続では違反の「疑い」の段階で是正を促せるため、消費者被害の拡大防止と行政リソースの効率的な活用につながります。
とりわけEC・広告業界では、インフルエンサーマーケティングやアフィリエイト広告、定期購入の返金条件表示など、表示をめぐるトラブルが後を絶ちません。確約手続はこうした分野における「事後処分リスク」を和らげる一方で、自主的に是正・再発防止できる体制を持っているかどうかが企業評価に直結する時代が到来したことを意味します。
制度の概要 ― 確約手続の仕組みと対象
手続開始の条件
確約手続は、消費者庁が「景品表示法に違反する疑いがある」と判断した場合に開始されます。違反疑いのある行為(違反被疑行為)について、消費者庁が「確約手続に付すことが適当」と考えると、事業者に対して「確約手続通知」を発出します。通知には次の内容が記載されます。
- 違反被疑行為の概要
- 適用されると考えられる条項
- 違反の影響を是正するために必要な措置の方向性
ここで重要なのは、通知は違反を認定するものではないという点です。あくまで「疑い」の段階であり、事業者に自主的是正の機会を与えるためのステップとなります。
申請にあたって
通知を受けた事業者(被通知事業者)は、60日以内に「確約計画」の認定申請を行うことができます。確約計画には、是正措置や影響回復措置の具体的な内容を盛り込む必要があります。
また、申請後であっても追加資料の提出や計画の変更が認められており、柔軟な対応が可能です。一方で、申請を取り下げれば調査が再開されますが、それ自体を理由に不利益な扱いを受けることはないとされています。
認定の要件
消費者庁が確約計画を認定するには、次の2つの要件を満たす必要があります。
- 措置内容の十分性
- 違反被疑行為やその影響を是正するのに足りる内容かどうか。
- 過去の措置命令での対応内容が参考にされる。
- 措置実施の確実性
- 実際に計画が履行される見込みがあるか。
- 被害回復の方法、資金の確保、周知方法、実施期限が具体的に示されているか。
確約計画が認定されると、当該行為については措置命令や課徴金命令といった法的措置は適用されません。ただし、これは違反そのものを認定したことを意味するのではなく、あくまで自主的是正を前提に行政が処分を行わないという扱いです。
EC・広告に関わる具体的論点
- レビュー表示:投稿者が実利用者であるか否か、編集・依頼の有無をどう開示するか。
- 定期購入契約:表示内容と契約条件の齟齬がないか。
- 広告表現:効果や割引条件の裏付け資料を備えているか。
こうした領域は、確約手続の対象となりやすく、事業者が自主的是正を通じて迅速に対応する余地が広がった分、平時からの備えが一層問われることになります。
また、確約手続の対象外となるケースも明示されています。
- 過去10年以内に法的措置を受けた事業者
- 根拠がないと知りつつあえて虚偽表示を行ったなど、悪質かつ重大な違反
この場合は、迅速な是正を期待できないため、消費者庁は通常通りの行政処分に移行します。
確約措置の典型例 ― 事業者が取り得る是正の形
確約計画の中心となるのが「確約措置」です。これは、違反被疑行為やその影響を是正し、同様の行為を再発させないために事業者が実行する具体的な取り組みを指します。消費者庁が認定するかどうかは、措置内容の十分性と措置実施の確実性の両方を満たすかどうかにかかっています。
運用基準では、以下のような措置が典型例として示されています。
①違反行為の中止
まず基本となるのは、現在行われている違反被疑行為を速やかにやめることです。例えば、誤解を招く価格表示や、根拠のない効果をうたった広告を直ちに停止することが該当します。
②消費者への周知徹底
誤認リスクを防ぐためには、過去に行った表示が不適切であったことや、その是正内容を消費者に伝えることが求められます。ウェブサイトやメール、プレスリリースなどを通じて、どのような表示に問題があったのかを周知することが措置の一つとなります。
③コンプライアンス体制の整備
再発防止に向けて、内部体制を強化する措置も重視されます。
- 表示や広告のチェックフローを明文化する
- 担当部署や役員への責任分担を明確にする
- 従業員研修を行い、法令遵守意識を徹底する
といった取り組みが盛り込まれることが想定されています。
④履行状況の報告
確約計画は「書くだけ」では不十分です。措置を実際に履行していることを示すために、事業者自身や第三者機関が消費者庁に報告する仕組みを設けることが要件となります。報告時期や回数は計画内容に応じて設定され、履行を担保する役割を果たします。
⑤消費者への被害回復
返金や商品交換など、被害を受けた消費者に直接対応する措置も有効です。例えば、定期購入で誤解を招いた契約条件があった場合、返金や無償解約を実施することが「措置内容の十分性」と「実施の確実性」の両面で評価されます。
⑥契約や取引条件の見直し
違反の要因が外部委託先にある場合や、取引条件自体に齟齬がある場合は、契約の見直しも必要です。
- アフィリエイトASPとの契約を改定する
- 調査会社に依頼する調査の方法を修正する
- 表示内容と契約条件を一致させる(例:返金条件を明文化)
といった対応が考えられます。
⑦典型例の活用と実務上の留意点
運用基準は、確約措置の典型例を示しつつも「これらに限られない」としています。事業者は、自社の違反疑いの内容に即した措置を組み合わせて計画を策定することが求められます。
EC・広告業界では特に、
- ステルスマーケティングの投稿表示の停止・周知
- サブスク契約条件の修正と返金対応
- 社内チェック体制の強化と第三者監査の導入
といった措置が実務上よく想定されるでしょう。
確約計画が認定された企業とその対応策
それでは前段の是正の形を参考に、実際に確約計画が認定された企業がどのような対応策を取ったのか実例をもとに見ていきましょう。
▼参照
caname(かたぎり塾):https://www.caa.go.jp/notice/entry/041208/
株式会社イングリウッド(三ツ星ファーム):https://www.caa.go.jp/notice/entry/043618/
味の素&イングリウッド(冷凍宅配食「あえて、」):https://www.caa.go.jp/notice/entry/043617/
株式会社LAVA International(フェイシャル専門サロンDanjoBi/MUQU):https://www.caa.go.jp/notice/entry/043369
表からわかるように、各社とも違反行為の中止と消費者への周知徹底、再発防止策と報告体制の整備が基本となっており、被害回復措置(返金)の有無が事案に応じて異なります。また、典型例の活用では、それぞれの違反内容に応じた措置を組み合わせて計画が策定されていることがわかります。詳細は参照元のリンク先をご覧ください。
EC・広告業界における実務的示唆
確約手続は、景品表示法全般を対象とする制度ですが、とりわけECや広告を展開する事業者にとって影響が大きい制度です。表示や広告の透明性をどう確保するかが、今後の事業運営に直結してきます。
①ステルスマーケティング対策
SNSやインフルエンサーを活用したプロモーションでは、投稿が「広告」であることを消費者が明確に認識できるようにする必要があります。
- 商品提供や報酬の有無を明示しているか
- 投稿内容を事業者が編集・指示していないか
- 「あたかも利用者の自発的な感想」のように見せていないか
こうした点を適切に開示できていなければ、ステマと判断されるリスクが高まり、確約手続の対象となる可能性があります。
②レビュー・口コミ表示の透明性
ECサイトでのレビューや口コミ表示も要注意です。
- 実際に購入・利用していない人のレビューを掲載していないか
- 提供条件(サンプル提供やモニター募集)が消費者に伝わっているか
- 一部のレビューを選別・改変して掲載していないか
消費者の合理的な判断を阻害する表示は、典型的な「違反被疑行為」に該当しやすいため、事前にチェック体制を整えることが重要です。
③定期購入・サブスク商材の表示
近年トラブルが多い定期購入やサブスクリプションサービスでは、表示と契約条件の一致が不可欠です。
- 「いつでも解約可能」と表示しながら実際には条件がある
- 返金保証をうたいながら例外規定を契約に記載している
といった齟齬があると、取引条件表示の不当表示として指摘される恐れがあります。確約手続では「取引条件の変更」も典型的な是正措置とされており、契約の透明性確保が重視されます。
④広告表現の裏付け
優良誤認表示を避けるためには、広告でうたう商品効果や割引条件に客観的な裏付け資料を用意しておく必要があります。特に「世界一」「最安値」「医師推薦」といった強い表現は、確実な根拠を示せなければリスクが高まります。
⑤内部体制とガバナンス
確約手続の認定要件の一つに「再発防止策」が含まれるため、社内体制の整備が不可欠です。
- 表示・広告チェックを行う部署や責任者を明確化
- 役員・従業員向け研修の定期実施
- 外部委託先(ASPや広告代理店)との契約見直し
これらを整備しておくことで、違反疑いが生じた際に迅速に確約計画を策定でき、リスク対応力が高まります。
⑥レピュテーションリスクへの備え
確約計画が認定されると、その概要や事業者名が公表されます。これは「違反認定ではない」と注記されるものの、企業名が消費者や業界関係者に広く知られることは避けられません。一方で、誠実な是正対応を行う姿勢を示すことは、逆に信頼回復の契機ともなり得ます。広報・法務部門が連携し、事後のブランドマネジメントを見据えた対応が必要です。
チェックリスト:EC事業者が備えるべき対応
確約手続の導入により、EC事業者は「問題が起こってから是正する」のではなく、「事前に体制を整備して違反を未然に防ぐ」ことが一層重要となります。本章では、EC事業者が実務で確認すべきポイントをチェックリスト形式で整理しました。
1. 広告・表示の事前チェック体制
- 広告に使用する効果や数値に、客観的な根拠資料を保管しているか
- 「世界一」「最安値」「医師推奨」など強い表現に十分な裏付けがあるか
- 割引・キャンペーン表示に、適切な比較対象や条件を明示しているか
2. ステルスマーケティング防止
- インフルエンサーやレビュワーに商品提供や報酬を支払う際、広告であることを明示しているか
- 投稿内容を事業者が編集・指示していないか
- 「自然な口コミ」と「広告」が区別できるように表示しているか
3. レビュー・口コミ管理
- 実際に購入していない人のレビューを排除できる仕組みがあるか
- サンプル提供やモニター参加の条件を明確に開示しているか
- ネガティブなレビューを不当に削除・改変していないか
4. 定期購入・サブスク契約
- 「いつでも解約可能」と表示する場合、実際に条件なしで解約できるか
- 返金保証の表示と契約条件が一致しているか
- 初回限定価格や自動継続の条件をわかりやすく明記しているか
5. 再発防止策と内部体制
- 表示・広告のチェックフローを文書化しているか
- 法務・コンプライアンス部門とマーケティング部門の連携が取れているか
- 外部委託先(ASP、代理店など)との契約で表示責任を明確化しているか
- 従業員向けの定期的な研修を実施しているか
6. トラブル発生時の対応フロー
- 消費者庁からの調査通知に対応する窓口を明確にしているか
- 60日以内に確約計画を申請できる体制があるか
- 被害回復措置(返金、周知、契約変更など)の準備があるか
- 確約計画の認定が公表された場合の広報対応を想定しているか
このチェックリストを日常的に確認することで、EC事業者はリスクを低減できるだけでなく、いざというときに確約手続を活用して迅速に是正措置を講じることが可能になります。結果として、消費者からの信頼性向上にもつながります。
まとめ
確約手続の導入は、従来の「摘発・命令型」から「協調・是正型」へと執行手法を広げる大きな転換点です。景品表示法の執行がより柔軟になることで、事業者にとっても「問題が起こってから厳罰を受ける」だけではなく、「自主的な是正を通じて早期に信頼回復を図る」選択肢が開かれました。
制度導入がもたらす変化
- 透明性の確保が競争力に直結
消費者の信頼は、商品やサービスそのものと同じくらい重要な価値となっています。確約手続を背景に、表示や広告の透明性を高めることが事業者の競争力に直結します。 - リスクマネジメントからブランディングへ
違反疑いが生じても、確約計画を迅速に策定・認定されることで「誠実に対応する企業」としての評価を得られる可能性があります。法令対応が、単なるリスク回避にとどまらず、ブランディングの一部となる時代が来ています。
EC・広告事業者に求められる姿勢
- 事前対応の徹底
日常的に広告表現や契約条件を点検し、違反の芽を摘む体制を整えること。 - 消費者視点での運営
「表示と実態が一致しているか」「消費者が誤認しないか」を常に検証すること。 - オープンなコミュニケーション
消費者庁からの調査や通知があった際は、防御的になるのではなく、積極的に相談・対応を進めること。
確約手続は「罰則を免れる制度」ではなく、「消費者の合理的な選択を守る制度」です。EC・広告業界における信頼は、一度失うと回復に長い時間を要します。しかし、確約手続を前向きに活用すれば、早期是正によって消費者に誠実な姿勢を示すことができ、むしろ信頼を強化する契機になり得ます。
今後は「いかに違反を避けるか」だけでなく、「いかに透明性を示すか」が問われていくでしょう。事業者にとって確約手続は、法務対応の一環であると同時に、企業価値を高める新たなツールでもあるのです。
あわせて読みたい