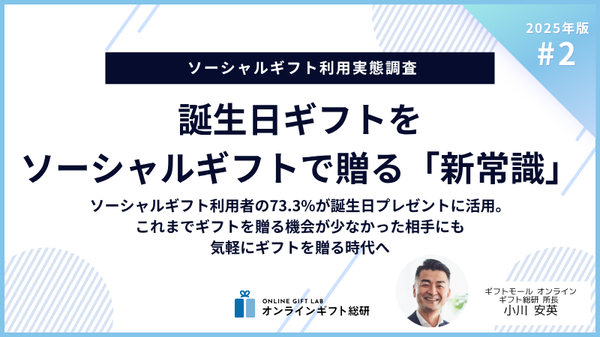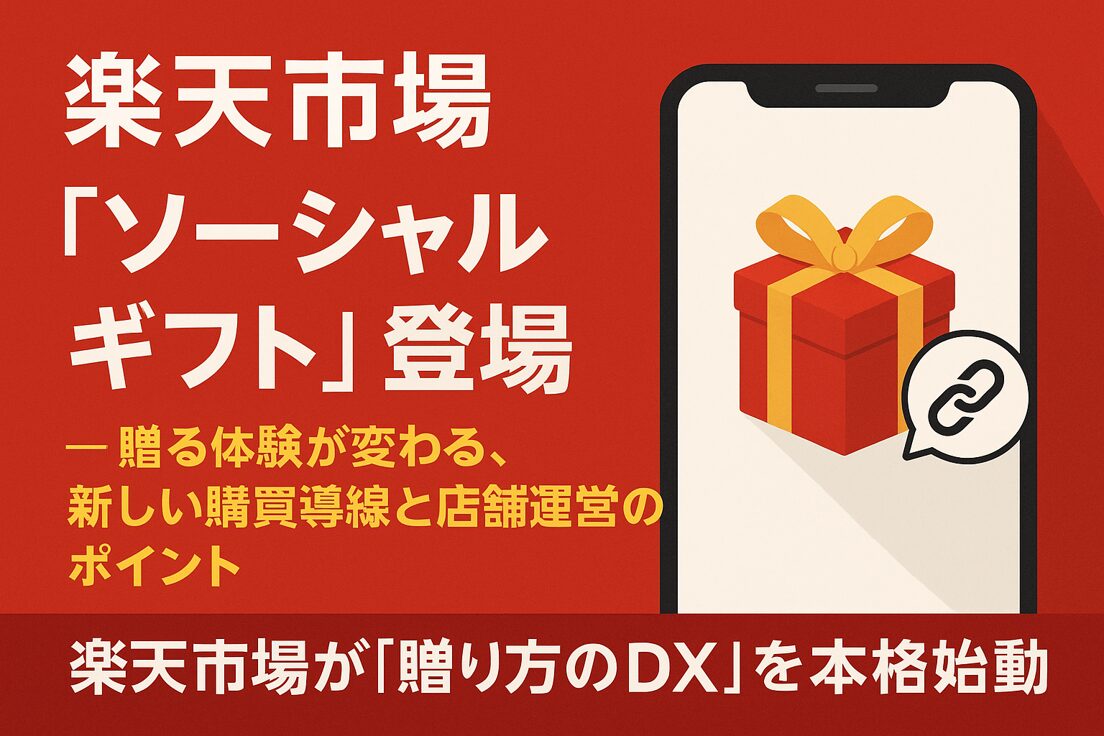
この記事の目次
楽天市場が贈り方のDX「ソーシャルギフト」を本格始動
楽天市場で、住所を知らない相手にもギフトを贈れる新機能「ソーシャルギフト」が登場しました。2026年4月下旬のサービスインに先立ち、2026年1月下旬に商品登録機能がリリースされる予定です。この機能は購入者が決済後に発行される専用URLをSNSやメールで共有すると、受取人が自ら住所や配送希望日を入力できる仕組みです。
これにより、贈り手は「贈りたいと思った瞬間」に購入を完結でき、受け手は自分の都合に合わせて受け取れる。ギフトのDX(デジタルトランスフォーメーション)を象徴する機能と言えるでしょう。
背景には、コロナ禍を経て定着した“非対面での贈り物文化”があります。SNSを中心としたカジュアルなつながりが増えたことで、「住所は知らないけどお礼を贈りたい」「ちょっとした気持ちを形にしたい」といったシーンが広がっています。Amazonの「eギフト」やLINEの「ギフト機能」が若年層に定着する中、楽天市場もついに本格参入。出店店舗にとっては、ギフト市場の拡大と販促の新機会を同時に得られるアップデートとなりました。
想定される利用シーン
ソーシャルギフトが利用されるシーンとして、下記が想定されます。
- SNSやオンラインゲーム上でつながる友人へのお祝い
- 社内キャンペーン・アンケート謝礼などのインセンティブ配布
- ファンコミュニティやインフルエンサー企画のプレゼント発送
これまで「住所がわからないから贈れない」と諦められていたシーンにも対応でき、贈答体験をよりカジュアルかつシームレスにします。
ソーシャルギフトにおいて必要な設定
楽天市場のソーシャルギフトは設定するうえで次の条件が必須となります。
- 登録商品の全SKUの送料が無料になっていること
- 予約/頒布会/定期購入商品でないこと
- 楽天指定のジャンルに該当しない商品※25年11月下旬公開予定
- 価格が100万円を超えない商品
- 役務提供やギフトコードなど配送を行わない商品
- 海外から発送されない商品
- ふるさと納税の返礼品でないこと
販促インパクトと顧客体験の変化
「贈りたい瞬間に完結できる」UXがCVRを押し上げる
ソーシャルギフトの最大の特徴は、購入者の心理的ハードルを取り除く点にあります。ギフトを贈るとき、多くの人が「贈りたい相手の住所がわからない」「手間がかかりそう」と感じて購買を中断します。この“情報取得の壁”を取り除くことで、決済完了率(CVR)の向上が見込まれます。
また、SNS経由での購入は「お祝い」「ありがとう」「おつかれさま」といった感情がトリガーとなるため、購入意欲が感情に直結しやすいです。楽天市場における「ポイント付与」や「レビュー投稿文化」といった仕組みとも親和性が高く、“気持ちのギフト”と“経済的インセンティブ”の両立ができるUX設計といえます。
ギフト商戦の通年化 ― 日常の贈り物市場を狙う
従来のギフト需要は母の日や年末年始など季節イベントに集中していました。しかし、ソーシャルギフトは“住所不要”という性質から、誕生日・送別会・お礼・推し活など、通年で発生する小さな贈り物需要を拾いやすくします。
店舗ページに「住所がわからなくても贈れる」「LINEで気軽にギフトが送れる」といった導線を設ければ、ギフト訴求が年間を通して可能に。特に食品・スイーツ・コスメなど単価3,000円前後の軽ギフト商材にとっては、新規顧客獲得チャネルとして期待できます。
「受取体験」がブランド接点になる
ギフトの受取人は楽天市場の既存ユーザーとは限りません。つまり、受取ページが“店舗との初めての接点”になるケースも多く存在します。
ここでブランドの世界観や信頼感を伝えられれば、受取人がそのままリピーターへと転換する可能性があります。
たとえば、
- 受取完了メールに店舗ページへの導線を設ける
- 同梱チラシでLINE公式アカウントやSNSを案内する
- ギフト包装やメッセージカードをブランドイメージに合わせて設計する
といった工夫で、受け取る体験そのものを「販促の入口」に変えることができます。
ギフトキャンペーンやUGC施策との親和性
「ギフトを贈ってレビュー投稿でポイント獲得」「受け取った人が再購入すると割引」など、既存の楽天キャンペーン機能とも連携しやすい設計です。SNS拡散やUGC(ユーザー生成コンテンツ)を促す文脈でも、贈る瞬間の共有は非常に拡散性が高く、自然な形でブランド認知を広げられます。特に楽天市場のレビュー文化を生かした「ギフトレビューキャンペーン」は、導入初期の販促施策として効果的です。
対応商品と非対応条件
対応しやすい商材
ソーシャルギフトは、購入者が住所を知らない相手にも商品を贈れる仕組みです。そのため、購入手続きがシンプルで、商品仕様が購入時点で確定できるものがスムーズに対応できます。
具体的には、次のようなカテゴリが中心になります。
- お菓子やコーヒー、紅茶などの軽食品
- コスメや雑貨など、贈る相手を選ばない日用品
- 価格帯が2,000〜5,000円前後で、カジュアルギフトとして成立する商品
ソーシャルギフト経由の購入は、URLを通じて贈る形になるため、受取人とある程度のコミュニケーションが伴うケースが多く想定されます。その意味では、冠婚葬祭や内祝いといったフォーマルなギフトに限定されず、日常のちょっとしたお礼やお祝いにも利用できる選択肢が増えたと捉えるのが自然です。
包装や熨斗(のし)対応の有無にかかわらず、気軽に贈っても違和感のない商品がこの仕組みと親和性が高いといえます。
非対応・または運用上の注意が必要な商材
一方で、楽天市場のソーシャルギフトは購入時点で商品仕様が確定していることが前提となります。受取人が後から色やサイズを選択したり、セット内容を変更したりすることはできません。このため、以下のような商品は現時点では注意が必要です。
- サイズ・カラー・種類など、購入時に選択を求めるファッション・雑貨系商品
- 名入れ・刻印など、注文後に加工工程が発生する商品
- 予約販売・受注生産など、発送日があらかじめ固定されている商品
- 酒類や医薬部外品など、年齢確認や法令対応が求められる商品
これらの商品をソーシャルギフトに対応させる場合は、購入者が相手に事前確認できる関係性かどうかや、選択肢をどこまで固定して販売するかといった設計判断が求められます。
対応範囲を広げるための考え方
現時点の仕様では制約があるものの、商品構成や登録方法を工夫することで、対応の幅を広げることも可能です。
たとえば、
- サイズがフリーのファッション小物やアクセサリー
- 色や柄のバリエーションを限定したギフトセット
- オプションを省き、即日出荷に対応できる定番商品
といった商品であれば、ソーシャルギフトとして販売しやすい傾向があります。
重要なのは、「受取人が商品仕様を選べない」という前提を理解したうえで、購入者が迷わず選びやすい構成に整えることです。これにより、購入体験のシンプルさを保ちながら、ギフト需要の新しい層を取り込むことができます。
RMS設定と受注ステータスの変更点
設定箇所と有効化方法
RMSの「店舗設定」>「ソーシャルギフト設定」から利用を有効化できます。商品単位でON/OFF設定が可能で、有効化された商品ページには「ソーシャルギフトで贈る」ボタンが自動表示されます。
また、購入完了後に発行されるギフトURLは購入履歴ページにも反映され、購入者が後からでも確認できるようになっています。
受注データの流れとステータス仕様
ソーシャルギフト注文は、受取人の住所入力が完了するまで「受取待ち」ステータスで保持されます。この段階では配送情報が未確定のため、倉庫連携を行っている店舗は在庫引当処理を保留にする必要があります。
受取人が住所入力を完了するとステータスが「受取情報確定」となり、通常の受注と同様に出荷フローへ進みます。受取期限を過ぎた場合は自動的に「期限切れ」としてキャンセル扱いになり、購入者に返金処理が行われます。
注意点:
- RMSの自動メール設定で「受取情報確定時の通知」をオンにしておく
- 外部倉庫利用時は「受取待ちステータス」の同期方法を確認
- キャンセル後の再販処理を自動化しておく
こうした細かな調整が、オペレーションの安定につながります。
出荷フローと在庫管理のポイント
出荷リードタイムの再設計
ソーシャルギフトでは「購入=即出荷」ではなく、受取入力後に出荷準備が始まります。そのため、リードタイムを“受取確定日基準”で設定するのが適切です。特に賞味期限商品は、受取待ち期間中に期限が迫るリスクを考慮して、バッファを取る設計が求められます。
委託倉庫との連携(修正版)
RSL(楽天スーパーロジスティクス)を利用している店舗では、ソーシャルギフトの受注が「受取待ち」の状態であっても、自動的に出荷処理が進むことはありません。受取人が住所を入力して配送先が確定した時点で、初めて出荷可能な状態になるため、特別な設定変更は不要です。
一方で、外部倉庫や自社倉庫システムを併用している場合は、「受取待ち」注文を在庫引当扱いにするかどうかを社内ルールとして整理しておく必要があります。受取期限(3日・7日・14日間で選択可能)を過ぎると自動キャンセルとなるため、その間の在庫確保・再販処理の扱いをあらかじめ決めておくことで、在庫ロスや誤出荷を防止できます。
トラブル防止とCS対応
よくある問い合わせと対応策
- 「受取URLを紛失した」→再送メールを案内
- 「受取期限を過ぎてしまった」→自動キャンセル処理の流れを説明
- 「住所を間違えた」→発送前であれば変更対応を実施
これらの問い合わせは一定数発生するため、FAQページや自動返信メールにテンプレートを設けておくことで対応コストを削減できます。また、ギフト受取メールに店舗連絡先を明記し、CSとの連携を円滑にする体制を整えておきましょう。
表記上の注意点
「住所不要で贈れる」などの訴求を行う際は、受取期限や返品条件を明示する必要があります。特に景表法上の“誤認防止”観点からも、利用条件や注意事項は商品説明内に明記しておくことが推奨されます。
まとめ ― 贈る体験を「新しい顧客接点」に変える
ソーシャルギフトは単なる新機能ではなく、「贈る瞬間」そのものをビジネス化する仕組みです。店舗にとっては、新規顧客の流入経路であり、既存顧客の購買頻度を高める手段でもあります。
導入時は設定や運用に一定の手間がかかりますが、贈る体験を“ブランド体験”として設計できれば、受け取る人が次のファンになる循環が生まれます。ギフト需要がSNSを軸に広がる今、楽天市場が提供するこの仕組みは、EC事業者にとって「販促」と「体験設計」を両立する新しい武器となるでしょう。
現時点で公開されているイメージ画面などについてはRMSにログインし、店舗運営Naviの情報をご覧ください。
https://navi-manual.faq.rakuten.net/item/000052104
※楽天市場店舗アカウントへのログインが必要です。
あわせて読みたい