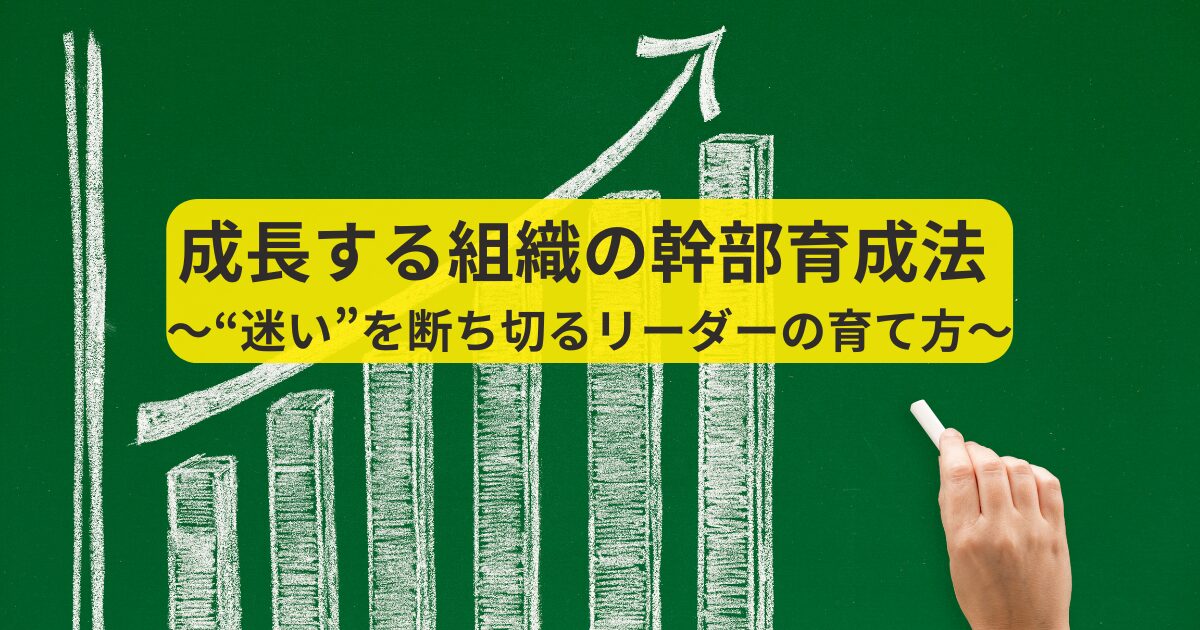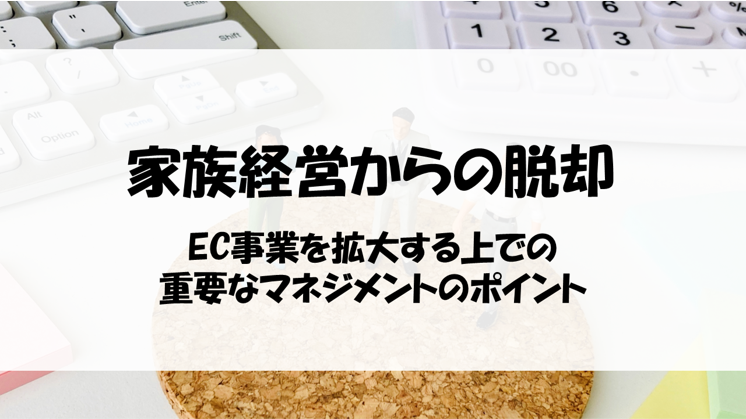株式会社識学
識学は「意識構造学」からとった造語であり、人が物事を認識してから行動に至るまでの思考を構造的に理解し、体系化したメソッドです。
株式会社識学は、このメソッドを応用し、いかなる組織でも生産性向上を実現するための方法を追究しています。
識学について詳しく知りたい方はこちら
https://corp.shikigaku.jp/
この記事の目次
No.2の役割と責任を明確にする
識学では「組織内の役割が曖昧であると、意思決定が混乱する」と考えます。
そのため、No.2の業務領域を明確にし、責任の所在を明らかにすることが必要です。
役割と責任を明確にする具体策
- No.2の業務領域を定める(例:事業統括・組織運営・財務管理など)
No.2の役割定義を明確にすることが重要です。役割定義は事業戦略が正しく表現されているべきものであり、3か月ごとに見直すことが推奨されています。また、No.2の責任と権限を明確にする必要があります。責任と権限は常にセットで考え、バランスを取ることがポイントです。 - 社長とNo.2の業務分担を明確化し、ドキュメント化する
No.2の業務がトップの業務と重複しないよう注意が必要です。責任の重複は避けるべきで、それぞれの役割を明確に分けることがポイントです。 - 成果評価を定量化し、感覚的な評価を避ける
完全結果で目標設定を行います。完全結果とは、期限と誰が"できた"を判断するのかを明確にすることを意味します。評価は結果のみに基づいて行い、経過や努力ではなく、達成された結果のみを評価の対象とします。例えば、売上や利益などの数字、または具体的な成果物の完成度などが評価の基準となります。
自己評価や主観的な評価は避けましょう。評価は他者(上司)が行うものであり、自己評価には価値がないとされているからです。
能力に関係なく誰でも守ることができるよう業務への姿勢のルールは原則として評価項目に含めません。ただし、姿勢が良くない場合は一定水準まで早期に改善する目的で期間を限定し、実施することは問題ないです。
評価項目と評価基準を完全結果で設定し、上司が確認することで、目標の達成難易度を揃えます。
権限を委譲し、No.2を「決定者」とする
No.2が単なる社長の補佐役に留まると、組織の成長が社長に依存してしまいます。識学では 「権限を与えなければ人は成長しない」 とされているため、No.2には意思決定権を持たせるべきです。
権限委譲するための具体策
- No.2に「判断・決定」を義務づけ、相談よりも報告を基本とする
No.2の役割と責任範囲を明確に定義します。これにより、No.2が自身の判断・決定に必要な領域を理解できるでしょう。また、下記の3点を実践することでNo.2に権限を委譲しやすくなります。
●完全結果で目標設定を行います。期限と誰が"できた"を判断するのかを明確にします。
●設定された目標達成のための権限を与えます。責任と権限のバランスを取ることが重要です。
●判断・決定した内容とその結果を報告することを求めます。 - 「社長の意向を確認する」のではなく、「自身で決定し、その結果を報告する」仕組みを作る
社長は、No.2の経過に介入せず、結果の管理に集中します。これにより、No.2の成長を促します。No.2が報告する際は、事実情報を基に行うよう求めます。感情や個人的見解ではなく、客観的な事実に基づいた報告を重視しましょう。 - No.2が決定した事項については、最終的な責任を持たせる
感情を排除し、論理的な判断を徹底する
組織の意思決定において 「感情を排除し、論理とデータに基づいた判断を行う」 ことが重要とされています。
論理的に判断するための具体策
- 判断の際は、データや数値に基づいて意思決定することを徹底する
目標を設定する際に、具体的な数値や達成基準を明確にします。これにより、判断の基準が明確になります。可能な限り、結果を数値化できる指標を用いましょう。例えば、売上や利益などの数字、または具体的な成果物の完成度などを判断の基準とします。
判断の際は、感情や個人的見解ではなく、客観的な事実情報を基にします。これは、データや数値に基づく意思決定につながるからです。自己評価や主観的な評価は避け、他者(上司)による客観的な評価を重視します。これにより、感覚的な判断を避けることができます。結果のみを評価し、経過への介入を避けることで、データや数値に基づく判断を促進します。決定とその結果を報告する際は、具体的なデータや数値を用いて行いましょう。これにより、結果の完了を客観的に行うことができます。 - No.2には「なぜこの判断をしたのか?」を常に説明させる文化を作る
- 組織のルールを優先し、「個人的な価値観」や「感情論」に左右されない体制を整える
社長とNo.2の関係を「ビジネスライク」に保つ
識学では「組織内の上下関係を明確にしなければ、混乱が生じる」 としております。社長とNo.2の関係が近すぎると、組織内に誤った影響力が生まれ、健全なマネジメントができなくなる可能性があります。
No.2との関係を「ビジネスライク」に保つ具体策
- 社長とNo.2の関係は、あくまで「役職の違い」として捉える
重要なのは、個人的な関係ではなく、組織における役割と責任に基づいた関係を構築することです。また、「役職の違い」として捉えることは大切ですが、同時にチームとしての一体感や共通の目標に向かって協力する姿勢も必要です。役職の違いを認識しつつ、組織全体の目標達成に向けて協力する関係を構築することがポイントです。 - 業務外の付き合いを最小限にし、公私の区別を明確にする
- No.2には社長への忖度ではなく、「組織の利益を優先する判断」を徹底させる
組織の目標や戦略に基づいて、適切な基準を設定することが重要です。また、「組織の利益を優先する」ことと「社長の指示に従う」ことが矛盾する場合もあり得ます。そのような場合の対処方法についても、組織ごとに明確なルールを設定することがポイントです。
「修羅場経験」を積ませ、責任を取らせる
No.2が真に成長するためには、実際に組織の中で責任を負い、困難な状況を乗り越える経験が不可欠です。識学は 「責任を持たなければ成長はない」 とされているため、No.2には難易度の高い業務を積極的に任せるべきです。
No.2に責任を持ってもらう具体策
- 重要なプロジェクトやトラブル対応をNo.2に担当させる
- 短期間で結果を求めるミッションを与え、プレッシャーの中で意思決定をさせる
- 失敗した場合も、言い訳を許さず、責任を持ってリカバリーさせる
失敗を責めるのではなく、失敗から学び、成長につなげることが重要です。失敗を恐れるあまり、挑戦を避けるような組織文化にならないよう注意が必要です。
記事のまとめ
「頼れるNo.2」の育成には、以下の5つのポイントが重要となります。
- 役割を明確化し、責任を一元化する
- 権限を委譲し、No.2を「決定者」とする
- 感情を排除し、論理的な判断を徹底する
- 社長とNo.2の関係を「ビジネスライク」に保つ
- 修羅場経験を積ませ、責任を取らせる
これらを徹底することで、No.2は単なる社長の補佐役ではなく、組織の一部を担う責任者として、主体的に意思決定ができる存在へと成長していきます。組織の持続的な成長を実現するためにも、No.2の育成を計画的に進めていくことがポイントです。
識学について詳しく知りたい方はこちら
https://corp.shikigaku.jp/
あわせて読みたい