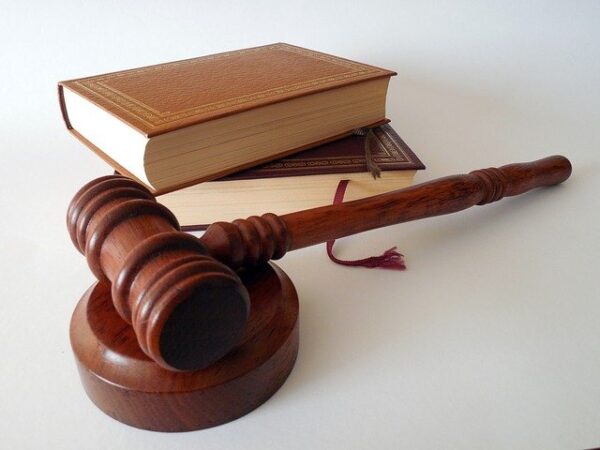2021年(令和3年)8月1日より、薬機法に課徴金制度が導入されます。この制度では、薬機法の対象規定に違反した場合、対象となる売上金額の最大4.5%を納付することが定められています。制度導入でこれまでと変わる点とその背景を解説した上で、今後EC事業者は何に気をつけなければならないのかをまとめました。
この記事の目次
課徴金制度の導入で変わる点
そもそも薬機法とは?基本をおさらい
薬機法(やっきほう)とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。薬機法の主な規制対象は、「医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品」(以下「医薬品等」)となっています。
薬機法は、医薬品等の「品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止」を目的とした規制です。そのなかで特にEC事業者に関わりがあるのが、薬機法第66条第1項の「虚偽・誇大広告等の禁止」という広告規制です。この項では、「医薬品等の名称、製造方法、効能・効果、性能に関する虚偽・誇大な記事の広告・記述・流布の禁止」が定められています。そして、この項が8月1日より導入される課徴金制度の対象にもなっています。
薬機法の広告規制について簡単に説明すると、医薬品等は、広告訴求して良い効果効能、安全性、用法用量等が定められており、それを超える訴求はできないことです。また、薬機法の規制対象外の製品が、医薬品等と誤認されるような広告表現をすることも薬機法違反となるおそれがあります。そのため、医薬品等を扱っていないEC事業者にとっても多いに関係のある法律なのです。
課徴金制度で変わるのは違反後の対応
8月1日から導入される課徴金制度では、薬機法の規制自体に変化はありません。変わるのは、薬機法に違反した場合の行政処分の流れです。
薬機法の広告規制に違反している疑いがある場合、従来は、厚生省または都道府県の調査が入り、状況に応じて行政処分が下されていました。行政処分は、業務改善命令→措置命令→業務停止命令→許可・登録取消の順に厳しくなります。
しかし、課徴金制度導入により、「対象行為に対して課徴金納付命令をしなければならない」という変化があります。つまり、薬機法第66条第1項の「虚偽・誇大広告等の禁止」に違反したことが明らかになった事業者は、原則、必ず課徴金を支払うことになります。課徴金額は、原則、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×4.5%となります。
ただし、課徴金以外の他の行政処分が下される場合や、課徴金額が225万円未満の場合など、課徴金納付の例外はあります。
課徴金制度導入の背景
課徴金制度導入の背景として、まず、薬機法の広告規制に違反する事例が増えていたことがあげられます。
そういった事例に対して、従来は行政処分により対応していました。しかし、広告違反は、薬機法上の業許可を持たない事業者によって行われることも多く、行政処分では十分な抑止策にならない問題がありました。
また、広告違反の多くは経済的利益を目的として行われ、たとえ行政処分が下されたとしても、広告違反により得た経済的利益はそのまま事業者のものになることも問題視されていました。つまり、行政処分が下されるまでに売ったもの勝ち、売り逃げができるような状態だったのです。
そこで、薬機法に先んじて導入されていた景品表示法(以下「景表法」)の課徴金制度や、欧米の事例なども参考にして、薬機法にも課徴金制度が導入されることになりました。
このような背景で導入される薬機法の課徴金制度の目的としては、広告違反により得た経済的利得をはく奪することで、違反行為の抑止を図るところが大きくなっています。
景表法の課徴金制度
景表法では、商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことが規制されています。薬機法の広告規制は、医薬品等に関する広告表現が対象ですが、景表法の規制は、販売されている商品・サービスすべてが対象となります。
広告表現について確認するときは、薬機法と合わせて景表法にも気をつけましょう。景表法でも以前は課徴金制度がありませんでしたが、2016年(平成28年)に導入されました。
EC事業者が気をつけるべきポイント
薬機法の課徴金制度導入によりEC事業者が気をつけるべきポイントは、大きく以下の2つになります。
- 医薬品等を販売するための表現について、承認されている範囲内で表現を行う
- 医薬品等でない商品を販売するための表現について、医薬品等と誤認させる表現をしない
これらは、課徴金制度導入に関わらず、以前からの薬機法の注意点と変わりません。これまで薬機法を遵守してきた事業者であれば、課徴金導入はほとんど影響がないといえます。
なお、広告規制の「広告」は、お金を払って出稿する広告に限らず、商品・サービスを販売するための訴求すべての表現を含みます。つまり、Webサイトやチラシでの商品説明やDM、メルマガ、SNSなど、商品に関する情報発信はすべて含まれます。
課徴金制度導入によって、広告表現の調査が活発になることも考えられます。もし、これまで薬機法についてあまり意識せずに商品を販売してきた場合、課徴金制度導入前に広告表現を見直してみましょう。
まとめ:市場の成長とともに規制が明確になってきた
薬機法や景表法は、EC・通販だけを対象としたものではありませんが、EC市場の成長とともに違反事例が増え、今回の課徴金制度のように時代に合わせた整備が進んでいる面があります。ECの利用率がまだそこまで高くなかったころの広告表現は、完全OKではないものの完全NGともいえない微妙なグレーゾーンの表現はそれほど問題視されませんでしたが、ECが一般的になるにつれてそういった表現のリスクは上がっています。
薬機法の規制対象となるのは医薬品等なので、該当する商品を扱っているEC事業者はまず注意が必要です。特に化粧品は、ECで扱われることが多い反面、表現できる範囲には意外と規制があるため、商品ページなどを作成する際に詳細を確認しましょう。また、健康食品や雑貨などで、知らずに医薬品等の効果効能と誤認されるような表現をしてしまっていることもあるので、薬機法の規制対象の商品を扱っていない場合も、確認は欠かせません。
合わせて読みたい