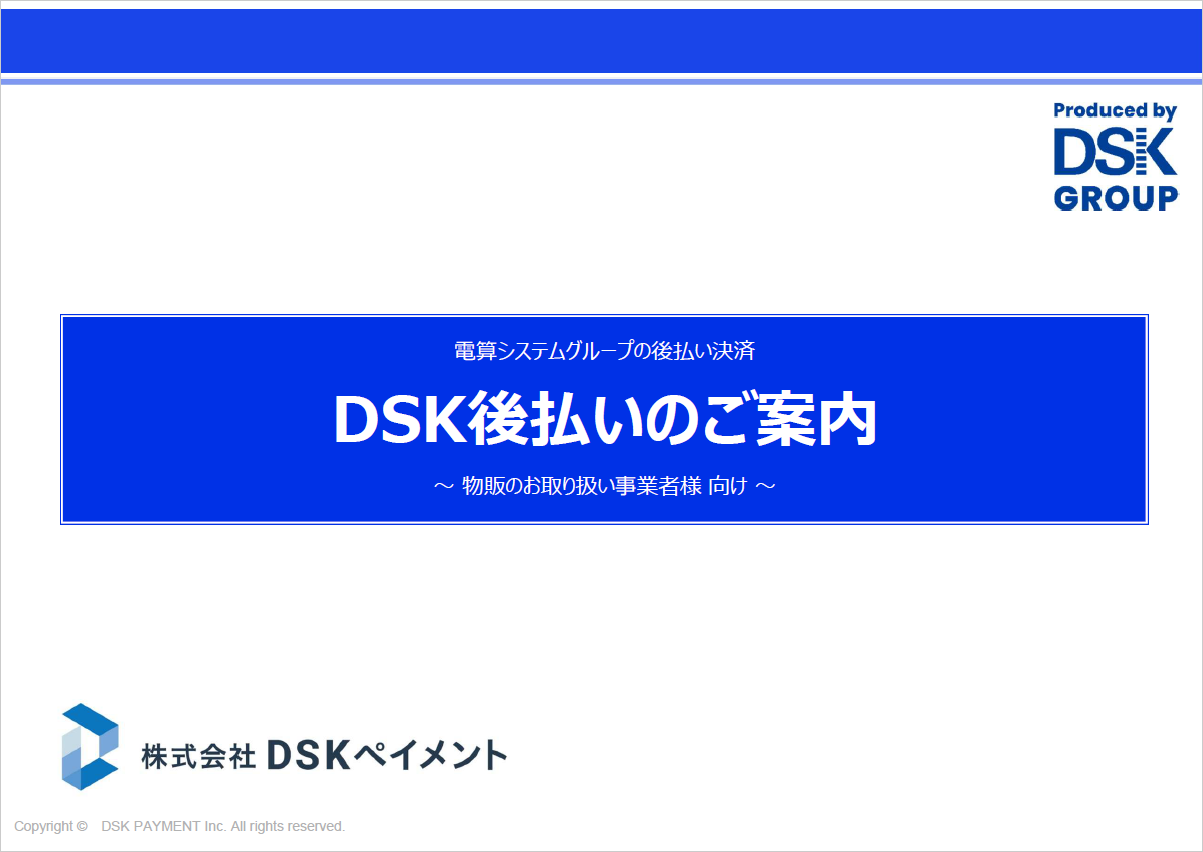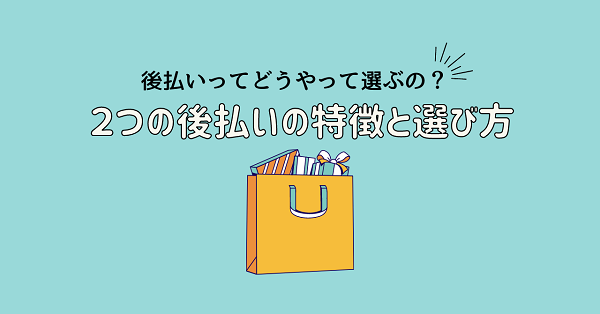
前回のコラムにてコンビニ決済は前払いと後払いについて、ご紹介いたしました。後払いについては、2種類ある旨もお伝えいたしましたが、今回は、さらに詳しく掘り下げていきます。
後払いとは?
「後払い」とは広義で商品やサービスの提供後に支払いを行うことを指します。
そのため、前回お伝えした「自社債権型後払い」も「債権保証型後払い」もどちらも「後払い」ではありますが、近年「後払い」の主流が代行会社に債権を譲渡する「債権保証型後払い」にシフトしつつあります。
通販売上上位300位(2020年)での後払い導入率※1は55%、また債権保証型後払いを導入している事業者は53%と後払い導入事業者のほぼすべてが債権保証型の後払いを利用しています。
※ 参考:日本ネット経済新聞より当社調べ
※1:自社債権型後払い、債権型保証型後払いの両方を含みます。
このような導入率の高さから「後払い」と言えば「債権保証型後払い」という認識が広がっています。
では、後払いを導入するなら「債権保証型後払い」がマストなのでしょうか?
絶対的にそうとは言えません。自社債権型後払い、債権保証型後払いのどちらを選ぶのかはそれぞれの特徴やメリット・デメリットを抑えて判断することが重要です。
「自社債権型後払い」と「債権保証型後払い」の2つは何が異なるのか、またどのような事業者がどちらの後払いに向いているかについて以下の図表でご紹介致します。
自社債権型後払いと債権保証型後払いの特徴
| 自社債権型 | 債権保証型 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 債権リスク | × | ○ | 自社債権型は事業者が不良債権を負担する必要があるが、債権保証型は代行会社に債権を譲渡するため、債権リスクはない。 |
| キャッシュ フロー | △ | ○ | 自社債権型は3ヶ月程度の期間をかけて債権の大半を回収するのに対し、債権保証型は翌月には手数料を除いた現金化が可能。 |
| ノウハウ | △ | ○ | 自社債権型は最低限の与信・督促のノウハウが必要だが、債権保証型は債権管理のノウハウがなくても利用可能。 |
| 業務負荷 | × | ○ | 自社債権型は与信・払込票発行・入金管理・督促など債権管理の一連の作業を行う必要があるが、債権保証型は全て代行会社が行うため、事業者の業務負荷は少ない。 |
| コスト | ○ | △ | 債権保証型は自社債権型の督促費用や人件費を含めた手数料となるため、割高。 ※注文件数や未払い率によっては債権保証型が割安となる可能性もある。 |
| 運用自由度 | ○ | × | 債権保証型では事業者が顧客と支払いに関する直接的なコミュニケーションが取れないため、特定の顧客への特別対応はできない。 |
| 機会損失 リスク | ○ | △ | 債権保証型は代行会社の基準で支払い者の与信審査を行う為、代行会社都合で取り引きが消失する可能性がある。 |
| 顧客育成 | ○ | × | 債権保証型は顧客の入金状況等が確認できないため、優良顧客判断が難しく顧客に合わせたアプローチがしづらい。 |
債権保証型後払いは、利用者の未払いによる債権(貸し倒れ)リスクがないというのが最大の特徴です。
商品の到着後、代行会社から立替払いがされるため、キャッシュフローが早いという点や、請求書の送付や入金確認が不要なため業務負荷がかからない点が自社債権型後払いと比較した上での利点となります。
しかし、デメリットもあります。
自社債権型後払いに比べて手数料が高い点や、与信判断が画一的になってしまう(正常な注文でも条件によっては不正とみなされてしまうこともある)点、事業者側が支払い状況を把握できない点などは注意が必要です。
一方、自社債権型後払いは与信確認や請求書の発行などをすべて自社で管理する必要があるため、その分の業務負担と、未払いが発生した場合のリスクを負わなければなりません。
逆に、購入データを分析し販促等に利用したり、顧客ごとに支払いのタイミングを変えたりできるなど、運用の自由度が高い点は債権保証型後払いと比較して優れた点と言えます。
まとめ:こんな事業者にオススメ
以上の特徴を踏まえると、債権保証型後払いは主にこのような事業者にオススメです。
✔ 債権管理にリソースを割けない
✔ コア業務以外はできるだけ外注化し、事業拡大に注力したい
✔(顧客層、商材、販売方法から見て)未払いとなる可能性が高い
✔ 新規顧客の獲得に注力したい
自社債権型後払いは以下のような事業者様にオススメです。
✔ できるだけ費用を抑えたい
✔ リピーターからの注文が多く未払いの心配がない
✔ 後払い利用者の支払い状況を把握したい
✔ 顧客に合わせて支払い期限を変えるなど独自の運用をしたい
債権保証型後払いが人気となっている理由は、通販事業で売上が伸びるにあたり必要となる業務負担を少しでも減らしたいという事業者のニーズとマッチするためと考えられます。
しかし、事業者のニーズや事業形態、今後の成長戦略によって「自社債権型後払い」と「債権保証型後払い」どちらが適しているのかは変わります。今ご紹介した基準を参考に、様々な判断材料から適切な決済手段を選びましょう。
電算システムの決済ラインナップ
電算システムでは「前払い」のコンビニ決済、「債権保証あり」「債権保証なし」タイプのコンビニ決済を1社で取り扱っている数少ない決済代行会社です。決済のプロが事業者様の状況をヒアリングさせていただいた上で最適な決済をご提案させていただきます。
・DSK後払い(債権保証型後払い)
・コンビニ収納代行サービス(請求書タイプのコンビニ決済)
・クレジットカード決済サービス
・ペーパーレス決済サービス(請求書レスのコンビニ決済)
・口座振替サービス
・送金サービス
合わせて読み多い