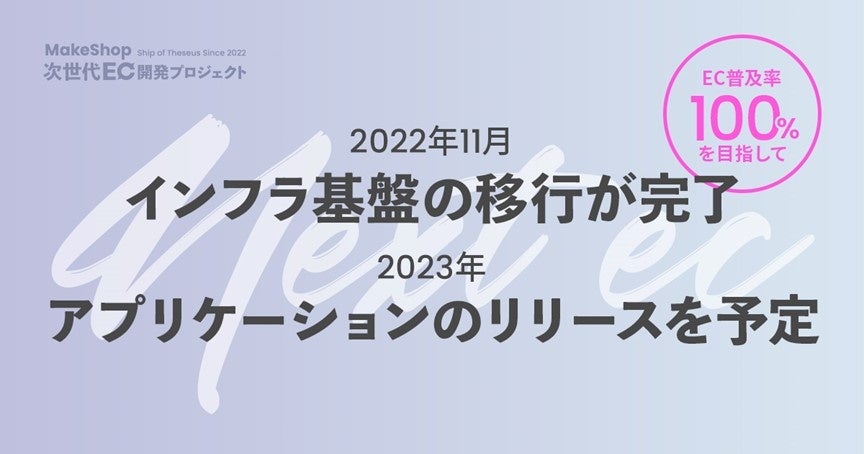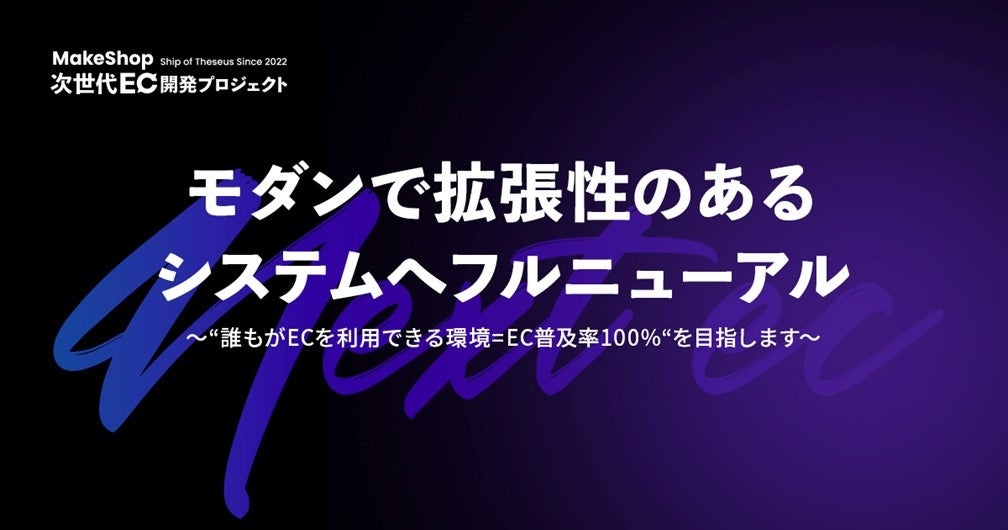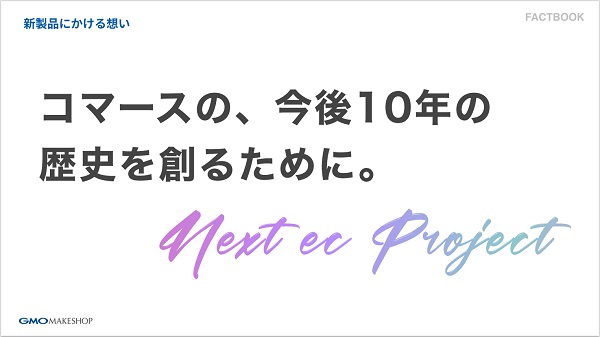
2022年9月15日に開かれた「MAKESHOP DAY」でGMOメイクショップ株式会社(以下、GMOメイクショップ)は『次世代EC開発プロジェクト』を掲げ、ECサイト構築SaaS「MakeShop byGMO」(以下、MakeShop)のフルリニューアルを発表。その後、2022年10月26日に事業戦略説明会で、これまでのEC業界の歴史からMakeShopの今後について語られます。その内容についてまとめました。
この記事の目次
EC業界の歴史から見るMakeShopのこれまでとこれから

事業戦略説明会は代表取締役社長CEOの向畑さんのお話から始まりました。“Commerce for a better future.”をミッションに「大事なバリューであるショップ様のGMV(流通総額)を上げることが全社員の判断基準であり、行動基準として浸透している」と話します。サービスの提供を開始してから18年以上が経過し、継続的な成長と時代に即した機能提供を行っているのは導入しているショップだけでなく、その先にいるエンドユーザーを見据えた行動を社員一丸となって取れていることが窺えます。
GMOメイクショップ創業にかけた想い
1994年にECモール「キュリオシティ」が三井物産を提供したことを皮切りに、楽天市場やYahoo!ショッピングが続きます。一方、自社ECサイトは1999年にEストアーがSaaS型のカートシステムとして最初に提供されたサービスとなります。MakeShopはそれから5年経過した2004年に誕生しました。
当時の時代背景を振り返り、向畑さんの「いつか個人がブランドを持って発信できる時代が来ると感じたが、モールでブランドを表現することは難しい」といった想いから、モールでは民主化のハードルが高いため、誰もが簡単にできるソリューションを提供するに至ったお話をしていました。ECモールはマーケットプレイスごとにルールが整えられており、自社ECサイトと比べ、機能的な制限やUI/UXの表現に限界があるでしょう。そこに自社ECサイトのニーズを感じて誕生したのがMakeShopだと感じられました。
ECの過去・現在・未来

ECが始まった当初は機能や価格が一意なもの、いわゆる型番商品やネットを通じないと買えないようなニッチな商品が購入される傾向が強くありました。現在では、米や水のような日常的に必要な商品や、つくり手や見せ方によって値段が異なるオリジナル性のある商品が売れるようになっています。時代の変遷に合わせて、消費者がオンラインで買い物をすることに慣れ、それと同時にECサイトの機能や物流網が進化したことで、買い物をしやすい商品カテゴリは増えていると感じられます。
しかし、「まだまだECでの買い物は面倒だ」と向畑さんは話します。「ネットで探していたら2時間経っていて、これなら店頭で専門の人に話を聞いたほうが良かったと思うこともあります」とご自身の経験を通して、ECがまだ担いきれていない役割についてお話を続けました。
ECでの買い物体験にはまだまだ課題があります。思いがけない形で商品と出会うセレンディピティの弱さや、商品の大きさや質感、存在感を五感で感じ取りきれない情報量の少なさ、レビューの不正や詐欺ショップの横行など安心安全に買い物をする環境整備、そしてネットでは超えられないリアルとの融合。こういった課題を超えていくことがオンラインでの買い物体験の向上につながるでしょう。
MakeShopの現状と今後の戦略
MakeShopのプロダクトオーナーは2020年に向畑さんから常務取締役COOの古屋さんに変わりました。この章ではGMOメイクショップの社内やMakeShopの状況についてお話されています。
稼働店舗数はCAGR(年平均成長率)13%で順調に推移し、2021年には11,372店舗となっています。また、稼動店舗による流通総額を示すGMVは2021年に2,700億円、2022年は3,000億円となる見通しです。コロナバブルで伸びた数字が一過性のものとならず、継続的に成長できていることがわかる数字となっています。
事業の成長に合わせたシステム提供を目指す中長期的な展望
GMOメイクショップではSaaS型の「MakeShop」とパッケージ型の「GMOクラウドEC」を提供しています。SaaS型は決まったシステムに利用者が運用を合わせる形式ですが、価格を抑えて利用できる特徴があります。その一方で、パッケージ型は利用できる機能やサイト運用の自由度こそ高まりますが、SaaS型と比較すると利用料は高額です。
事業者は売上が拡大するに伴い、SaaS型からパッケージ型やゼロからサイトを構築するスクラッチに移行することがありますが、その移行作業は容易なことではありません。

GMOメイクショップでは「to High to Wide戦略」を掲げ、「ショップの成長(to High)に応じて指数関数的に広がるビジネス要件に応えられるよう、クラウドECでさらなる事業成長を取れるようにしている」と古屋さんは話します。また、「すべてを自社サービスでカバーするのではなく、その道のプロと連携(to Wide)していく」と、パートナーとの今後の連携を広げていく旨を明らかにしました。
to High戦略:課題と解決策
店舗数、GMVが順調に伸びている一方で、機能・性能要件が不足し大型店が解約することもあるようです。そこで、MakeShopのグレードアップ、GMOクラウドECへの積極投資・開発強化を行い、ハイエンド向けのサービスを強化することが発表されました。SaaS型の枠に縛られない自由度の高いサービスへと進化することが期待されます。
to Wide戦略:課題と解決策
現時点で100以上のサービスと既に連携されているMakeShopですが、それでも「新しく生まれるビジネス要件に追いつけていない側面を課題として感じている」と古屋さんは話します。APIを整備・拡充し、APIエコノミーを構築することで、MakeShopとの連携をオープンにできることで変化の早いEC市場でテックリードすることを解決策として掲げています。
「次世代EC開発プロジェクト」の決定事項と方針
最後にMakeShopのリニューアルに関して、具体的な内容を事業推進部部長の石井さんが話しました。
「技術的な負債は成功したサービスに例外なく起こることだ」と話す中、現在のMakeShopが18年の歴史からバランスを取りながら、綿密な計画とシミュレーションの上で新機能をリリースしていることをジェンガに例えながら伝えていました。

この技術的な負債をフルリニューアルによって取り払い、スピーディな機能開発を実現するべく立ち上がったのが「次世代EC開発プロジェクト」です。エンドユーザーが利用するショップのフロント、事業者が利用する管理画面、外部システムと連携するAPIやすべてを支えるインフラに至るまで、システムを構成するすべてを刷新します。
プロジェクトが掲げる2つの約束
この「次世代EC開発プロジェクト」の実現に向けてGMOメイクショップでは2つの約束をしています。
- ショップは止めてはいけない
- ショップに移行の手間・作業を発生させない
「流通額ファーストの中で商売は止まらない」と、この2つの約束を話す前に石井さんがおっしゃっていたのが印象的でした。
この約束を果たすため、今年の4月に一部ショップを対象にβ版をリリース。フィードバックをもらいながら調整を重ね、2023年末にはオープンプラットフォーム化に向けた目処が立っているとのことです。
具体的なリニューアル内容
本説明会で共有が合った具体的なリニューアル内容について一部お伝えします。
オープンプラットフォーム化によるアプリストアの開設
今後、MakeShopではアプリストアを開設し、パートナーが機能提供をしやすくなる環境が構築されます。そうなることで、MakeShopの導入店舗は現状抱えているビジネス課題をスピーディに解決できることになるでしょう。そのために、開発者向けにDevelopersサイトを用意し、APIのリファレンスやサンドボックスの提供がされる予定です。
アプリストアの一般公開は2023年夏を目指して動いているため、他のカートシステムに搭載さているアプリを利用したいと思っていた事業者にとっては待ち遠しいニュースといえるでしょう。
AWSへのインフラ移行
インフラをAWSに移行することで、急激なアクセス増のタイミングでサイトが落ちることや重くなることを避けられます。説明会開催時点で既に56%のショップが移行を完了し、2022年11月29日までに全ショップの移行が完了するとのことでした。
移行済みのショップで、セールのたびに億単位の売上を立てている傍ら、今まではサイトが落ちたり重くなっていたりしました。移行完了後はスムーズに決済を行えるようになり、売上が倍になったそうです。
管理画面のUI/UX改善
管理画面はショップの運営者が毎日触るため、快適な操作性が欠かせません。現在のMakeShopの管理画面は「情報量が多く、字が小さくて(デザインが)今っぽくない」と石井さんが話すほどです。
リニューアル後は、一括処理や検索のしやすさ、一覧画面から編集できるなど、直感的な操作ができるようになっています。デモ画面が公開されていましたが、ストレスなく操作できる様子が映像から感じられ、デザインも現代風に刷新されて見やすくなっている印象を受けました。
「MakeShop byGMO」事業戦略説明会に参加して
売上が伸びて、事業が成長するにつれて、事業者はより良い買い物体験を提供するためにさまざまな打ち手を検討するはずです。そのとき、利用しているカートシステムを理由に実現できないことは、成長の芽を積むことになってしまいます。日本国内ではコロナの影響により、消費者がECに触れる機会が急増しました。環境の変化や消費者の求める買い物体験に適応するため、GMOメイクショップの今回の事業戦略は今後10年先の未来を見据えた大きな一歩になるように感じます。
今後、アプリストアが開設されることでMakeShopがどのように変化し、事業者にとってどのような影響が出るのでしょうか。アプリの活用により新規機能連携がスムーズになる一方で、機能的なカニバリや意図せぬ障害が発生する可能性など、事業者が混乱せずに導入しているアプリの交通整理ができるような環境構築も大切になりそうです。進化を続けるMakeShopの今後の動向から目が離せないでしょう。
合わせて読みたい