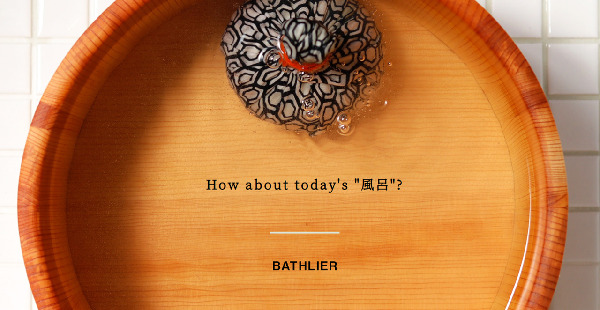5年前までは、商品撮影に関する情報はプロカメラマンのノウハウであり、ブラックボックスになっていましたが、Youtubeやブログ、セミナーなどで有益な情報が多く手に入るようになった今、撮影は社内でできるようになってきました。
ECの普及とともに商品撮影も自社で行うのが一般的になっていますが、実は見た目以上に商品撮影は奥が深く、簡単にはいかないと感じている企業は多いのではないでしょうか。
そこで、今回は商品を売れるようにするための商品画像とは何かという点において、重要なポイントを3つに絞ってお伝えします。
- Point1 商品撮影に重要なのはきれいな写真ではなく、魅力が伝わる写真
- Point2 独自コンテンツで、他社と差別化する
- Point3 商品画像を活かすことを目的に作成する
きれいな写真と魅力が伝わる写真の違い ★Point1
身につけてほしいのは撮影ノウハウではない
こんな経験はないでしょうか。検索を30分くらいしているけど、なかなか自分の知りたい情報にたどり着かない。それは、オンライン上に掲載されている情報は回遊しており、少数派の有識者の情報をみんなで使いまわしているためです。

こちらを見て下さい。情報の流通量は年々爆発的に増えているのにも関わらず、人間の進化は限界が来ているとなると、ほとんどの情報は誰の目にも触れられずに流れているだけということがわかります。
そのため、ネットにあるノウハウを集めるのではなく、物事の本質、商品撮影の本質と向き合って経験を積んでほしいと思います。
きれいな写真で売れるのではなく、売れる商品は写真がきれい+α
とはいえ、基本的なノウハウがないと進みません。カメラの基礎知識や商品撮影の基本は絶対に押さえないといけないです。正直、高単価商材(5万円以上)でもない限り、基礎知識があればそれなりにきれいな画像は作れます。
商品撮影をする際に3つの学んでほしいこと
- カメラの機能と効果を把握する
- 商品撮影の基本を学ぶ
- 成功例ではなく、失敗例を学ぶ
1.カメラの機能と効果を把握する
カメラの基本的な機能は3つ覚えておいておけばいいです
① 絞り
② シャッタースピード
③ ISO
絞りはF値と呼ばれるもので、ピントの合う範囲と画像のきめ細かさ調整できる値です。シャッタースピードは、シャッターの幕を下ろす時間のことで、値の変化で動いている被写体の捉え方が変わってきます。ISOは、デジタル上で明るさを補正できる機能で、値を上げれば簡単に明るく撮影できますが、写真にノイズが入るなどのデメリットがある機能です。
2.商品撮影の基本を学ぶ
商品撮影の基本は3つ押さえればOK
① ライティング
② 背景
③ カメラ知識
まず、ライティングについてですが、被写体に強い光でしっかり当てることが最重要です。知識の浅い方であれば、太陽光を使って撮影することをおすすめします。市販の撮影ボックスなどではライティングの質が良くないケースもあるので、スタンド式のライトなどを別途当てるなどして、補うといいでしょう。
次に、背景についてです。背景は撮影において必ず映り込んでくるものですので、背景を疎かにした写真は、どんなにいいカメラやライトを使ってもいい商品写真にはなりません。背景紙や背景布でしっかり背景を整えたり、ロケ撮影を行ったりなどして、きれいな背景で撮影をしましょう。
③ の「カメラ知識」は先述した3つを抑えれば問題ないです。
3.成功例ではなく、失敗例を学ぶ
これも上記のページで説明していますが、成功ではなく失敗を学ぶ意図としては、成功の概念が1社1社異なるため、A社の成功はB社の成功とは限りません。成功体験を追うのではなく、失敗談や失敗するパターンをしっかり学び短期間で自社独自の成功路線を見つけることが商品撮影においては重要です。
きれい=魅力的とは限らない
この部分を勘違いしてしまうと道が逸れていくのは明らかです。確かにきれいに撮影できていればそれに越したことはありません。ですが、私たちはきれいな画像を作るために商品撮影をしているのではなく、より商品が魅力的に映り、より商品が売れるようにするための手段として、商品画像をきれいに撮影しようとしています。
要するに、顧客のニーズは写真のクオリティ(100を上限)を70から90に上げてほしいわけではなく、商品がいいものかどうかを的確に判断するためにきれいな画像を求めているのです。70のクオリティでもその魅力が伝わればクオリティを無理に上げる必要はありません。
それよりも動画やGIFなどの動くコンテンツの幅を広げる方が魅力は伝わるかもしれません。
画像品質のいい商品写真=売れる商品写真?には、当然ながら疑問がよぎります。
ユーザーのニーズを捉えた商品写真=売れる商品写真であることは忘れてはいけません。
独自コンテンツを作成し、他社と差別化する ★Point2
ユーザーの求めている画像を徹底理解
今、お伝えした通り、ニーズを捉えた商品写真こそが売れる商品写真なので、ユーザーがどんなことを求めて商品ページに入ってきたのかは徹底的に理解をする必要があります。
そのユーザーの心理に寄り添うようにコンテンツを作っていく必要があるため、何となく今までのやり方を踏襲し、ユーザーが求めているものに応えられない画像は時間とコストを無駄にしてしまう危険性があるのです。
動画、360度ビューなどの立体コンテンツ
日本はインフラが整い過ぎているのと、「集団行動」の組織体制、「変化を好まない国民性」も相まって、5年前とほとんど変わらないコンテンツを出していたり、レギュレーションを組んでいたりします。
今、海外では動画で商品をアピールすることが主流とされていて、動くコンテンツをいかに簡単に撮るかというところにテクノロジーでメスを入れているのです。
商品画像を一生懸命に様々な角度から撮影し、3Dのように見せるのではなく、3Dをうまく活用して魅せ方を変えていくことを強くおすすめします。
現にそれを簡単に実現できるシステムや機材は販売されていて、導入を進めている企業も少なくないです。
生活の一部に溶け込ませた魅せ方で使用イメージを持たせる

商品画像といえば、白背景で商品だけが写っている写真ですが、それが一番商品の魅力は伝わるというのはどのECプラットフォーマーも言っていますし、規約に落とし込むくらいデータが物語っています。
商品の魅力が伝わってもそれはモノ(商品や機能)を知っただけで、コト(価値や効果)はわからないです。コトを無意識に感じてもらえるようにするにはどうすればいいのでしょうか。
それは、「生活の一部に溶け込ませた魅せ方で使用イメージを持たせる」ことです。例えば、おしゃれなコップを販売したいのであれば、白背景で商品の魅力を伝え、仮想リビング、仮想テーブルの上にコップを置き商品撮影するといいでしょう。またはそれを使ってコーヒーや紅茶を飲んでいるシーンを動画で撮影するのも手です。それだけで考えなくても使用シーンは浮かべられるでしょう。このコンテンツがあるかどうか、この考え方ができるかどうかでユーザーに与える印象は変わりますし、売上やファンの増加につながります。
商品画像を作ることではなく活かすことが目的 ★Point3
商品画像と商品ページはマーケティングと一緒に考える
ここまでお話ししてきた通り、商品撮影はどのように売るかから逆算をしてどう撮るかが決まるのであって、商品撮影をしてからどう売るかを決めるのは本質的ではありません。
それこそ皆さんも経験があると思いますが、「ここが見たいんじゃないんだよな…」という商品ページが後を絶たないのです。
魅力的な商品画像と商品ページはマーケティングと一緒に考えられたものです。そのことを理解している企業は2020年の大不況の中でも売り上げを伸ばしていますし、むしろ投資を多くしています。
インハウスでできることは自社で行う
簡単にサービスやシステムが作れて、会社も簡単に立ち上げられる現代では、自社で営業をしなくても売れる、経理も外注できる、サポートも外注でき、社内でやることを面倒に考えている企業は多いのではないでしょうか。
社内にあった方がいいノウハウと個人や外部にあっても大丈夫なノウハウがありますが、商品撮影は社内にあった方がいいノウハウだと考えています。
その大きな理由は先述した通り、マーケティングとの連携が命であり、その打ち出すスピードこそが売り上げを左右する時代だからです。技術職とされてきた、商品撮影や画像編集はもはやインハウスでプロ並みの画像をプロよりも2倍から3倍の速度で作成できる程、テクノロジーは発展していることをご存知でしょうか。
投資を継続する
自動撮影システムは500以上国内ユーザー数を誇る、商品撮影とマーケティングやチームをつなぐ撮影システムです。商品撮影から背景切り抜き、リサイズ、形式変換までを一元管理することにより、1人で3人分の働きをします。アナログな商品撮影のインフラにメスを入れられる唯一の手段ではないでしょうか。中小零細企業がユーザーの8割~9割を占め、有名企業も密かに使う現場のミカタです。
2020年の春先からほとんどの企業が投資を一旦凍結してきたことは、身をもって感じていますが、そんな時代だからこそ投資に踏み切った企業も少なくないです。
投資に踏み切った企業のほとんどは現状維持のためではなく、前を向いた積極的な投資をしています。この期間を我慢する期間と捉えた企業と準備期間と捉えた企業の差は今後大きな差を生むでしょう。
アナログな商品撮影、人を選ぶ画像編集によってECサイトやオンラインショップのメイン業務が圧迫されている企業様には、1人で3人分の仕事がこなせるオートリーの「自動撮影システム」がおすすめです。
―自動撮影システムの効果―
■ 業務の圧迫から解放
■ コスト削減
■ 画像品質の向上
■ 商品ページの差別化
■ サイト内コンテンツの質の均一化
■ マーケティングへ注力
=売上UPや利益拡大のきっかけを作れます。
現状を変えたいと考えているなら是非、ご相談ください。
https://www.ortery.jp/
合わせて読みたい