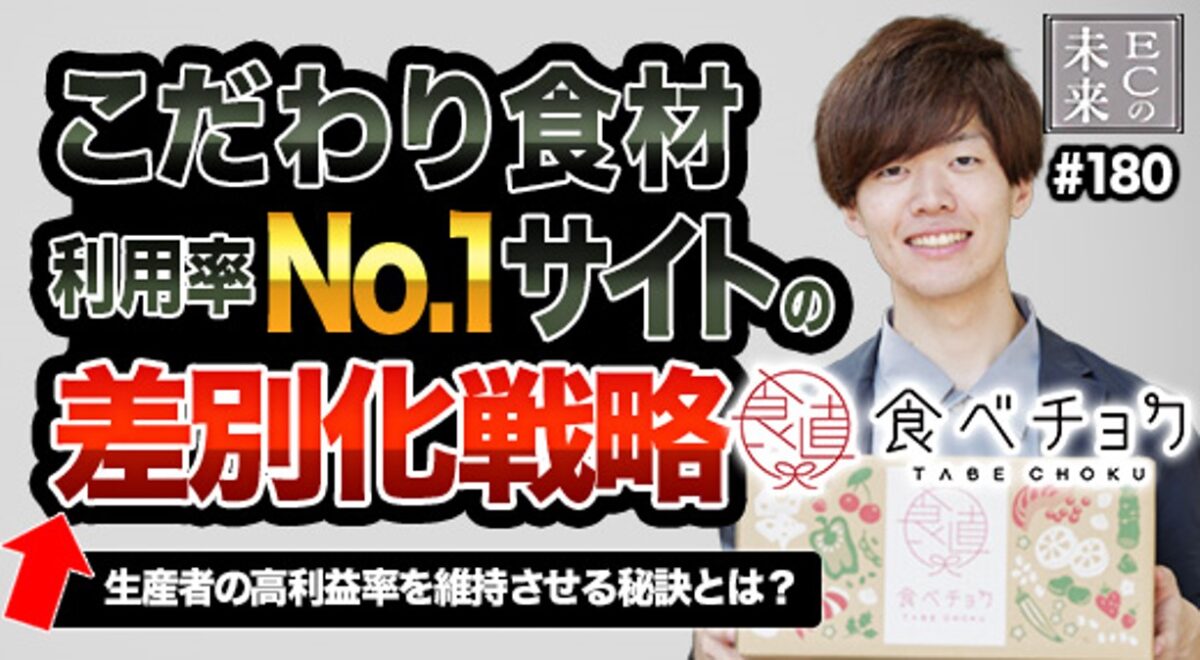【ゲストスピーカー】
松浦 悠介さん
株式会社ビビッドガーデン 取締役
直産EC「食べチョク」
【チャンネルMC】
柳田 敏正さん
株式会社柳田織物 代表取締役
ワイシャツ専門店「ozie(オジエ)」
この記事の目次
美味しいものづくりに時間を割くために
柳田さん:生産者の持ち味や個性を生かしながら販売を広げていく中で、業務の役割分担を促していると伺っています。実際には、どのくらいの規模感の生産者が多いのでしょうか?
松浦さん:一部には企業として大規模に取り組まれている方もいらっしゃいますが、多くは家族経営で、1〜2名ほどの体制で運営されています。
柳田さん:役割分担については、「食べチョク学校」のセミナーで指導されているのですか?
松浦さん:食べチョク学校では、セミナーのほかにもさまざまなサポートを行っています。例えば「食べチョクアワード」では年に一度、お客様からの評価が最も高かった生産者を表彰しています。受賞者に対しては、「どのようにうまく運営しているのか」「人数が少ない中でどのように取り組んでいるのか」といった質問が飛び交い、双方向で活発な意見交換が行われます。そこでは販売のテクニックだけでなく、経営やオペレーションに関する話題も多く挙がります。
柳田さん:一次産業に限らず、EC全般にも言えることですが、パソコンの前に座っていると際限なく仕事ができてしまいます。時間の使い方は非常に重要ですよね。
松浦さん:そうなんです。出品されている方々からは、「本当はもっとやりたいことがある」という声をよく聞きます。例えば、食べチョクは多くのお客様から感想やメッセージをいただけるサービスですが、全てに丁寧に返信したいと思っても、数が多くて対応しきれない。あるいは、同梱する手紙を手書きにするかプリントにするかなど、やろうと思えば無限にやれることがあります。その中で「どこまでやるべきか」というバランスに悩む方が多い印象です。
柳田さん:食べチョク専業の方は対応すべきことが増えやすいかもしれませんが、BtoBとBtoCの両方に取り組んでいる方であれば、双方のバランスを考えることで、効率的な運営もできそうですね。
食べチョクとしては、「価値あるものを適正な価格で販売し、決まった時間で仕事を得られる産直がメインとなる方を増やしたい」という想いがあるのではないでしょうか?
松浦さん:はい。良いものをつくることに時間を使いたいという方は多くいらっしゃいます。こだわりがあるからこそ、「時間があればもっと美味しくできる」とおっしゃるのです。それにもかかわらず、十分な時間を割けないという課題があります。
私たちがより高単価で、効率よく販売できるようサポートできれば、その分“美味しいものづくり”に時間を充てられるようになります。それこそが、食べチョクが目指している姿です。
何度も選ばれるために。負担をかけずに発信できる仕組みづくり
柳田さん: 無農薬にする、特殊な作物を栽培するなど、農家の方々はさまざまな工夫をされていますよね。その工夫こそが差別化であり、ブランディングにつながりますが、それをアピールするのが苦手な印象があります。
お客様にしっかり伝われば、多少価格が高くても購入してもらいやすいと思いますが、小売の経験がない方にとってはハードルが高いのかもしれません。良いものを作っても選ばれないというのは、大きな課題だと感じています。
松浦さん:生産者が持つ魅力を引き出すために、私たちは“ヒントを渡す”ことを大切にしています。商売をするのは生産者自身ですから、私たちが介入して形を変えるのではなく、あくまできっかけを提示し、それぞれの生産者が自分なりに実践できることを試してもらいたいと考えています。
「食べチョク」には「レシピ」という機能があり、いわゆる“農家飯”“漁師飯”を紹介できます。生産者にとっては日常の食事でも、消費者から見ると興味深い情報です。そうした生産者本人が気づきにくい魅力を発信できるよう、機能やキャンペーンを提供し、お客様からの反応を得られる場を設けています。
マーケティングや販売には一定のセオリーがありますが、私たちが“正解”を知っているわけではありません。本来の魅力を最大限に発揮できるようサポートすることが、私たちの役割です。
柳田さん:大規模に展開している生産者であればマーケティングに注力できますが、家族経営など小規模な場合は、いかに“らしさ”を出すかがポイントになりますね。これは農業に限らずあらゆる商売に共通することで、特色をどう表現するかが重要だということが、生産者に伝わると良いですね。
松浦さん:しっかりと買っていただくためには、リピートが非常に重要です。日本市場が縮小していく中で、購買者数が減少することを踏まえると、一人のお客様に長く使ってもらい、繰り返し買ってもらうことが不可欠です。
ネット通販事業者が多数ある中で、再購入してもらうには“非常に良い体験”が必要です。その体験をつくり、生産者にファンがつく取り組みを進めていかなければ、永遠にマーケティングを続けることになってしまいます。リピートしてもらえるようなコミュニケーション、商品づくり、売り場設計、写真の撮り方などを、「食べチョク」として支援していきたいと考えています。
柳田さん:松浦さんのお話は、農業だけでなくECや物販全体にも共通する内容ですね。広告効率が下がる中で、いわゆる“ファンマーケティング”の重要性が高まっています。とはいえ食品は移ろいやすく、買いやすい反面、リピーター化が難しいという側面もあります。
松浦さん:そこは食べチョクとしても課題を感じている点です。一方で、非常に高いリピート率を実現している生産者もいらっしゃいます。例えば栃木県の養鶏家は、「どういうお客様がリピートするのか」「どんな工夫をすれば選ばれるのか」を熱心に研究されています。もちろん卵そのものも非常においしいのですが、その上で“リピートされる仕組み”を追求している姿勢には、私たちも学ぶことが多く、身が引き締まる思いです。
柳田さん:そもそもおいしくないものは売れませんが、今は「おいしさ」だけに注目が集まりすぎている印象です。おいしいものを作り、それを理解してもらうための努力を、忙しい中でどこまでできるかがポイントだと感じます。
どの産業においても、“わかってもらうための努力”がなければファン化は難しい。一定の品数を揃え、リピートしやすい環境を整える必要があります。農業は季節によって出荷できる野菜が変わり、漁業は漁の状況に左右されるなど、コントロールが難しい面もありますが、その中で“どうやって伝えるか”を考え続けることが大切だと思います。
松浦さん:まさにそこが、私たちが産直業界でNo.1の立場として“間に立つ理由”だと考えています。一次産業の現場と、ECやITの知見の双方をフェアに見ながら取り組む必要があります。一次産業の理解がないまま一般的なEC手法を持ち込むと、生産者をないがしろにしてしまう。一方で、生産者側に寄り添いすぎると、消費者が求めていないものを無理に売ることになってしまいます。
そのため私たちは、両者の知見を蓄積し、大切にする会社であろうと努めています。エンジニアやマーケターが多く在籍しており、ITに強いメンバーにとっては難しい場面もありますが、「一次産業を変えたい」という思いをぶらさずに取り組んでいます。橋渡し役としての私たちが間に立つことで、生産者が支払ってくださる手数料に見合う価値をきちんと還元できるよう努めています。
柳田さん:消費者が“何を知りたいか”を理解し、橋渡し役として伝えていくということですね。先ほどの農家飯や漁師飯の取り組みは、とても面白いと感じました。
松浦さん:珍しい料理が多く、しかも短時間で作れるものばかりなので、私たちも興味深く拝見しています。
柳田さん:もっとこうした情報を吸い上げて発信していけると良いですね。一時期、クラブハウスで農家の方々がよく話しているのを聞いていましたが、話を聞いていると、その方の野菜を買いたくなってしまうのです。
農家の方々も、きれいな文章を書いたり写真を用意したりする必要がなく、気軽に話せるようでした。ところが、その内容が熱く、想いが強く伝わってくるんです。クラブハウスには購入機能がないので、「それ買いたいんですが、どうすればいいですか?」という質問をする人もいました。その体験からも、生産者の皆さんは強い情熱を持っていることがわかります。それをいかに商品ページなどに反映できるかが、今後の課題ですね。
最近では、特に若い世代を中心に「文字離れ」が進んでいます。だからこそショート動画が流行しているとも言えます。音声やショート動画は気軽に始めやすいので、生産者との相性も良いと感じます。
松浦さん:私たちも一部でYouTube活用のサポートを始めています。農家や漁師の魅力を音声や動画で引き出せる可能性を感じており、今後しっかり取り組んでいきたいと考えています。
柳田さん:双方向のコミュニケーションであることも大事ですね。音声や動画を見たお客様がどう感じたか、購入後の口コミで「なぜ買ったのか」「おいしかった」といった声が届くと、生産者の方も励みになります。
直接販売の魅力の一つは、そうしたお客様の反応を直接得られることです。特に産直で購入する方はリテラシーが高い傾向にあり、商品への意見も具体的です。その声を拾えること自体が貴重ですが、一方で「すべてに返信するのかどうか」という問題もあります。
おいしい商品ほど反響が大きくなり、全てに対応していたら寝る時間がなくなってしまうこともあるでしょう。気軽にコミュニケーションを取れる環境が整ってきたからこそ、プラットフォームとしてどのようにサポートするかが重要になりますね。
松浦さん:発信者が発信しやすい時代になったと実感しています。以前は発信のために多くの準備が必要でしたが、今はスマートフォン一つで配信ができ、コンテンツや商品が次々に生まれる時代になりました。これは非常に良い変化だと思います。
柳田さん:農作物の魅力を伝えるときも、実際にその作物を手に持って話すだけで説得力がありますよね。
松浦さん:ライブ感や“目の前で見せる”という要素には高い効果があると感じています。たとえばオンラインの料理イベントを開催したり、「タイムライン」機能で今日の海や畑の様子を写真で投稿したりできるようにしています。日々どんなことを考えているのか、現場がどのような状況なのかを発信しやすくしていくことが重要だと思っています。
柳田さん:今はほとんどのことがスマホで完結しますから、投稿のハードルを下げればコンテンツはどんどん増えていきますね。農作業中に「今日はこんな虫がいました」と投稿するだけでも、反応があるかもしれません。
接触頻度が高いほどファンの熱量も高まりやすいので、「食べチョク」さんの場合は、生産者に負担をかけず、いかに簡単に投稿できる仕組みをつくるかが鍵になりますね。
一次産業の相談役として、支え続ける存在に
松浦さん:私たちは商品を持っていないので、主人公はあくまで一次生産者の方々です。農家や漁師の方々が良い商品を作り、積極的に投稿・発信してくだされば、自然とファンがつく。私たちはその仕組みを整え、サポートしていくことしかできません。
柳田さん:ですが、それが実現できれば、お客様を含めて“三方よし”の関係になりますよね。食べチョクさんが最も注力すべきなのは、生産者の強みを見つけて、それをどう伝えるかをアドバイスできる体制づくりだと感じます。
松浦さん:そうした中で、特に感謝していることがあります。食べチョクに参画している生産者の方々が「一緒にやろう」という前向きな姿勢で、「食べチョクをもっと良くしたい」「もっと売れるようにしたい」と言ってくださるんです。
機能追加の要望や発信の仕方など、厳しいご意見も含めて多くの声を頂きますが、クライアントと企業という関係を超えて、頻繁にコミュニケーションを取れることをとても嬉しく感じています。
柳田さん:わからないことがあれば聞くしかない中で、「ヒントは出すけれど答えは言わない」という食べチョクさんの方針は素晴らしいですね。答えを与え続けてしまうと、考える力が育たなくなりますから。
松浦さん:そこは非常に大切にしていて、弊社の行動指針やチーム体制にも反映しています。たとえば、生産者サポートチームの名称は「生産者のパートナー」。私たちは何かを“教える”のではなく、“伴走するパートナー”として日々の業務に取り組んでいます。
横の立場で、同じ方向を向く仲間として支えていく。そんな関係を築いていきたいと考えています。
柳田さん:「D2C」という言葉がアメリカで広まり始めたのは2014年頃ですから、今となっては新しい概念ではありません。ただ、日本では長らく、生産者が自ら販売に取り組む文化があまりありませんでした。
そうした中で、直接お客様とつながり、声を聞き、高い価値で販売できる仕組みをつくるのは、とても意義のあることだと思います。
最後に、一次産業を持続可能な形にしていきたいというお考えについて、改めてお聞かせいただけますか。
松浦さん:産直ECという概念が生まれ、少しずつ広がってきましたが、まだ十分に収益を上げられている生産者は一部にとどまっています。「食べチョク」を通じてお客様の声を聞き、しっかり利益を出しながら継続できる方をもっと増やしていきたいと考えています。
販売面の支援をまずは安定させ、そのうえで一次産業が抱えるさまざまな課題にも向き合い、サポートしていきたいと思っています。
柳田さん:大きな視点で見ると、一次産業者の“相談役”のような存在を目指しているということですね。
松浦さん:そうですね。伴走し続けられる会社でありたいと思っています。何かあったら「食べチョク」や「ビビッドガーデンに相談してみよう」と思ってもらえるような存在になることを目指しています。
柳田さん:国内で自給できるものが減り、担い手も少なくなっている今、食の重要性はますます高まっています。一次産業に携わる方々の努力は欠かせませんし、私たちが気軽に直接購入できるようになるのも、とても良い流れだと思います。
おわりに:伴走で育む、持続可能な一次産業の未来
松浦さんのお話からは、「食べチョク」が単なる販路提供にとどまらず、生産者のそばで共に考え、支える存在であることが伝わってきました。
小規模だからこそ抱える悩みに寄り添い、無理なく個性を発揮できる仕組みを整えることで、ファンを生み、リピートへとつなげています。生産者と消費者、そしてプラットフォームが“三方よし”の関係で関わり合う姿は、一次産業が直面する課題を乗り越える大きなヒントになるはずです。
これからも伴走を続けながら、生産者と共に産直ECの可能性を広げていく。その姿勢に、持続可能な一次産業の未来が見えてきました。
EC市場の真の発展に貢献をという想いで、「ECの未来」を運営しているサヴァリ株式会社は楽天市場・Amazonなどネットショップ運営代行をはじめ、モール通販を中心にECサポート・ECコンサルティングを行っています。EC運営に不安を抱えている事業者様は問い合わせてみてはいかがでしょうか。
■サヴァリ株式会社へのお問い合わせはこちら
https://savari.jp/contact/
あわせて読みたい