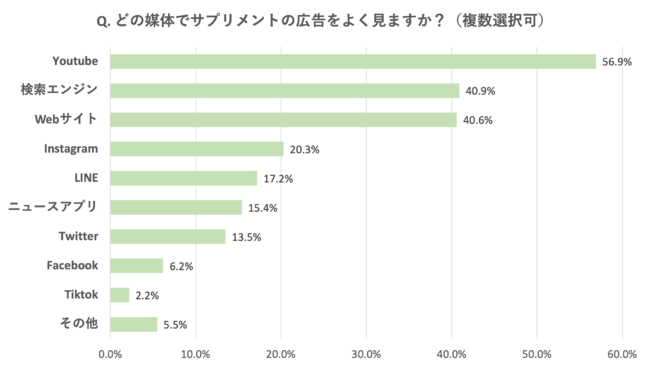この記事の目次
399のうち148のECサイトがダークパターンに該当
欧州連合(EU)23カ国の399のECサイトを対象にした欧州委員会による調査で、148のECサイトが、「ダークパターン」を取り入れていることが明らかになりました。ダークパターンとは、価格をわかりづらくしたり、あたかも期限があるようにカウントダウンタイマーを表示したり、消費者に誤認を与えるような情報で購入を促す手法のことです。
また、同委員会はECサイトのモバイルアプリについても同様の調査を行っています。その結果、102のアプリのうち、27のアプリがダークパターンに該当することが判明しました。
ダークパターンで最も多いのが情報の隠蔽
重要な情報を隠すことがダークパターンのよくある手口です。148のECサイトのうち、配送料の表示をしなかったり、安価な商品の用意がありながら高額な商品を訴求したりと、消費者視点で考えると知りたい情報が見れないものは70サイトありました。また、23サイトが、消費者が知らないうちに定期購入に登録してしまうような仕様になっています。
情報の隠蔽に加え、視覚的なトリックや誤解を招くような表現を使って、より高額な定期購入や商品、配送オプションを訴求しているECサイトは54ありました。商品の購入期限を偽ったカウントダウンタイマーを使用しているECサイトは42です。
消費者保護法はダークパターンに対応しているのか
欧州委員会によると、各国当局はダークパターンに該当する企業に連絡を取り、必要があれば是正措置を講じるとのことです。さらに、同委員会は、現行の消費者保護法がダークパターンに対応できているかどうかを調査すると発表しました。
欧州司法担当委員のディダー・レインダースさんは、「ダークパターンは明らかに間違っており、消費者保護に反する」と話します。そして、「我々はこの問題に対処するために、各国の当局が執行権力を活用する必要があるでしょう。ダークパターンから消費者を守らなければなりません」と続けました。
日本でもダークパターンによる被害が発生
コロナ以前より景表法や薬機法を違反している事業者、消費者に誤解を生むような表現を多用する事業者は一定いましたが、コロナ禍の影響でECを初めて利用する消費者が急増したことで、消費者センターへの問い合わせが格段に増えました。これにより、近年日本では定期通販を巡るトラブルにより、法改正が進んでいます。
店頭や対面であれば起こり得ない契約上のトラブルがECサイトであれば起きてしまうのは看過できないことといえます。消費者に”買わせる”仕組みづくりではなく、消費者が気持ちよく”買いたい”と思えるような魅力を押し出す表示に力を入れるべきではないでしょうか。消費者の声が広がりやすい現代において、ダークパターンや虚偽の表示、コンプライアンス違反をしている企業の情報はSNSを介して広まりやすい環境にあります。
高騰するCPAになんとか合うような訴求を考えた末、ギリギリを攻めるような表示になることもあり得るかもしれません。しかし、その表示を見ている消費者は、「自分の悩みが解決できるかもしれない」と信じて買い物をしています。ECや通販で裏切られる経験は業界全体の発展を滞らせてしまうのです。買い物が楽しめる世界のために、数字にとらわれるのではなく、商品を受け取った消費者の笑顔を想像できる商売をしていきましょう。
※この記事は「Ecommerce News」に掲載されているニュースをもとに翻訳しています。日本のEC事業者の方の参考になればとのことで、Ecommerce News社にご協力いただいております。
合わせて読みたい