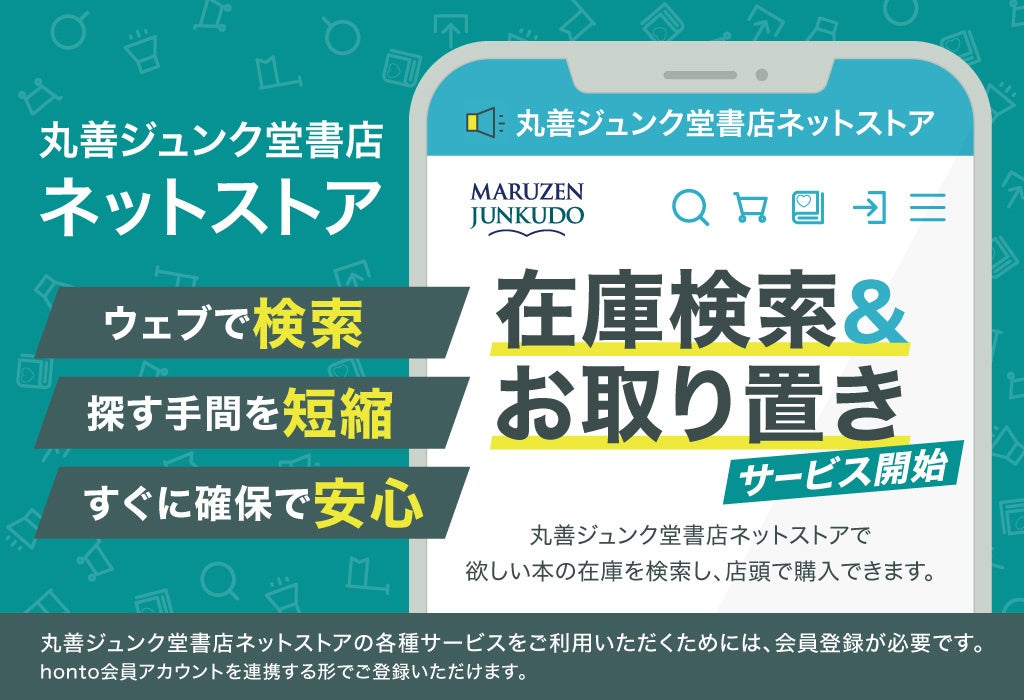2024年9月26日、W2株式会社が主催した「Unified Shift 2024」では、ユニファイドコマースをテーマに、ECやリテール業界の最新動向が熱く語られました。業界のトップリーダーが集まり、リアルとデジタルの融合が今後のビジネスにどのような影響を与えるかが、さまざまな視点から討論されたカンファレンスです。
特に僕が関心を持ったのは、丸善ジュンク堂書店の工藤淳也さんと事業クリエイターの真田幹⼰さんが登壇した「本を売ることを目的としない書店の体験戦略を語る」というセッションでした。年々売り上げが減少する書店業界において既存の書店がオンライン書店にどう対抗するのか、会場の多くの参加者も同様に関心を抱いていたと思います。その内容を以下にまとめました。
この記事の目次
丸善ジュンク堂書店が描く新しい顧客体験
書店業界は1996年をピークに、売上が減少し続けています。特に、2000年11月にAmazonが書籍販売市場に参入し、オンライン書店が急速に普及したことで、大きな転機を迎えました。Amazonのオンライン書店は利便性に加え、豊富な在庫と送料無料のサービスを提供し、従来の書店にとって大きな脅威となりました。また、書籍は定価販売制度の影響で、どこで購入しても価格が同じであるため、価格による差別化が難しく、従来の書店は選ばれる理由を失いつつあります。
工藤さんは「書店の強みは、何を買うか決めていないお客様に対して、選択肢を提供できることだった」と振り返りますが、デジタル情報の普及によりその必要性が薄れてきていることも指摘されています。
「ただ本を売るだけではなく、書店は『体験価値』を提供しなければならない」と工藤さんが語ったように、丸善ジュンク堂書店は物質的な書籍販売に依存するのではなく、新しい価値を提供する方向へと進化しています。
書店の仕事の変化:モノからコトへ

従来、書店の役割は、送られてきた本・注文した本をどのように配置するか、どの本を目立たせるかに注力することが中心でした。しかし、現在の書店は、それ以上の価値を提供する必要があります。丸善ジュンク堂書店では、特定の本をもっと多くの人に知ってもらうために、著者と共同でグッズを開発したり、企画展を開催したりするなど、書籍に関連した体験を提供しています。これにより、単に書籍を売るだけではなく、その背後にあるメッセージや価値を顧客に伝えているのです。
「書店を訪れるお客様が必ずしも購入目的を持っていないことが多く、新しい発見や興味を引き出す体験を提供することが、現代の書店に求められている」と工藤さんは強調しています。特に、「書籍をただのモノとして売るのではなく、顧客が求める中身のIPや情報、その動機に立ち返り、体験価値を提供することが重要だ」と述べました。
体験価値を高めるイベントとコト消費への注力
丸善ジュンク堂書店は、顧客に「コト消費」を提供するため、年間を通じてさまざまなイベントを開催しています。代表的なイベントには「“価値観”で出会える!良縁書店」や「丸善ジュンク堂に住んでみる」、「M.LEAGUE OFFICIAL SHOP」、「EHONS」などが挙げられます。
中でも、詩人の最果タヒさんとのコラボ企画展は「売上に直結した成功例」として工藤さんも自信を持って語ります。この企画では、最果タヒさんが選んだ書籍や詩集の展示を通じて、彼女の世界観を顧客に体験させると同時に、展示された書籍やグッズの販売促進を行いました。単なる商品販売ではなく、作家の魅力や作品の背景を深く伝えることで、顧客が「コト消費」を通じて書籍やグッズを手に取るきっかけを作り出したのです。
「コト消費を重要視して、果たして売上は上げられるのだろうかという懸念もあるでしょう。もちろん、こうした取り組みには失敗のリスクも伴います」と工藤さんは認め、「しかし、業界が縮小している中で、新しい顧客体験を創り出す挑戦が未来を見据えた成長には不可欠だ」と強調しました。
現場の熱量を伝える重要性

丸善ジュンク堂書店の現場では、リアル店舗ならではの「熱量」をいかに顧客に伝えるかが重要視されています。たとえば、「本の掲示板」として、手書きのカードで本を紹介する取り組みがあります。この方法は非常に効率が悪いですが、スタッフが感じた本の魅力を直接伝える熱量が顧客に響くことも多いのです。「DX(デジタルトランスフォーメーション)によって業務が効率化され、余裕ができた時間をこうした熱量を伴う取り組みに充てたい」と工藤さんは話されました。
最果タヒさんの企画展でも、書店スタッフが現場の意見を元に、自分たちの手で企画を作り上げています。デジタルが普及する現代だからこそ、リアルな接点を持つことが重要であり、現場の熱量を直接顧客に伝えることが、成功の要因となっているのです。
未来のEC・リテール業界の姿:デジタルとリアルの融合
今後、書店業界が直面する最大の課題は、デジタルとリアルの融合です。オンラインショッピングの利便性に対抗するためには、書店が提供できるリアルな体験を強化し、顧客が書店でしか得られない価値を提供する必要があります。「書店はゼロからプラスを作り出す場所」と工藤さんは位置づけ、単なる販売の場を超えて、新たな発見や体験を提供することを目指しています。
「お客様が求めていなかったものや、新たな興味を引き出す瞬間、いわゆるセレンディピティが、リアル書店の強みです」と工藤さんは言います。書店内を歩き回る中で、偶然目に留まる本との出会いや、その場で感じる直感が、オンラインにはない価値を生み出すのです。
「ECとリアルの一体化が進むユニファイドコマースの時代において、それぞれの役割を明確にし、顧客にとって最適な体験を提供することが大事」だと工藤さんは話されます。丸善ジュンク堂書店が描く顧客体験は、書店業界に限らず、どの業界にも共通する課題とチャンスを示しています。モノを売るだけでなく、顧客に新しい価値や体験を提供することが、ECとリアル店舗の共存においてますます重要になるのではないでしょうか。
オンラインカンファレンス「5年後のリテールを考える Unified Shift 2024」はアーカイブ配信をしています。他のセッションも気になる方は下記からご覧いただければと思います。

あわせて読みたい